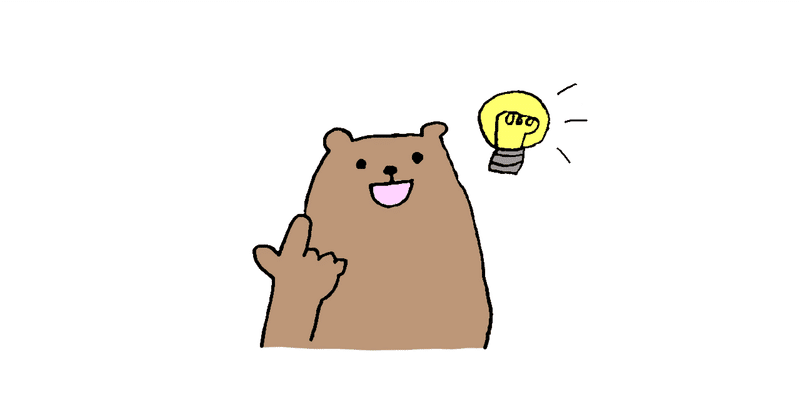
【読書記録】齋藤孝『5日間で「自分の考え」をつくる本』【とにかく読んで考えて書こう】
「自分の考え」を気軽に発信できる時代になりました。
このnoteもそうですね。
他者に読まれる保証はありませんが、逆に高い評価を受ける可能性もあります。
「自分の考え」を持つ重要度がどんどん高くなっていくと、齋藤氏は語っています。
従来の学校教育では「自分の考え」をまとめ、発表する訓練ができていません。
これからはこの力がなければ勝ち残っていけません。
そのために本書の5つのレッスンを通して、「自分の考え」を表明し、「意思決定」して自分と周りを動かせる人間になりましょう。
そういった内容となっています。
下記、印象に残った部分は引用を織り交ぜながら、重要だと個人的に感じた部分をまとめています。
レッスン① レビューで思考力を高める
「自分の考え」とは、すべてを自分の頭で考える必要はなく、8割を事実や情報、2割を自分の意見を述べる程度で良い。
その一歩として、レビューを書くことは「自分の考え」を表明する訓練として最適である。
レビューは、そのレビューした対象を知らない人にとって、新しい世界への架け橋となる。
その点から、いいレビューは社会貢献ともいえる。
書き方のコツとしては、対象について把握し、要約をすることである(前述した通り、6~8割が要約でもレビューとして成り立つ)。
哲学者カントは、「私たちは物自体に触れることはできない」と説いている。目の前に一つの物があったとしても、「これは何々である」と断言はできない。「こういうように見える」「こういうように感じる」と言えるだけ、というわけである。
レビューにかぎった話ではないが、文章としてつまらないのは、抽象的な言葉の羅列だ。(中略)
そこで重要なのが、キーワードをつくるという感覚だ。ある作品を「おもしろい」と思ったのなら、その根源的な理由は何か。ひと言で表現するとすれば、どんな言葉になるか。
レッスン② 考えるワザを習得する基本キット
⑴「比較する」
ある対象に接したら「比較して考える」クセをつける。そうすることで何かしらの「自分の考え」を表明できる。
⑵「比喩を活用する」
比喩をコンセプトとして使うと、頭の中で整理しやすい(その比喩をしようした時点で、「自分の考え」がある程度定まるため)。
⑶「弁証法的思考」
「対話的思考」のこと。対話をすると矛盾が生じたり、対立が起こったりする。それを解決するために打開策を模索する。それが思考の活性化につながる。
⑷「現象学的思考」
思い込みを取り払い、その事象自体を見ること。
⑸「システム思考」
個人の視野にとどまらず、組織全体を見る。広い視野を持つと合理的な結論に達しやすい。
「量」と「質」とは一見するとまったく違うもののように思えるが、そうではないと説く。平たくいえば、何かの量をこなすことによって質は向上するし、質が向上すれば量も増える、ということだろう。
そこで現象学的な態度として重要なのは、自分なりに新しいレッテルを次々と貼り替えることだ。一般的に「こういうものだ」といわれているものがあったとしても、そこで思考停止してはいけない。実情に即していないと思えば、剥がす必要がある。
レッスン③ 行動の習慣を変える
語彙力がなければ、自分の意見を詳細に表現することができない。
日常的に概念を探し、当てはめる視点を持つ。
その習慣をつけることはまさに「考える」ことである。
ある対象を輝かせようと思うなら、そのものではなく、額縁で引き立たせることを考える。あるいは、何か輝いている対象があるとすれば、その周辺に額縁のような引き立て役が存在すると考える。
レッスン④ 「自分の考え」を深める読書術
読書も運動と同じで、日課にしなければ量は読めず、頭の持久力がつかない。
多く読むことで長く思考し続ける力がつく。
古典を読むことは、その人にとっての”重石”を持つということでもある。
現代の情報は、旬がきわめて短い。最新や流行の情報であっても、たちまち古くなって価値を失ってしまう。そういう時代だからこそ、古典を錨のように下ろしておくことで、流されない自分を持つことができるわけだ。
目次の見出しをざっと見て、キモだと思う部分を探し当ててざっと読み、さらに「もし自分がこの本の推薦文を書くとしたら、どの文章を選ぶか」という観点で三つ選ぶ。それを新聞広告に載せるとか、帯にアイキャッチとして書くといったイメージを持ってもいい。そうすると、読む意識がまったく変わってくるはずだ。たとえ短時間であっても、深く読めるのである。
レッスン⑤ 意思決定が速くなる思考術
意思決定してそれを行動に移すこと。
それが「考えること」の最上級である。
意思決定力の養い方は、物事のプラス面とマイナス面をすべて挙げ、検証していくことである。
意思決定のコツは、「真似る」「見習う」こと。
責任のある立場で場数を踏むのも重要である。
「自分の考え」とは10割、自分の頭からひねり出す必要はないという所が発見でした。
(0から自分発信の考えというのはありえないとは思いますが。)
レッスン②の内容は無意識に行っていることもあり、それを言葉にして自覚でき、その意義が納得できました。
私もこのnoteを使って、アウトプットの場数を踏みたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
