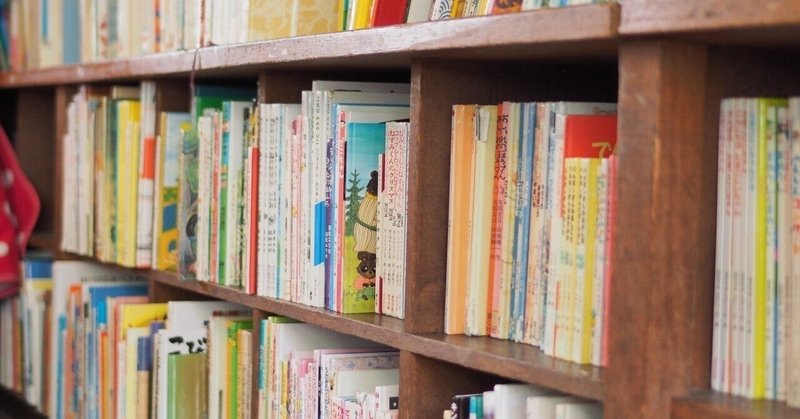
絵本の奥深さをさらに感じる
保育士養成校に入学し、
『児童文学』の講義の中で、
「キャベツくん」作 長 新太(文研出版)を知り、
「絵本、おもしろい!!」となり、
その後、自身の子ども時代を振り返り、
「あおい目のこねこ」作 エゴン・マチーセン 訳 瀬戸貞二
「ぐりとぐら」文 中川 李枝子 絵 山脇(大村)百合子
(ともに福音館書店)を好きだったことを思いだし、
その後、現場にたって2年目か3年目くらいから、
絵本を毎月、少しずつ購入し始め、
知れば知るほど、読めば読むほど、
絵本にどんどん魅せられ、
読んだり、集めたり、絵本作家の著書を読み、
「そんな背景があったのかぁ~」や
「そんな思いがこの作品につながったのかぁ~」と知り、
今に至っている。
保育所・幼稚園・養成校勤務という仕事柄、
新作だけでなく、
廃版になった絵本等にも触れることができる環境にもあり、
多くの絵本と出逢えたと思っていた。
さらに、柳田邦男さんの講演会(ある大会の基調講演の講師)の際に、
その会の実行員会のメンバーとして、
柳田さんのスライドのお手伝いをさせていただき、
講演後、柳田邦男さんと休憩室室で30分近く、
「今日紹介されていたあの絵本のシリーズで〇〇が大好きなんです」
「それもいいねぇ」と二人で盛り上がり、
「よく、色々な絵本を知っているね」なんて言われて、
それなりに絵本のことを知った気になっていた。
ただ、「絵本のたのしみ」(こどものともの折り込みふろく)を
読み続けていると、
「いや、俺全然浅い!!」と痛感させられました。
絵本作家の作品を作り出す際のその奥にあるものを知ると、
何十年も前の出来事(小さい頃)がベースにあったりして、
ただただ「すごいなぁ・・・」となります。
創作活動は、「日々の暮らしの解像度があがる」という言葉をある絵本作家の方から教わったが、
まさにその通りなのだと感じていると同時に、
絵本(紙芝居含め)は、ホンマに奥深いとなった
8月6日の朝でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
