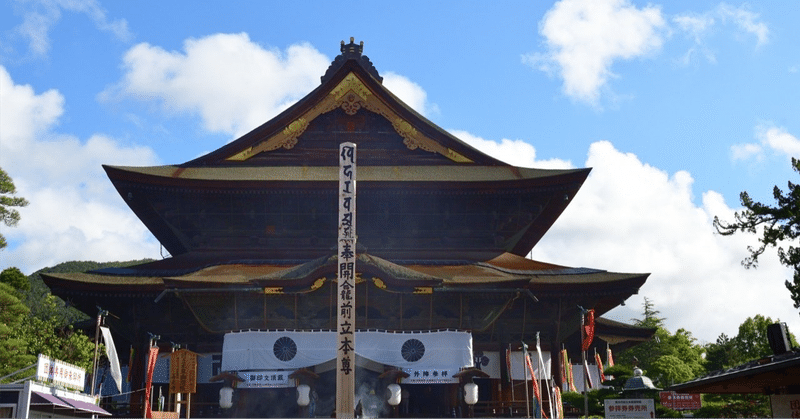
『華厳経』睡魔・雑念 格闘中22
「金剛幢菩薩〔十〕回向品」 ― 回向について 前編 ―
不遜の誹りを免れないであろうが、正直なところ、この品が1巡目で、いちばん眠気を誘われてしまったのである。品自体も長いということもあるのだが、表現の繰り返しや、言い換えがかなり続き、読みながら実際に何度も寝てしまい、本を取り落としたり、何度も数ページ読み進んでは、戻りを繰り返してしまったのである。
そのため、2巡目の今回は、1巡目よりも丁寧に読み進むべく、一気に読み進めることは止めて、2回に分けることとした。
この品では、前の「兜率天宮菩薩雲集讃仏品」に於いて最初に説いた、金剛幢菩薩による回向についての説法が中心となっている。(注:なお、品の題名に於いて、日本語訳では「回向品」となっているのであるが、伝わっている漢訳において、"十"の文字が入っているものと、入っていないものがあるようで、訳者の衞藤即應先生は、日本語訳に於いては、"十"の文字を外した題名としている。また、"エコウ"についても、漢訳では"廻向"が使われているのだが、衞藤先生は、"回向"の文字を採用しておられる。)
さて、仏教の重要な語は、普段の生活に入り込んでいるものが多く、この品で説かれる"回向"の語に関してもそうであろう、なんとなくニュアンスは分かっているものの、いざ、それをはっきりと説明しようと思うと、難しいと感じるようなものが多いのである。
品の題名が示すように、この品では、菩薩の回向に関して十種説かれているのであるが、まず、その"回向"の語について確認したい。
渡辺照宏先生は、その著書の中で、回向について、次のように述べている。
「大乗仏教ではこの語にまったく独自の意味を持たせることになった。す
なわち、ボサツが自分の善い行為によって得た果報を他の人びとに譲って
彼らを苦悩から救ってやる、そのことを廻向というのである。日本では、
『願わくばこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆とも
に仏道を成〔じょう〕せん』という〔中略〕が一般的に"廻向文"として用
いられている。」
注:渡辺先生は、漢字の”菩薩”を使わず、カタカナの”ボサツ”の語を用
いておられる。
渡辺先生は、ここで、初期仏教からの”回向”の変遷を述べていらっしゃるのだが、ここにこそ、大乗仏教の特徴が現れていると言えよう、大乗仏教においては、自己のみならず、他者(他者へのまなざし)が常に意識されているのである。
そのことは、金剛幢菩薩が説く、以下の十の回向にも表れている。
1)救護〔ぐご〕一切衆生離衆生相回向 ・・・ 一切の衆生を救護
2)不壊回向 ・・・ 壊すべからざる信による回向
3)等一切仏回向 ・・・ 過去・現在・未来の諸仏の回向を学ぶ
4)至一切処回向 ・・・ 一切のあらゆる処に至らしめる回向
5)無尽功徳蔵回向 ・・・ 無尽の十功徳蔵による回向
6)随順一切堅固善根回向 ・・・ 一切の堅固なる 善根による回向
7)等心随順一切衆生回向 ・・・ 平等心による一切の衆生への回向
8)如相回向 ・・・ 真如相〔無相〕による回向
9)無縛無著解脱回向 ・・・縛著なき解脱の心による回向
10)法界等無量回向 ・・・ 法界に等しき無量の善根を回向
※『国訳大蔵経』,経部第五巻,第一書房,2005,pp.563-619、ならびに
『国訳大蔵経』,経部第六巻,第一書房,1993,pp.1-178を基にまとめた。
これらの、回向について説くなかに、数限りない「衆生をして」の表現が取られており、仏への回向もさることながら、他社へ自身の功徳を振り向けることが示されているのである。
ここで、1巡目に読んだ際には余り気にならなった、”善根”の語の意味が分かるような、分からないような曖昧な理解であったので、辞書を確認したのだが、こちらもあまり腑に落ちるような説明が無かった。
他の資料をあたってみたところ、中村元先生の文章の中に、納得できる説明が有ったので、挙げてみたい。
「『善根』とも訳される。つまり、善いこと、徳、を積むと、それがあと
で良い果報をもたらすから、根のようなものである。もとになるので、
『徳本』とか、『善根』とかいわれる」
では、回向とはどのように行われるのであろうか、もちろん、回向するだけの功徳を積まなくてはならないのであるが、その功徳が十分積み上がった際に、人に振り分けるだけの量的なものがあることに、気が付いたりするものなのであろうか。(それ以前に、徳を積みなさいとの声が、どこからか聞こえて来そうな気もするのではあるが。)
この品で、かなり細かく説かれているのが、布施についてなのであるが、やはり、直接的に見える形で、他者への行為ということが、回向としては分かりやすいのかも知れない。
「此の善根を以て、一切の衆生をして人の楽見〔ぎょうけん〕する所、見
て忻〔よろこ〕ばざることなく、見て輒〔すなわ〕ち親善し、見て愛せざ
るなく〔後略〕」
ここには、功徳を受け取った(回向された)側の、楽しげで、喜んでいる様子をみて、功徳を渡した(回向した)側の微笑んでいる姿が想像される。
布施以外の回向のし方というのは、残念ながらここまでの段階では、明確になっていないのであるが、ここに表されているように、回向を受けた側、回向を振り向けた側のどちらもが、微笑んでいる、幸せな状態というのを目指すという、単純で素朴なことなのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
