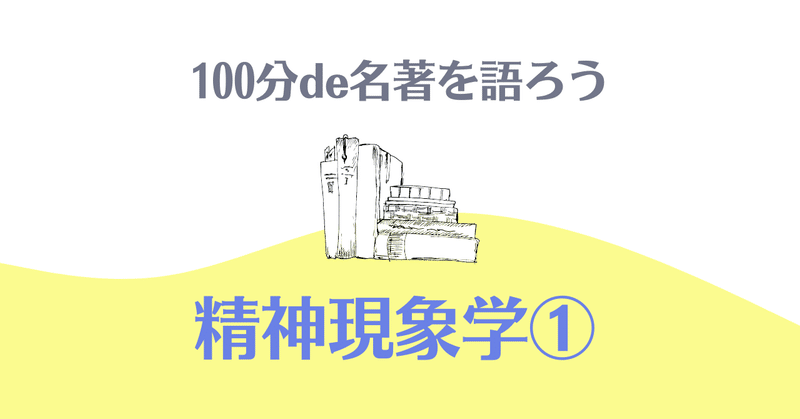
【100分de名著を語ろう】レジュメ『精神現象学』①
こんにちは。
今月(2023年5月)度のEテレ「100分de名著」は、斎藤幸平さんによるナビゲートで、ヘーゲルの難著『精神現象学』に挑みます。朗読は八嶋智人さん。哲学科のご出身だそうです。今回は5月4日(木)のclubhouseルームのための「レジュメ」です。
目次
【はじめに】社会の分断を乗り越える思想
第1回 奴隷の絶望の先に 「弁証法」と「承認」
第2回 論破がもたらすもの 「疎外」と「教養」
第3回 理性は薔薇で踊り出す 「啓蒙」と「信仰」
第4回 それでも共に生きていく 「告白」と「赦し」
【はじめに】社会の分断を乗り越える思想
ヘーゲル(1770-1831)はベートーヴェンやナポレオンと同時代を生きた。『精神現象学』は1807年、37歳の時に刊行された。
難解である理由=①独特な言葉づかい、②構想のスケールが破格なまでに大きい、③「序論」とは別に、全文を書き上げた後の「序文」があること。
しかし「意見や価値観の違う他者と共に生き、自由を実現するための手がかり」が書かれており、今こそ読まれるべき一書。
第1回 奴隷の絶望の先に―—「弁証法」と「承認」
①遅咲きの大哲学者
31歳でようやく大学に職を得る(ただし「私講師」として)が、37歳の時、ナポレオンの侵攻により大学が閉鎖され失職。46歳で正教授になるが、1831年にコレラで死去(61歳)。
②ヘーゲル哲学を現代に生かす
『ヘーゲル全集』(20世紀後半)=研究が進む。
今日、「弁証法」と「相互承認」が大きな意義を持つ。
③ヘーゲルが考えようとしたこと
「自由」と「対立」がキーワード。
社会に対立が生じるのは、近代に特徴的な現象。
前近代社会=役割や価値観が伝統的に固定。自由は制限されている反面、安定し、調和している社会でもあった。
「急速な不安定化のなかで、どうすれば、社会の対立や分断を乗り越え、調和を取り戻せるでしょうか」=ヘーゲルの問いの哲学的出発点。
④「自由」と引き換えに近代社会が失ったもの
「自由で自立した個人」という理想像が力を得てきた→価値を共有できない個人間の対立を生んだ。
「古代ギリシャ」という理想像を捨て去ったヘーゲル。
⑤対立は永遠になくならない
「矛盾」「対立」「否定」をとことん考えたヘーゲル。
他者の価値判断とのぶつかり合い。
⑥真理は「過程」である
科学からは矛盾や対立の解決を導けない。
矛盾や対立こそ「真理」。
真理は「主体」である=真理とは固定され動かない「実体」ではなく、生成の過程として表現されなければならない。
失敗し学び捨てながら、新たな知を紡いでいこうとする、「学び方」を学ぶ本。
⑦「意識の経験の学」とは何か?
「意識」=何かを知っていること、知っている状態だが、「今のままでは世界をうまくとらえられない」と、一面性や矛盾に気づくことがある。
素朴な見方から多角的、全体的に見られるように学び、成長していく。その過程を分析したのが「意識の経験の学」としての『精神現象学』。
⑧みずからを疑うことで成長する
「自分を疑う」経験を重視。
「絶望のみちすじ」=自分を疑って、間違いに気づくこと。懐疑を契機として絶望していくプロセス。
素朴で自然的な意識=思いなしや先入見でしかない、「実在的な知」ではない。
かつての自分と決別して、新しい自分と新しい知を獲得していく。
⑨人間だけができる「ほんらいの経験」
「弁証法的な運動」=「懐疑と絶望という自己否定を経て新たな知を獲得」すると、「現実が大きく変化する」「あらたな真の対象が出現する」。
「ほんらいの経験」は人間にしかできない。
⑩「弁証法」とは何か?
重視される「矛盾」。
どちらも一面的で不完全な状況において、両者を統合する、新たな知に至る方法論。アウフヘーベン(「止揚」)=①廃棄する、②保持する、③高く持ち上げる。
折衷案や妥協案を見出そうとするものではない。
矛盾や対立をなくそうとするのではなくて、「根本原理」とする。
⑪人間にあって、動物にないもの
「主奴の弁証法」=弁証法と承認論が、いっしょに展開されている。
人間は自分の欲望を自覚的に反省し、距離を取る=反省する意識のあり方を「自己意識」と呼んだ。
⑫世界を意のままにしたい「私」同士の闘い
世界を意のままにしたい「私」として表れてくる自己意識。
「他者」との出会い=相手は邪魔な存在であるが、相手が死んでしまうと「承認」する者が消えてしまうので「降伏」を迫る。
⑬主奴の逆転現象
非対称的な、主人と奴隷の関係。奴隷の側に「非自立的な意識」。
主人は奴隷の労働に依存しきっている。
主人が依存的で、奴隷が自立的と逆転が見られる。
⑭社会を変革するための武器
自立概念を解体、刷新していく必要性と可能性。
「既存のルールや常識を疑い、世の中の見方を変え、社会を変革していく武器」としての弁証法的思考。
⑮本当の自由はいかに可能か?
自立した自由な存在になるために、
二者関係が対照的となること
一定程度の相手の自立性を否定
自分自身の自立性も否定すること
相互承認のあるべき姿を探っていく=「精神」章後半。
⑯追記
※5月5日以降に追記する場合があります。
今回の「レジュメ」は以上となります。最後までお読みくださり、ありがとうございました。それではまた!
最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。ときどき課金設定をしていることがあります。ご検討ください。もし気に入っていただけたら、コメントやサポートをしていただけると喜びます。今後ともよろしくお願い申し上げます。
