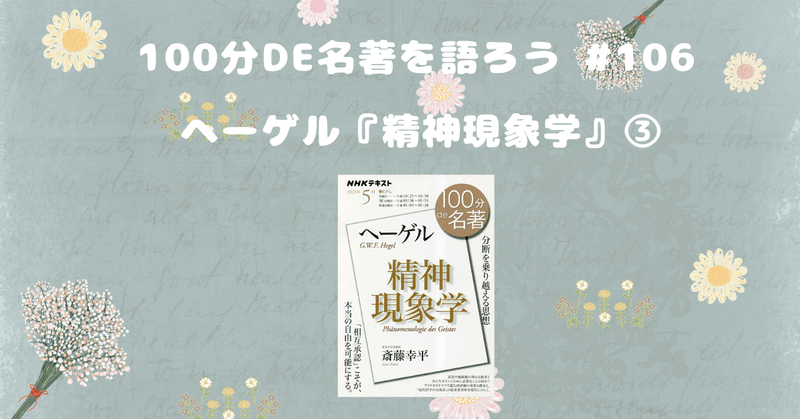
【100分de名著を語ろう】レジュメ『精神現象学』③(23/05/18)
こんにちは。
本日(23/05/18)のclubhouseルーム「100分de名著を語ろう」では、前回までに引き続き、ヘーゲル著『精神現象学』の第3回放送分を扱います。
もう一度「目次」を確認しておきましょう。
【はじめに】社会の分断を乗り越える思想
第1回:奴隷の絶望の先に 「弁証法」と「承認」
第2回:論破がもたらすもの 「疎外」と「教養」
第3回:理性は薔薇で踊り出す 「啓蒙」と「信仰」
第4回:それでも共に生きていく 「告白」と「赦し」
【はじめに】や、表紙にもあるように、今回重要な言葉は「分断」です。この第3回のテキストの記述を読んで、その感は一層深まったのですが、放送を拝見したところ、少し難しいなという感想を持ってしまいました。
そこで、第4回相当部分の記述も読んだのですが、その難しいという印象は拭えませんでした。第4回の放送を待つことにして、今回はテキストに沿って進めてみたいと思います。
①陰謀論が生まれる土台
近代社会では、伝統的な価値観とは距離を置いて(疎外して)、それらを反省的にとらえることができる。しかし、判断の根拠となる社会的規範(実体)が揺らぎ、流動化していく。
このルールはおかしいと声を上げられるが、いき過ぎた疑いを持つことは、むしろ社会の分断を深めていく。
②啓蒙と信仰の戦い
自由を守るためには、ある程度の安定した規範や規則が必要。
判断を「普遍的」なものにしたいという欲求が意識に芽生える=啓蒙の意識。
普遍性を追求していく「啓蒙」と、残存する伝統的思考・価値観(=「信仰」)との間の戦い。
啓蒙の本質=「絶対的な否定性」:相手の立場を切り崩そうとする態度。
③啓蒙が「非理性」に顚倒してしまう理由
「啓蒙されなければならない」一般大衆。
そうした啓蒙のあり方は、最終的に自己否定につながる。
「自己反省」を欠く啓蒙。自分が誤っているかもしれないという可能性を認めていない。
自然科学やデータを特権視していては、「真理」には辿り着けない。
「自分の考えが単なる独りよがりの思い込みではなく、本当に正しいのかを吟味するためには、他者と共同していくことが欠かせません」。
④啓蒙が見落としていること
啓蒙に欠けている「信頼する」という態度。
他者と同じものを確信しあえる=共通認識が成立しうる。
⑤大衆はアホではない
「啓蒙は一方的に相手を否定するばかりで、相手の立場に対する理解や、自分たちが間違っている可能性への自己反省を欠いています。ゆえに立場の違う信仰と共同できない。ここに啓蒙の限界があります」。
⑥啓蒙は信仰である
「しかし真に憐れむべきは、貧しい世界観のうちにある啓蒙の側ではないでしょうか」。
それ自体が「信仰」である科学主義。
⑦ヘーゲルの自然主義批判
⑧実らなかった信仰の反撃
「根拠」を示せとする啓蒙の圧力に応じてしまった信仰の側。
「結局のところ、啓蒙の側にも信仰の側にも、みずからは反省し、対立する相手と信頼関係を築こうとする態度は生まれないとヘーゲルは言います」。
⑨現代における「啓蒙と信仰の戦い」
「エビデンスがあれば、対話のための信頼関係が構築されるなんてことはなく、信頼関係があって初めてエビデンスが意味をもつということです」。
⑩対立の果てにあるもの
「世界はもはや理性によってではなく、むき出しの利害関心に支配されるようになっていきます」。
「むしろ、自由とは、あらゆるものの否定の先にはないのだ、と」。
⑪薔薇としての理性を求めて
「啓蒙に決定的に欠けていたのは、科学だけでは説明できないものを大切に考える『精神』としての理性です」。
⑫追記
追記① 集まってくださった2人と、収録・公開を前提に語り合いましたので、その分を添付しておきます。
今回の範囲についての記述は以上となります。最後までお読みくださり、ありがとうございました。それではまた!
最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。ときどき課金設定をしていることがあります。ご検討ください。もし気に入っていただけたら、コメントやサポートをしていただけると喜びます。今後ともよろしくお願い申し上げます。
