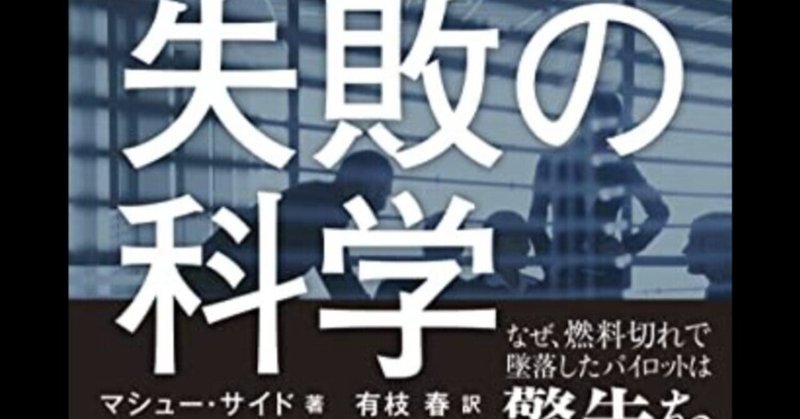
『失敗の科学』
Amazonで評価数が1700以上で、星も4.5という人気の本。
この本では数々の「失敗」についてその失敗はなぜ起こったのか?
その失敗について人はどう行動したのか?
そしてどう改善されたのか?を書いている。
いくつかの実話から見える真実を作者の視点から論じている。
イギリスでは10人に1人は何かしらの医療ミスで患者が死亡または健康被害を受けているということだ。
ただ重要なことは医療過誤が最も起こりやすいのは、医者に悪意があるときでもやる気がないときでもなく、患者のために真面目に仕事にとり組んでいるときなのだ。
医療の現場でミスが起きる原因として、
①疾患や障害の数が多く、複雑なため診察から治療までのあらゆる地点でミスが起こりやすくなっていること。
②資金や人手が不足していること。
③医者が咄嗟の判断をしなくてはならないこと、などが挙げられる。
それに比べ、航空業界ではミス(命に関わるような失敗)がかなり少ない。それは何故か?
それは航空機が事故に遭えば、ブラックボックスが回収されデータ分析によって原因が解明される。二度と同じ失敗が起こらないように速やかに対策がとられる。この失敗からシステムを改善し、錯乱状態でもある程度直感的に操作できるように改善されたことで事故が劇的に減っているそうだ。
しかし、他にもまだ大きな問題がある。
それは人が失敗を咄嗟に言い訳したり、隠したりすることだ。
何故かというと、まだ真相がわからないうちから、周りからの叱責を受けるからだ。
自分の面目を保つために失敗を隠すのだ。
医療業界では、完璧でないことは『無能』に等しいという考え方があるという。
最終的に、人は記憶の履歴書(ミス)さえ書き換えてしまうのだ。
そのほかに、企業の失敗(倒産)がある。
企業が倒産するのは、システムの欠陥でも不運な事故でもなく、むしろ進化のプロセスに不可欠な結果がもたらすと考えられる。
自由市場も独占、談合、価格操作などの問題が起こったりする。そのシステムは失敗が多くても機能するのではなく、失敗が多いからこそうまくいく。
革新的と言われる企業の多くは、進化のプロセスを意識した戦略を取り入れているのだ。
人は「後付けで因果関係やストーリーを組み立て」てしまっている場合がある。
例えば市場の値動きを解説している経済専門家だが、実に理論は整然としていて理解しやすく解説してくれる。それならば、なぜ最初からそう予測できなかったのだろうか?
これは、「どうせ答えはもうわかっているんだから、、、」と考えてしまっているからだ。
アメリカのある刑務所で、少年たちを早いうちに更生させるプログラムが行われた。想像以上に効果を発揮し、再犯者が減ったように思われ、そのプログラムは賞賛された。しかし、のちにそのアンケートの偏りに問題があるのではないかということで徹底的に調査され、さらにはそのプログラム(失敗だとされる)が行われなかったら実際はどう変わっていたのか?
他の要因が影響し、変化が起こっていた可能性も十分に考えられるのではないだろうか。
失敗に思い罰則を科せば科すほど、ミスは深く埋もれていく。すると失敗から学ぶ機会がなくなって、同じミスが繰り返し起こる。それにより、さらに隠蔽体質が強くなる。
どの分野でもミスは貴重な学習のチャンスだ。
非難したところで問題は解決しない。
まずは早計な非難をやめ、失敗から学ぶことが最優先されるべきである。
また、ある研究では子供の頃のマインドの研究がなされた。
自分の能力が理由でできないと悲観する子供たちと、
失敗を自分の成長に欠かせないと受け止める子供たちがいる。
その考え方の違いは後々大きな差を生み出す。
失敗しても「やり抜く力」が大切なのだ。
失敗は誰にでも起こる。
その失敗を隠さず、どう改善していくかで、未来の事故が防げたり、
より大きく成長する糧になるのだと改めて気付かされる一冊である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
