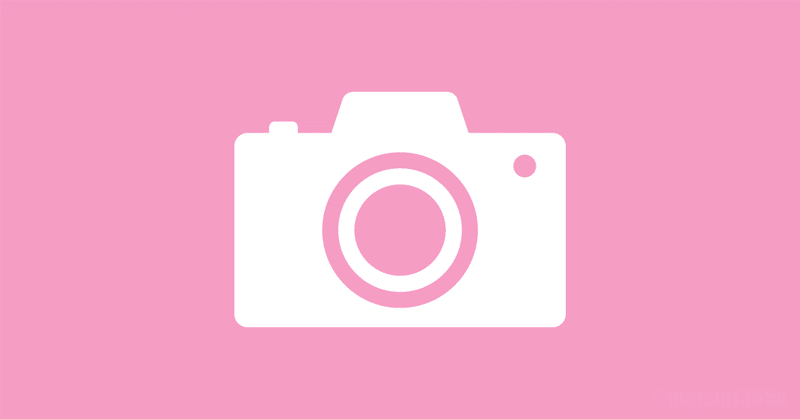
立体作品の二次利用について 美術と著作権について知っておきたいこと(2)
美術品の画像をネットで自由に使いたいと思っても、著作権によって保護された作品を無断で使ってはいけないことは社会の一般常識だといっていい。ところが、著作権保護期間が満了している作品の場合でも、ネットで自由に使えるとは限らないと言われたらどうだろう。それはいったいどうしてだろうと疑問に思うのもまた自然な反応ではないだろうか。
立体作品を撮影した写真の場合、たとえ被写体となっている作品の著作権保護期間が満了していたとしても、その写真に創造性が認められる場合があり、そうした写真を自由に使えるとは限らないことを前回の記事で述べた。なるほど、たしかに写真家の著作物を勝手に使うわけにもいかないし、それはしかたない。
そうであれば創造性がないような写真であれば使用できるわけだから、そっちを使えばいいことになる。ところが、やっかいなのがこの創造性の有無の判断が素人には難しいことである。「この写真には創造性がないから使ってもいいだろう」という判断で写真を利用しても、もしかしたら違法かもしれないという不安が常に付きまとってしまう。なら、もし訴えられたら怖いから立体的な写真は使わないようにしようという判断がリスク管理上は「正常な判断」になり、著作権保護期間が満了したとしても立体物の写真であるというだけで、実質的に利用できないことになってしまっているのだ。
ならば、写真としての著作権保護期間も満了している場合ならどうか。これはまったく問題ない。被写体となっている立体作品も、それを撮影した写真も著作権が切れているなら、その写真は二次利用可能である。そこで写真の著作権についても一度整理しておこう。
写真の著作権は、基本的には絵画や彫刻と同じで、作者の死後70年までは著作権が保護される。ただし例外が3つある。第一に、1967年以前に作者が亡くなっている場合。これはまだ作者の死後50年ルールが適応されていた時期に保護期間が満了しているケースだ。第二に、作品が1956年以前に発表されている場合。これは保護期間が短かった旧著作権法から現行法へと移行する過程で、すでに保護期間が満了した作品については、遡及して現行法が適応されなかったことによる。第三に、1946年以前に撮影された場合。未発表作品であっても撮影された時期が明らかであれば、そこから一定の期間しか保護されていなかった。
これらの例外に当てはまる場合は、作者の死後70年が経過していなくても著作権の保護が満了している扱いになり、作者が誰であっても、たとえその写真に創造性が認められるとしても、著作者人格権に配慮していれば、自由にその写真を使うことができる。
したがって、作者が積極的に権利を放棄している場合も含めれば、いまのところ個人が気軽に二次利用できる立体作品の画像は、以下の6パターンになる。
①作者の死後70年が経過した写真
②1967年以前に亡くなっている作者の写真
③1956年以前に発表された写真
④1946年以前に撮影された写真
⑤権利者がCC0ライセンスによって権利を放棄している写真
⑥権利者が二次利用を部分的に許可している写真(CCライセンスなど)
ところで、1956年というのはまだ白黒写真が主流だった頃なので、立体作品の写真で安全に利用できる写真はほぼ白黒写真ということになる。カラー写真が主流の現在において、著作権保護期間が満了していたとしてもそれが立体作品だからというだけで白黒写真しか利用できないというのは不自由さを感じてしまう。
歴史を振り返ると、写真はそれが発明された当初は科学技術であった。そうした再現技術としての写真を学問の基礎として活用したのが美術史であり、いまでも写真は美術史に具体的な視覚的イメージを与えるために不可欠な要素である。
写真が芸術としての価値を認められるようになるのはだいぶ後になってからだ。写真が芸術のカテゴリーとしても扱われるようになり、著作権法の保護対象になってゆくにつれて、美術史においても技術としての写真の利用というシンプルな考え方はできなくなってきているということだろう。たとえ著作権保護期間を満了していたとしても、彫刻や工芸品などの立体作品の二次利用が難しいは、写真が記録と創造性という二つの要素を併せもつとされているからである。
美術史書に掲載された図版も誰かが撮影した写真であり、立体物の場合は誰かの著作物である可能性がある。思えば、私はいままで美術史書の図版がひとつの表現物であり、作者が存在するとは考えたことがなかった。だが考えてみれば、このような見方は本来望まれていないのではないか。図版を示したときに見てほしいのはまず被写体となっている作品そのものであり、撮影者の表現としてではないからだ。あえてそう捉えようとすることのほうが不自然だろう。
そうはいっても撮影者が存在するのは確かであり、図版に用いられるような写真に創造性がないと言い切ることもまた難しい。立体作品の写真には、たとえそれが表現物であったとしても、表現として扱うことは慣習的に不自然であるという捻じれがある。
先ほども述べたように、著作権のない立体作品を撮影した写真の二次利用については美術図版をめぐる直接的な判例がないため、法的な解釈にいまだ通説がないようだ。そのため、商品写真の商用利用に関しての判例を参考にして、実質的にどんな写真であっても著作権は成立しうるとする見解と、創造性が認められない写真であれば二次利用に問題ない場合もあるという見解の両方がある。
どちらの見解においても念頭に置かれているのは、文化財写真の著作権である。文化財写真とは、文化財の状態を記録し、資料として調査研究に役立てる目的で、文化財の目に見える情報をできる限り客観的に記録した写真のことだ。奈良国立博物館の写真技師を務めた佐々木香輔によれば、文化財写真は「撮影時の文化財のコンディションを記録するために、極端な陰影やアングルを避けて撮影」される。つまり文化財写真はその撮影目的から、意図的に創造性を排して対象を客観的に記録する撮影スタイルだといえるだろう。
ただし、佐々木によれば、文化財写真には記録的写真と芸術的写真という二つのカテゴリーが存在する。芸術的写真とは、例えば仏像の場合、「それ(仏像)を作成した仏師の意図やその時代の人々の美意識、また発願者や祈りを捧げた人々の思いに焦点を合わ」せた写真のことだ。いわば資料性と芸術性を折衷させたような写真である。佐々木は、芸術的文化財写真が「文化財写真の定義に照らせば好ましくないと判断されるだろう」としながらも、極端な陰影や工夫したアングルをあえて用いた写真によってしか捉えられない仏像の魅力があると説く。
では、記録的文化財写真と芸術的文化財写真は、どのように違っているのか。佐々木は、記録的文化財写真の例として奈良国立博物館所蔵の《南無仏太子立像》の写真(図1)を、芸術的文化財写真の例として同館所蔵の《伐折羅大将立像(戌)》の写真(図2)を挙げている。

出典:国立博物館所蔵品統合検索システム(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/narahaku/1430-0?locale=ja)

出典:国立博物館所蔵品統合検索システム(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/narahaku/858-11?locale=ja)
記録的文化財写真の特徴には、第一に白や灰色など彩度のほとんどない無地を背景にしていること、第二に極端な陰影やアングルを避けて客観的なイメージになるように撮影していること、第三に立体物を三面図的に正面や側面、背面から捉えていることなどが挙げられる。一方、芸術的文化財写真は、黒地を背景にして、被写体に強い照明を当てたり、アングルを工夫したりすることでドラマティックな演出がなされている。
芸術的文化財写真はたとえ資料性をある程度備えているとしても、作品を捉える角度や照明の扱い方を工夫しているわけだから、そこに新たな創作的表現が認められ、著作権が発生すると考えられる。問題は、記録的文化財写真の著作権の有無をどう考えるかである。
弁護士の数藤雅彦は「発掘調査報告書のインターネット公開に向けた権利処理」という論文で、記録的文化財写真であっても著作権は成立すると指摘している。数藤によれば、たとえば土器を正面から撮ったときのように被写体を正確に紹介するために撮影するような場合には、誰が撮ってもほぼ同様のありふれた表現になると考えられるとしながらも、裁判所はそのようにして得られた写真にも著作物性を認める傾向にあるという。つまり、記録的文化財写真の著作権を裁判所は認める傾向にあるということだ。
その根拠として参照しているのは、写真の無断使用による著作権侵害をめぐって争われたスメルゲット写真事件とIKEA商品写真事件という二つの裁判である。いずれの場合も写真は著作物と認められ、写真の無断使用は著作権侵害であるという判決が下っている。

スメルゲット写真事件においては、図3の写真の著作物性が問題になった。裁判所はこの写真について「その創作性の程度は極めて低いものであって、著作物性を肯定し得る限界事例に近いものといわざるを得ない」と評しながらも、「被写体の組合せ・配置、構図・カメラアングル、光線・ 陰影、背景等にそれなりの独自性が表れているのであるから、創作性の存在を肯定することができ、著作物性はある」と判断し、著作権侵害を認めた。ただし、「創作性が微少な場合には、当該写真をそのままコピーして利用したような場合にほぼ限定して複製権侵害を肯定するにとどめるべきものである」という見解も同時に示し、別の人間によって撮られたほとんど同様の写真を使用する場合、著作権侵害は成立しえないことも示唆した。


IKEA商品写真事件では、 図4や図5などの写真をめぐって争われた。裁判所は「いずれも、被写体の影がなく、背景が白であるなどの特徴がある」と前置きしながら、図4の写真について「同種製品を色が虹を想起せしめるグラデーションとなるように整然と並べるなどの工夫が凝らされている」として著作物性を認めている。
スメルゲット写真事件でもそうだが、商品写真の創造性の要件として重要な位置を占めるのが、複数の商品の組み合わせ方や配置の工夫のようである。したがって、単体の立体物だけを被写体にした記録的文化財写真の場合、これらの写真よりもさらに創造性が少ないという評価になると考えられる。
問題は図5の写真に対する評価だ。この写真が重要なのは、白い背景でアングルに工夫もなく、照明を当てた結果生じた影なども皆無であり、それでいて素材の質感などはちゃんと再現している点にある。そのような写真は、創造性を排して客観的に対象を記録する記録的文化財写真の理想形といえるだろう。たとえば、先ほど記録的文化財写真の例として挙げた《南無仏太子立像》(図1)も、理想的な写真の一つだろう。そうした写真でさえ著作物性が認められるのであれば、なんらかの立体物を撮影した写真であれば、ほぼ自動的に最低限の著作権が発生することになる。
裁判所は、「マット等をほぼ真上から撮影したもので、生地の質感が看取できるよう撮影方法に工夫が凝らされている」として図3の写真の著作物性を認めた。だがこの判決には疑問が残る。まず、写真はマットを真上から撮影したものでほぼ平面的な商品を写真で再現したに過ぎないから、絵画などの場合と同様に著作権は成立しないのではないか。そして、素材の質感の再現を著作物性として認めていることも奇妙だ。それなら絵画を正面から撮影し、その質感を捉えた写真にも著作権を認めなければならなくなる。だが絵画を正面から撮影した写真の著作物性が他の判例で否定されているのは周知のとおりである。
平面的な絵画を再現した写真には著作権が認められないように、立体物を写したものであっても対象の再現に徹した写真は著作権が認められないと考える余地はあるのではないかと思う。
創造性が認められない写真であれば二次利用に問題ない場合もあるとする見解を示しているのは、内閣府が主催するデジタルアーカイブジャパン推進委員会の資料である。前回の記事でも引用したが、もう一度引用する。
3 次元の作品・原資料であっても三面図的に記録した場合は、新たな創作的表現がないとして、撮影者やデータ作成者の著作権が認められない場合も多いと考えられる。ただし、特定の角度、照明等により撮影者の芸術表現として撮影された写真等、撮影者の創作的表現が認められる場合には、その創作的表現により、撮影者の著作権が発生する場合があることについて、注意が必要である。
作品を捉える角度や照明の扱い方に工夫がみられるような写真には著作権が発生するが、三面図的に記録した場合は新しい創作的表現がなく、したがって著作権が認められない場合もあるとしている。つまり、記録的文化財写真のような写真は被写体を忠実に再現するための技術的配慮しか加えておらず、新たな創作的表現はないので著作権は認められないだろうと言っているわけだ。
資料は総論的なテキストであり、説得的な議論をする目的ではないため見解の根拠は詳しく示されていない。そのためこの見解が妥当なのかは私には検証する術がない。もし仮に正しいとすれば文化財写真における記録的写真と芸術的写真の違いを見極めて創造性の有無を判断できさえすれば、カラー図版で立体作品を二次利用できる道が開かれることになる。そして、この程度であれば素人でも創造性の有無を判断することは容易だろう。
ただ、仮に記録的文化財写真の二次利用が可能であるとしても、そうすることで望ましくない結果を招いてしまうことがあるかもしれない。無断使用にたとえ問題がなかったとしても、それよってたとえば写真撮影のために発生した費用を回収したいなどと考えて、作品の所有者が写真利用にインセンティブを期待している場合、その態度を硬化させてしまうことなどが考えられる。使用するとしても、使用方法を限定したり、解像度を意図的に落としたりするなどの自主的な配慮も考えられるが、決まったルールがない以上、依然として不確定な要素が多すぎる。
以上のことから、たとえ記録的文化財写真の二次利用が論理的に可能であっても、現時点ではそれは控えたほうがいいだろう。前回の記事ではおそらく大丈夫そうだから二次利用してもよいのではないかなどと述べたが、それはひとまず撤回したいと思う。
最後に、記録的文化財写真に対する評価ついて述べておきたい。絵画を忠実に再現するのであれ、記録的文化財写真として立体作品を撮影するのであれ、作品の全体的な印象を損なわずに再現し、かつ細部を忠実に捉えた写真を得るには、照明やカメラなどの撮影機材をコントロールする高度な技能とそれを可能にする特殊な環境が必要だ。そのような写真は誰でも撮れる凡庸な写真などでは決してない。
そのようにして得られた記録的文化財写真には創造性がないといった言い方をすると、なんだが低い評価を下しているみたいに聞こえるかもしれない。しかし、繰り返し述べてきたように記録的文化財写真は意図的に創造性を排する特殊な撮影スタイルであり、不要な情報を削っていくことが文化財写真としては評価の対象になる。
創造性という基準だけに気を取られてしまうと、文化財写真を撮影する技師たちの仕事への敬意を忘れてしまいかねない。そういうことがないように気をつけたいと自戒を込めて思う。
ここから先は
¥ 100
Twitterで日本美術史について呟くbotをやっています。こっちのフォローもよろしくね! https://twitter.com/NihonBijutsushi
