
日本語教師日記86.国語や古典に意外にお世話になっていた話(1)言葉の由来
小説家志望で英和の翻訳家の超上級生徒。
このところ私と彼は、各々の書いたものを訳しあったり、添削したりしています。どっちかが賞でも取ったり、大出版社に発掘などをされたら、ぜひ「この人の本も出してやってください」と、お互いを紹介し合えばいいんじゃないの? 効率的で? と、妄想しましたが、そんな馬鹿なことは生徒には言いません。大丈夫です。
出版社が、「お友達の本もなんなら出しましょうか?」なんて、ありえません。
妄想妄想。
さて、直近の授業の様子です。
私:続きを読みましたよ。
面白かったから、もっとドキュメントの方に入れておいてください。
彼:あ、先生。あれはあれで終わりです。短編です。
私:えっ、そうなの?
ここまでがほんのプロローグかと思って、
これからレミゼみたいな大長編になるかと思ってしまいました。
彼:すみません。もうないです。先生の続きは?
私:あ、あれね〜。
あれというのは、前に練習で書いたものです。
ネット投稿用に横書きで、読みやすさを考えて、
よくあるようにたくさん改行をし、行間もやたら開けていたのですが、
せっかくなら読み慣れた文庫本のような画面でやってみたいなぁと思い、TATEedidorというアプリを入れて、放ってあった習作を、
そこにコピペしてみました。
そうしたらあら不思議。
横書きの時には感じなかった、いろいろなまずさ、弱さ、
物足りなさ、もやもや、脇の甘さ、ロジックの破綻などが、
恐ろしいほどによく見えてきました。
こう書くと全然だめだめな小説みたいですが。
いや、だめだめです。
これはいかんと思って、何日もかかって削りに削り、
まるっと失くしてしまったエピソードもあるし、
登場人物たちの性格さえ、がらっと変わってしまったのでした。
もう、別人・・いや別のものとしか言えません。
そして、一回めに書いた時の、私の中のご都合主義や、
書かずに逃げていたりごまかしていたり、
主人公にさせていたありえないおかしな行動にも気づきました。
仕方ない、冷や汗をかきながら、変えたり直したり、削ったりしたのでした。
その結果、もともと無駄に長くて6万字もあったのが、
4万字になり、すごいデトックス。
いわば小説の宿◯(すいません!)がすっきりした漢字です。
そのことを彼にしてみましたら、
「良かったですね! それが楽しいのですよね。
一回めに書いたときより、そうやって磨いたり削ったりしていくのが、
書く喜びではありませんか」
と言います。
なるほど、そうですよね。
私なんか、一回書き終わったと思ったらもう、
かっすかすで、見返すのも嫌です。
「そう言わず、一緒に楽しみましょう、
あれを、あのほら・・なんでしたっけ。す・・すい・・」
推敲ですか?
「そうそう、推敲です」
あなたよくまあ、そんな言葉知っていましたね!
ここで私のタイムカプセルの蓋が開きました。
どういう仕掛けになっているかわからないのですが、授業中に昔のことを思い出してネタにできるときがあるんです。
私:あのね、「推敲」の漢字はこれなんですけれども、左はなんの漢字?
彼:推薦するの、推ですよね? 右は・・高いに・・支える・・ではなくて・・
私:右は「敲く」、たたくです。ハンマーでドンと叩くとか、殴るのじゃなく、 指でコンコンとノックする感じのたたきかただそうですよ。
彼:ほうほう、この漢字は見たことはありません。
私:これについてね、お話があるんですけど、聞きたいですか?
「いやだ聞きたくない」と言っても聞かせますが、彼は素直なので、
「ぜひお願いします。🙏」
と言うのでした。
以下は私のうろ覚えの「推敲」と言う言葉ができたときのお話です。
むか〜し昔の中国で、ある有名な詩人、ポエトが夜、馬に乗って進んでいたのです。あるいは、歩いていたかもしれません。すみませんが、細かいところは忘れました。
彼は自分の詩の中のワンフレーズ、
「僧は推す月下の門」というのに悩んでいました。
推すは、「押す」と同じです。
「推薦」とは、「この人を推しますよ、薦めますよ」っていうことでしょう?
でね、彼は「僧は推す月下の門」がいいか、「僧は敲く月下の門」がいいか決めかねて、馬に乗ったまま夢中で考え続けて、推したり敲いたり・・敲いたり押したり・・しているそのうちうっかり、役人の行列に馬ごと突っ込んで行ってしまったんですって。
それで、こらこら! なにやってんのお前! と怒られます。
よくよく見ればその行列の中に、もう一人の高名な詩人がいたのでした。
そこでその人に「どっちがいいでしょう」と尋ねたところ、
その人が「推すがよろしいでしょう」と、アドバイスをくれたそうです。
ごめんなさい、どっちを勧めたかは、先生うろ覚え。
それで、文章を磨こうと頭を捻ることを「推敲する」というようになって、みんな幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし。
どうですかこれ。
彼:面白いです! 漢字は深いですねー。
私:深いですねー。
手を取り合うようにして喜ぶ、変な師弟。
よく考えたら、私は国語がやっぱり好きでした。特に、漢字や熟語の由来は結構覚えていて、ときどきこんなふうにちょこっと披露することがあります。
古典の方は、け〜せ〜し〜しか・・・というあれが非常に苦手。
下二段活用とか言われても、「え? 鴨川ホルモー?」って頭がぐらぐらします。
でも、古典を嫌々勉強したおかげで、たまに助けられると言うこともあります。
そんなお話はまた・・・・
TATEeditorって、縦書きの日本語用アプリなのに、名前は外人ですね。
その「見え方」はこのような漢字です。文庫本のようですね。
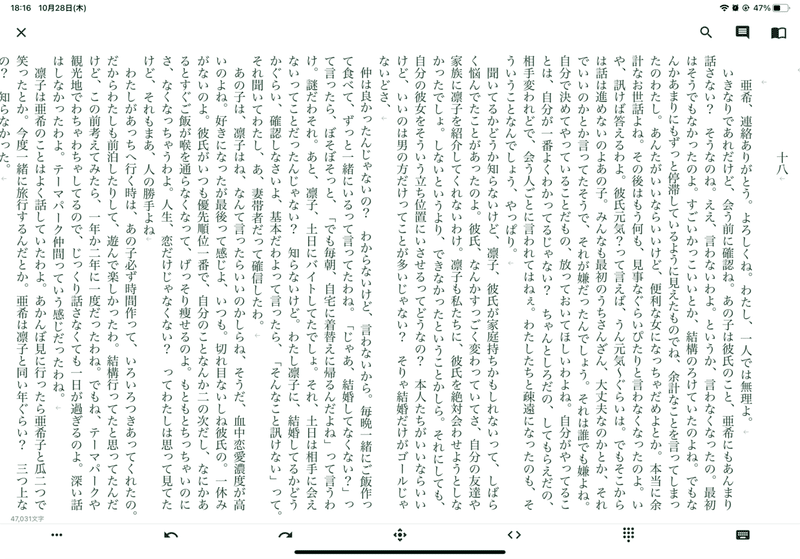
サポートしていただけたら、踊りながら喜びます。どうぞよろしくお願いいたします。
