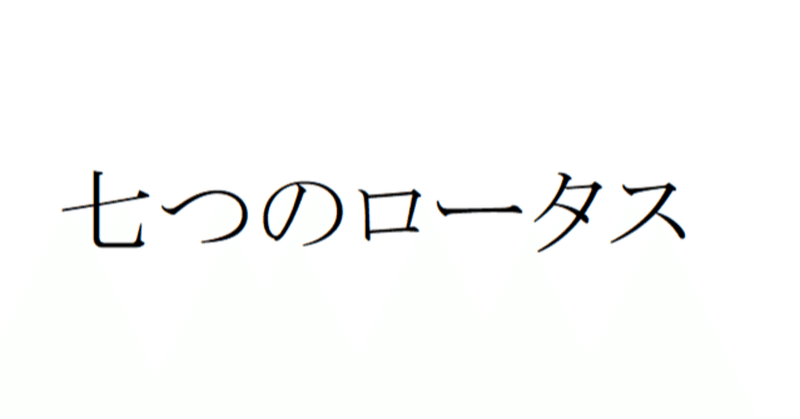
七つのロータス第7章 イッポ
朝日が昇り、前日の戦いの後始末がようやく終わったばかりの城内を照らし始める頃、サッラ城外を囲む敵に新たな動きが起こっていた。頭上に盾をかざした兵士たちの一団が、城壁に取りつき日干し煉瓦の城壁を崩し始めたのだ。大槌、鑿、鉄棒、鍬などが次々に城壁に叩きこまれる。城壁の上からは、矢、投槍、煉瓦や大石などが降り注ぐが、いくらか損害を出しながらも、城壁に穴を穿つ勢いは止まりそうになかった。
「まずいな」
報告を受けたゾラは一言呟いたきり、黙って座り込んだまま動かなかった。サッラの市街を巡る城壁は、堅く突き固めた土盛りを日干し煉瓦と焼き煉瓦で覆ったものである。分厚い土盛りの中には幾重にも障害物が埋めこんであるとはいえ、時間さえかければ決して掘り抜くことは不可能ではない。問題はその時間だ。帝国からの援軍の到着と、どちらが早いか。アルタスが発って以降の帝都の情勢はまったく伝わってこない。アルタスの出立後、すぐに帝国軍が派遣されたのなら、徒歩の兵士中心の帝国軍といえども、もう何日もかからずに到着するだろう。しかし援軍が派遣されてくるという保証はなにもない。
宙の一点を見つめたまま瞬きもしない族長を、幕僚たちもまた息を殺して見守っている。その緊張感に耐えられなくなったのは、最も歳若いアルタスだった。
「何を迷う事があるのです!」
新参の騎兵隊長は、族長の前に進み出た。
「ここでいつまでぐずぐずしているのですか!城壁に守られた中では、騎兵の本領は発揮できません。このまま騎兵を温存したままで城壁を突破されたら、二度とサッラ騎兵の出番はありません!武勲を謡われ、最強を称えられ、世にその名を轟かすサッラ騎兵が戦わずして敗れる。これほど愚かなことがありましょうか!」
アルタスは居並ぶ騎兵隊長たちを見まわし、なおも続けた。
「本来先頭に立って戦うべき我ら戦士階級が見物を決めこんでいる間に、城壁を守る兵士たちが数多く倒れました。一生涯、武器を手に取る事もなかったかもしれない市民階級の人々が、われわれ戦士階級以上に勇敢に戦ったのです。これ以上、我々がぼんやり時を過ごすことは許されません。先頭に立って戦うのでなければ、戦士階級の存在意義がどこにあるというのですか!」
ゾラは厳めしい顔つきを一瞬も崩すことなく、内心ではほくそ笑んでいた。騎兵隊長たちの間に流れる空気が変わったのだ。しかし…。
「もうよい、下がれ」
ゾラは不機嫌な声、不機嫌な顔つきで唸る様に言った。
「しかし…」
「下がれと言っておる!」
アルタスはしばし沈黙し、諦めて引き下がった。言いたい事はまだあったし、なにが父親の気分を害したのかまったくわからなかったのだ。
「お前の言いたい事はよくわかる。だが、我々が何の為に戦っているのかを忘れてはならぬぞ。そう、お前の言った通り、城壁の歩兵は良く戦っておる。だが彼等は、名誉を得んがために戦っておると思うか?サッラの市民兵は騎兵に負けぬ、と世間に示すために戦っておるのか?」
射抜くような視線がアルタスに向けられている。若武者は言葉を発することもできず、立ち尽くしていた。
「わかるな。彼等はサッラの為、いや、自らが生きんが為に戦っておるのだ。決して名誉のためではない。彼等がそのように勇敢に戦っているのならなおのこと、我等騎兵の責任は重くなるのだ。ただ死後の名誉を追い求めて、華々しく討ち死にする。このような身勝手は許されない。いつ騎兵を出すかは、感傷ではなく、冷静な判断によってなされねばならない」
ゾラは一同を見まわした。父親が息子を諌めるために発した言葉が、他の隊長たちに与えた効果を見定めたかった。一度かきたてられた戦意を押さえこまれて、引き絞った弓のようになっていれば成功。せっかく燃えあがった炎に冷や水を浴びせてしまったのなら失敗だ。
周囲は何とも言えぬ重苦しさに包まれている。騎士たちの固く食い縛った口元には、戦への情熱が押し込められている。
「とは言え、城外の状況は放置を許されないものだ。いつ来るか、いや、そもそも来るのかどうかも定かではない帝国軍をあてにすることも愚かであろう。しかし城外の敵は多い。騎兵を出したとて、敵が城壁を掘りぬこうとしている地点まで行きつけるかどうかも怪しい」
歴戦の騎兵隊長たちまでが、恥辱に乱れた心をあからさまにしていた。あるものは険しい顔で空を睨み、あるものは顔を紅潮させ、またあるものはしきりに脚を踏み変えている。良い具合に仕上がった。あとは最後の指示を与えるのみだ。
「イッポ!」
ゾラは年齢的には中堅ながら、過去の戦いの中で際立った冷静さを見せていた騎兵隊長の名を呼んだ。
「貴様に全体の指揮を任す」
騎士は一歩前に進み出ながら、思わぬ抜擢に顔をほころばせた。
族長は次々、攻撃に参加させる隊長の名を呼んだ。騎兵隊長たちの半分が、中央に進み出る。ゾラはサッラの全騎兵の半数、五百騎を投入するつもりだということだ。
「目標は無論、城壁に穴を穿つ敵を阻止すること。だが蛮勇を奮う事は許さん。敵の抵抗によっては諦めて戻るように。最優先させるべきは一騎も失わずに戻ることだ。幾万の敵の中で、味方は僅かである事を忘れるな」
ゾラはそこまで言って、声と表情を少しだけ和らげた。
「頼りにしているぞ」
出撃する隊長たちは、大きく頷く。そして自らの率いる部隊の元へと、天幕を駆け足で出ていった。
天幕の中にはゾラと、半数の騎兵隊長が残っている。その中には族長の嫡子であるアルタスの姿もあった。青白い顔で地に視線を向ける息子に族長は目を向けるが、視線がぶつかることはない。
「大切な戦士を、猪武者に預けるわけにはいかぬ」
身動き一つせずに立ち尽くすアルタスの前を通り過ぎざま、ゾラは呟いた。こいつはもう少し飢えさせておくのがよかろう。含み笑いが顔に浮かびそうになるの をこらえながら、木枠から垂れ下がる重い獣皮のおおいを押しのけて天幕の外へ歩を進める。中天に昇った太陽が容赦無く照りつけて目が痛かった。
城門が開け放たれ、イッポに率いられた五百騎の騎兵が飛び出してゆく。それに続く弓兵や投石兵が騎兵を援護し、武器を使い尽くしてから退却する。開け放たれたままの城門の後には、長槍を構えた歩兵の密集方陣が敵を待ち構えているが、二度に渡って落とし戸の威力を見せつけられた敵は、近寄ろうともしなかっ た。
通常の騎槍の他に短弓も持つ重装備で出撃したイッポ率いるサッラ騎兵は、城壁に沿って全速力で駆けた。敵は城壁の上から矢が届く距離には布陣していなかったので、城壁自体を攻撃している敵の一群まで、無人の通路が開けている。城壁から離れて待機していた敵が、まるで草原を食い尽くす飛蝗の群れのような勢いで押し寄せてきた。歩兵も騎兵も一群となって向かってくる敵を、最初は矢で、続いて槍に持ち替えて打ちのめす。城壁に向かってくるかたちの敵に対して、城壁の上からも矢が降り注いだ。
イッポを先頭に馬の肩と肩が触れ合うほど固く身を寄せ合ったまま、一団となった騎兵隊は進んだ。この騎兵隊を阻止しようと、前方に割り込んでくる敵を、 突き刺し、弾き飛ばし、時には蹄で踏みにじって進む。しかし打ち倒しても打ち倒しても前に立ち塞がる敵に、遂に手綱を引き絞らざるを得なくなった。勢いを殺された騎兵隊はそれでも密集したまま、矢で槍で手当たり次第に近寄る敵を倒した。
必死で戦うイッポの耳に、甲高い銅鑼の音が届いた。城壁に穴を掘っていた敵が逃げ去ってしまったことを知らせる合図だ。イッポの頭の中を幾つかの思考が駆け巡る。自分たちがここにいる限り、敵は穴掘りを再開できない。とはいえ前を塞がれて進めなくなった部隊は敵に取り囲まれつつある。歩兵をただの一人も従えていない騎兵隊が、立ち止まってしまえば、後は取り囲まれて倒されるだけである。イッポの思いがそのまま具現化したように、麾下の一騎が倒れた。素早く目をやると、腹部を切り裂かれた馬が、横たわったまま狂った様に四肢をばたつかせている。傷口からはらわたがはみ出しているのが、無残だ。馬から投げ出された兵士は、その側らで立ちあがるところだった。どうやら大きな怪我はしていないらしい。
「退却だ!」
密集した上に敵に取り囲まれている部隊は、馬を動かす場所の狭さに苦労しながらも、向きを変えた。方向転換で先頭に変わった兵士たちは、比較的手薄だった後方を早くも突破して、城門への道を進み始めている。殿を務める覚悟で、もう一度周囲を見回す。城壁の上からも、戦場をよく見てくれていたのだろう、縄梯子が降ろされ、下馬した兵士はそれにしがみついて城壁の上に引き上げられようとしている。その兵士の周囲には次々と矢が飛んできてはいるのだが、これ以上は心配したとて仕方のない話だ。向きを変え、再び勢い良く駆けることのできるようになった騎兵隊は、敵を振り切りはじめていた。退却が順調に進み始めているのを見届け、イッポも両脚で馬の脇腹を叩く。前方には既に、全速力で馬を進めることができるだけの空間が開けていた。
もしサポートいただけたら、創作のモチベーションになります。 よろしくお願いいたします。
