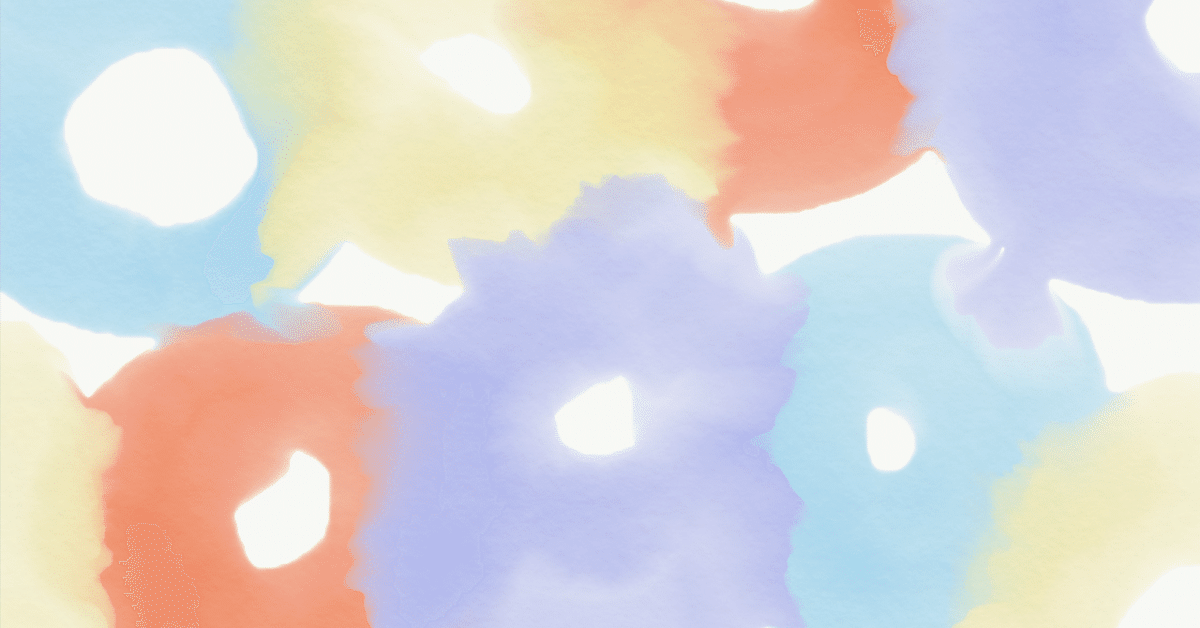
「街に救われる」という感覚
私には、「街に救われた」という感覚がある。
6年前、谷中の街に引っ越してきた。
物件探しには、なぜか友人だけでなく、
知らない赤ちゃん連れの家族がついて来て、あれこれ教えてくれた。
家具を運ぶのに、婦人会の方が台車を貸してくれて、
数回会っただけの藝大生が手伝ってくれた。
道端でばったり会ったよく行くカフェのママに、
「焼肉行くよ!」と連れて行かれたこともあった。
私のことを何も知らなかったはずの人たちが、すごく優しかった。
たくさん話した昔からの友人もいるし、
ほんの少し話しただけの人もいるけれど、
弱っていた私には学生から70代くらいまで、
いろんな人の優しさがじんわりと心に染み渡った。
カフェ、銭湯、コインランドリー。
あちこちにあるお寺。
ちゃんと暗くなる夜。
いつも同じところにいる猫。
夕焼けや朝日がよく見える、広い空。
仕事でどんなに疲れていても、
最寄りの駅に着くと「帰ってきた」とホッとしていた。
弱っていたから、そう見えたのかもしれない。
けど、
人もお店も景色も含めて、
「街に受け入れられている」という感覚があった。
あれから6年。
私はここで子育てをしている。
「ママ、ママ!!」と手を繋いで歩く我が子も、
きっと徐々に自分だけの世界を広げ始める。
辛い、苦しいことがあった時、
子ども達は、この街に救われるだろうか。
「子育てしやすい街」という大人目線ではない、
「子どもが、子どもとして生きやすい街」とは何かを考える。
教育に携わっていると、ICT、プログラミング、道徳、探求など、
〇〇学習という言葉たちに溺れそうになるけれど、
「あなたは、あなたのままでいいんだよ。」
というメッセージがその子の育つ環境にあるかどうかが、
大前提としてすごく重要だと思っている。
そして、それを家庭内だけに任せるのはとても難しい。
学校も含めて、街全体で
子どもも大人も「ゆるやかに受け入れる」ことができたらなと思う。
