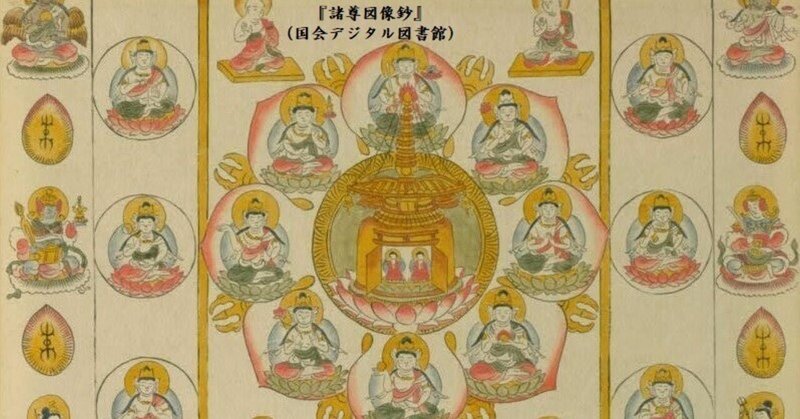
木を見て森を見ず?~個々に視点を当てる多福禅師~
多福禅師の対話
臨済宗・釈宗演上人の講話録『禅海一瀾講話』を拝読していたところ、禅僧・多福禅師の問答が載っており非常に感銘を受けた。
その問答が以下である、
僧あり多福に問う、如何なるか多福一叢の竹。福曰く、一茎両茎斜めなり。僧曰く、会せず。福曰く、三茎四茎曲れり。
そのまま訳すと以下のような対話になる、
ある僧が多福禅師に、
「多福禅師のところに集まって生えている竹はどういうものですか?」
多福禅師は云う、
「一本あるいは二本が斜めに生えていたりする」
その返答を受けてその僧は、
「よくわかりません」
さらに多福禅師は続けて云う、
「三本あるいは四本が曲がって生えている」
直訳すれば上記のような対話になるが、本当は多福禅師の云いたいことは植物としての竹のことを云っているのではない。多福禅師が住持する寺院の有り様における問答である。
理釈と事釈(仏教書の読み方)
経典にしても語録にしても仏教書の解釈には事理の両側面から考える必要があり、特に理に重きを置いて仏書は読む必要がある。
釈宗演上人云わく、
総て経文の解釈には、事釈とて事実の上の解釈と、観心釈といって、精神的に我が心を主として解釈する、という二通りの方法がある
理釈というは道義的解釈である。事釈というのは事実的解釈である。この言葉も初めから幾度か繰り返してお話し致している。その事釈、理釈と仮りに二つの解釈はあるが、なかんずく、我々のいま重きをおくところは理釈すなわち精神的に始終眺めるので、事実は第二である。
宗演上人は事実的解釈も大事だがそれは二義的で、仏教は道義的解釈を重んじて経典を読むことが重要であるとおっしゃる。
理釈(観心釈)から対話を読む
宗演上人の説示から多福禅師の対話は理釈、即ち観心釈から読む必要がある。
つまり、上記の対話は、
ある僧が多福禅師に、
「多福禅師の住持する叢林(禅林)はいかなる所ですか」
多福禅師は云う、
「ここに所属する僧たちのうちには邪見に囚われている者が一人あるいは二人いたりする」
その返答を受けてその僧は、
「それだけではこの叢林の特色がわかりかねます」
さらに多福禅師は続けて云う、
「またここには機根の勝れた者が三人あるいは四人いたりする」
私訳するとこのような対話になろうかと思う。多福禅師の観点が素晴らしい。大抵、寺院などを訪れた際にそこの住持なり所属僧侶などにどのような寺院か尋ねると、その歴史であったり歴代住持の徳を聞くことが多いが、多福禅師は全く違う。
多福禅師は、わが寺院にはまだまだ真理に暗い邪見の抜けない凡夫の僧もいれば上機のずば抜けた覚者の僧もいるとして、現在の寺院の有り様、特に所属する僧たちの有り様そのことが叢林を顕しているということであろうか。
禅師が所属僧侶たち一人一人の境地や性格をよく観察していることが見て取れる。
森を見ずして木を見る
多福禅師から全体を構成するのは個々であり、個々をよく見ることで全体が解かるから、個々の個性や性格などを観察することの大切さを説いておられるように思う。言い換えるならば、森を見ずして木を見るということであろう。無論、これは管見の域を出ない解釈であり、また私の信仰が浄土門であるからして、禅門については門外漢である。したがって大いに間違っているかもしれないが、多福禅師から感銘を受けた自分の信仰上の事実をここに示したまでである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
