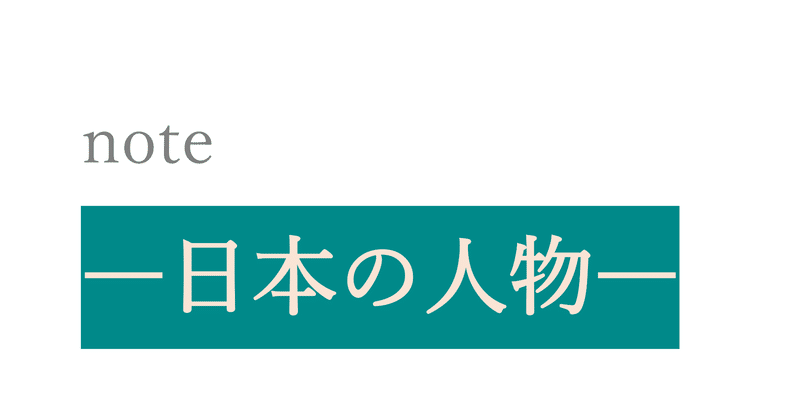
《大学入学共通テスト倫理》のための安藤昌益
大学入学共通テストの倫理科目のために歴史的偉人・宗教家・学者を一人ずつ簡単にまとめています。安藤昌益(?~1762)。キーワード:「万人直耕」「自然世」「土活真(どかつしん)」「互性(ごせい)」主著『自然真営道(しぜんしんえいどう)』『統道真伝(とうどうしんでん)』
安藤昌益といえば

江戸時代中期の、農業を国の根幹に据える「農本主義」の思想家です。肖像がなく、画像は農業を彷彿させるものにしてみました。この、肖像がないことでもうかがえますが、昌益は当時ほとんど無名の思想家です。年表的な不明点が現在も残っています。発掘された主著の稿本(原稿版)『自然真営道』も関東大震災でほとんどが焼失。しかし、熱心な研究者たちの研究によってその思想の姿が明らかにされています。
📝まず、安藤昌益は支配というものを否定します!
支配者としてふるまい、働きもせずに他人のものを盗み取る収奪者が増え、この世に争乱の根が絶えないのだ。
上ニ立チ、不耕盗食ノ者世ニ多ク、乱ノ根絶ユルコト無シ。
(『安藤昌益全集 一』(寺尾五郎代表・東均・石渡博明・泉博幸・新谷正道・和田耕作編集・執筆、農文協)から引用)
「不耕(耕さない)」=「盗食(盗んで食う)」という立場で、支配層が存在すること自体を批判しています。
📝昌益が肯定したのは、自然の営みと自然と共に生きる農の営みです!
道は、天地が万物を生成する道と、農民が耕して穀物を生産する道と、天下にただ一道あるのみである。法は、聖人・賢人がよこしまな意識によって作り上げたものであり、いろいろあるがすべて誤りである。
道ハ、転定ノ万物ヲ生ズル道ト、衆人ノ直耕シテ五穀生ズル道ト、転下ニ只一道ナリ。法ハ、聖賢・利己ノ私作、区品ノ妄失ナリ。
(『安藤昌益全集 四』(寺尾五郎代表・東均・石渡博明・泉博幸・新谷正道・和田耕作編集・執筆、農文協)から引用)
これが昌益の「万人直耕(ばんにんちょっこう⇒全ての人が農業を営み自給自足の生活をすること)」。万物を生成する道に沿うて、農業を営むことが人間の道である。こんな風に世界を理解して、全ての人間が農業を行う理想社会を描いています。ところで、これまでの支配を「妄失/誤り」とサクッと断定するところにアナーキーな魅力があります。
往古自然世ニハ人人無欲ニシテ男ハ耕シ女ハ織リ、穀精満テ交合ノ念起レバ夫婦合シテ子ヲ生ズ。(『安藤昌益全集 十五』(寺尾五郎代表・東均・石渡博明・泉博幸・新谷正道・和田耕作編集・執筆、農文協)から引用、ただしルビは全て略した)
「太古の自然の世界では人々は無欲で男は耕し女は機を織り、穀物の精気が満ちて交合する念が起これば夫婦はそうして子をもうけた。」が拙訳。そしてこれが安藤昌益の「自然世」。「支配」のない、古代にある想定の理想社会を思い描いています。意外と理想として共有できるイメージです。
📝昌益の「支配的なもの」を拒否する情熱はすごいです!
いっさいの文字は、支配者である聖人が勝手にでっちあげたもので、これを書物だ学問だともったいぶり、その知識を独占して上に立ち、下を教えるなどとして私欲にもとづく制度をこしらえ、みずからは働きもせずに他人の生産物を貪り食い、生産活動(直耕)という自然の法則を私物化し、世の中に搾取と争乱の根を植えつけておきながら、社会を治めるなどとほざいている。これ以後永い間、搾取と争乱の絶えない世が続いてきた。
一切ノ文字ハ、己レガ得手勝手ニ私作シ、書学ト為シ、之レヲ以テ上ニ立チ、直耕ノ転道ヲ盗ミ、盗乱ノ根ヲ植ユルヲ、転下ノ治ムルト為ス。是レヨリ永永・盗乱ノ世ト成ル。
(『安藤昌益全集 一』(寺尾五郎代表・東均・石渡博明・泉博幸・新谷正道・和田耕作編集・執筆、農文協)から引用、ただしルビは全て略した)
こんな風に、上下を生む対象と意識されれば、「文字」さえもラジカルに否定していきます。別の箇所では現行の支配体制に寄与しているような儒学神道仏教たちもばっさり否定。また、「天」を変化するものとして「転」と書いたりする既成の文字への抵抗も魅力的です。
📝昌益は世界を上下のない「ひとつ」と捉えました!

これは安藤昌益ととくに関係ない稲の家紋の画像です。ただ、生成の運動がひとつにまとめあげられるような安藤昌益の世界観に似合います。以下でそれをチェックしていきましょう!
運動は一瞬たりとも停止することなく、万物を次々と生み育て、尽きることがない。これこそ、根源的な物質である土活真の宇宙的規模での生産活動(直耕)であり、また万物の存在法則でもあると言えよう。
運回一息止ムコト無シ。万物、生生無尽、是レ活真・転定ノ直耕ナリ。
(『安藤昌益全集 一』(寺尾五郎代表・東均・石渡博明・泉博幸・新谷正道・和田耕作編集・執筆、農文協)から引用、ただしルビは全て略した)
だいぶダイナミックな世界観です。何かを生み出しつづける世界の肯定の運動と、それを受け継ぐ人間の世界の運動が「農」ということになります。省略しますが、安藤昌益の世界観は、当時の代表的な世界観の五行思想の新解釈として述べられているので、ある人にとっては宗教的すぎたり、また別の人にとっては形式的すぎたりと感じることもあるでしょう。
📝「ひとつ」の世界の運動の中心にあるのは「土」です!
「活真」とは何か。その実体である「土」と、天と海の中央にある大地であり、その精である「土真」は(略)活き活きと気を産みだし永遠の活動をつづけ、停止も死滅することがない。
活真トハ、土ハ転定ノ央ニシテ、土真は(略)活活然トシテ無始無終、常ニ感行シテ止死ヲ知ラズ。
(『安藤昌益全集 一』(寺尾五郎代表・東均・石渡博明・泉博幸・新谷正道・和田耕作編集・執筆、農文協)から引用、ただしルビは全て略した)
これが安藤昌益の「土活真」です。「土」を天地の交わる中央と位置づけ、そこに生成のエネルギーが内蔵されていると論じています。つまり、「直耕」は何かを生むだけでなく、天地の中央から何かを生む価値ある行為であることになります。
「互性」とは何か。言ってみれば、「土活真」という根源的物質の始めも終りもない永遠の自己運動
互性トハ何ゾ。曰ク、無始無終ナル土活真ノ自行
(『安藤昌益全集 一』(寺尾五郎代表・東均・石渡博明・泉博幸・新谷正道・和田耕作編集・執筆、農文協)から引用、ただしルビは全て略した)
そしてこれが「土活真」の「互性」。対立するものが実は相互的に関わっておりその関係の運動からものが生じるイメージです。昌益にとっては、天地の間の、男女の仲の、生死の裡の営みは全て、この「互性」から生まれます。
📝東洋的世界観から繰り出された、平等の言説がまぶしいです!
転定ハ二別無ク、男女・一人ナルハ備ハリナリ。故ニ万人ニアラズ、一人ナリ。一人ナル故ニ上下ヲ指ス所無し。(『安藤昌益全集 一』(寺尾五郎代表・東均・石渡博明・泉博幸・新谷正道・和田耕作編集・執筆、農文協)から引用)
「天地は二つの分別は無く、男女が一人であるのは則である。故に万人ではない、一人なのである。一人である故に上下を区別する所などない」が拙訳(出典の現代語訳を参考に短縮しました)。封建時代に人間に上下などないと言い切り、衆人と聖人の差別も否定した思考の強靭さには瞠目します。
📝最後に、思想家の昌益の本業は町医者でした!
先頃病気にて御町医安藤昌益に療治申し付け、快気仕り候に付き、薬礼として金百疋、昌益へ差し出し候処、上より仰せ付けられ候儀故、受納仕らぬ(『安藤昌益全集 十六下』(寺尾五郎代表・東均・石渡博明・泉博幸・新谷正道・和田耕作編集・執筆、農文協)から引用、ただしルビは全て略した)
「先頃病気で町医者安藤昌益氏に療治を依頼し、回復したので、医療費として金一分、昌益へ差し出し申し上げたところ、上から仰せつけられたという理由で、受け取らない」が拙訳。これは当時昌益が藩人の診察を依頼した藩の日記です。当時としてエキセントリックな思想をつむぐ背景に、医師として一人一人のいのちを平等に治す態度と、優秀な東洋医学の医師として自然と人体を貫く法則を感じていたことが大きいでしょう!
後は小ネタを!
安藤昌益の『自然真営道』や『統道真伝』は問答形式の書物ではないが、ときどき「昌益の説を批判してすぐに言い負かされる」負け役が登場する。「返答に窮して泣きながら去った」など、退場のしかたも役目に忠実である。生き生きとして、時に過激に、時にユーモラスにも感じさせる記述が昌益の文章の魅力なので、このまとめでは、それを全然再現しなくて申し訳ないところです。
外交官で歴史家のハーバート・ノーマンは安藤昌益を「明治以前の日本の思想家の中で、封建支配を完膚ないまでに攻撃した唯一の人」と評した。自明だった《世界》を問いつめて、思考の強度をいまも感じる存在が安藤昌益です。この強度を「早すぎたマルクス主義者」や「世界初のエコロジスト」や「世界を百科全書的に記述しようとした学者」などなど、安藤昌益のポテンシャルを受け止めるための研究者による読解が現在も活発に継続しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
