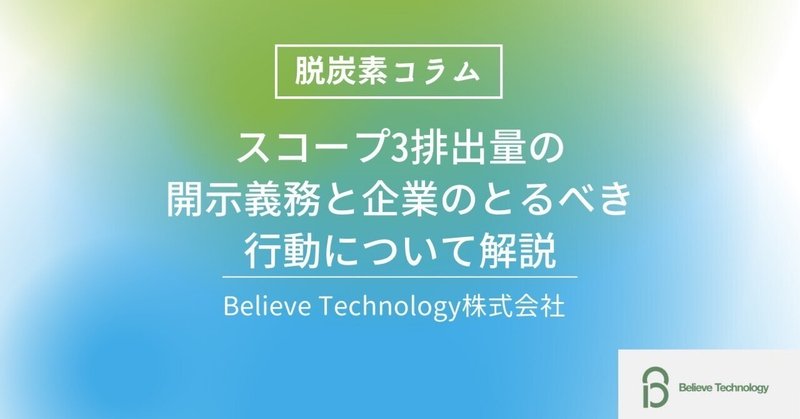
スコープ3排出量の開示義務と企業のとるべき行動について解説
2023年6月26日、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)は国際会計基準(IFRS)によるS1とS2基準を公表しました。これにより企業のサステナビリティや気候変動リスクや機会についての開示を明確に行う必要性が生じます。予定では2026年3月期から義務化がされる見通しです。しかし
「開示義務というものはどういったものなのか?」
「それに応じて企業はどのような対応を取るべきなのか?」
このような疑問を抱えていませんか?特にこれまでサステナビリティ、温室効果ガスの排出量の算定をどのようにすれば良いのかと迷われている方には更に大変な作業が増えるのでは?と思われると思います。
本記事では、今回、公表された開示内容の詳細及び今後企業が取り組まねばならない対応について解説していきます。
ISSBと新サステナビリティ開示基準の目的

冒頭で紹介したISSBとは2021年11月にイギリスで開催されたCOP26にて設立された組織です。
・ISSBの目的
投資家及び他の資本市場参加者の十分な情報に基づく意思決定を支援する為、
企業のサステナビリティに関連するリスク及び機会に関する情報を提供する。開示基準の包括的なグローバル・ベースラインを提供する
ISSBは財務情報の国際基準を策定している機関ですが、世界のサステナビリティや温室効果ガスの与える影響の大きさからESG情報についても世界基準となるように活動しております。
しかし、ESG情報開示は必要という一方で、開示基準の乱立及び国ごとの慣習や法律の違いによる差が存在し、企業評価を行う投資家や開示をする企業の負担も大きいものです。そこでこれら双方の問題を解決するためにESG情報の基準を明確に定め企業を応援する投資家が安心して意思決定できる環境を整え国際的にESG情報開示の質を向上させようと期待されており、その為に大きく2つ「IFRS(S1)」と「IFRS(S2)」の2つの開示基準の策定を行っております。
サステナビリティ開示基準の内容と影響

■S1基準とは
IFRSサステナビリティ開示基準の一般原則定める基準
・投資家の情報ニーズを満たす為、重要性のあるサステナビリティ関連のリスクと機会の開示
・TFCD提言を取り入れ、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標&目標の4つのコアとなる要素に基づく開示
S1基準はその名の通り、IFRSサステナビリティ開示基準の原則です。上記のように投資家の情報ニーズを満たす重要性のあるサステナビリティ関連のリスクと機会を開示していることがポイントです。すなわち、S2という個別の基準が存在する気候変動に限らず、企業にとって重要性のあるその他のサステナビリティ項目があるならば、例えば生物多様性、人的資本、人権といった開示も要求されます。また、TCFD提言で4つのコアについても開示が求められております。
■S2基準とは
FRSサステナビリティ開示基準のテーマ別基準で気候変動に関する情報開示を定める基準
・一般目的財務報告、利用者の投資意思決定に有用な気候関連のリスクと機会に関する情報を開示する事
・TFCDの4つの要素(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標&目標)に基づく開示を要求
S2基準の目的は投資意思決定に有用な気候関連のリスクと機会に関する情報開示を企業に要求することです。投資意思決定に有用であるとされる短期・中期または長期にわたり企業のキャッシュフロー、資金調達、資本コストに影響を及ぼすと合理的に予想されるものをさします。S1基準にもある4つのコアとなる要素が要求されます。
企業に求められるスコープ3排出量の開示

S1とS2の基準により企業は新たに温室効果ガスにおける「スコープ3」までの開示が求められます。自社で燃料の燃焼や電気の使用等の直接的・間接的排出量である「スコープ1」「スコープ2」だけでなく、原材料調達から輸送、製品の使用、破棄までのバリューチェーン全般にわたる排出量が含まれます。また金融機関の投融資先企業のスコープ3も含まれます。その為多くの企業様がスコープ3の開示の為に算定をする動きがございます。
ー事例1:ロート製薬株式会社
プライム市場への移行をきっかけに情報開示の必要性を感じられておりました。そこで2022年よりスコープ123の算定を行い、開示を行うとともにロート製薬様全体で脱炭素に向けて主要なグループ会社を含めた形で実態はあくまで行おうとしております。
詳細はこちら
ー事例2:日本ピラー工業株式会社
会社全体でESGやサステナビリティといった取り組みの拡大に動かれており、既にスコープ1とスコープ2までは自社で行われておりました。2022年からは多岐にわたる取引先までを算定すべくスコープ3にも着手。今後更なるCO2削減に向けた取り組みを本格化されようとしています。
ISSB基準の導入と日本における展望

日本では、ISSBと連携しながら、日本版のサステナビリティ開示基準を開発しています。2024年3月に公開草案を、2025年3月には最終基準の制定を目指しています。これらの日本版基準は、ISSB基準と同様に、国内企業に対して一貫性のあるサステナビリティ情報の提供を促すことを目的としています。特に、有価証券報告書におけるサステナビリティ情報の記載が拡大し、情報の保証が義務化される可能性があるなど、企業にとっては新たな報告要件が設定されることになります。
さらに、日本の企業は2026年3月期の有価証券報告書からISSB基準に基づく開示を開始する可能性があります。これにより、国際的な投資家とのコミュニケーションが強化され、グローバルな資本市場での企業の信頼性と競争力が高まることが期待されます。
お問い合わせ
ISSB基準の導入とSSBJの動向は、日本企業にとっては新たなチャレンジですが、これによりサステナビリティへのコミットメントを世界に示し、持続可能なビジネスの実践を加速させる大きなチャンスとなります。日本企業もこの変化に対応し、グローバルな基準に沿ったサステナビリティ情報を提供することで、国内外の投資家に対してより信頼される存在となることが期待されています。また何か分からない点があれば問い合わせフォームよりご連絡ください。
参考
https://www.youtube.com/watch?v=woF1QEWhJLY
参考
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/news/2023/issb-standards-launch-
参考
https://www.asb.or.jp/jp/ifrs/press_release_ssbj/y2023/2023-0626.html
参考
https://earthene.com/media/1450
