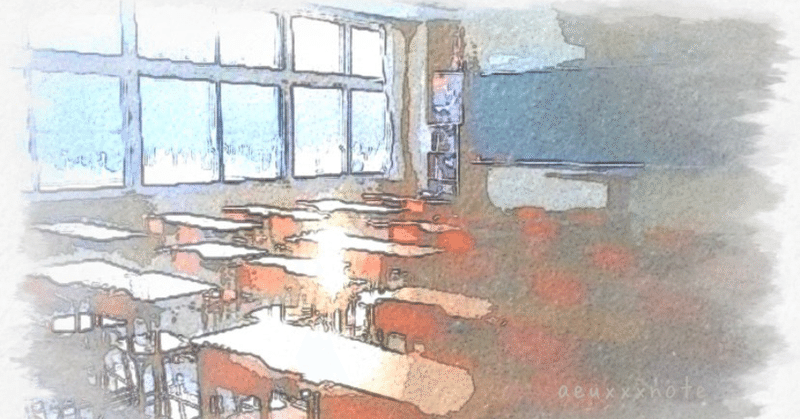
【掌編小説】チョコレート#シロクマ文芸部
(読了目安4分/約2900字+α)
チョコレート。チョコレート。チョコレート。
ピンク色に飾られた会場には、右も左もカラフルな包装をされたチョコレートが並んでいる。プレゼントの山でつくられた迷路を、所狭しと女たちが歩き回る。艶々と輝く髪を結い、口紅と頬をピンクに色付け、甲高い声できゃあきゃあと笑う。
私は思わず眉をしかめ、通路をふさぐようにして話している女たちに背をぶつけてすり抜ける。ツンとした香水か、ヘアオイルの匂いがする。
入口で手に取った正方形の箱を二つ、迷路の出口のカウンターへ置く。緑色のタータンチェックで、ダークチョコレートが四つ入って八百円。二つで千六百円。これくらいが丁度良い。
「ご自宅用ですか? じゃなかった、小分けの袋はゴイリヨウですか?」
金髪に染めた大学生のバイトみたいな女だ。自分の言い間違いに笑いながら訊いてくる。私はかろうじて「いえ」と声を発して、小刻みに首を横に振った。後ろの方でキャハッと笑う声が聞こえる。これだからこういうところは嫌いだ。
以降は無言で会計を終わらせる。真っ黒いジャージにコートのフードを被り、人目につかないようにまっすぐに家に帰る。
ご自宅用ですか、だって? 私が自分のためにこんな不快な場所に来るとでも思うのか?
イライラする。やはりコンビニでポッキーでもブラックサンダーでも買えば良かった。
自室の机に箱を投げ出し、ベッドに倒れ込む。行成はどういう反応を示すだろう。そもそもチョコレートは好まないとか言い出す可能性もある。それこそ今日も「手作りのチョコレートは本来そのまま食べた方が美味しいチョコレートをあえて溶かして雑味を生み出し劣化させているのだ」と話していた。そもそもバレンタインデーというものをどう思っているのだろう。
私は女らしさが嫌いだ。両親は一人っ子の私を愛美と名付け、ものごころもつかないうちから、フリルの付いた服やらリボンやらをつけさせられた。中学校に上がるとき、両親を説得し髪をショートカットにして、スカートを一掃した。制服だけは諦めたが、スカートの下にジャージを履くことを許してもらった。
昨今は多様性とやらを認める時代らしく、理解がある風の先生方に私の主張は受け入れられた。それは高校も同じで、面倒くさそうな顔をした教師は容認し、「わかるー」という鳴き声の女子には養護され、「男女」と揶揄する男子に避けられた。誰もが腫れものに障るのを煩わしく感じ、それぞれの仕方で距離を置く中、行成浩也は私に近づき、こう言った。
「スカートを貸してくれ」
放課後。誰もいない教室で、彼は私をまっすぐに見据えて頼んできた。
「お前、ふざけてんのか」
「真面目だ。真面目に頼んでいる」
彼は学年でもトップクラスの成績を誇る秀才だ。素行も真面目なヤツで、他人をからかって遊ぶイメージは無かった。私は迷いながらも、履いていたスカートを差し出す。彼は礼を言って受け取ると、何のためらいもなく目の前でスカートに足を入れる。
「行成、お前女装の趣味があるのか?」
「無い」
「じゃなんで」
「斎藤のそれは男装なのか?」
「ちげーよ」
「僕に女装の趣味はない。ただスカートを履いてみたかっただけだ」
彼は私のスカートを履き、自分の履いていたスラックスを脱ぐ。細く筋肉質な白い足に毛が生えているのが見える。彼はそのまま教室の後ろの方までゆっくりと歩き、私の方へ振り返る。
「で、感想は?」
「どこかの部族の民族衣装を着ている気分だ」
「何だよそれ」
「すかすかして心もとない。斎藤がジャージを履く意味がわかった」
虚を突かれた。上手い返しを思いつかないうちに、彼はスラックスを履きスカートを差し出した。
この日以降、自然に彼と話すようになった。親を含めても、唯一気を遣わず話せる相手だった。お互い帰宅部で塾も無い日は、何とは無しに放課後の教室で他愛もない話をする。
十四日は水曜日だ。普段なら放課後はすぐに空になる教室に、浮ついた空気のまま数人が残っている。
私はただぼんやりと机に座り、太陽が次第に傾くのを眺めていた。やがてクラスメイトはいなくなり、一人になった。私は椅子から立ち上がり、机に座り、椅子の座に足を下ろす。部屋の後ろ、ちょうど正面にゴミ箱が口を開けている。
校内を歩く生徒も下校する生徒も減り、少しずつ静かになる。私は緑色の箱をしばらく眺めていたが、渡したい相手は帰ってしまった。わざわざ追いかけて渡す気にはならない。
大きく息をつくと、緑の箱を右手で振りかぶる。まっすぐストレートでゴミ箱にインだ。
「それ、捨てるのか?」
教室の入口に彼が立っていた。走っていたのか少しだけ息が上がっている。普段の冷静な彼と異なる雰囲気に、呆然とする。
「捨てるのなら僕にくれ」
「いや、捨てない。でももう帰ったと思ってた」
「一度帰ったよ。大切なものを忘れてしまって」
そう言うと彼はカバンの中からジップロックの袋を取り出す。中にはくすんだ茶色のハート型チョコレートが入っている。
「悪いな。入れ物にまで気が回らなかった」
「これ、行成が作ったのか? 手作りチョコレートをバカにしてたのに」
「バカになどしていない。往々にして、本来そのまま食べた方が美味しいチョコレートをあえて溶かして雑味を生み出し劣化させている、という事実を述べただけだ。だが知識としては知っていても、本当に劣化するのか試したことは無かったからな」
手渡された袋から取り出し、観察する。表面がデコボコしていて明らかに手作りだった。
「斎藤のそれは、二つあるのか?」
私の手元にあった箱を目で示す。
「ああ、うん。一緒に食べようと思って」
「さすが斎藤。ではプロと素人の食べ比べをしよう」
そういうとさっそく箱を開けて、彼はチョコレートを口へ放り込む。一、二度口を動かすと少しだけ目を見開く。
「旨い。全然違う」
嬉しそうに食べる彼を眺めながら、私は手に持っていたデコボコのハートを食べる。キャンディのように固く、口の中でなかなか融けない。噛み砕こうにも歯が折れそうだ。
「かってー」
「それが手作りだ」
「行成はこういうのも器用に作りそうだけどな」
「テンパリングについては勉強した。温度も気をつけたが失敗した。そう簡単にできないからプロがいるのだろう」
私は笑いながら、もう一粒チョコレートを掴む。先ほどよりも少しだけ厚みがある。
「でもまさか行成からチョコレートをもらうとはね。行成がもらう方なんじゃないの?」
「性別で制限をかけているのは日本くらいだろう。それも風習だ。法律じゃない」
口に放り込んだチョコレートはさらに硬い。彼らしくて笑ってしまう。
「斎藤」
彼は手を止めて、真面目な顔をして私を見つめていた。
「僕は日本のバレンタインデーの風習は好きではないが、その手作りのチョコレートにはそういう想いを込めた。斎藤のくれたこのチョコレートも同じ想いが込められている、と捉えていいか?」
夕焼けが彼の顔を照らしていた。まっすぐな瞳に射抜かれたように言葉が出ない。私はただ小さく何度も頷いた。硬いチョコレートが口の中でゆっくりと溶ける。
シロクマ文芸部の企画応募です。
テーマは「チョコレート」。
季節柄、noteの世界ではチョコレートと青春が大量発生していて虫歯になりそうです。ちょっとファンタジーとか他の方向へ行こうかなぁと思ったけど、バレンタインネタは書いてなかったので、王道?ラインで行きます。
よろしければサポートをお願いします!サポートいただいた分は、クリエイティブでお返ししていきます。
