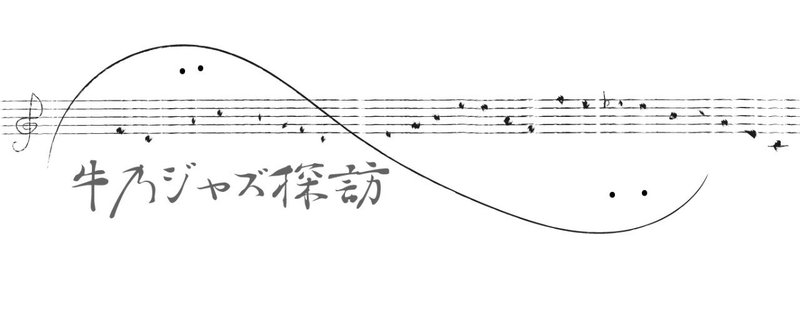
牛乃ジャズ探訪(9) Joe Locke
高知の音楽家・ギタリストの牛心。です。
ジャズプレイヤーは自分の楽器以外のプレイヤーをあまり知らないという観点から、様々な楽器奏者を紹介していこうという連載です。よしなに。
でも、分かります。別に深掘りする必要もないし、ピアニストはビル・エヴァンスでいいし、ベーシストはロン・カーターでいいし、エルヴィン・ジョーンズとウェス・モンゴメリーでいいし、ってなるのは当然ですよね。
そして今回は、ヴィブラフォン奏者です。
ジョー・ロック(Vib)
ジョー・ロックは1959年カリフォルニア生まれのヴィブラフォン奏者です。
いきなり余談ですが、彼は20歳くらいにニューヨークに出てきて、1990年頃にはレコーディングを残し始めてるので、結構下積み長いめの人だと思います。いや、もっと下積みしてデビューしてる人は沢山いるんですが、彼ほどのテクニックをもっていてもそんなかぁという印象でした。
僕が知ったのは2000年代に入ってからジェフリー・キーザーと始めたNew Sound Quartetくらいからです。
モントルージャズフェスティバルをBS2(懐かし!)で録画した中で「超絶技巧ジャズユニットがいるぞ」とびっくりしたのを覚えています。何がすごいかって、タイム感がすごい。
このアルバムはドラムとベースがいないトリオなんですが、とても美しいのでめっちゃオススメです。
こういう室内楽的なジャズは恐らくゲイリー・バートンの影響でしょうね。
ジョー・ロックの即興演奏は、チャーリー・パーカーのようなオールドスクール・ジャズをより洗練させたようなものですが、一聴すると非常に現代的に響きます。
その大きな要因は、やはりタイム感です。
ヴィブラフォンは見ての通りマレットで鉄の棒を叩く鍵盤打楽器です。鉄琴のデカイやつですね。
奏法としては打楽器なので、ドラムみたいなマレットコントロールが要求されます。片手に2本のマレットを持っているのですが、ほんとどうやってんだこれって感じですよね(笑)
それにしてもフレーズが早い。
ピアノでもこれだけの高速フレーズをずっと引き続けるのは難しい上に、ドラマーのようなスピード感です。
ジョー・ロックはドラムのタイム感をヴィブラフォンで応用しているのですね。
採譜できる奇数拍子のプレイ
僕がジョー・ロックのプレイで学んだことは「ジャズは雰囲気でやれるほど簡単じゃないぞ」ということでした。
彼のプレイは端から端まで採譜できるほど洗練されたリズムで構築されています。それはヴィブラフォンが打楽器でもあり、ドラムのフレージングが応用しやすく、練習メソッドもパーカッションのそれに近いのが理由です。
手グセっぽい奇数拍子のランニングフレーズなどが象徴するように、複合的にリズムチェンジを繰り返していることがよく分かります。
昔、ギターの師匠に「現代のジャズプレイヤーはみんなタイムを完璧に管理しとるからな」「タメてるみたいに聴こえるのは5連符とか7連符とか、32分裏から始まっとるだけ」と教えてもらったのですが、まさにジョー・ロックのプレイはそんな感じです。
(師匠は関西人なのです)
そう思って色んなレコードを聴いてると、確かにパット・メセニーもケニー・バロンもマイケル・ブレッカーも、ほぼ全ての人がそういうプレイでした。
16分や32分の偶数拍子のフレーズと7連符や5連符の奇数拍子を組み合わせて走ったりブレーキをかけたりしているのですね。
ということは、現代のジャズプレイヤーは奇数拍子を正確にプレイできなきゃいけないんだって話になります。
偶数拍子はまぁ、普通にやってりゃなんとかなりますけど、奇数拍子はちゃんとしたメソッドでないと身につかないですからね。
(そういえば先日某ジャズ誌でカート・ローゼンウィンケルのソロ採譜が載ってたんですが、5連フレーズのところが頑張って3連で書こうとしてて逆に訳わからんことになってたんですが、雑誌的にNGだったのか採譜主の勘違いなのか気になってます)
偉大な先人を越える現役達
ジャズでヴィブラフォンといえばミルト・ジャクソンが有名ですが、そういう超有名プレイヤーがいる楽器でジャズプレイヤーを目指す場合、必ず偉大な先人「みたい」に見られちゃいます。
トランペッターがミュートをつけてソロを取ると「マイルスっぽいね」と評される現象ですね。実際のところ、そういう「みたい」「ぽい」という雰囲気ジャズおじさんは日本では少なくないと思います。いや、日本に限らないかな。
でも、偉大な先人のスタイルが定着しているからこそ、それを乗り越える努力が積み重ねられているのも事実です。
ジョー・ロックとミルト・ジャクソン・トリビュートバンドによる、ミルト・ジャクソンの曲を集めたライブ盤です。
元の曲を聴くとその差が際立つのですが、明らかに昔よりも現代のプレイヤーの方が丹精で上手いです。演奏テクニックに関するノウハウは年々良くなってきていて、50年前では考えられなかったようなタイム感を持ったプレイヤーがたくさん登場しています。
楽器は変わってなくても、どうすればテクニックが向上するかという科学的考察は日々研究が重ねられているんです。テクノロジーと同じですね。
僕は現役プレイヤーの方が過去の偉人より上手いしかっこいいと思っているし、これからも進化していけるなぁと感じています。テクニックの向上=演奏内容の向上っていうのも、ジャズの性質ですからね。
トリビュート・アルバムは、作ってる側がどういう考えでやっているかは置いといて、偉大な先人を現役世代が追い抜いているとよく分かるので好きです。
とにかく正確なタイム感!
ジャズのレッスンをしていると、フレーズの理屈を伝えるのは難しくないのですが、それをどうジャズのリズムにするかについては骨が折れます。
一番多い勘違いは、「スウィング=3連中抜き」だと思い込んでいることですか。これ、グルーヴをタメとモタりだと思い込んでいるのと似てます。
違う違う、スウィングもグルーヴも、とりあえず正確なタイム感です。正確さが先にないとどうやってもダメです。
そして、どれだけ正確を目指しても100%は無理で、その微小なズレがスウィングやグルーヴになります。
そこを勘違いしていると「タメてもいい」とか「モタりも味わい」みたいな雑な音楽になるし、しかも「それが人間の味」みたいなヒューマニズムに話がシフトしちゃってテクニック向上を阻むのです。
ジョー・ロックの演奏を体験したら、言ってる意味も分かってくれるんじゃないかなと思います。
タメてるようで、彼らのプレイは想像以上に譜割り管理で構築されています。
トップ・プレイヤーとは、そういうものです。
牛心。
高知在住の音楽家・ギタリスト。バークリー音楽院中退。バークリー中退組のスター「スティーヴ・ヴァイ」をこよなく愛するが故に彼のフォロワーではない。デヴィッド・フュージンスキーに師事し最高峰のリズムトレーニングを学んだのでタイムとグルーヴについては考えが揺らがず、先日も面倒くさいスウィング語り型ジャズおじさんを討伐した。
サポートなんて恐れ多い!ありがたき幸せ!!
