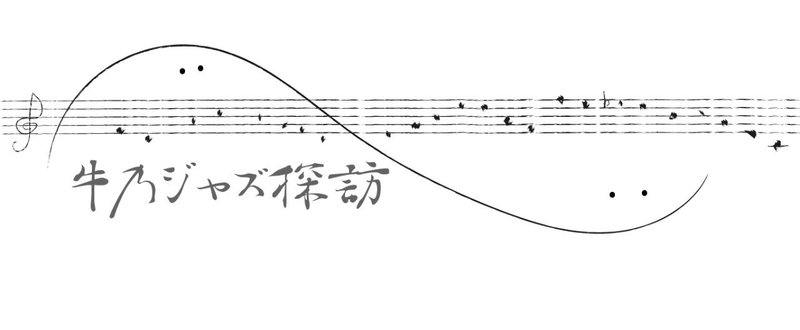
牛乃ジャズ探訪(13) Matthew Stevens
高知の音楽家・ギタリストの牛心。です、一応自分もギター弾きとしてギタリストを沢山知らなきゃ!と思っているんです。思っているものの、ピンとくるプレイヤーとそうでないプレイヤーってやっぱりいます。
好みとしては今回紹介するような、いわゆる東海岸系ジャズの人が好きです。
こういう小難しいのが苦手なジャズ好きも多いとは思いますが、まぁ食わず嫌いせずにどうぞ。
マシュー・スティーブンス(Gt)
マシュー・スティーブンスは1982年カナダ生まれのジャズ・ギタリストです。
2004年から国境を渡りバークリー音楽院に入学して本格的にキャリアをスタートしています。エスペランサ・スポルディングと同期くらいでしょうかね。
リーダーアルバムはこれと、
これの2枚ですが、彼はサイドマンとして沢山のアルバムに参加しています。
演奏スタイルは東海岸系のど真ん中というか、バークリーサウンドというか、ちょっと変わったハーモニーとリズムを楽しんでいる感じです。
特に2017年のアルバム「Preverbal」は実験的で、サウンドはロックぽいし、ミニマルミュージック的な曲もあるし、ファンクっぽさもあるという。
これは僕が思うに、現代フュージョン・ジャズですね。
ウェザーリポートがやってたようなコンセプトを今の人がやるとこうなるぞ、という感想です。
こういったサウンドは一聴すると難解ですし、BGMにならないしですが、音楽を作る側からすると「おぉぉおおおすげぇええ!!」と大興奮する、かも?(笑)
こういうのを英語ではFunnyと呼ぶ。
融合していくジャズ
自身のアルバムでもエスペランサと共演しています。
にしてもこのサウンド、歪みっぷり、一般的にいわれる「ジャズっぽい雰囲気」はあんまり感じられないですよね。
けど、これこそ直系のジャズ・スピリッツです。新しいテクノロジーやアイデアでバリエーションを増やそうという取り組みこそジャズの歴史ですからね。
マイルス・デイヴィスもジミ・ヘンドリクスに影響を受けてエレクトリック・ジャズを実験してましたし、ロックとジャズの融合は随分前に果たされています。
現代では、例えばクラブミュージックやヒップホップのサウンドをベースにした即興演奏が「新しい」という感覚として受け入れられつつあります。
言い方によっちゃ雑多なサウンド。
でもその中にもジャズの基本姿勢は息づいています。コードトーンをちゃんと使ってソロをする、とかイン・テンポであるとか。
プレイヤー目線でみると、サウンドこそ新しくとも、演奏する即興コンセプトはあんまり変わってない気がします。
大事なのはサウンドの自由さ
エスペランサ・スポルディングでのマシューのサウンドがカッコいいので聴いてみてください。
複雑なことをやっているんですけど、全体のサウンドデザイン、ディストーション、ディレイやコーラスなど空間系の使い方がとても上手だなぁと感心します。
マシュー自身もコンポーザーでありプロデューサーなので、しっかり楽曲についてディスカッションをしてから音決めをしているような雰囲気です。
昔、恩師に「(ジャズの勉強してるからといって)全員がジャズプレイヤーを目指す必要ない。ジャズは演奏能力を向上させるデバイスであればいい」と諭されたことがあります。
日本のジャズプレイヤー観は求道者みたいなところがあったりしますが、アメリカではそういうステレオタイプはあまり感じませんでした。
むしろ、エスペランサやマシューのような歌モノに抵抗なく挑戦していくスタイルの方が「いいね!」と評価され、ジャズギターだからといってクリーントーンじゃないとダメとかいうルールもない。
あるギグでギタリストが遠慮なくソロでディストーションペダルを踏み込んだらば、ジャズ・バーにいたお客さんがみんなワーッと盛り上がった。
渡米中の僕は「ジャズには、そういう自由さがあっていいんだ」と確信したもんでした。
牛心。
高知在住の音楽家・ギタリスト。ライブでは面倒なのでディレイとプリアンプしか持っていかないけど、そろそろペダルボードも欲しいしワウも新調しなければと考えている。Xoticの音が好き。
サポートなんて恐れ多い!ありがたき幸せ!!
