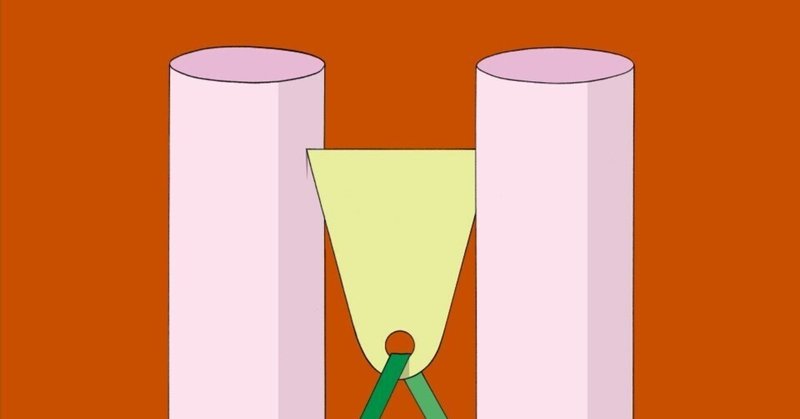
連載 第六回:自分 ÷ 友達
最果タヒ『MANGA ÷ POEM』
Text:Tahi Saihate / Illustration:Haruna Kawai
ビームスが発行する文芸カルチャー誌 IN THE CITY でも大好評だった詩人・最果タヒの新連載が登場。好きな「漫画」を、詩人の言葉で見渡すエッセイ

フィクションの中にいる人に、たまに「友達になれそうだ」と思うことがあり、そうするとそれだけでどうしようもなくその人物に執着し、心の底から好きになる。実在の人物にそんなふうに思うことはない、というのは、現実にいる人とは実際に親しくなろうとすることができるし、そして「思うようにはいかなかった」となる可能性がかなりあると肌でわかるからだ。フィクションの人物は、その人の人柄や趣味嗜好だけを理由にして「近づける」と思うことを許してくれる。それは絶対に、試してみることも、失敗することも(そして成功することも)ありえないから。だから、そんな夢を見せてくれる。
思えば私は10代の頃から、人に自分について何かを言われると小さなことでもそれが自分の把握している範囲の指摘でなければ、恥ずかしくて何も答えられなくなってしまっていた。好きなことにはすぐに早口になるよね、とか、プライドが結構高いねとか、きみが思ってるほどきみは冷静ではないよ、とか。今ならなんとも思わない指摘も、当時は自分が見せたくない部分が他人に露呈していると感じて怖くなってしまった。私は、私のものだと思っていた。他人から見える自分は、自分とはまた別人であると知らなかった。そしてだから誰かに何かを思われることが、自分そのものの価値に直結する気がして、好かれることや嫌われることを気にしていた。他人は自分の思う通りに自分のことを見てくれないし、土足で踏み込んでもくる。どうしてそんなことをするのだろうと思う。私は、他人の視界に入りたくなかった。その人とは仲良くしたいと思っても、私自身がその人の「友達」や「知人」になるのは恐ろしかった。ただその人のことだけを好きと思い、その人の話を聞きたい。その人が自分に何かを思うのは、きっとそれ自体が耐えられなかったのだ。自分を、たとえ好きになってくれようと。好きな人のことは好きだ、でもその人が、私の知らない「私」を見るのは嫌だ、好かれることさえ嫌だった。
この話をすると自意識過剰とか、プライドが高い、という話にされてしまうことが多々あり、それは当時も今もそうで、昔は「そうなのか、私は傲慢なのか」と落ち込んでもいたけれど、でも今の私は、プライドが本当に高いならあんなにも簡単に他人の言葉に落ち込まない、と思う。誰に何を言われても自分が信じる自分の像だけを抱きしめる人でありたかった。他人が、どんな自分を愛そうと、それは幻覚だと思いながらそれと現実の矛盾に平然としていたかった。けれどあの頃の私は、何か言われるたびに他人の指摘こそが真実な気がして、それに気づいていない自分が愚かだったり高飛車である気がして、簡単に自分の中にある「自分」を捨て恥じていた。惨めで、他人の目にしか委ねられない自分の弱さを憎んでしまうあの頃のことを、『バーナード嬢曰く。』を読んでいると何度も思い出すのです。
この物語に出てくる神林やさわ子のことを、私は多分「友達になれそうだ」と思って見ている。そうしてこの話では頻繁に、二人が互いの自意識に土足で踏み込んで、相手からの指摘に過剰なほど「恥ずかしい」と思うシーンに出くわしてしまう。私はそれが好きだった。「見せたい自分」ではない自分を見られてしまうということが、彼らにとってもちゃんと恥で、苦痛で、戸惑うもので、でもそれでもそれが二人の仲には関係ないというか、二人はその繰り返しを経て、いつのまにかより仲良くなっていく。それでも恥じらいには美化がなかった、その瞬間の「恥ずかしさ」はシンプルに弱さと人間関係の不慣れさに裏打ちされていて、だからこそ二人が互いと話す時間から逃げないことがよくわかった。本の外から「友達になれそう」なんて思うのは勘違いで、二人に必要なのはこの二人の関係だけ。むしろ、それが薄々わかっているから、彼らと友達になりたいと思う、私は恥ずかしくても、他人に見られたくないと思っても、それでも誰かと話したかったのかもしれない。
性格とか趣味とかだけでその人と仲良くなれるかどうかなんてわかるはずもなく、そんな情報だけじゃ「私」も「きみ」も見えるわけがない。人に土足で踏み込んでこられて、知らない自分を教えられて、ショックを受けることは自然で、そうして他人が自分を見る、ということに慣れないのも当たり前で、いつまでも乗り越えられるものではない。人はそれくらい弱く、不安なまま他人と接して、それでも、話したい人と話すのだ、ということがゆっくりと描かれている。絶対にこちらを置いて行くスピードで「友情」が描かれない。「友達になれそうだ」と思いながら読むとき、その先にあるものがどんどん物語の中で描かれて、いつの間にかそんなふうには思わなくなることはよくあって、なのに、この物語では、私の頭の中にある期待を簡単に超えながら、それでも、何よりも見覚えのある他者と自分の居心地の悪さがはっきりと描かれつづけ、安心をした。私はさわ子に話しかけた時、どんな返事が来るか想像できる。というより、こんな返事が来るだろうと期待してしまう。でも神林は多分、何が返ってくるかわからない、と思いながらさわ子に話しかけている。私より、それはずっとさわ子と近い人だから。そのことが見ていて嬉しい。そんなふうに立ち入れない二人の関係に触れる時、私は昔のうまくできないと落ち込みながらも必死で紡いでいた他人との関係が、それでもまっとうに「人と人」の関わりだったと、確信することができるのです。だから、「友達になれそうだ」と思うのかもしれない。友達という関係に再び立ち向かう勇気をもらった、という意味で。
・『バーナード嬢曰く。』(施川ユウキ・著)一迅社WEB
https://data.ichijinsha.co.jp/detail/75806371

さいはてたひ。詩人。詩やエッセイや小説を書いています。
はじめて買ってもらった漫画は『らんま1/2』。
はじめて自分で買った漫画は『トーマの心臓』。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
