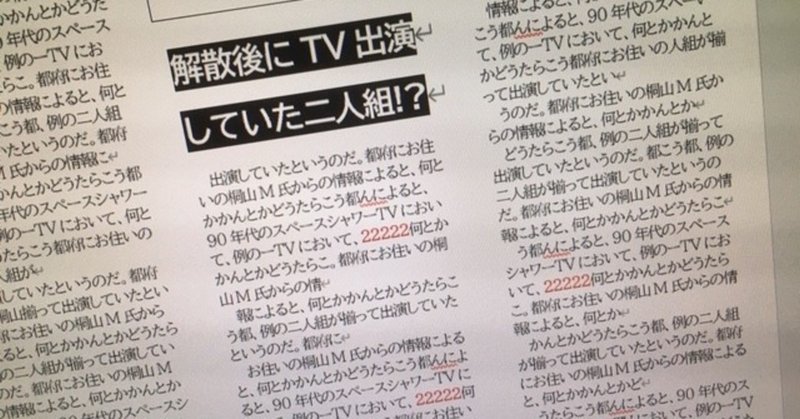
03号編集日記 0901-0906
「ベレー帽とカメラと引用」の03号の製作を本格的に始めたので、ときどき進み具合の断片的なメモや思いつきの記録を紹介します(最終目標は11月22日の文学フリマ東京での販売)。
文中、MさんやKさん、Yさんなど、仮名の部分がありますが、必ずしも同一の人物ではなく、複数の人物を指していることもあるためご注意ください。
とりわけ「Mさん」「M氏」は何回も登場しますが、年齢も性別も立場もまったく別人の「Mさん」「M氏」が数人登場する日もあります。
・・・・・
0901
4日にM氏が上京して埼玉まで来てもらえることになった。
ヘッド博士のジャケットのような、黒地にドット柄の文房具や服を集めたら面白いと思うのだが、時間と金と手間がかかる。せめて20~30種類くらいはないといけない。
そういう没企画も少しずつ発表して宣伝に結びつけたい。
noteは読まれているかと思ったらせいぜい1記事が数ページビューで、一つだけ167くらいだった。もっと広告を考えないといけない。メールマガジンも考えたが、noteを効果的に使わないといけない。
BASEにたまっている利益を振り込み申請しないと、いくらか損になるというので申請する。×××××円ほど。これではまだまだ。
0902
夜になって菊池成孔と大谷能生の「東大ジャズ講義」を読み返すといろいろな発見があった。刺激になったし、こういう調子で書けばいいのだという指針になった。
菊池大谷コンビは40代後半で東大でジャズの講義、自分も40代の終わりに〇〇大学でフリッパーズ・ギターの講義と考えれば、大変なことだ。しかし内容は、講義の時間も話題の濃度も数百分の一くらいでしかない。
文章を書くのがしんどい理由として、無駄なことを含めて広げる方向と、無駄をなるべく切りつめる方向と、両方あるからだと気づいた。両方を同時に行おうとするから精神的な負担になるのでは。
両方を行ったり来たりするというつもりで、「広げる」と「切りつめる」を交互に行った方がよい。
0903
朝、急に忙しくなった。それでかえって勢いがついて、延び延びにしてしまっていた某さんへのイラストの依頼(メール)を書く。
明日はもうMさんが大宮へ来る日だが、何を相談すべきかすら整理できていない。紙に書きだして、2019年10月の講義の話を再構成しなければいけない。話しながら書くことにするべきか。
やるべきこと
・自室にある筈の雑誌の整理
・手元にある記事の整理
・Eさんの原稿のための整理
・テープ音源をMP3に変換
0904
たまたま書店で目について買った「戦後日本のジャズ文化」(岩波現代文庫)が面白かったので刺激になった。
ギンズバーグの詩とか、ケルアックの小説はどこが良いのかさっぱり分からなかったが、この本の中で若き日の大江健三郎が相当に高く評価している(と紹介されている)。五木寛之はいかにもジャズを理解している風だがそうでもないとのこと。
「ジャズメン」という呼称に見られるように男性優位の世界で、にもかかわらず秋吉敏子が最重要人物になっているとか、「ライブハウス」は日本語に再度訳すと「生きている家」など。ちょっとした指摘が鋭い。
東大ジャズ講義は、二人の著者のうちどちらが喋ったのか曖昧になるように継ぎ接ぎされている(分けられている部分もある)。このスタイルは少々フリッパーズ・ギター的な面がある(どちらの手によるのか不明な点が多くある)。
FGの匿名性。1st、2ndあたりまでは誰が誰なのかはっきりしない。二人になった当初もどっちがどっちなのかすら、雑誌の記事によって補足しなければならない。雑誌もいちいち名前を示さない。CDだけでは分かりにくい(この話題は2019年10月の講義で少し話した気がするが、思い出した)。
夜、18:30に大宮で会う予定が土砂降りなどで少し遅くなって19:30にHSでMさんに会う。
その前にCDの帯やチケット、チラシなどをファイルに入れているうちに、雑誌の記事も整理できて、ファイルに入れる作業がはかどった。大判の紙はA4用では入らないが、おそらくどれも「パチパチ」の記事で、面白いものが多い。
「カメラトークレコーディング潜入記」も発見。
当時、一度しか立ち読みしていないはずだが、細かい点はよく覚えている。風邪のくだりのツッコミやジャズのクリシェの箇所など。おそらく「宝島」ではないかと思っていたが記憶違いだった。
小沢、小山田のやり取りの妙が素晴らしい。この微妙な味わいは、この時期のこの二人だけのものである。書いた人を表彰したいほど。
Mさんと会う前にEさんに「明日のあれの後で座談会をしましょう」と誘うと、二つ返事でOKのうえ、Yさんも誘いましょうということになり、トントン拍子で話が決まる。議題は好きな曲ベスト10、各順位に一曲というルールを厳守。一位を三曲にして二位三位はない、というのはダメ。
M氏に「FGの歌詞のある要素を引き継いでいるのは〇〇だ、なぜなら云々」という話をして図を書いたりする。それはいいのだが、佐藤雅彦を知らないというので驚く。
小沢健二と対談してただろうと言うと「広告批評」の表紙しか知らないという。「小沢健二の相棒」という立場を小山田圭吾から継承して、「小山田圭吾の相棒」という立場を小沢健二から継承しているのだから、ひとりFGではないか、という話をする。
0905
批評とは〇か×かを判定する役割ではなくて、むしろ「どちらでもない」と明言するか「さらにまた別の答え、考え方」を示すべきではないか。
どちらでもない例として/心理学的に「何々は何々の象徴」の例として。
車の広告、赤いスポーツカーの前で幼女がバナナを食べている。
意識してやっているとしたら、非難されるべき。意識せずにやっているとしても、やはり非難されるべき。
似たようなことはあちこちにあるのではないか。
「カメラ!×3」であれば、「可愛い」という印象を受けて好むのも、「可愛い」という印象を受けて嫌ったり、バカにしたりするのも、どちらも違う。「どちらも違う」「どちらも正しい」「どちらもどうでもよい」と示すパターン。ごちゃごちゃになってきた。
AHが言っていた「批評塾の生徒は孤独がない」という発言も納得できる。つまり、批評とはまず認識の断絶から始まるものなので。孤独というより孤絶。
某某のタイトルがフリッパーズ・ギターを思わせる件について、ちょっとMさんに話す。この件から考えると「*****」というのは「カメラ・トーク」の邦題にぴったり。
すると堂島孝平についても似たケースがあると指摘された。しかしちょっと甘いかもしれない。帰宅してから調べてもやはり甘い気がする。
また別の見方もできる。「カメラトーク」全編に登場する「僕」は本当の、現実の小沢健二本人を反映していない。もし当時の彼に自己紹介をしてくれとお願いした場合、まず自分は「ミュージシャン」であると言うのではないか。そして次に大学生であること、親戚は誰誰で……。
しかし、あの歌詞には「ミュージシャンとしての自分(僕)」は出てこない。ギターをいじったり、中古レコード屋に行く「僕」はどこにもいない。暑いお昼過ぎにはラジオを聴いたり「ジャンとディーン」を揃えはするが……(ベンチャーズやビーチ・ボーイズではなくて)。
大学生として課題を片付けたり、図書館に行ったり、友達がいたりする「僕」もいない。
恋愛と自我の葛藤ばかりで、つまりそういう側面だけの「僕」である。
だから、「Young,alive,in love」という「恋とマシンガン」の英題は、アルバム全編の表題として、実は最もふさわしいし、本質を突いている。
大げさに言うなら、このフレーズができた瞬間は「カメラ・トーク」の製作過程において画期的な何かが起こった瞬間といえる。大げさ風に言えばいくらでも大げさに言える。
ある集まりの後で、M、Eさん、Yさん、それにKさんも加わってバーミヤンに行ってお茶を飲みながら話す。座談会は早めに切り上げたのだが、それでも3時間くらい。「クラウディ」が好きなのに、フェアーグラウンド・アトラクションを知らないとか。それはオザケンだって何回か言及しているくらいだ。
その後、またM氏と餃子屋で話す。オザケンのお父さんと遭遇した例の話から、さらに「こうした方がいい」と話が進展する。今日、KJさんに質問できたので、ZINEを一冊送ろうかと思いつく。
0906
昼はMさんにイラストの件でメール。やっとEさんにも原稿のメール。Eさんがちょっとツイッターで宣伝してくれただけで、30分もしないうちにすぐ注文が来た。M氏は「昨日話してて気づいたこと」としてアンケートを行っている。
(来週に続く↓)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
