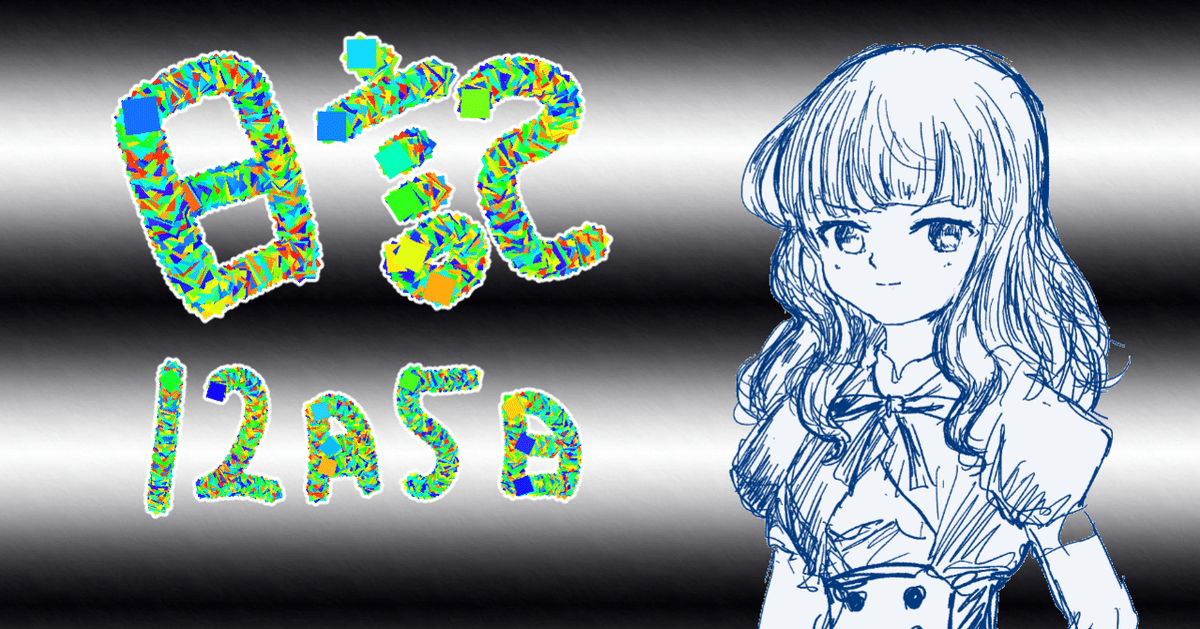
12月5日の日記(『浦川大志 × 名もなき実昌 -異景の窓-』、ドールいろいろ見た)
今日は思い立って家を出てみた。
浦川大志 × 名もなき実昌 -異景の窓-
日本橋は茅場町のコンテンポラリーヘイズで行われている二人展に行きました。
めちゃくちゃ良かった~。のだが、ぜんぜん写真を撮らなかったので、ぜんぜん知らない方のツイートを参考までに貼っちゃうぞ。
コンテンポラリーヘイズで浦川大志×名もなき実昌二人展を見てきた。美術や社会が持つ虚飾が入れ子構造になって作品や展示を行ったり来たりしている。面白い展示だった。 pic.twitter.com/Mlv74aasvV
— 飯島モトハ (@mochiunagi) December 3, 2021
浦川大志さんと名もなき実昌さんの展示「異景の窓」@ Contemporary HEIS
— R HIRANO (@r_prairie) December 3, 2021
インスタレーション的な展示は、空間と絵画が入れ子のようだった。
大作が中心で見応えある。 pic.twitter.com/asw0JjDvjK
浦川大志さんと名もなき実昌さんは今までも共同で展示をされているそうで、今回の展示も福岡県の大川市立清川美術館で行われたものを「再構築したもの」だそう。
浦川さんの作品を見たのははじめてなのですが、おふたりの作品が近い質感を持ちながらそれぞれが際立たせた特異性が目立つ感じで、空間其の物がとても良かったですね。
また、平面作品と立体作品で明確に同じモチーフを扱っているのも面白かった。
福岡の美術館の展示、東京巡回展の搬入が完了した。12/1より pic.twitter.com/j2U0ENprpN
— 浦川大志 (@HANIWATaisi) November 29, 2021
この浦川さんのツイートでわかるように絵に使われているのと同じグラデーションの物体があってそういう趣向もあるのですが、この絵の中にクリーム色の箱状のものが描かれていて、覗く形になっているのがおわかりかと思います。この「窓から覗く」というモチーフが立体でも行われている。

会場にあるこの段ボールのなかに穴が開いていて、別の展示での様子が模型的に表現されている。

これが楽しかったですね。『異景の窓』という題通りの展示だと感じました。
名もなき実昌さんの作品は、絵の中にキャラクターの顔のようなものが断片的に挿入されていて、オタク的な現代美術(正しい言い方を知らない)の流れに属しているんだとは思うんですが、要素としてだいぶ分解されているし、そもそも地に当たるものも不可解で…単なる「萌え」とは違う異物感と統一感があって独特な良さがあるように思いました。

この筆を置くような筆致が上層に張り付いている感じや、カクカクした書き文字は、アスキーアート的なインターネットっぽさがあると感じるのですが、それが一貫されずに、筆先の力加減にいたるまでのたくさんの技の中で溶解しているのが良かったです。さっき要素として分解されていると書きましたが、特にこの作品は腐乱した卵のような分解感があって好きですね。
ほかの言い方をすると、自然の暴力性とでも言いましょうか。血や刃物のような人工的な暴力と違って、それが普通のこととしてある破壊ってあるじゃないですか。災害によって形変わっちゃう地形とか、使い古された画像のjpegノイズとか、足取りおぼつかない幼児がソフトクリーム落としたりとか……?そういう不可避の現象っぽさを感じるんですよね。
特に浦川さんの作品に顕著ですが、おふたりともグラデーションをよく入れているようです。wordみたいな鮮やかなグラデーションをあえて筆でやったうえで、別な筆致を混ぜるとなにか暴力的な魅力が出るんですよね……、すごい発明だなあと思います(文脈とかちゃんとあるのかもしれませんが……)。
在廊されている情報を聞いて訪ねたのですが、名もなき実昌さんがいろいろお話しくださった。しかしま~緊張してしまって、口からなんかとなんかが出そうだった。そもそもギャラリー自体緊張するんだよね…。広くない空間で作品と対峙することを余儀なくされて疲れる。でもそれに見合うパワーのある作品のある展示は良いものですね。もっと展示行きたいなと思いました。展示は12/25までやっているそうです。
本当に疲れたので外堀(日本橋川)にもたれかかって休憩した。肉眼だと闇のなかに水面が揺らめいて幽玄だったのにアイフォンのナイトモードで撮ると綺麗になりすぎる。

アキバでドール見た
お人形が欲しい!ドールを御迎えしたい!…とつねづね思っていますが、金がないので買えない。たとえ収入が入ったとしてもおいそれとは買えない代物。ということで秋葉原に行ってじろじろ見てみた。ウィンドウショッぺングというやつですな。
今の新ラジオ会館にはドール系のショップがたくさんあるので、あそこだけでかなりの種類が見られる。が、日曜のラジオ会館は、観光で来た家族連れやデートしてるオタクなどがいっぱい居て居心地が悪い…、駿河屋同人ブースに戻りたい……となってくる。
しかしドールショップにはキモオタ男性と変な髪色のオタク女性しかいないので安心した…。オイラも早くドールのマスターになって戦いたいぜ。
AZONEレーベルショップには、服以外プラで作られた、フィギュアにほど近い小型タイプ(アサルトリリィなど)と1/6くらいのやや小型のドールがたくさんあった。


いっぽうボークスのドールショップでは1/3くらいの大きめのドールがたくさん売っていた。

あとお店の名前は忘れちゃったけど作家性強めの別のお店では耽美な男性ドールも売ってた。エロいの~。

で、色々見た結果思ったんですが、生きてる度合いが重要かもしれない。
まず髪の毛が実際に毛束でできているかフィギュアみたいになってるか。いろいろ長短があるようですが、個人的には毛一択かな。フィギュアはもうたくさんもってるというのもあります。
重要なのはおめめ!小型のドールはプリントされた目が多いのに対して大型のものは眼球がある(入れ目)らしい。で今のドールの眼球は大抵の場合クリアパーツの内側に瞳がある(仏像用語でいう玉眼)構造で、ものによってはかなり奥側に瞳を配置することでこっちを見てくれる錯視効果を作っているものもある。
ということで前者は「死んだ目」、後者は「生きた目」となる。

じゃあ入れ目がいいの?といえばそうではないのがミソ。キャラクターのかわいさというのは物質感と生き物らしさの”汽水域”にあるもので、その死んだ目のかわいさというのもすばらしい。
文楽(人形浄瑠璃)は主となる演者が素顔と服をそのまま出してるけど最初はそうではなかったらしい。人形の構造が進化したときに、操演者が顔を出すようになったらしい。つまり人形が人間に近づいたときに、あえてそれが人に操られた人形であることを強調するような演出がくわわったということだ。それは人間が人形のどこに感情移入するか考える上で重要なことなような気がする。個人的には前段の名もなき実晶さんのキャラ性の分解の仕方とかも近いことな気がする。
話をもどすとドールの目は生きてるの、死んでるの、どっちがタイプよ~?という話。いろいろ語ったが部屋にいたらうれしいのはやっぱ生きた目の方かも(ぼくの部屋には動かしてくれる傀儡師のオッサンはいないので)。でも小型の方が並べやすいし買いやすいし、いっぱいいるとかわいい…。うーん迷うんだなあ。というわけで以上。

にょ
