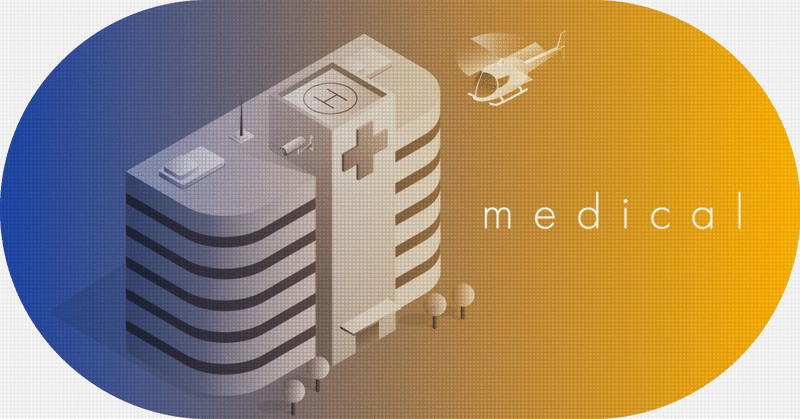
脳神経内科医のおしごと①
はじめに
僕は脳神経内科という科の医師をしています。
脳神経内科って聞き慣れないな
精神科・心療内科・脳神経外科と何が違うの?
って思われる方も多いと思います。
そんな脳神経内科が何をしているのか、どんな時に受診したら良い科なのかをお伝えしたいと思います。
そしてもし学生さんや研修医の方がいたら、脳神経内科の魅力の一端をお伝えできたらと思います。
めちゃくちゃボリュームのある話になってしまうので、何部かに分けます。
脳神経内科が診る病気
僕たち脳神経内科医は、脳・脊髄・末梢神経・筋肉に関わる病気を内科的に(原則手術をしない範囲で)診ています。
具体的に知られてそうな病名の一部を挙げると
脳
脳卒中 認知症 てんかん パーキンソン病
多発性硬化症 クロイツフェルトヤコブ病
脊髄
頚椎症(性脊髄症) 多発性硬化症 ALS
末梢神経
ALS ギランバレー症候群
筋肉
筋炎 筋ジストロフィー
その他
片頭痛 群発頭痛 髄膜炎 めまい症
など。まだまだたくさんありますし、複数領域にまたがる疾患も多く分類に悩むものもあるのですが。
これらの病気はまた別に
脳血管疾患
脳卒中
神経免疫疾患
多発性硬化症、ギランバレー症候群、筋炎など
神経変性疾患
パーキンソン病、アルツハイマー型認知症、ALSなど
神経感染症
髄膜炎、クロイツフェルトヤコブ病など
機能性疾患
てんかん、片頭痛など
などという括りでも分けられていて(もちろん単純に分けられないところもありますが)、脳神経内科医の中でもさらに、分野ごとに専門が枝分かれしていく形になります。
脳神経内科という名前
実はついこないだ名前が変わったんです。
2017年9月に、日本神経学会(脳神経内科の一番大きな学会)で神経内科→脳神経内科への改称が決定しました。
理由は、非医療者の人から見て精神科や心療内科と区別しにくいことや、対をなす外科領域が脳神経外科という名前で既に浸透しているから、とのこと。
英語ではNeurologyなので、”神経科”あたりが適切な和訳なんでしょうけどね。
どうやって脳神経内科にかかればいいの?
地域にもよりますが、消化器内科(胃腸の内科)や循環器内科(心臓の内科)などに比べてややマイナーな科なので、脳神経内科はすべての医療機関にあるわけではないです。
近年は大きな病院に受診するのに選定療養費といって、初診料+αのお金がかかることも多く、直接受診する機会は多くないかもしれません。
脳神経内科に初診(何かの症状で初めて受診すること)となるには、以下の流れが多いのではないでしょうか。
・大きな病院に直接
救急搬送され、そのまま脳神経内科が主担当になる
・かかりつけクリニックから大きな病院に紹介
かかりつけを受診したところ大きな病院の脳神経内科受診を勧められ、紹介
・脳神経内科クリニックを直接受診
ご自分で直接そのクリニックを選んで受診(数は他の科に比べて少ない)
という感じですね。
じゃあどんな症状があったら脳神経内科が担当することになるのでしょう?長くなってしまうので一旦ここで一区切り。次回以降の記事で書かせてください。
まとめ
・脳神経内科医は脳・脊髄・神経・筋肉の様々なメカニズムの病気を幅広く診る
・脳神経外科と違って原則手術をしない
・精神科とも得意分野が違う
・最近、神経内科→脳神経内科に(原則)名前が変わった
・脳神経内科医の数はそれほど多くなく、大きな病院にあることが多い
脳神経内科の認知度が上がれば良いなと思います。よろしくお願いします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
