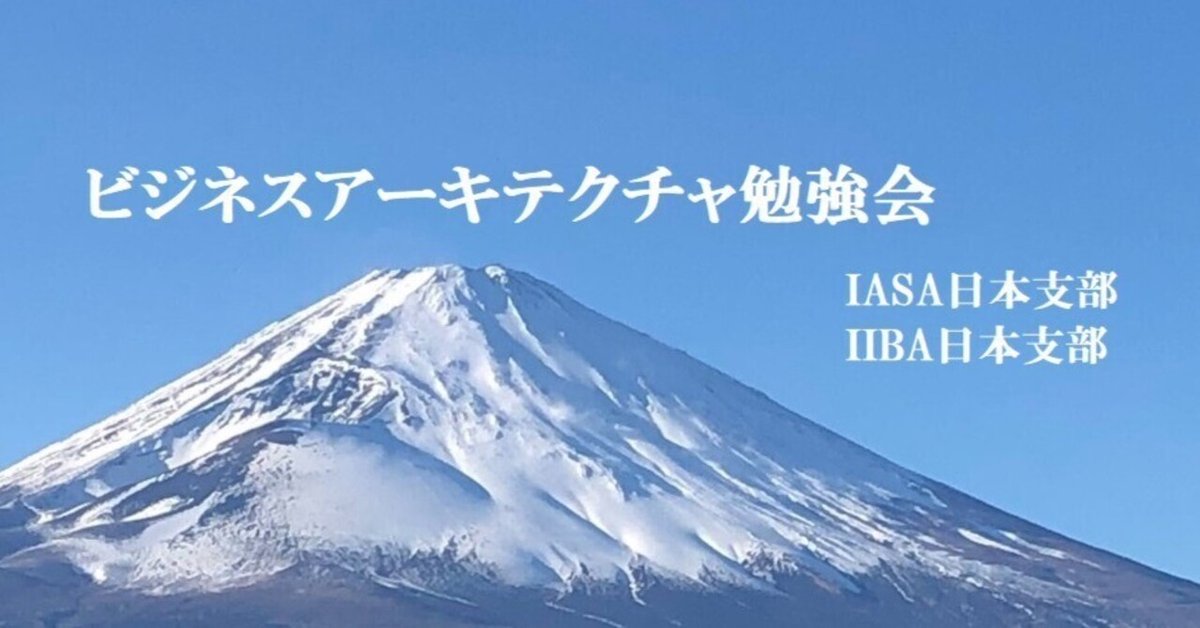
#19 2つのBA -DX推進の実際⑨- 【ビジネスの現状把握】

前回は
DX推進のプロセスである「ビジネスの現状を知る」について考えました。「ビジネスの現状を知る」ために、現状のビジネスを構成する要素を抽象化したモデルで表現することを述べました。特に重要なビジネス構成要素を「ビジネス遂行の能力(Capabilities)」「価値創造の流れ(Value Streams)」「ビジネス遂行組織形態(Organization)」「ビジネス要素概念(Infomation)」の4つとしました。
今回は
「ビジネス遂行の能力(Capabilities)」のモデリングについてお話します。
ケイパビリティ・マップ
ケイパビリティはビジネスを実行する上で必要な、「能力」や「機能」のことになります。例えばうどん屋さんがビジネスをする上で必要な能力は「麺を打つ」「だしを取りスープを作る」「天ぷらを揚げる」「うどんを作る」などの製造にかかるものと、商品をお客に提供するための「設備や店舗の維持」「商品の配膳」などがあります。他にも「人材の確保」や「食材の発注」「食材の管理」など付帯する能力が頭に浮かびます。
これらのビジネス能力をモデルで表します。このモデリングされた対象をここでは「マップ」と呼びます。つまりケイパビリティ・マップを作るということになります。
ケイパビリティ・マップは一つ一つの詳細な機能を並べて行くのではなく、抽象度によりレベル分けして考えます。「麺を打つ」だと「生地を作る」「生地を切る」というより詳細化された能力が必存在します。さらに「生地を作る」には「粉をこねる」「生地を足で踏む」「生地を寝かせる」と詳細化することができます。これで3レベルのケイパビリティ・マップが表現されます。
いかがでしょうか、もちろん実際のビジネスでも同様にレベル分けしたモデルを考えるわけですが、その抽象度について考慮することが重要です。ありがちなのは、レベルの階層をどんどん深くして行って、詳細な機能まで表現しようとしてしまうことです。
ビジネスアーキテクチャは、ビジネスの全体像を理解することを優先するため、抽象度の高いレベルでモデルを作成します。あまり詳細に落ち込むと全体像が見えにくくなるのと、時間とコストがかかり過ぎてしまうため、ほどほどが重要です。2階層から多くても4階層程度に納めましょう。
簡単にマップ例を見てみましょう
1.麺を打つ
1-1.生地を作る
1-1-1.粉をこねる
1-2.生地を切る
1-2-1.生地を伸ばし成型する
これは視覚的な階層表現ですが、表形式で表すこともできますね。利用しやすいモデル形式でマップを作成してください。
あとこのケイパビリティ・マップにその能力の程度を色付けをすることでビジネス遂行能力の程度を見えるようにすると、ビジネス分析を行う際大きなヒントを提供してくれます。例えば、現状充分な能力を有しているものは「緑」、能力はあるが充分ではないものは「黄色」、能力が足りていないものは「赤」という具合です。こうするとケイパビリティ・マップ全体を見た時、自社の能力の弱点が一目瞭然となります。
次回は
さて、ケイパビリティ・マップの作成について述べましたがいかがだったでしょうか?考え方としては単純なマップなので、イメージし易いと思いますが、やはりその抽象度の設定を慎重に考えることがコツになります。
次回は、ちょっとややこしくなりますが「価値創造の流れ(Value Streames)」マップについて説明します。
筆者的には、最低ケイパビリティ・マップとバリュー・ストリーム・マップの2つがあれば、ビジネスの全体像の理解に繋がると考えています。どうぞお楽しみに!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
