
スコア・リーディングの勧め、或いは「謎」
今日はクリスマスです。昨夜、私は家族で外食をして暴飲暴食をしてしまいました。先ほど起床したばかりです。しかも極度の「胃もたれ」。最近、胃腸の調子が悪く、胃薬を飲むことが多いです。今日も先ほど飲みました。それでなくても私は成人したころから消化器系が弱く、トイレと大親友なのです。年齢も年齢なので、きちんと病院で精密検査しろ!と有難いお言葉をいただくのですが、検査内容が想像に難くないので、躊躇している次第なのです。
という言い訳を前書き替わりにして、私が以前、ラジオ番組に投稿した内容を #拘りと偏見の音楽 (第5回目)にさせてもらおうという、言うなれば「使い回し」の口実にしているだけなのです。
クラシック、それもオーケストラ好きの方には是非とも、好きな曲のスコアを見ながら演奏を聴くことをお勧めします。「一粒で二度おいしい」からです。ある程度、その曲を聴き込んだら、ポケットスコアを見ながら聴いてみてください。その曲の新たな側面が見えたり、新たな発見があったりするはずです。作曲家にもよりますが、そもそも想像していたのと記譜に乖離があるのが普通です。だから面白いのですが...
とはいうものの、最初は演奏される速さに着いていけないけないと思います。それでも何回か、何曲か見ていくうちに慣れてくるはずです。まずは小編成でテンポもAndanteくらいのものが良いかもせれません。最近はネット上でもいろいろとスコア・リーディングについて解説していたりしますので、それを参考にするのも良いかと思います。
と、普通にこう書いておススメしてもきっと、やらないでしょ?私が消化器の検査に行かないのと同様に。なので、今回はおもしろい例題をお示しします。大変、珍しいことなのですが、プロのオーケストラの演奏が間違っているのです。それも結構、わかり易く。それもそれも聞いて驚くなかれ、かの「カラヤン&ベルリン・フィル」ですよ。
私がこのCDを買ったのは30数年前。先ほど調べたら、いまだに販売されています。まだ、ライブ録音ならわかります、一発勝負ですからね。でも、そうでは無くスタジオ録音(最近はセッション録音とも言う、個人的には変な言葉だと思いますが...)であるにもかかわらずです。曲は「ショスタコーヴィチの交響曲第10番」です。どこが間違っているのかというと、第4楽章の一番最後、感動のフィナーレの部分のティンパニが1小節ずれているのです。
まずは、間違い探しです。その音源とスコアだけを掲載します、おわかりになりますか?ちょっとテンポが速いですが。
【ファイルを削除しました】
では、タネ明かし。ショスタコーヴィチは良く自分の名前をモノグラムにして作品の中で使用するということをしています。「Dmjtri SCHostakowitsch(ドイツ語表記)」のボールドの4文字、D、S(Es)、C、H、を4つの音にして曲のモチーフにするのですが、これを「DSCH音型」と呼びます。第4楽章はこの「DSCH音型」が曲の終盤、随所に出て来ます。間違っているのは、ラスト2ページ、ティンパニがこの音型を連打する箇所で、勢い余ったのか、1小節分多く叩いてしまっているのです。ただ、そうなると1小節ずれてしまうので、すぐさま、1小節削って上手く帳尻を合わせているので、曲の最後はきちんと合っています。
【ファイルを削除しました】
それにしてもです、あの完璧主義者のカラヤンが、間違った演奏をなぜ、CD化したのでしょうか?。ディレクターやレコーディングエンジニアも、本当に些細なところまでチェックしているはずです。間違いに気づかないってことは無いと思います。そもそも、ティンパニ奏者は自分の間違いが分かっているはずですし...。普通だったら、録り直して然るべきだと思います。
しかしながら、このCDは最初に書いたとおり、現在でも販売されているのです。それは何故か。1981年の録音なので、もうちょうど40年経ってますが、いまだにこの曲のベスト3に選ばれるくらいの名盤だからです。カラヤンが生涯に録音したショスタコーヴィチの作品は、この交響曲第10番だけなのですが、2回も録音しているのです。つまり、それだけこの曲には思い入れがあったんだと思います(今回のCDは2回目の録音)。その甲斐あってか、とんでもない名演なのです。一番最初にこの演奏を聴いた時の、心臓を鷲掴みにされたような緊張感や切迫感は、今でも覚えています。良い意味でも悪い意味でも、ショスタコーヴィチらしさよりも、カラヤン色が色濃く出ていますけどね。とにかく、演奏が間違っていようが何だろうが素晴らしいので、初めてこの曲のCDを買うという人がいれば、このCDをお勧めします。
おお!そんなこんなしているうちに、胃もたれが治ってきました。太田胃散、いい薬です。
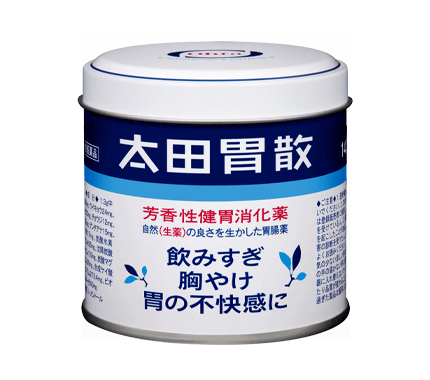
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
