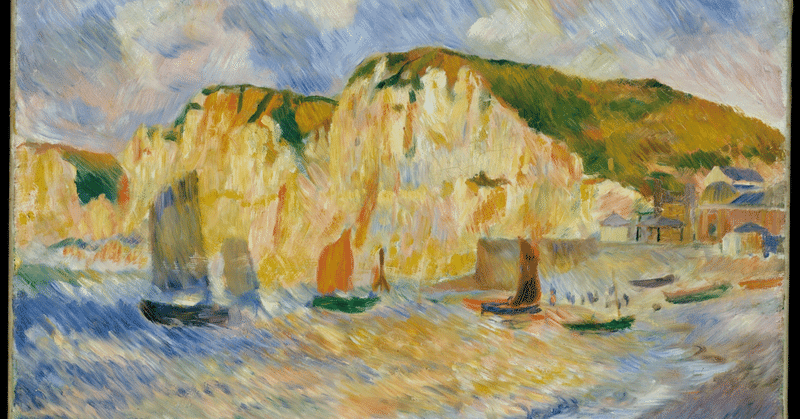
お菓子の家のゆめみたい
「天使の姿をみたいと思わない?」
その話を持ちかけられたとき、考えられる頭じゃなかった。差し出された手が、誰のどんな思惑でも掴んでしまっただろう。殺してあげるといわれたとしても、そんなに楽なことはないと喜び勇んで飛びついたはずだ。
私は布団で寝ている。ガスコンロがある。電気はついていない。冷蔵庫は空っぽだ。拾った千円札がある。貯金はない。10日には10万もらったのに口座は空っぽだ。部屋の隅には食玩が山になっている。お菓子は食べられないからいつも捨ててしまう。
はずれ。はずれ。また、はずれ。私の買う食玩は、合計5種類の中でひとつがランダムに入っている。パッケージに描かれている5種類のほかに、1種類のシークレットが存在している。
はずれ。はずれ。またまた、はずれ。パッケージの玩具が魅力的だったわけじゃない。お菓子が欲しかったわけじゃない。シークレット。シルエットだけの、黒い影をみたら、買っていた。スーパーを回って、店員にバックヤードから箱入りで出してもらった。
千円。二千円。ダース単位で入っている箱で買っても、ひとつひとつはそれほど高くない。
一万円。二万円。
はずれ。はずれ。
買っている間に、食玩コーナーでほかのシークレットをみつけた。まただ。ATMもよくないとおもう。お金を簡単に手渡すくせに、引き止めてはくれない。お金を貸してほしいと頼んだときのお隣さんぐらい、ちゃんと返せるかしつこく聞いてくれてもいいのに。何に使うか、生活費に余裕はあるか、職員さんぐらい確認してくれてもいいのに。黙って、やさしいふりで、お金をくれるからよくない。どこにでもあるし、人目も少ないのがよくない。十万円ぐらい、簡単にぜんぶおろしてしまえるのがよくない。また、はずれだ。
四畳半には食玩が山になっている。お腹が空いて、仕方なくお菓子のラムネを舌にのせた。粉っぽい甘さが唾液で溶けていく過程が気持ち悪くて吐き出した。駄目だ、お菓子は食べられない。甘くても、しょっぱくても、かたくても、やわらかくても、少しも食べられない。思い出すからだ。思い出したくないからだ。
アラームが鳴った。朝8時になっていた。日当たりの悪い私の部屋は薄暗いままだ。
お金がないのに、ケータイだけはもたせられた。いっしょに契約に行ってくれた職員さんがぜんぶ教えてくれて、私は言われた所に名前を書くだけでよかった。ケータイを買ったのに、代金を渡していないことが不思議だった。職員さんはすこしズルい充電の仕方も教えてくれた。これ、ナイショね。片目をつぶった笑顔はチャーミングで、童顔に可愛げをトッピングしていた。かわいい、とおもった。天使みたい、とおもった。
「あの……ごめんなさい」
『体調はどう? どこか痛かったり、寒かったりしない?』
電話口であやまっただけなのに、職員さんはやさしい。布団から起き上がれない私をけして責めない。甘えているなぁ。バイトに行くこともできません、と口に出すことさえも甘えている。やさしい口調がいけない。心配してくれるのがいけない。怒らない職員さんもいけない。
『お腹へってない? きょうは私もサボっちゃおうかな。お昼すぎぐらいにお家に行ってもいい? もし気分が良くなってたら、お肉でも食べにいこうか? いやぁ、煙たいのはだめだね。グゥさん、くしゃみ止まらなくなっちゃうし。あ、そうだ、グゥさん辛いの好きだったよね?』
職員さんは身体に悪いものでも平気で食べさせてくれる。私が辛いのを食べるのは吐き出せるからだ。吐き出せば、吐き出しているときは辛くとも、出してしまえば少しだけスッキリする。私の内側に溜まったどうしようもない悪いグズグズが外に出てくれたみたいで。吐きすぎたせいで喉が焼けても、辛いものでお腹を下してバイトに出れなくても、職員さんはやさしい。背中をさすってくれて、吐いたものを片してくれる。
職員さんは絶対に『だいじょうぶ』とはいわない。『だいじょうぶ?』とも聞かない。私が世間的にだいじょうぶでないのは一目瞭然だからだ。
私は昔からいつもお腹がへっている子だった。食べられないし、吐き出すしで、常に胃が空っぽだった。一度だけ、お母さんがどこかのスーパーのお菓子売り場に連れて行ってくれて、好きなだけ選んでいいよといってくれた。私は棚の前で、それこそ何時間も、お菓子を値踏みしていた。なんでもいいといわれたのだから、ひとつに選ぶ必要なんてなかったのに、私は時間を掛けてシークレットを探していた。一番いいものを選び取ろうとしていたのだと思う。とうとう空腹に耐えかねて、お菓子の袋を勝手に開けて食べ始めたとき、店員にみつかって声をかけられた。迷子のアナウンスが響いた。お母さんは現れなかった。バックヤードでお菓子を食べさせてもらっていた私はそのことを理解できなかった。その時食べていたアソートの味は覚えている。お母さんの姿は天井の蛍光灯に照らしだされて、暗い影でしか思い出せない。どんな顔だったっけ。どんな声だったっけ。もう覚えていない。
「辛くってさ、癖になるんだよねぇ〜。でも、刺激だけじゃなくて、ちゃんと旨いんだね」
職員さんはテンションがあがると、おいしいじゃなくってうまいという。なかば引きずられるようにしてやってきた激辛ラーメンの店。器からラー油が蒸発して、鼻の粘膜を刺してきた。食べる前から鼻水を垂らした私を、すこしも気にせず盛大に一口目をすする職員さん。吸い込んだ粉末唐辛子にもめげず、むせながらバリカタ麺を呑んでいく。いつ見ても気持ちのいい食べっぷりで、私もつられてひとつまみ。湯気を呑み込んだ先から汗が吹き出していく。スープが食道を伝っていくのがわかる。熱の塊が体内を燃やしながらゆっくりと落ちていく。溶岩だ。おもたく、真っ赤に血を舐める、力強さの象徴。激辛ラーメンは火山に似ている。まっかな溶岩を湛えて、もやしが山とそびえている。憧れているんだ、激辛ラーメンから立ち昇る力強さに。
すする。痛い。真っ赤だ。眼がチカチカする。胃がおかしい。止められない。噴き出した汗と涙と鼻水で、私が内側から溶け出していく。塩をかけられたナメクジみたいに、水分が絞り出される。どろっとした油膜の張ったスープ。赤いおもい水が飛ぶ。たべる。たべる。のむ。体はわかっている。急な刺激に叩き起こされた胃が痙攣している。喉も引きつっている。舌は麻痺している。たべる。たべる。痛くても、苦しくても、やめられっこない。
「グゥさん!」
職員さんが慌ててナプキンを差し出す。赤くおもたい汁が飛ぶ。ぬるい。これ、私の鼻血だ。
あっ、と思ったときには手遅れで、ロクに噛まずに呑み込んでいたから喉にもやしをひっかけた。水に伸ばした手を勘違いした職員さんがナプキンを握らせ、私はえずくのを抑えられなかった。
「はい、これで拭いて?」
噴火が起こった。ひどい匂いだった。
私は自分の吐瀉物におぼれて目を回した。それでも吐き気は収まらなくて、呼吸もままならない。私は真っ赤な胃液を吐き出し続けた。
「ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい」
無理して辛いものを食べて、毎回全て吐き出して、その度に出禁を食らって、職員さんは私の粗相を片付けて迷惑料を多めに支払う。
「ごめんなさい」
「うん。また新しいお店探さなきゃね」
職員さんは家まで付き添い、介抱してくれた。私は毎回謝ることしかできない。口に張り付いたごめんなさいは、塞がりかけてはむしり取ってしまうかさぶたみたいだった。
その後、私が疲労で寝落ちしてしまうまで、他愛ない話を聞かせてくれた。職員さんはお話のネタが豊富で、どんな些細なことでも楽しそうに、ドラマみたいにしゃべって尽きることはない。
「天使っていると思う?」
私は半分枕に沈んでいて、返事を考えることができなかった。
「ある有名な芸術家は、大理石のなかに天使をみつけたんだって」
「私はいると思うな、天使。そうじゃなきゃ、可哀想じゃない?」
「どんな子でも、生きていてよかったって思わせてくれるような」
それって、まるで職員さんみたいなひとだね。私はお金をもらったって、私みたいなヤツの世話を焼くことなんてごめんだよ。自分のことを脇に置いたとしてもね。
目が覚めたら、暖かいカップスープが見計らったように用意してあった。食べ物の香りで猛烈に吐き気を催すかと思ったけれど、私は昨晩どころか、ずっと食べていなかった。傷だらけの胃と食道には、優しいだけで味の薄い出涸らしみたいなスープでも十分だった。夢中で飲み干した。少しずつなんて我慢がきくヤツだったなら、こんな有り様になってない。下腹部に排水溝ができたみたい。飲み込んだ先から空腹感に引きずり込まれて消えていった。お腹が減った。普段だったら絶対に食べないけれど、いつが消費期限だったかも忘れた食玩のお菓子に手を伸ばす。ラムネでも、グミでも、ウエハースでも。なんでもいいから食べたかった。
「天使の姿を、みたいと思わない?」
手首が掴まれた。職員さんがまだいたことに気づかなかった。
天使はいるんだよ、と職員さんは言った。私がみつけた天使だよ、と。その瞳には逆らえなかった。
私が連れて行かれたのは、街中の、大学の構内のようだった。前に一度、職員さんは大学生で、実はアルバイトなのだと聞いたことがあった。
その建物は体育館のように天井が高く、床も天井も白一色で塗りつぶされていた。薄い合板の建屋内は、透明なアクリルで囲まれた二重構造になっていた。十メートル四方の透明な立方体いっぱいに、焦げ茶色のブロックが詰め込まれていた。
「これね、私の卒業制作なんだ」
「なんだかおっきくて、迫力すごい。もう完成なの?」
空腹は私の頭を絞るほどだったけど、情けない感想を置いた。私にはなにがなんだかわからないし、ゲイジュツの遠さは宇宙規模だった。
「まだ素材のまま。これから削るんだよ。用意するのも大変だったけど」
「削るのも大変そう。だってこれ、ずっと大きいよ。なにができるの?」
「天使を」
職員さんは区切られた部屋に入る扉を開けた。
匂いがした。甘い、すっぱい、辛い、しょっぱい、香ばしい。いろんな匂い。お腹がすく匂い。
「さぁ、思う存分。あなたの天使を自由にしてあげて」
誘われるまま、指を伸ばした。日干しレンガに思えたブロックの表面は、焼き立てのパンのようで、大した抵抗もなく指が沈み込んだ。
すんなり私の意識は食欲に飲み込まれた。
「ずっと思ってたの。グゥさんかわいいなって」
どこかから職員さんの声がする。私はそれを上の空で聞いていた。体と思考は分離して、脳だけが浮かんで漂っている。ひどくぼんやりした気分だった。手と口は慌ただしく動き回っていた。あいにくだが、返事はできそうにもない。
「ブロックは炭水化物と脂質で――つまりはバタークッキーね。食べやすいようにやわらかく作ったんだ。グゥさんは消化も嚥下機能も衰えているから。ちゃんと飽きがこないように工夫したんだ。ランダムな味付けを分布させているの。もちろん、どの味もグゥさんの好みに沿った、美味しく感じられる味だと思うな。グゥさん、見た目の割に濃い味付けが好きだから。食べっぷり見ていればわかるよ、美味しいでしょう?」
貪るごとに、シルエットでしか知らなかった影が近づいてくる気がした。歯を立ててかぶりついて、鷲掴みでむしり取って。穴でも掘るように、私は巨大なブロックの内部に埋没していく。抑制できない食欲の内側に沈んでいく。たべても、たべても、みたされない。
これまでもそうだった。たくさん吐き戻した次の日には、強すぎる空腹のせいで、朝に出されたゴミ袋に顔を突っ込んでいたこともあった。我慢ができない。私にはなにも、抑えることができない。
「グゥさんをみているだけで、私は生きていることを勇気づけられるの。だからね」
あなたの天使さんも見つけてほしいの。
その大きな、素材のなかから自由にしてあげてほしいの。
たべても、たべても。シルエットの背中に追いつかない。
顔を見せてほしいのに、ベタ塗りの記憶は黒い影のまま。
「好きなだけたべて。私の天使さん」
彼女は私に呼びかけた。
私は食べ続けた。目の前の茶色い塊を貪り続けた。
私は職員さんの名前も知らなかった。
はずれ。はずれ。また、はずれだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
