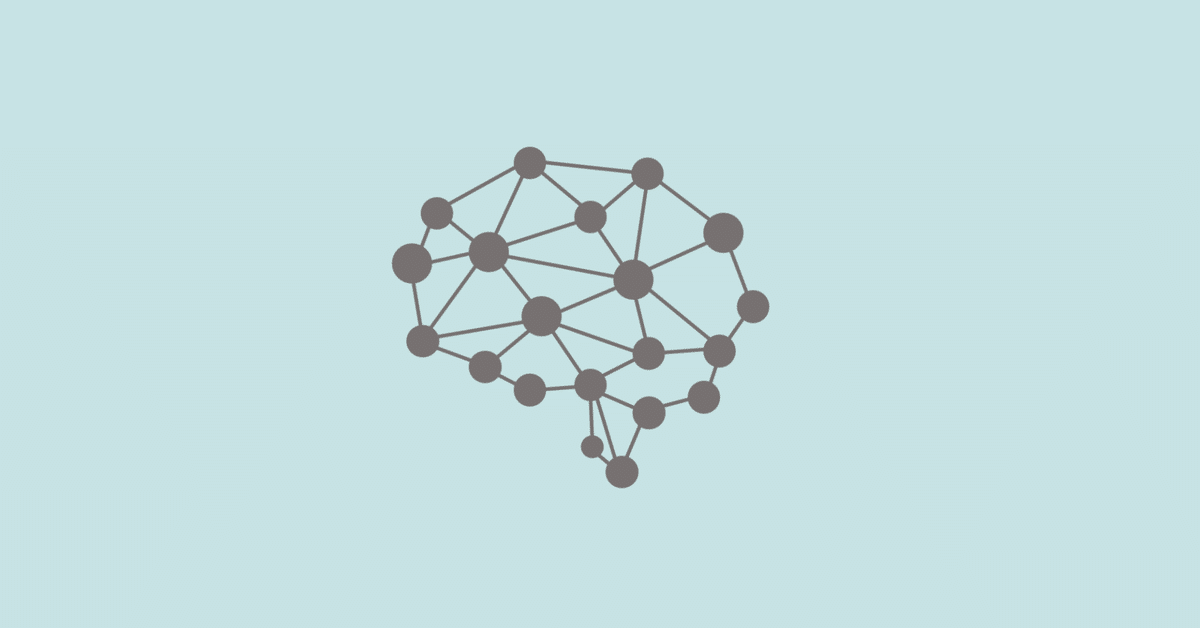
分離した脳の理解を通して見る世界:The Matter with Things(読書メモ)
(この記事の英訳が著者のウェブサイトに掲載されました。尚、このウェブサイトにはマギルクリストのトークのビデオなど豊富に収録されています)
人の記憶はあいまいで、しばしば後から話を作り上げる。人は不合理なバイアスに支配されており騙されやい。脳科学や行動経済学の本を読むのが好きで、こうした脳についてのいろいろ知識を仕入れてきたが、それで何が本当かを見分ける力がついたり、より良い人生を送るための指針が得られたりしたかというと、残念ながら、そのような手応えはなかった。
Iain McGilchrist (イアン・マギルクリスト) の「The Matter with Things(モノの問題)」 は現代文明が抱える問題の背後に何があるか、世の中の様々な言説をどう評価すべきか、さらには宇宙や私たち自身の本質とは何かまで、確かな拠り所を与えてくれる本である。マギルクリストは、オックスフォード大学で英文学を学びフェローとして文学や哲学の講師・研究者として人文学の深い素養を身につけた後に、医学に転じ神経画像の研究者や精神科医としての実践を積んだ。昨年11月に出版された本書は1,500ページを超える大著(Kindle版は2,996ページ)で、専門である神経心理学や哲学に加えて物理学や生物学まで実に幅広い文献を参照して議論を展開している(参考文献だけでも180ページに及ぶ)。また、もともと文学研究者であることから、随所に詩や神話から豊かなイメージを持つ言葉が引用され、この本でマギルクリストが描き出す新たな世界像を深みのあるものにしている。まさに碩学と呼ぶにふさわしい人である。
この本は序章と本論3部から構成されている。このメモは私が着目し解釈した限りでの本書の論旨だが、誤解や読みの浅い点も多々あると思うし、その豊かな内容を伝えられているか自信はない。関心をもたれた方は是非、原書をあたっていただきたい。 (引用箇所は私訳でページ数はKindle版による)
序章では脳の左半球と右半球の違いとその影響についてあらましが語られる
ヒトの脳の左半球と右半球がそれぞれ固有の性格を持つほどまでに分離し、世界を2つの大きく異なった方法で見ている。近代以降の西洋文明(西洋に限らず先進国共通だと思うが)は左半球に偏った世界観に支配されており、このことが環境破壊、疎外感、極端な立場同士の深刻な対立など現代の文明の危機の根底にある。マギルクリストは2009年出版の「The Master and His Emissary」において、すでにこの説を展開していたが、本書「The Matter with Things」ではこの脳半球に関する仮説をベースに、人間はどのようにして物事を正しく知ることができるのか(哲学の認識論の問題)、さらには、空間、時間、意識、物質など世界の基本的な構成要素の本質にまで深い考察を展開している。
脳の左半球と右半球が分離しており、機能に大きな違いがあることは1981年にノーベル賞を受賞した神経心理学者ロジャー・スペリーとその弟子であるマイケル・ガザニガの研究で良く知られている。しかし、一般向け読み物などで科学的根拠のない拡大解釈や歪曲された情報が広まったこともあり、脳科学の分野では長い間、左右の半球の違いは真剣な研究分野とは見なされてこなかった。マギルクリストは世間一般に理解されているイメージ ―左脳は言語と数学を担当し、理性的、感情に左右されず信頼できる、真面目な会計士;右脳は画像処理を担当し、クリエイティブだが感情的でやや信頼できない夢想的な芸術家― は誤りだという。実際には両方の半球ともすべてに関わっている。例えば言語の文法や語彙の機能が左半球に集中していることは事実だが、文脈の理解はむしろ右半球に深く依存している。違いの本質は、それぞれの半球が何を扱っているか(What)ではなく、いかに、どういう方法で扱っているか(How)にある。左半球は、操作したい細部に的を絞って注意を払い、右半球は、世界に対して広く、オープンで、持続的、警戒的な注意を払う。こうした脳の非対称性は進化論的に説明できる。動物は生存のために、食べられることなく食べるという難題を解かなければならない。鳥は砂利の上にあるタネを見分けて素早く正確に拾い上げ、あるいは小枝を使って巣を作らなければならない。しかし、生き残るためには、同時に捕食者に警戒し敵と同類を見分ける、幅広い、オープンで、持続的な注意を世界に払う必要がある。左右の機能分化は哺乳類のみならず、鳥類、は虫類、両生類、魚、さらには虫や軟体動物にまで見られる。人間では左右の半球を接続する脳梁の神経経路は小さく、特に分離度が高まっている。重度のてんかん症治療法として脳梁を離断する手術が行われることがあるが、術後に患者が欲しい物に右手を伸ばそうとすると、そこに左手が割り込んできて争う症状を起こすことがある。これは、左右の半球が固有の意識を持つほど、はっきりと分離していることを示している。
注意の向け方の違いにより、左半球と右半球が生み出す世界は全く異なったものになる。左半球にとっての世界は、見慣れ、確かで、固定され、孤立し、明示的で、文脈から離れ抽象化され、実体がなく、一般的で、数量化でき、部分によって説明できる生命のない世界である。 右半球の見る世界は、ゲシュタルト心理学でいうゲシュタルト (全体性を持ったまとまりのある形態) の世界であり、部分への分解によっては説明できない、ユニークで、常に変化して流れ、相互に結びつき、暗黙的で、文脈の中でのみ理解され、実体がある生きた世界である。右半球の世界は私たちに現前する(presences[*1])経験そのものの世界であり、左半球の世界は地図のように抽象化された表象(representation)の世界であると性格づけられる。表象された世界は実経験の世界の豊かさを持たない。

現実世界とコンタクトするのは右半球であり、そこで経験された材料は左半球に渡され、そのルールや手続きに従って処理、分析される。その結果が右半球に戻され、そこで再び現実世界と照らし合わせて再評価され新たな理解として統合される。これが両半球の実りある協働のあり方だが、左半球は、その視野が狭く確かなものを求める性向により、しばしば自分が知っていることが正しく、それ以外のものは存在しないという「either/or」の姿勢を取る。これに対して幅広い可能性にオープンで曖昧さを許容できる右半球は左半球の見方も含む「both/and」の姿勢を取ることができる。マギルクリストは両者の関係は対等ではなく本来は右半球が主君で左半球は家来の立場であるべきだという(前著「The Master and His Emissary」のタイトルは賢い主君(右半球)に仕える有能な使者(左半球)が実際に物事を知り働いているのは自分だと過信して主君として振舞った結果、栄えていたコミュニティが滅びてしまう寓話に基づいている)。左半球が分析したことを右半球がとりいれることで全体の理解は豊かなものになる。
左半球と右半球の世界観は両立し得ないものだが、日常の生活で私たちがこの対立を意識することはない:私たちは世界が複雑、多面的で真実は常に部分的であらざるを得ないことを認め、その時々の状況に応じて賢く、自覚することなく、いずれかの半球が与えてくれるものに頼っている。しかし、現代の公の場面では、あいまいな態度は弱さと見られ、人は不自然なまでに自己整合的であることを要請される。こうして、より単純で、白黒はっきりし、明瞭な言語化ができる左半球の見方が優先的に採用される。
現代科学文明のコアにあるのは、世界は、それを構成する要素に分解し、分析すれば理解できるはずだとする左半球の世界観に従った還元主義(reductionism)である。還元主義は、モノの宇宙、それも単純に物質的なモノの宇宙を想定している。自然は意味なく衝突を繰り返す粒子の集まりにすぎず、モノを部品に分解し、観察し、積み上げていくことであらゆるものの性質を理解できるとする機械的な世界観である。マギルクリストはこの見方は、自然世界を物理的に破壊しているだけでなく、心理的、道徳的、精神的にも私たちを傷つけており、私たちが価値をおくべきものを損なっていると警告する。The Matter with Things ―世界はモノ(things)でできているという考えに問題がある(the matter)。
第一部「半球と真実への手段」では注意、知覚、判断、理解、感情と社会的知性、認知的知性、創造性について各半球がそれぞれどう貢献しているか、いずれの半球の見方をより信用できるかが議論される
マギルクリストの描き出す半球の性格は、脳梗塞や腫瘍などの病変や磁気刺激によって一時的に片半球の機能を抑制する実験など神経科学と精神医学の豊富な証拠に基づいている。左半球の使命は自分のために世界を操作・コントロールすることであり、正確さを求め、視野が狭く、比喩、ユーモア、皮肉を解せず、ものごとを文字通りにしか理解できない。短絡的に結論を出し、自分が知っているものが全てと信じ、自信過剰で、楽観的で、騙されやすい。右半球はより慎重で広い視野を持ち異常に気づく能力がある。他人の心を理解し共感する能力も右半球による。マギルクリストは知覚、判断、知性全般において右半球が左半球よりも信頼がおけると結論づける。右半球部分の脳梗塞などにより左半球に依存せざるを得なくなった人には、統合失調症や自閉症に典型的な妄想的な症状を示す例が多く見られる。そのような人にとって世界は生気を失った非現実的なものと見える。他方、左半球の病変では、右半身の麻痺や発語の障害が多く見られるものの、人格や世界に対する認識に大きな変化は見られない。各半球の特徴的なパターンを理解して、様々な思想や社会現象に、いずれの半球の「筆跡」が確認でいるかが分かれば、それはより確かな理解に向けた進展といえるだろう。
第二部「半球と真実への道筋」では科学、理性、直感、想像力など人間が真実を探求するときに辿るルートが半球仮説のレンズを通して検討されている
理性には2つの側面がある:限られた範囲での因果関係を探る逐次的で直線的な左半球の分析的な思考(合理性、Rationality)と、広い見地からの統合的で全体的な右半球の理解(分別、Reason)の2つの相反する側面である。科学は世界がどう動いているかを説明し、環境をコントロール・操作することに大きな成功をおさめてきた。それが左半球の分析とメカニズム解明の能力によっていることは疑いない。しかし、科学や合理性が提供してくれる知識の範囲と種類には限界がある。科学は主観を排して客観性を追求しようとするが、前提と価値観から自由ではあり得ない。客観は常に誰かの立場であり「どこでもないところからの眺め[*2]」は存在しない。科学におけるデフォルトのメタファーは機械である。しかし、すでに機械モデルの説明能力の限界が見えてきている。生物は機械のように分解しても理解できないし、部品から組上げることはできない。マギルクリストはリチャード・ドーキンスなどネオ・ダーウィズムの論客が機械モデルに固執していることを批判する。科学的手法の重要性はもちろん否定されるものではない。科学的に確かめられたことには大きな価値がある。しかし、真に偉大な科学の発見は、右半球の直感と想像力によってもたらされてきたことを忘れてはならない。
右半球に依存する直感は、無意識で自覚していないことも含めより速く、より多くの要因を統合することができ、明示的な推論よりもむしろ信頼できる。経験に基づいて形成された専門家の無意識のマインドは多くの情報に同時にアクセスし、しかも情報同士の相互関係性も理解する驚くべき能力を持っていると考えられる。マギルクリストは、驚くべき的中率を持つ競馬予想屋や世界で最も危険な競技と言われるイギリスのマン島のバイクレースのレーサーの認知プロセスなど、直観の驚くべき力について興味深い事例をここであげている。行動経済学では直感に基づく瞬間的な判断の多くは、間に合わせ(quick and dirty)のヒューリスティックによるもので信用できないので、意識的に熟慮する重要性が説かれている[*3]。マギルクリストは直感が実際には幅広い要素を統合して判断する力を持っており、複雑なパターン認識においては意識的な考慮よりも、むしろ優れた結果を出すという。暗黙知に基づいた優れた専門家の直感を明示的なルールや手続きに置き換えることは逆効果だという。
洞察は直感から生まれるが、しばしば直感に反する意外なものとなる。見慣れたものに新たな形や美しいパターンを見いだし、似ていないもの類似性を見いだす想像力は科学の進歩や、優れた芸術に欠かせない。想像力は意思の力で呼び起こせるもではなく、無意識の働きに依存している。小説家はしばしば登場人物が勝手に動き出し物語を進めるというが、そこでは自己と他者の境界はあいまいである。マギルクリストのいうように、世界は単に受動的に認知されるものではなく、かといって頭の中だけで生み出されるものでもなく、「半ば創造し、半ば認識する」(ワーズワースの詩の一節[*4])ものとして立ち現れる。「私たちの経験する世界は私たちと世界の出会いの中で常に新たに作り出されている・・・現在の認知は過去の知覚と予測の相互作用の上に常に新たな経験が影響し成り立っている」[*5]。誰とどこにいるか、どういうムードか、どういう動機を持っているかなど全体の文脈が関係している複雑で豊かな実体を持つ経験である。通常の経験の多くは退屈な現在の知覚の追認にすぎないが、時に私たちは真に新たなユニークな経験をする。表面上変化はなくても核が全く別のものとして経験される奇妙で畏敬の念を覚えるインスピレーション、洞察の瞬間、「見えた」瞬間である。このように想像力は現実と結びつき既知で見慣れたものを新たなユニークなものとして再創造する働きであり、実体験と関係なく頭の中だけで既知のものを目新しい方法で異なった配置に組み替えるだけのファンタジー(空想)とは明確に区別される。
現実の理解には科学、理性、直観、想像力のどれか一つに頼るのではなく、できる限り全てを適用すべきである。左半球と右半球の両方が寄与するが、最終的には左半球も含めた統合的な見方ができる右半球が頼りになる。
第三部「現実の意外な性質」では、脳の半球に理解に基づいて時間、空間、物質、意識など宇宙の基本構成要素の本質が議論される。
さらに次のような哲学の最も根源的な問いに対する一つの新しい見方が提示される:「なぜ、何も無いのではなく、何かが在るのか? その「何か」は、無意味で醜いカオスではなく、なぜ複雑で美しく秩序立っているのか。なぜ宇宙は物質の存在を可能にするように、完璧に、絶妙に、微調整されているのだろうか。そして生命や感覚のある存在を可能にするのはなぜなのか。そして、なぜ私たちはその複雑さ、美しさ、秩序を理解することができるのか?」[*6]
私には、ここでマギルクリストが論じていることを適切に要約する力はない。また、それは言葉にできない現実の深い本質を豊かなメタファーや神話の力を借りて伝えようとするマギルクリストの努力の精神に反することになるだろう。しかし、ここでは今後この本を再読し、より深く勉強していくために、私にとって特に深く響いたテーマをいくつか書き留めておきたい(できれば、この内のいくつかのポイントについてはまた別途書いてみたいと思っている)。
1.対立するものの一致によって深い真理に近づく-Coincidentia Oppositorum (Coincidence of Opposites)-
パラドックスは時に深い真実を含む。対立するように見える真実が同時に成り立つこと、さらに対立するものが調和することで豊かな形と構造が生まれるという洞察 -Coincidentia Oppositorum(対立物の一致[*7])- は古代ギリシャのヘラクレイトス、エンペドクレスや中国の陰陽思想に見られるもので、近現代ではヘーゲル、ゲーテ、ニーチェ、シェリング、ベルクソン、ジェームズ、ホワイトヘッドなどの哲学思想に通じる(マギルクリストは触れていないが日本の西田幾多郎の哲学の鍵となる概念でもあるらしい)。
一つであることと多数であることのパラドックス(「All is One, All is Many」)は特に重要なテーマで、複数の含意を持つ。一般性と独自性の対立はその一つである。この世界に存在するもので他のものと全く同じものはない。従って現実をありのままに見るためには、まず対象をユニークなものとして見なくてはならない。しかし、物事の本質をとらえるには、それが他のすべての物事とのコンテクストの中でどのように位置づけられるかを知る必要があり、そのために一般性が要請される。あるレベルでユニークなものは、別のレベルでは一般的で、あるレベルで一般的なものは、別のレベルではユニークである。私たちは、ユニークなものと一般的なものの両方を同時に見なければならない。「子どものころは、『鳥さん!』『うさぎさん!』『ワンちゃん!』というように、すべてがユニークなわけではなく、世界に形を与える一般的なカテゴリーがあることを発見することに興奮を覚える。…大人になった私たちは、これに慣れきってしまっており、逆に慣れきったものにユニークさを取り戻した時に興奮を覚える」[*8]。 「一方の極端では全て同じであり、もう一方の極端では何一つ似ていない。どちらの極端にもパターンがない。もし一般的なパターンが全くなかったら、そこにはユニークさではなくカオスしかない。コンテクストに応じて最も豊かなパターンが現れるレベルを見つけることがこつである」[*9]。対立とその調和は、現実を生み現実に多様な形や構造を生み出すプロセスであり、美とはこの同一性と差異の調和を体験することに他ならない。
個々の独自性と全体としての単一性を同時に理解できるのは右半球である。右半球は違いの中に類似性を見いだす統合的な気質と類似性の中に違いを見いだす微細な識別能力を併せ持っている。左半球の分割的な性向は、類似性と違いを互いに相容れない単純な対立としてしか見ない。
2. 万物は流転する
「私たちは速く変化するものはプロセスとして、ゆっくり変化するものはオブジェクトとして見る。宇宙的スケールで見れば、噴火し、流れ、堆積し、そして浸食される山は、便宜的に境界を持ち、しばらくの 間だけ永続性を持つにすぎない:銅像、詩、人間でも同様だがより明らかなように。万物は流転するというのは、本当に真実である」[*10]。
流れ、動き、プロセスが現実の本質であり、それが固定されたモノとして見えるのは左半球の分析的な心がなす一種の抽象化の働きである。物質は、しばらく永続するプロセスにすぎない。流れの中の要素は互いに浸透しており分割できない。モノが先にあってそれが動くのではなく動きそのものがモノに先立って存在する。マギルクリストはこの洞察を表すものとしてイェイツの詩の一節「どうして踊り手と踊りを分かつことができようか」を繰り返し引用している。[*11]
3. 関係が関係するモノに優先する
私たちが慣れ親しんだ考え方では、まず物質が存在し、その後に物質同士の関係が決まる。しかし、マギルクリストによれば「関係というものは、関係するものよりも第一義的であり、より根源的」であり、関係は、「単に既存のものを『つなぐ』だけではなく、『モノ』によって意味するところを変更し、その結果、それらが関係する他のすべてを変更」する。モノの性質は関係のあり方に他ならない[*12]。このような考え方は量子論の先端の物理学者に通じるものである。イタリアの物理学者のカルロ・ロヴェッリが量子論について書いた「Helgoland」という素晴らしい本が昨年日本でも出版されたが、その邦題は、まさしく「世界は『関係』でできている」[*13]であった。
対立するものの付かず離れずの緊張関係をマギルクリストは「betweenness」という言葉で表現し、日本語の「間」という言葉の意味に近いものだという。間は空間、時間、感情的な深さやエネルギーと感覚に満ちた創造的なポテンシャルを示唆する。「betweenness」で表される関係は、一方向ではなく相互的で再帰的なものである。そうした関係のあり方は関係しているモノよりも重要である。
4. 全体と部分の関係
全体と部分の関係も深い真理を含む対立と一致である。部分は、より小さな部分との関係では全体と見なされ、その全体は、より大きな全体との関係では部分と見なされる。部分が全体の性質について明らかにするのと同様に、全体がその部分の性質の多くを教えてくれる。
蜘蛛の巣のようにどこかを刺激するとすべての糸の張りが変化するように生物は本質的にシームレスに統合されている。生物の部分は、人間がそのときの関心に従って注意を向けたものをそう見ているにすぎない。それは機械の部品のように、全体を構成する前に存在するものではなく、全体と同時に生まれるものである。部品同士の関係だけでなく、常に全体との「betweenness」が問題になる。
5. 将来はオープンである 自然は贅沢な多様性を生み出す
世界の本質が、流れ、プロセス、関係だという洞察は、世界は因果関係の連鎖だけでは理解できないことを示唆する。直接的な因果関係は限られた時間と範囲内でしか成り立たない。将来は過去の条件から決定されるものではない。宇宙の歴史は絶え間ない多種性と独自性への分岐であったように見える。また生命の進化は新たな多様性を贅沢に生み出すプロセスに見える。オープンで全く新しいものを生む自然の創造力は決定論とは相容れない。
6. 自然の創造力:流れの中の抵抗の創造力
こうした自然の創造性について、18-19世紀のドイツ哲学者フリードリヒ・シェリングは、水の流れの中に水自身の抵抗によって多様な渦のパターンが生じる様に、宇宙に流れる原初的エネルギーが、流れを妨げる抵抗によって多様なモノを生み出すと考えた。渦は流れから見分けがつくが分離はしておらず流れそのものといえる。これも自らの中に他のものを含む、あるいは連続するものと不連続の間の対立の一致といえる[*14]。マギルクリストはこうした考え方は現代物理学の知見や最新の量子場の理論とも矛盾しないという。
7. 私たちには現実を直接経験する力が備わっている。意識は幻想ではない。
マギルクリストは意識という言葉を経験的なこと(the experiential)という広い意味で使っている(自覚的な意識のスポットライトがあたっていない無意識の領域も含む)。マギルクリストはベルクソンやジェームズの思想の系統に従い、私たち(右半球)が経験することは何か他にある現実の表象ではなく、現実そのものだと見る。これは意識に関する脳科学理論の主流の考え方と異なる。脳科学の主流は、私たちにアプローチできるのは私たちが直接には知り得ない現実の脳内における表象のみであり、私たちの感覚的な世界体験は一種の幻想であるという考え方をとる。マギルクリストは意識が幻想だという信念も意識によるものである以上こうした考えを「自爆的」と批判する。
何であれ何かを知るための基本が経験だということは確かである。私たちは、皆、経験というものを自分の経験から直接的に理解している。色、味、痛みの経験は現実であり、それを幻想と呼ぶ必要はない。騙されることが無いという意味では無い。経験そのものは動かしようがないが、その解釈は様々でありえる。しかし、身体性と創造性をもった生き物として私たちは決して現実から分離されていない[*15]。
8. 意識と物質は同じ現実の異なる側面を反映した現象である
メカニズムはまだ分かっていないが、意識は脳が生み出す現象に違いないというのが脳科学の主流の考えである。これに対してマギルクリストは、意識は物質的なものに還元できない宇宙に根源的なものだという。さらにこの根源的な意識は生物だけでなく無生物を含むすべてのものが持つという立場を取る(もちろんすべてのものが人間のような意識を持っていると言うわけではない)。これは非常に奇妙に思える考え方だが、汎心論(panpsychism)と呼ばれ多くの哲学者や物理学者支持されている考え方という[*16]。意識は物質的現象として説明できるはずという考えは、私たちはまだ意識について理解できていないが、少なくとも物質は確固なものとして知っているという信念に基づいている。しかし、既に見たように物質というものはそれほど確かなものではない。物質は一種の抽象であり、私たちが意識の中で物質的な属性を与えた要素をそこに見ているだけである。マギルクリストは意識と物質は同じ現実の異なった様相であるという:存在論的には意識が物質に先立つ。意識と物質は全く異なるものと感じられるが、氷と水や水蒸気と全く異なる性質を持つように、物質は意識の一つのフェーズと考える[*17]。
9. 脳は意識をフィルターする
脳と意識の関係をどう考えるか:マギルクリストは脳が意識を(1)発する (emit)、(2)伝送する(transmit)、(3)許可する(permit)という3つのオプションを挙げ、この中から(3)許可するという見方を取る。「脳の機能は許可によって創造すること、言い換えれば一種のフィルターとして働くこと」であり、「意識は彫刻される:ミケランジェロの手が、形のないブロックから石を取り除き、他の石を残すというプロセスによってダビデ像を誕生させたように、あるものに「ノー」と言うことによって、他のものが前に立って存在することを可能にする」という[*18]。
10. 価値と目的:新たな見方
マギルクリストが描く新たな世界像においては、意識は宇宙に根源的に偏在するもので、その中に生じる抵抗によって多様性を生み出す創造的な傾向をもっている。「根源的な意識は、創造という絶え間ない行為の中で、潜在的な可能性を実現することによって、自分自身を理解し、自分自身を実現する」[*19]という目的を持つ。
目的には2つの異なった意味がある。これも、左半球と右半球の異なる見方に対応している。一つは目的を外因的、道具的、決定論的なメカニズムに従い、狭く局所的に捉える左半球の見方である。例えばコピー機のコピーを作成するという目的はコピー機を設計した人間によって外から与えられる。二つ目は目的を内在的、未決定で自由で、広く全体に関わるものとする右半球の考え方で、例えば音楽や詩の目的はすべてそのプロセスの中で充足している(リラックスして仕事の効率を上げるという目的は本来の価値を損なっている)[*20]。
マギルクリストが描く宇宙の創造的なプロセスは、この2つ目の意味での目的―それ自身で充足する内在的な目的を持っている。それは、美、複雑性、豊かな独自性の展開に向けた傾向を持つが、決して、決定論的なプロセスではなく、宇宙のメカニズムを設計する全知全能のエンジニアとしての神を想定していない自由でオープンなプロセスである。
11. 価値と目的は人間が発明したものではなく宇宙・自然に内在する
真実、善、美などの価値は、一般に人間が作り出した概念と考えられている。これに対してマギルクリストは、価値は人間が発明したものではなく、宇宙に本来的にあるもので、それは発見され、明らかにされるべきものだという: 「宇宙の真理や善や美の可能性を生み出すのは私たちではない。私たちは、それらを実現する(あるいは実現しない)手助けをするのだ。私は、価値は宇宙に内在するものであり、価値を認め、それに応える可能性、つまりその可能性を満たすことが、宇宙が生命を進化させた一つの理由であると考える」。[*21]
唯物論は、すべては完全にランダムで意味はなく、物質以外に何も存在しないことを前提にしている。意識が存在するとすれば、それは進化のある時点で意識とは根本的に異質なものから二次的に生まれたものである。この考え方からでは、物事が秩序や美、目的に向かう動因を持っていることや、私たちが少なからずそうした価値を理解する能力を持っていることを説明できない。
マギルクリストのこうした目的論とランダムな突然変異と自然淘汰のメカニズムで進化を説明するダーウィンの進化論は互いに相容れないものだろうか? マギルクリストは、目的論はランダムな偶然やローカルなレベルでのメカニズムを排除するものではないという。むしろ、多様で自由な創造性を発揮するためにある程度のランダムさは必要とされる。
* * *
マギルクリストは最終章「聖なるものの感覚」で、「なぜ、何も無いのではなく、何かが在るのか?」そして「その何かは、無意味で醜いカオスではなく、なぜ複雑で美しく秩序立っているのか」という根源的な問いに取り組む。「存在の根拠 (ground of being)」は本質的に言葉で表現できないものであるが、それでも人間はこうした疑問を問い続けるために、様々な宗教を生み出してきた。
イギリス人に、宗教心があるかと聞くと、大多数が無いと答えるという。しかし、現実には科学で説明される物質的な領域を超えるものがあると思うか、と尋ねるとより多くの人々がイエスと答えるという。私自身もこのイギリスの多数派と同じ、どちらつかずの不可知論者(Agnostic)に属する。毎朝両親を祀った仏壇に手を合せ、命日や折に触れ墓参りをする習慣を持つが、特段の宗教心は持っていない。むしろ教条的な宗教からは距離をおきたいと思っている。しかし、一方で科学が説明できる範囲を超えるものが現実にはあるとは感じている。「聖なるもの」が、宇宙の設計者としての神や教義への盲目的な忠誠を強いる存在ではなく、マギルクリストの描くように、自由で豊かな多様性を生み出す宇宙の傾向とでも言うべきものに近いものならば、この本で繰り返し説明された右半球の幅広く、あいまいさを許容できるオープンなマインドを持って近づいてみても良いかも知れない。それには無意味でランダムな物質の世界で、生存のための有用性のみを価値として進化する遺伝子のメカニズムという「信仰」よりも、はるかに惹かれるものがある。
マギルクリストは、この本の中で数回、京都の龍安寺の石庭に言及している。龍安寺の庭には、15個の石が配置されているが、どの場所からも少なくとも一つ見えない石がある。すべてが見える場所はない。このことは私たちの持つ素晴らしい力とその限界のメタファーとなっている。私たちには世界を直接経験する力があるが、一度に見えるものは部分的でしかありえない。とてもマギルクリストの幅広さと深さには及ばないにしても、ヘラクレイトスの箴言「知恵を愛する者は、実に多くのことを良く探求する者でなければならない」[*22]に従いたい。

[*1] マギルクリストはここでpresenceを動詞として使い、世界と私たちの関係が双方向で互いに能動的に関わっていることを表現している
[*2] 哲学者トーマス・ネーゲルの表現(本書 P.944)
[*3] マギルクリストはダニエル・カーネマンの「ファースト&スロー」で紹介されているファーストなシステム1とスローなシステム2の区分は左半球と右半球とは対応しないと説明している。システム1とシステム2は、むしろ脳を上下(自動的な思考を司る古い皮質と人間の理性的な思考を司る新しい皮質)に分割している。同じファーストでもヒューリスティックにもとづき結論に飛びつくのは左半球だが、経験に基づく右半球の直感はファーストであるが信頼できる。より慎重でスローなのは右半球だが、誤った前提・ロジックに基づく左半球の推論はスローであっても信頼できない(本文P.1137)。
[*4] ワーズワース 「ティンターン修道院上流数マイルの地で」(本文P.1175)
[*5] P.1180-1181
[*6] P.1678
[*7] 15世紀のドイツの神秘主義哲学者ニコラウス・クザーヌスの言葉として知られる。Coincidentia Oppositorumの訳語としてはウェブ検索して出てきた「対立物の一致」をここでは当てた。Coincidenceには偶然の一致と同時に起きるという意味があるが、マギルクリストが重視している後者の同時性という意味を伝えるには不十分かも知れない。
[*8] P.1286
[*9] P.1286
[*10] P.1350
[*11] ‘How can we know the dancer from the dance?’ イェイツ 「Among School Children」(本書 P.26)
[*12] P.16
[*13] 世界は「関係」でできている カルロ・ロヴェッリ 2021年 NHK出版
[*14] P.1463-1464
[*15] P.1674
[*16] マギルクリストが汎心論的を支持している哲学者として言及しているのは、ヘラクレイトス、エンペドクレス、エピキュラス(ローマ)、スピノザ、ライプニッツ、ゲーテ、ショーペンハウアー、バートランド・ラッセル、パース、ジェームズ、デューイ、ベルクソン、ホワイトヘッド、ハーソーンなど。物理学者はニールズ・ボーア、マックス・プランク、デービッド・ボームなど。
[*17] P.1612
[*18] P.1665-1666
[*19] P.1686
[*20] 哲学者ジェームズ・カースはゲームには、有限ゲームと無限ゲームの2種類があると言った。「有限ゲームは勝つことを目的に、無限ゲームはプレーを続けることを目的にプレーされる」。有限ゲームは結果を強調し結果が出れば終了だが、無限ゲームはプロセスを重視し、プロセス自身が目的である。(Finite and Infinite Games 2012年) (本書 P.590)
[*21] P.1722
[*22] “‘men who love wisdom must be good enquirers into many things indeed’ (本書 P.1698)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
