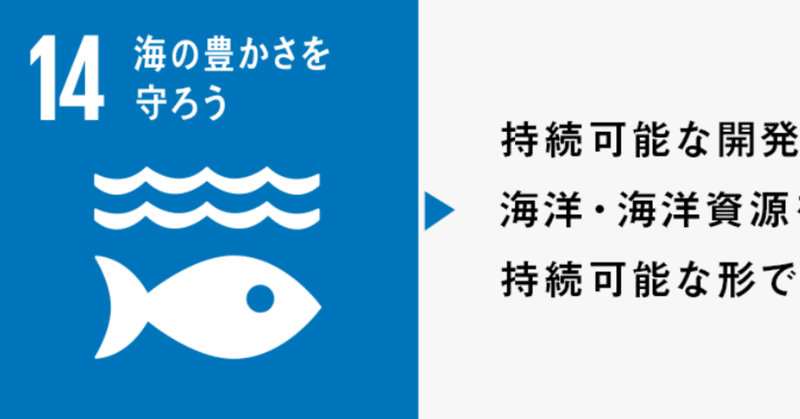
<No.24>SDGsの各ゴール解説⑭ 目標14:海の豊かさを守ろう
SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)の各ゴール(目標)の解説とアクションのヒントを国連開発計画(UNDP)、国連広報センター(UNIC)の資料を基に行います。SDGsのゴールを達成するためにも、SDGsの各ゴール詳細を知っておくことはアクションに繋げる上で重要になります。ぜひ最後までお付き合いください。
今回は「目標14:海の豊かさを守ろう」です。
UNDPでは「目標14:海の豊かさを守ろう」を次の通り解説しています。(灰色部分は引用。)
海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する
世界の海洋はその水温、化学的性質、海流および生物を通じて、地球を人類が住める場所にするシステムを構築しています。この極めて重要な資源をどう管理するかは、人類全体にとって、そして気候変動の影響への対策にとって、本質的な課題となっています。
30億人以上が、海洋と沿岸の生物多様性を頼りに生計を立てています。しかし、今日では世界の漁業資源の30%が乱獲され、持続可能な漁獲を維持するための水準を大きく下回っています。
海洋はまた、人間が作り出す二酸化炭素の約30%を吸収し、産業革命以来、海洋酸性化は26%進んでいます。陸上からの排出が主原因である海洋汚染は危険な水準に達し、海洋1平方キロメートル当たり平均で1万3000個のプラスチックごみが見つかっています。
持続可能な開発目標(SDGs)は、海洋と沿岸の生態系を持続可能な形で管理し、陸上活動に由来する汚染から守ると共に、海洋酸性化の影響に取り組んでいます。国際法を通じて、海洋資源の保全と持続可能な利用を強化することも、私たちの海洋が直面する課題の解決に役立ちます。
海洋資源の保全は、持続可能な開発のための2030アジェンダを構成する17のグローバル目標の一つです。複数の目標を同時に達成するためには、包括的なアプローチが必要不可欠です。
http://www.jp.undp.org/content/tokyo/ja/home/sdg/post-2015-development-agenda/goal-14.html
また、UNICでは、このゴールがなぜ必要なのか、という視点で以下のように伝えています。
外洋・深海域については、脆弱な生息地を守るための国際協力を強化する以外に、持続可能性を達成する方法はありません。生物多様性を保全し、水産業にとって持続可能な未来を確保するためには、政府が保護する海域について、包括的かつ効果的で公平に管理されたシステムの確立を図るべきです。私たちの身の回りのレベルでは、海洋に由来する商品を買ったり、海産物を食べたりするときに、海洋環境に配慮した選択を行うとともに、必要なものだけを消費すべきです。認証を受けた商品を選ぶことから始めてみるとよいでしょう。
公共交通機関を利用したり、電気製品のコンセントを抜いたりするなど、日常生活の小さな変化で省エネが可能です。こうした行動は、海水面上昇の一因となっているカーボン・フットプリントを削減します。
私たちは、プラスチックの利用を最低限に抑え、浜辺の清掃を行うべきです。
詳細は以下のURL参照
http://www.unic.or.jp/files/93bad7a2fc1eea3bb52d28ec54937a60-1.pdf
具体的なアクションを考えるためには、このゴールのターゲットについても知っておく必要があります。ゴール14に連なるターゲットは以下の10です。
• 14.1 2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。
• 14.2 2020年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。
• 14.3 あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し、対処する。
• 14.4 水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。
• 14.5 2020年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の10パーセントを保全する。
• 14.6 開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する2。
• 注釈2 現在進行中の世界貿易機関(WTO)交渉およびWTOドーハ開発アジェンダ、ならびに香港閣僚宣言のマンデートを考慮。
• 14.7 2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。
• 14.a 海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。
• 14.b 小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。
• 14.c 「我々の求める未来」のパラ158において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。
例えば、ターゲット14.1「2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。」で企業のアクションを考えた場合、廃棄物・排水管理の改善、燃料効率の改善、循環モデルを用いたプラスチック生産またはリサイクル可能な包装資材の使用などが考えられるとともに、消費者とのインターフェースを使用して消費者の行動を変え資源への配慮を促す方法などが考えられます。
とくに、ここ最近の動きとしてはマイクロプラスチックの問題が取り上げられることにより、プラスチックストローの使用が世界の各都市で利用禁止、または制限がかかるなどの動きが出るとともに、代替品に対する試行錯誤が見られ、新たなビジネスチャンスとなっている分野とも言えます。
海に漂う“見えないゴミ” ~マイクロプラスチックの脅威~-NHK クローズアップ現代 2015.10.29
http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3725/1.html
また、市民社会のアクションとして、世界各国で開催されている「World Cleanup Day」(ワールド クリーンアップ デー)があります。
「World Cleanup Day」では、150カ国、数百万人に及ぶ人々が、道路、公園、ビーチ、森林、河川を清掃し、全世界的な不法投棄ゴミ問題に立ち向かうアクションです。「World Cleanup Day」の主催団体は、エストニアのLet’s Do It Worldで、2008年にエストニアで5時間で5万人が全国を掃除した日に始まり、それ以来世界中に広がって、歴史上最も急速に成長している草の根運動の1つとなりました。
SDGsのゴール14以降は一国だけでは解決不能な世界の課題になります。一人一人は小さなアクションでもWorld Cleanup Dayのような世界規模のアクションとして各地の市民が繋がりました。これは、すべての国が同一の目標・指標で評価できるSDGs時代だからこそのアクションと言えます。
World Cleanup Day
https://worldcleanupday.jp/
また、個人のアクションとして、「海のエコラベル」と言われているMSC認証やASC認証のある製品を購入する方法が考えられます。
魚の獲り過ぎや、自然を傷つけることが起こらない方法でとられた魚からできた食べ物を「サステナブル・シーフード」といいます。サステナブルとは、ずっと未来にも続いていくということです。
水産資源と環境に配慮して獲られた天然の水産物の証がMSC「海のエコラベル」、環境と社会への影響を最小限にして育てられた養殖の水産物の証が、ASCマークです。
こういった製品を選ぶこともSDGsゴール14を達成する上での個人のアクションと言えます。
サステナブル・シーフードとは?-
http://sseafood.net/blog-entry-2.html
MSC認証
https://www.msc.org/jp
ASC認証
https://www.asc-aqua.org/ja/
最後に、2018年12月24日時点の国連本部のウェブページ(About the Sustainable Development Goals)に掲載されている17の目標ごとの「事実と数字(Facts and Figures)」のうち、ゴール14に関するものを挙げます。一見、自分自身に直接関係ないようなことであっても、新たな気づきやビジネスの機会になることがありますのでぜひ押さえておいていただきたい数値です。
• 海洋は地球の表面積の4分の3を占め、地球の水の97%を蓄え、体積で地球上の生息空間の99%を占めています。
• 海洋と沿岸部の生物多様性に依存して生計を立てている人々は、30億人を超えています。
• 世界全体で、海洋と沿岸の資源と産業の市場価値は年間3兆ドルと、全世界のGDPの約5%に相当すると見られています。
• 海洋には、確認できているだけでおよそ20万の生物種が生息していますが、実際の数は数百万に上る可能性があります。
• 海洋は、人間が作り出した二酸化炭素の約30%を吸収し、地球温暖化の影響を和らげています。
• 海洋は世界最大のたんぱく源となっており、海洋を主たるたんぱく源としている人々は30億人を超えています。
• 海面漁業は直接的または間接的に、2億人以上を雇用しています。
• 漁業への補助金は、多くの魚種の急速な枯渇を助長するとともに、世界の漁業と関連雇用を守り、回復させようとする取り組みを妨げており、それによって海面漁業の収益は年間500億米ドル目減りしています。
• 外洋地点の観測によると、産業革命の開始から現在までに、酸性化の水準は26%上昇しています。
• 沿岸水域は汚染と富栄養化によって劣化しています。協調的な取り組みを行わなければ、沿岸の富栄養化は2050年までに、大型海洋生態系全体の20%で進むものと見られています。
事業規模や企業か個人かによってできることも異なりますが、SDGsの各ゴールやターゲット、現状の数値を知って、そこから具体的なアクションを考えることがSDGsのゴールを達成する上で重要な活動の一つになります。
みなさんもぜひ自分のできるアクションを考えてみましょう。
資料:
UNDP SDGs
http://www.jp.undp.org/content/tokyo/ja/home/sustainable-development-goals.html
国連広報センター SDGs を17の目標ごとにわかりやすく紹介したチラシ、SDGs シリーズ「なぜ大切か」
http://www.unic.or.jp/news_press/info/24453/
国連広報センター 持続可能な開発目標(SDGs)ー 事実と数字
http://www.unic.or.jp/news_press/features_backgrounders/31591/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
