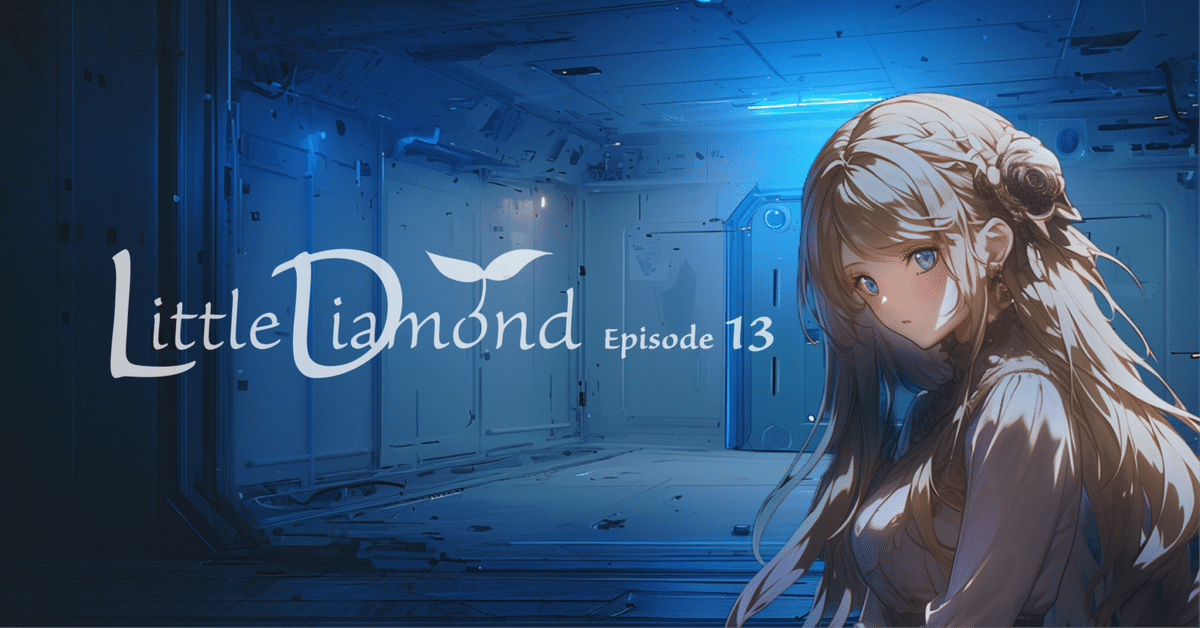
Little Diamond 第13話
前回のあらすじ
盗賊団「砂塵の狼」本部基地の安定した日常は、事件発生の報告によって破られた。
「メンバーが王女を拉致してきた」と。
リーダーであるドナンと数人の幹部らは、メンバーたちの軽はずみな行動に呆れと憤りを覚えながらも後始末に奔走する。
一般人への暴行は組織の主義に反するため、すぐさま王女を無事に返還する準備に取り掛かった。
しかし目を覚ました彼女は、兄の存在を口にしたのだ。
実行犯たちを改めて問い詰めると、犯行現場に居合わせ、怪我を負わせてしまった男性がいたことを白状した。
しかし何かがおかしい……情報が矛盾していた。
データ上では王女に兄はいない。
ではその男性は誰なのか。
彼女との関係は……?
リーダー補佐のオルクスは矛盾する情報の真相を探るため、情報部長シドと共に調査を始めたが……。
「……これはおそらく、やらかしちゃってますよ」
シドは、決定的な何かを見つけたようだった。
第13話 予測不能なスクリプト
13‐1 オルクス視点
「どういうことです?」
シドの視線の先に注目する。
「2年前のものですが……王女の画像。王都に潜入した諜報員が報告書に添付したものです。見つけるのに苦労しました」
モニターには古びた写真を取り込んだような、粗い画像が映し出されていた。
大勢の人たちに混じってもひときわ華やかな少女の姿。
腰まで伸ばした焦げ茶色の長い髪、優雅なドレスが美しく映えている。
まだ幼いが、独特の上品なオーラをまとった王女の姿があった。
パーティ会場か何かのようだが、特に不審なところは見当たらない。
「よーく見てください……ほらここ」
シドが手元で操作すると彼女の顔のあたりが拡大される。

「こ、これは……!」
息を飲んだ。
明らかに、光の加減とかではなく、瞳の色が全く違っていた。
モニターに映る王女は、明るい茶色。
それに対して先ほど会話した女性は碧眼、ブルーの瞳だった。
女性が髪を染めたりすることはよくあるが、瞳の色を変えるには幻術系の魔法で「見せかける」くらいしかできない。
しかしあの部屋では魔法を使った形跡は感じ取れなかった。
他の可能性としては、この写真を撮った時に魔法で瞳の色を変えていたケースも考えられるが……。
よく見れば顔も、全く別人のような気がする。
2年経ったといってもここまでの変化は不自然なのでは……。
「もしかして……人違い、ということですか」
「ですねぇ。雰囲気は多少似ていますが、やはり別人でしょうね」
シドはあきれ果てた様子でため息をつき、さらに続けた。
「あ、ちなみに王女には兄弟もいませんよ。建国当初の情報まで遡ってみましたが、王家で他に子供が出生した気配は見つけられませんでした」
彼女が王女でなかったなら。
先ほど考えていた可能性でいうところの、第4の可能性。
彼女の認識もデータもどちらも間違っていなかった。
彼女も嘘をついていないし、王女に兄はいないというデータも正しい。
ただ単に兄のいるどこぞの女性を、我々が勝手に王女だと勘違いしていただけに過ぎない。
シドは首を振りながら苦笑している。
「全くアイツらどこまでマヌケなんでしょうね……私のお仕置きの楽しみがまた増えましたよ」
言う通り、どうしようもないマヌケどもだ。
リサーチ不足で行き当たりばったりの行動が、組織全体を危険にさらすということを理解できないのか。
本当ならサクッと追放してしまいたいところだが、ドナンはそういう処分はきっと望まない。
「すみませんが、そちらはお願いします。返還を急がなくては」
「はいはい。お任せください」
連れてきたのが王女でないのならば、騎士団が隠蔽する必要は何もない。
通報されればためらうことなく、すぐに彼らは拉致事件として捜索を開始するだろう。
急いで部屋を出ようとした矢先、シドの引き留める声に立ち止まった。
「あ、オルクスー? ドナン様のあの件……決まったら教えてくださいね。実は結構、楽しみにしているんですよ」
あの件は……。
ドナンにとっては難しい問題のようで、珍しく私にも相談が来たのだ。相談されるのは嬉しいが、頼られたからにはしっかりやらなければというプレッシャーが少なからずある。
だからシドには、私個人としてこの件は告知してあった。
各所への根回しやシステムの改変を必要とする大きな動きになるはずだし、準備やサポートも彼にお願いせざるを得ないのだ。
しかしこちらの動きがドナン自身の判断の邪魔になってしまっては本末転倒だ。そのため、シドから直接ドナンには打診しないよう言ってあった。
「あの件なら、実行の方向でほぼ間違いないでしょう。ただ……ゴーサインはまだなので」
「ふん……なるほどね。ジワジワ準備は進めておきますよ」
「お願いします」
13‐2 ドナン視点
実行犯である3人と話を終えたあと、俺は自室に戻っていた。
事務仕事の続きを、と思ったがそんな気にはなれず、少し休憩をとることにした。
時刻はいつの間にか23時になろうとしていた。
コーヒーを淹れ、チェアに身をゆだねる。
「はぁ……」
いったい俺は、どうすれば……?
いつの間にか大きくなりすぎた組織。
伝わらない、想い。
俺はただ、思い出のあの土地に……本来の姿を取り戻したいだけなのに。
デスクに置いた写真立てに触れる。
まだ幼い俺を抱きしめる、両親の笑顔があった。
この当時に俺が住んでいたのは、ここから遥か北にある、立入禁止となった区画のすぐ近く。
両親は大戦によって汚染された不可侵領域と、そこに生息するモンスターたちを研究する動物学者だった。
モンスターとの共存を目指し、継続的な実験と調査のためにその地域に移り住み、自給自足の生活を送っていた。
戦後の復興でまともな生活もままならない時期。
しかし幸いにも両親は多少の魔法が使えたし、国公認の研究機関に属していたせいで国からの支援もあった。
家族3人だけで人里離れた場所に生活していても、何とかなっていたのだ。
不可侵領域もあの頃の俺にとっては遊び場であり、異形の動物たちは遊び相手だった。

大好きな両親と、大好きな動物たち。
……楽しかったし、幸せだった。
だがあの日突然、何の前触れもなく全てが変わってしまった。
何がきっかけとなったのか今でも分からないが、汚染区域が爆発的に拡大したのだ。
その影響で、異形であっても穏やかでよくなついていた動物たちが、凶暴なモンスターへと豹変した。
救助を要請したが間に合わず。
優しく頼もしく、憧れだった両親は俺をかばって……物言わぬ冷たい屍へと変わり果てた。
俺自身も瀕死の重傷を負ったが、生き延びた。
……俺だけが、生き残ってしまったのだ。
両親を失ってからしばらくは「今までの幸せを返して欲しい」「こんなことをした奴にやり返したい」という底の見えないマイナスの感情に、ただただ飲まれた。
きっと誰も悪くないのに。
全てを終わらせた何かが憎くて仕方なくて。
……無力な自分が情けなくて、悔しかった。
自分を含む誰かに責任を全部押し付けて、攻撃の対象にしたかったんだ。
そいつを倒せば心が晴れると勘違いして。
しかし時が経ち、冷静さが徐々に戻ってくると、それらは無意味で、とらわれていては何も進まない、ということに気づいた。
小さなころからよく聞かされていた、両親の言葉を思い出したんだ。
「人間は過去を変えることはできない。どんなに悔やんでも、どんなに恨んでも。だが未来を創ることはできる。悔んだり恨んだりしている無駄な時間やパワーは、未来を創ることに使え」
そう、彼らはまさに「過去の過ち=世界大戦」を踏み越えて、モンスターと共存する方法を模索するために研究を続けていたのだ。
すっかり無駄な時間を過ごしてしまったことを悟った俺は、今度は未来を創ることを考え始めた。
不可侵領域を浄化する。
それが俺の夢となった。
できるわけない、バカバカしいってよく言われる。
化学兵器、生物兵器、魔法兵器の残骸のゴミ捨て場。負のエネルギーの吹き溜まり。
様々な生き物が変異し魔力を帯び、現存の理論では説明のつかない異形となって生まれ続けている場所。それが不可侵領域。

世界規模の組織である魔法学会でさえ手に負えず、見て見ぬふり。せめて環境破壊を拡大しないよう、汚染をその地域に閉じ込めるだけで精一杯らしい。
けれど俺には、諦めることはできなかった。
不可能だって言われても、何年かかっても。
もし死ぬまでに成し遂げられなければ、次の世代に託していきたい。
だから仲間を募り、組織を作った。
両親を失った事故から数年後、俺は動きだした。
もちろん、知識も経験も何もないまま手探りで。
浄化には魔法の力が必要だが、俺には魔法適性はほとんどない。
だから魔法石を集め、それを利用するためのテクノロジーを研究する必要があった。
初めは騎士団への所属を試みたが、公的機関に所属しては自分の意志で身動きが取れなくなることが分かった。
そこで「魔法石」と「テクノロジー」をどちらも日常的に扱っている「盗賊」に目を付けた。
彼らはこの2つを横流しして金を得ることが目的だが、それだけに流通事情には詳しく、裏マーケットでの取引も慣れたものだった。
そのため、俺もみずからを盗賊と名乗ることにした。
だが盗賊を名乗る以上は当然、国の治安を守っている騎士団と対立することになるわけだ。
物資や情報を得るためには盗賊のアジトなどを襲撃する必要もあり、交戦は避けられない。
派手に暴れれば騎士団に検挙されそうなものだが、盗賊同士のケンカや縄張り争いはよくあることで、そんな小競り合いを仲裁するほどヤツらもヒマではないらしい。
一般人を襲わない限りは検挙の対象にはしないようだった。
そうして俺たちは騎士団の目をかいくぐり、裏マーケットの動きを監視しながら、効率的に魔法石と旧時代の優れたテクノロジーを集めた。
数年後には、組織は大きく成長していた。
今では魔法学会本部にも研究員としてメンバーが常駐して、最新技術の進捗を把握しながら独自の研究を進めている。
もちろん不可侵領域に近い北方地域の調査と記録も、長らく続けてきた。
しかし……。
その「本当の意味」が、末端まで伝わっていないのだ。
初めこそ、目標達成のために皆が一丸となって働いてくれることに感動を覚えたものだが。
人数が増え、この国最大の盗賊団となってしまったおかげで、今回のように組織の威を借りて乱暴を働いたりする者が出てきた。
いくら伝えてもなくならない。
目も意思も行き届いていないのが現状。
そのうち本当の盗賊になってしまうのではないかと思うと、心が折れそうになる。
俺が……。
俺たちが創りたいのは、みんなが笑って幸せに生きられる、平和なのに。
特に近頃は、前に進んでいる気がしない。
やり方が間違っているのかもしれないと、考えるようになった。
組織を解散して、別のやり方を考える必要があるのではないか、と。
だがここには、ほかの盗賊の監禁から保護した子供や、俺の意志に心から賛同してついてきてくれた者たちも大勢いる。この組織はすでにひとつの大きな家族のようでもあるのだ。
解散するということは、つまりそれらを放り出すことになってしまう……。
背負っているものは大きい。
捨てるなんてとてもできない。
……だがそれでは目的に向けて進むことは難しい。
夢をあきらめて皆を守るため生きるべきなのか。
それとも全てを捨てて、皆を裏切ることになっても、目的達成のために動き出すべきなのか。
13‐3 オルクス視点
ドアのインターホンを押して声をかける。
「ドナン、急にすみません。重大な報告があります」
返事はなかったがドアは静かに開いた。
そこには普段見ることのない、明らかに元気のない様子のドナンが立っていた。
部屋に入ると、足元の間接照明を残してほとんど真っ暗だった。
「どうしたんです? 明かりもつけずに……」
「オルクス、少しだけ……聞いてほしい」
ドナンはソファに座る。
思いつめたような、そんな音色だった。
きっとあの件についてだろう。
組織を解散するかどうか。
私の観察ではもうすでに結論は出ていると見ていた。
彼は普段から迷わない。
自分の直感に正直で、即断即決が持ち味だから。
「悩んでいる、というわけではないんだが……気持ちがスッキリしなくてな。オルクス、お前はどう考える?」
結論は出ているけれど踏み切れずにいるといった様子。
自分に正直でありたい彼のことだ。
迷いを断ち切れない状態が、ひどく気持ち悪いのだろう。
どうにかして欲しいのかもしれない。
今回の件で二の足を踏んでいる原因は……。
「捨てる、と考えるからツラいのではないですか?」
「……今まで面倒見てきたのに、突然放り出すんだぞ? 捨てるってことじゃないか」
彼は泣く子も黙る、この国最大規模を誇る盗賊団のリーダーなのだから、もっと冷酷でわがままで独裁的でもおかしくはないのに。
優しくて情に厚くて責任感も強い。
さらに強くあろうと努力を怠らない真面目な人……。
彼の人柄でなければここまでの規模にはなりえなかった。
ここのみんながドナンを慕っているのは誰が見ても明白であるし、
褒められたい、近づきたいという思いでやってきた者も多いだろう。
だからといって、ドナンがそこに縛られる必要はないはずだ。
「いいえ、捨てるのとは違います。何もできない赤ん坊をひとりで放り出すわけじゃないんですから。自分の身は自分で守れるよう育ててきました。今だって素晴らしい働きをしているし、彼らは皆とても有能です」
解散となれば彼らは目標を失うかも知れないけれど、それは一時的なものだ。きっとまた新たに生きる目的を見つけ、歩き出すはずだ。
彼らには彼らの人生があって、それは自分で選択し自分の力で歩いてかなくてはならない。生きている以上、それは誰だって同じなのだ。
「それに彼らだって、あなたのお荷物にはなりたくないはずです」
「あぁ……そうだな」
組織に依存しているのはこの人の方かもしれない。
居心地の良いここが大好きで、離れたくないのだ。
分からなくはない。
私も同様に、この人に依存している。
「あなたはあなたの選択をすればいいんです。そこから先は捉える側の問題です」
あえてバッサリ切り捨てる言い方をする。
決断を迫られているのであって、呑気な茶飲み話ではないのだから。
「……クールだな、お前は」
自分はこういう役回りでいい。
この人のお役に立てるのなら。
「他人のことまで考える余裕がないだけです」
「……ふッ。またそんなことを……。あぁ……いや、元はといえば俺がしっかりしていないせいだな。すまない」
「あなたは、それでいいんですよ」
しっかりしていたら、私が支える必要がなくなってしまう。
「……ありがとう。この件は、あとで直接シドに話す。解散する方向で進める」
「分かりました」
何となくまだ、スッキリしていない感じのする声だった。
でもその辺りは、進んでいくうちに踏ん切りがついていくものだと思う。
時間と、これからの経験が傷を癒していくはずだ。
「……あ!」
うっかり忘れそうになっていた。
「……そういえば、報告に来たんでした」
おまけのような形になってしまったが、今は一番大事なことだ。
ここにきた本来の目的を果たすために口を開いた。
「王女は、どうやら人違いのようです。シドと画像で確認しました」
「……人違い?」
ドナンに代わり、部屋にある端末を操作する。
思った通り、シドからの報告のメールはすでに来ていた。仕事が速い。
「これです」
添付されている画像を開く。
さっき確認した2年前の王女の画像と、拉致してきた少女の監視カメラの映像が隣り合わせで比較できるよう配置されている。
一目瞭然で別人と分かる。
画面を食い入るように見つめると、ドナンはおでこを押さえながらため息をついた。
その気持ちは分かる。
けれどさらに追い打ちをかけなくてはならない。
「そして実行犯の新たな証言から分かったのですが……目撃者が1名おり、犯行の際に怪我を負わせていたようです」
「は……?!」
「ナイフで刺したらしいので、かなりの重症かも知れません」
「……はぁぁ……アイツら……」
……慰めの言葉も見つからない。
せめて事務的に淡々と報告する。
「どっちにしろ返還は急がなければなりません。先ほどの打ち合わせの通り、今夜中に実行で問題ないと思います」
「……そうだな。一般人であるなら、まだ捜索は始まっていないだろう。今なら返還もしやすい。目撃者の方は……どうすることもできないな」
「そこはもう……仕方がないです。我々が何者かは知られていないと思うので、通報はされても捜索は難航するでしょう」
「彼女が返還されれば、その時点で捜索する必要もなくなる……か」
「はい、楽観的予測ですが。では記憶の封印をする準備を進めます」
「頼む。返還は予定通りイツキと第一部隊に任せよう」
「了解しました」
13‐4 ユウト視点
町を出てしばらく経つ。
このあたりはひたすら砂漠と岩山が続く荒野だ。

真冬の夜中はさすがに冷え込む……。
肌を切るような冷たい風に、小さく丸まって膝を抱えたジュリアはコートの前をかき合わせながら、ブルブルっと震えた。
「ごめんねぇジュリちゃん。もっとちゃんとしたのがあればよかったんだけど……」
オレ達は、急ごしらえのフローターで町の北東を高速で移動中だった。
「フローター」ってのはたぶん製品名か通称で、正式には「フローティングビークル」って言うみたいだけど。
主に長距離移動のために使われる魔法動力の乗り物のことを、世間ではフローターって呼んでる。
椅子やマットなんかを反重力魔法「フロート」で浮かせ、高さを固定した状態で念動力によって移動させる。
この国ではすでに一般的になっていて、運用形態も色んな形に応用されている。
大きな都市にはだいたい小型の「タクシー」があるし、街と街の間を大人数で移動する「バス」もあったりするから、魔法が使えない人もオペレーターに運賃を払って利用することができる。
まぁオレのようなスゴ腕の魔法使いにとっては、フローターの操縦なんて朝飯前だけどね。
ちなみにいま乗っているこれは、ちゃんとした市販品じゃない。
だいたい夜中に道具屋なんて開いてないし。
ちゃんとした「ガワ」というか、商品として売っているボディはカッコいいけど、管理が大変なのと値段が高いのがネック。
常に移動する旅人なんかは一台持ってると良いかもしれないけど、下手なとこに置けば盗まれる危険もあるし。
滅多に町から出ないオレには必要ないのだ。
んで、たまたま町の入口に、半分朽ちかけたようなボロいベンチがずっと放置してあったのを思い出したんだよ。
そう。
いま乗ってるのはそれだ……。
ジュリアと2人で、力づくで引っこ抜いて拝借してきた。
ぶっちゃけ途中で壊れて捨ててきたとしても、罪悪感がないレベルのボロさだ。
当然、耐久力はほぼゼロに等しい。
いちおう座れはするものの、吹きっさらしはさすがにツラい。しっかりしたガワを用意しなかったのを、ちょっぴり後悔している。
物理バリアで真正面だけ風防みたいなのを作ってはいるけど、回り込んでくる風はやっぱり寒い。
全方向にバリアを張らないのは、MPを温存するためだ。
でもそれに関して彼女は、何も文句は言わない。
「大丈夫……頑張る」
彼女は寒さに震えながらも真っ直ぐに前を見ていた。
その瞳には強い意思の光。
きっと今は……エミリのことが心配なんだ。
岩山や瓦礫の山はところどころにあるが、ほぼ見通しのいい砂漠。
直線的に、最短ルートで進んでいる。
オレの感覚的にはもうすでに1/3は来てると思う。
あと1時間ほどで到着するはずだ。
フローターは地表から浮かせてしまえばほとんど抵抗がなくなるから、曲がったり速度を変えたりしない移動であれば、大した集中もMPも必要なく、慣性でラクに走れる。
幸い今夜は満月に近く、辺りは明るい。
おしゃべりでもして寒さを紛らわそう。
よく考えたら、2人きりでじっくり話す機会なんてそうそうないもんね。
「それにしてもジュリちゃんさー、回復魔法使えるなんてすごいじゃん」
正直、彼女の助けがなかったら、今頃はまだベッドの上でウンウン唸っていたかもしれない。
「……どうしようもなかったから。 こんな時に限ってお医者さんは隣村に往診に行ってて、明日の朝まで帰ってこないっていうし。酒場にいたお客さんにも呼びかけてみたけど、医療系魔法なんて使える人いないし……」
確かに、元素系の単純な魔法は適性があれば訓練しなくても使えるけど、医療系はそういうわけにいかない。
身体の構造とかの専門知識は必要だし、魔法力を行使する範囲を絞らないといけないから、どうしても訓練が必要になる。
ちなみに今回ジュリアの使った回復魔法は、医療系の治癒魔法とはまた別。
身体の持つ自然回復力を高めるものだから、構造云々の知識は必要ない。
魔法に限ったことじゃないけど「助けたい」っていう気持ちや「心の底から信じて祈る」行為は、無意識にあるイメージにアクセスすることで集中力を限界にまで高めることができる。
彼女が回復魔法を発動できたのはきっとそのせいだと思う。
だから、オレとしては……すごく嬉しかったんだ。
「ユウトの部屋にあった教科書を読み漁って、護符描いて、一か八かでやってみたんだよ」
「うんうん、そんな気がした~」
嬉しい。
身体に残留するMPの波動を、オレは感じることができる。
不器用ながらも一生懸命さが伝わってくる、そんな波動だった。
「ありがと。もしかしてさぁ、ジュリちゃん魔法適性、案外高いんじゃない? 」
「え、ホントに?」
適性はあるんだけど訓練されてない。……っていう感じかな。
「基礎訓練をしたらもっと使えるようになるかもよ。もしかして……小さい頃、勉強サボってた?」
「んー、サボってたっていうか……魔法の勉強とか、しなかったから……」
こーゆーとこが、彼女のミステリアスなところだ。
このご時世で魔法の勉強してないとか……どんな山奥に生まれたんだろ?
そういえば小さい頃の話とかも、あんまり聞いたことなかったな。
「ジュリちゃんってさぁ……」
「……ねぇ。さっきから、何か変な音してない?」
オレの言葉をさえぎって、彼女は後ろを振り向く。
つられてオレも後ろを振り向いた。
「……!?」
なんだッ!?
真うしろ、たった1メートル ほどの近距離。
スイカほどの大きさで青白いモヤモヤした炎のようなものが、オレたちの乗るフローターにピッタリとついてきている……!
結構なスピードで移動してるってのに、風になびいてる様子がない。
明らかに不自然だ。
「ま……魔物ッ……!?」
振り払おうとしたのか、ジュリアは身を乗り出して、片手を伸ばした。
すると「それ」は急にボワッと大きく膨らんだかと思うと、真っ赤な口を開けた。
「きゃぁぁ!!」
「うわぁあ!!」
オレはとっさに彼女を抱えて引き寄せ、フローターのスピードを上げる。
ヤバい! ヤバい!!
これヤバい奴じゃん……!?
「スピード上げるから掴まって!」
効くかどうか分からないけど伏せたまま閃光を食らわせ、そのまましばらく必死でフローターを走らせた。
それからそっと振り向く。
ついてきている様子は……ない。
ふぅぅ……逃げ切れたか……。
少し、スピードを落とす。
「大丈夫だった?……ジュリちゃん」
「……か、かじられるかと思ったぁ……」
かじりはしないけど、きっと火傷するかMPを吸い取られるだろう。
あのタイプはエレメント系と呼ばれる魔物で、たしか物理攻撃は効かない。
きっと反射的に手が出てしまったんだろうけど……。
「アレはたぶん触っちゃダメなヤツだね」
「う……知らなかった」
オレも詳しいほうじゃないけど、小さい頃に図鑑で見たことがあった。
こんな夜中に町の外に出るなんてまずないから、すっかり忘れてた。
……外に出れば、モンスターに遭遇するってことを。
首都とククルの町とを繋ぐ街道は何度か歩いたりはしてるけど、昼間はモンスターが現れることはなかった。
騎士団が警備しているせいもあるけど。
でもこのあたりは街道から大きく外れているし、月が明るくても夜は夜だ。
「気をつけながら、行かないとな」
「う、うん……私、後ろ気をつけて見とくね」
ジュリアは神妙な表情で、フローターの上で膝を抱えるようにして座り、背もたれに掴まる。
もうしばらくだ。
またなんか出るかもしれないけど、今は相手してる場合じゃない。
エミリのもとへ急がないと。
13-5
……1時間後。
「えっと……何にもないけど?」
ジュリアは背伸びするように遠くまでぐるりと見渡しながら言った。
オレも同じように、もう一度ぐるりと一周見渡してみる。
しかしそこにあるのは真っ暗な砂漠と真っ黒な岩山が、南中した月の光にただ静かに照らされているばかりだった。
「あれーえ?ここで合ってるはずなんだけどな……」
「ホントに?」
ところどころに岩山や瓦礫が転がっているだけで、建物らしきものなんて見当たらない。
「うぅん……おかしいなぁ」
想像していたのと違う。
もっとこう、魔王の城とか怪しげなダンジョンの入り口とか?……みたいなのがあるんじゃないかと思ってたのに。
でも座標的には間違いなくこの辺……。
テレパシー、繋いでみようかな。
それが一番手っ取り早いよな。
繋いでる間は無防備な状態になってしまうが、ここは彼女に頼もう。
「ちょっと繋いでみる。ジュリちゃん、周り見といてくれる?」
「わかった」
彼女はコクリとうなずく。
オレは砂漠の真ん中に着地させたフローター……つまり古びたベンチに腰掛け、目をつぶる。
んんと……エミリの波動は……。
……あぁ、やっぱりこの真下だ。
オレは意識をリンクさせて、声をかけてみる。
「エミリ、大丈夫? 今話せる?」
「あ、ユウト? ちょっとまってね……ん、よいしょ。はい、いいよ」
エミリは何やらガサゴソやっていたが、落ち着ける場所が確保できたのだろう。
「建物っぽいものは見えないけど、たぶん真上にいる。これからそっちに飛ぶんだけど……そっちの状況はどう?飛んでも大丈夫そう?」
「こっちは……さっきと同じ、部屋にひとり。外の状況も相変わらず分からないけど……」
エミリは急にここから小声になった。
「監視されてるって言ってたでしょ。 どこから見てるのかは分からないけど……さすがにバスルームまでは監視してないと思って、今バスルームで話してる」
おお、さすがエミリ……冴えてる。
「いいね、バスルームならたぶん大丈夫だよ。着地スペースは充分にある?」
「うん、宿のお風呂より広いよ」
……ぇ、そこ基準?
宿のお風呂は結構狭いほうだと思うんだけど……まぁ平気かな……。
「オッケー。じゃあ着地スペースに身体の正面を向けて、手を広げて立ってて。そこを目印に行くから」
よし。
目を開けて、ジュリアに向き直る。
「ジュリちゃん。何にもないけど、やっぱこの下みたい。準備はできたからさっそく飛ぶよ」
「うん。私はどうすればいい?」
「ええと……。ハッ!」
……そうだった。
一緒に飛ぶときは抱えて飛ぶんだった。
そして承諾を取っていないことに、今さら気付いた。
安全のため、できればお姫様抱っこくらいの密着度合いは欲しい。
どうしよう。断られたらどうしよう。
「だっ……! ……いや違う」
「だ……?」
抱っこしていい?は誤解を招く恐れがある。
オレの経験と勘が、そう告げている。
いや……。
承諾なんか取ろうとするから、逆に変な意味に取られるのかもしれない。
ここはいっそのこと、説明書を読み上げるかのように機械的に解説したほうが、すんなり受け入れられるんじゃなかろーか。
「まずオレが、こうやってベンチに座るでしょ」
「うん、そして?」
「その上に、ジュリちゃんが座る」
「え……ユウトの上に? ホントに? なんで?」
彼女はいぶかしげな表情を見せる。
だがこのくらいは想定範囲内だ。
ここで慌てて弁解してはいけない。
悠然と構えて淡々と説明を。
「う……うん。安全性を確保するために、体をくっつけて固定する必要があるんだ」
嘘はついてない。本当のことだ。
「あ、そういうことね。てことは……え……えっと……こ、こうかな?」
「……へ? お、ぉぉ……こっち?」
待て。
いや、オレの上に座ってとは言ったけど。
「あれ、間違ってる?」
「いや、間違っては、ない……けど」
確かに、間違ってはない。
だが、そう来るとは思っていなかった。
彼女はなぜか向かい合わせで、オレの両脚にまたがるように、抱き着く形で座ってきた――。
横座りでお姫様抱っこの体勢に抱えられればと思っていたんだけど。
結果的に密着度は、予想を遥かに上回る形となったのだった……。
「重くない? 大丈夫?」
「あ、ああ……、うん全然」
大丈夫っていうか大丈夫じゃないっていうか。
別の意味で危ういけども、ここは集中力でカバーするしかない。
ジュリアは両腕をオレの身体にまわしてしっかりとしがみついている。
ヤバいよな……この状況は……。
「うう……ふぉぉぉぉ」
思わず変な唸り声が出てしまった。
「あ、ごめん、やっぱ重い?」
「いや……ちょっと今……自分と戦ってるから、話しかけないで」
「え……? あ、うん……」
乱れた呼吸と心拍音を聞かれている気がして、恥ずかしい。
静まれ……静まれぇぇ……。
彼女の柔らかさを胸と脚に感じながらも、必死で心を落ち着かせる。
いまは浮かれている場合じゃない。そう。
自分に言い聞かせながら、大きくうなずいた。
「よし、じゃあ行くよ」
「うん」
深呼吸……すーはー、すーはー。
集中ぅぅぅ……!!
しっかりとジュリアの体を包み込んだまま、イメージの中で両腕を広げているエミリの足元へと着地する……。
……ハズだったのに、なぜか天井付近から出てきてしまった。
「おわぁぁ!……ぎゃんッ!」
……落ちた。
「いって~~!!!」
ジュリアと自分の頭をとっさにかばったら、思いっきり肘をぶつけた。
バスルームの床は、思った以上に堅かった。
「ユウト!ジュリア!大丈夫?」
エミリが駆け寄ると、ジュリアはすぐに起き上がった。
「あ、あたしは平気! ごめんねユウト、大丈夫?」
「いや、ズレたのはオレのせいだからいいんだ……怪我がなくて良かった」
やっぱり雑念が少し、払いきれなかった……恥ずかしいぃ。
13‐6 ジュリア視点
とにかく。
エミリが無事でよかった。
ユウトもホッとひと安心したのか、つかの間の脱力感に浸っているようだった。
どうやってここを抜け出すか。
次はそれを考えなければ。
ユウトとエミリのおかげでここまで来れた。
ここからは私ががんばる番だ。
バスルームのドアをほんの少しだけ開いて、辺りを観察する。
見たところ別に何の変哲もない宿屋の一室のようではあるけれど。
なんとなく……違和感があるような……?
ううん……何だろう?
よく分からないけど。
とにかくここを脱出するには監視されてるこの部屋を通らないといけないわけだから、見つかる前に素早く行動したい。
「ドアは当然、カギがかかっているのよね?」
一応、エミリに確認する。
地下で窓もないなら、ドアから出るしかないもんね。
「うん。何か用があればドアの外の人に声をかけてくれって」
なるほど、ドアの前に見張りがいるのか……。
あぁ。
昔……王宮の自室に、閉じ込められたことを思い出した。
夜7時以降は外出禁止、なんて勝手なルールを作るもんだから。
隙を見てちょいちょいコッソリ抜け出していたら、ついにバレてしまって。
しまいには外鍵をかけられて、ドアの外に見張りを置かれたことがあったっけなぁ……。
……そうだ。
あの時と同じ状況だ。
あの時は確か……。
「……ねぇ、あたしに名案があるんだけど」
たぶんこの作戦は使える。
一か八かだけど。
◆◆ 第13話 「予測不能なスクリプト」終わり
あとがき
今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
もし面白いなっと思ったら、スキ、フォローをお願いします!
ご意見やご感想は本当に励みになります。
コメントはとっても嬉しいです!
Xにて「@ayayanmax」とメンションつけてポストしていただけたらリポストします!
もちろんXのDMでもOKです。
今後の創作の参考にさせていただきます!
————————————————
いつものパターンですが、また色々盛り込みたくなって長くなってしまってますねww
キャラが多くなってきたので視点がかなり移動してますが、本人でしか分からない心の動きをお楽しみいただければと思います!
次回はジュリアたちの脱出劇、ドナンたちの大捕物となる予定。イツキの部下たちを書こうかどうしようか迷ってるところですww
月1くらいで更新していけたらなと思ってます。
どうかのんびりと、続きをお待ち下さいませ。
挿絵もでき次第追加しまーす!
—————————————————
▶X(Twitter)では
創作活動の進捗や、過程での気づき、作品公開の情報などを発信しています。イラストやキャラ紹介、裏エピソードなども。
プロフィールのリンク集には、作者のその他の活動も公開中。
「Little Diamond」のキャラグッズも販売しています。
ぜひ見て行ってくださいね!
シリーズ続編も気になる方はぜひこちらもフォローお願いします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
