
【マレー半島縦断記⑥】漁師の町の秘密
外が暗くなってきて、宿が決まってないことが流石に不安になってきた。赤ちゃんをあやしているビュー(大学生)に相談する。「多分私の伯母に聞けば、いくつかアテがあると思います。待っていてください。」来た!若い娘から地元のおばさんへの、黄金ルートだ。翼くんから岬くんにボールが渡ったときくらい安心感がある。
事情は分かった、という感じで、荷台付きバイクのエンジンをかけるデューおばさん。「乗りな!」という掛け声で、ビューと二人で乗り込む。陽の落ちゆくコーヨー島の風を切る。デューおばさんがこちらを向いて色々話しかけてくるが、全く聞き取れない。それに対して「おばさん危ないから前向いて!」とビュー。意味わからない状況だけれど、めちゃくちゃ楽しい。デューおばさんが話をつけてくれて、一棟貸しのコテージに500バーツで泊まれた。ドアの敷居の向こうで、二人が手を振ってくれる。「おやすみなさい、また明日ね」と言ってくれた。
床がありえないくらい傾いていたし、湖にこそ建っていないものの、勿体無いくらいの条件だ。シャワーと日記と荷物整理をしてしまってから、あの祭りはいつまで続いているのだろうと気になってきた。夜の雰囲気も味わってみたくて、先ほどの空き地まで歩いて戻った。夜のコーヨー島はとても静かで、波の音がよく聞こえてくる。街灯さえ殆どない真っ暗な道をてくてくと歩いていくと、やっぱりまだ宴は続いている。ビューはもう帰宅していたので、またもや手持ち無沙汰になってしまっていたら、先ほど仲良くなったお父さんが発見してくれて、二人の娘を紹介された。近くの大学に通う学生で、英語で色々と情報を聞けた。妹さんの方は英語で話すのが恥ずかしいみたいで、少ししか喋らなかった。
「このお祭りは、タイ南部でしか見られないものなんです。地元の人以外が参加しているのを見たのは、あなたが初めてです。」
「だいたい一年に一回あるんですが、特に決まった日程でやっているわけではないんです。今日は多分2時ごろまで続くんじゃないかな?明日も午前中には再開して、明後日に終わるはずです。まるまる3日間続きます。」
「私もあまり詳しくないんですが、演目の順番や意味は伝統的に決まっているみたいです。今やっているのは、この土地の魂のための儀式です。」
なるほど、博物館の彼らが見たことのない理由がわかる。今日ここに来ていなかったら、あそこで街に戻る選択をしていたら、最初に紹介された宿に決めてしまっていたら、出会うことができなかったと思うと、すごく不思議な気持ちになる。相変わらずコーヒーを薦められたり、皿いっぱいの果物を出されたりしながら、深夜1時ごろまで観劇して、静かに引き上げた。

なぜか結婚式にまで参列する
コツ、コツ……コツ、と不定期な間隔で音がしたのでカーテンを開けてみると、近くで石垣を作っているのが見える。石を積む音で眼が覚めるなんて、ここまでが宿泊客へのサービスなのではというくらい演出された島感。レイクビューは叶わなかったけれど、深夜と朝の雰囲気が見られたし、やっぱりここに泊まって良かった。8時頃にチェックアウトして、湖に浮かぶ家のスケッチをしに向かう。
よく見てみると、元々の木の柱を補強するように、コンクリートの柱を建てたものが沢山見られた。昨日見えていた木の柱では、やはり腐ってしまうのだろう。コンクリートの柱が、規格品の排水管の中に流し込むように作られていたり、元々の木の床(腐りかけている)に鉄骨を用いて新しい床を作り、その二層の隙間に電気関連のコードを通していることなど、近代化と増築の妙が見えてとても面白かった。

「9時に集合して、朝ごはんを食べたあとに、島の向こうまで送ってあげる」という話だったけれど、件のビューおばさんが来る気配が全くない。あと他にも、朝9時くらいにまたコーヒーでも飲みましょうといってくれたお父さんも、来ない。まあタイ人が時間にルーズなのは全然想定通りだ。
というか彼らだけじゃなく、働き者の一部のお母さんたち数人しか来ておらず、せっせと昨晩のゴミを片付けている。手持ち無沙汰だったので手伝おうとするも、座ってて!とジェスチャーで言われる。別のお母さんから「カフィ!カフィ!」と言われたので、インスタントコーヒーを自分で作って飲みながら、朝ごはんの準備をする手際の良いお母様達を眺めていた。

昨日の舞台を覗くと、舞台裏で、Noraを演じていた若者たちがタオルケットにくるまって雑魚寝している。彼らは3日間、家に帰らずに踊り続けるのだろうか。
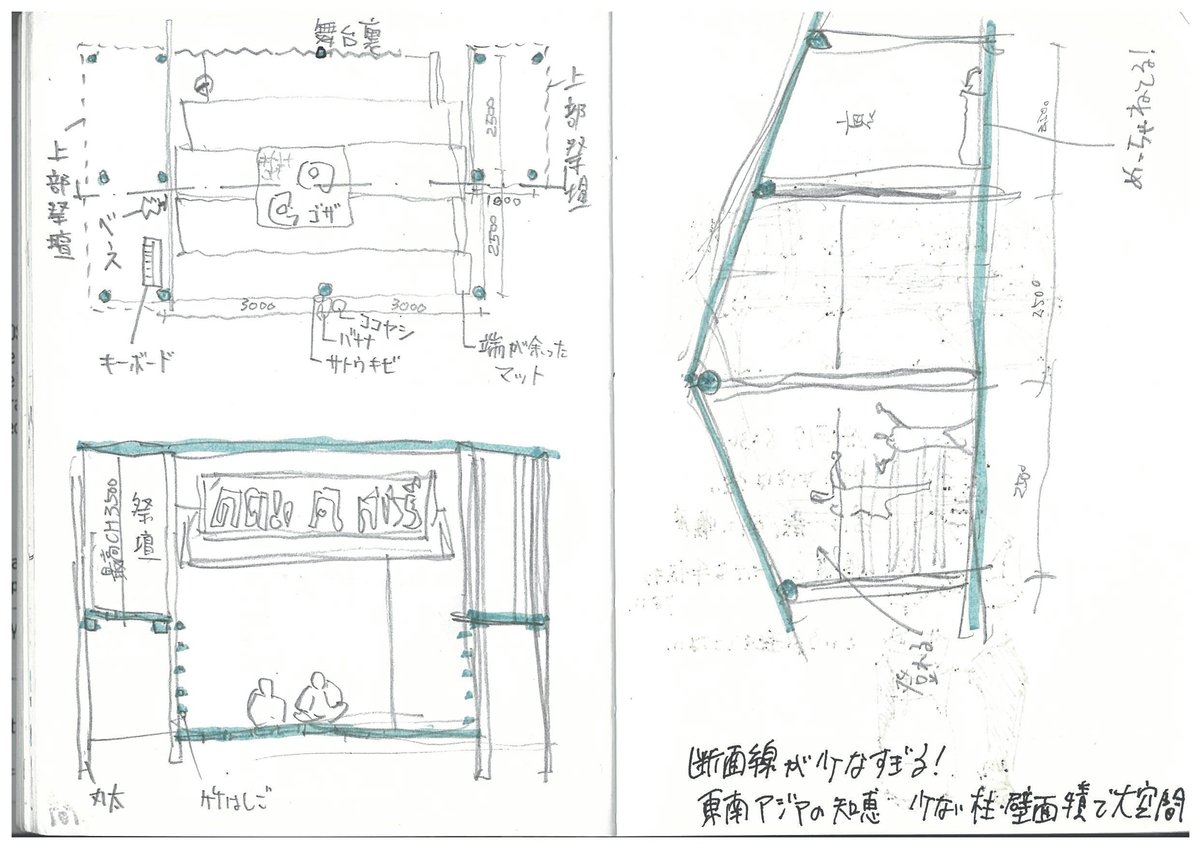
スケッチと写真に十分すぎるほど記録を残してしまって、またも手持ち無沙汰でいると、また音楽が聞こえてくる。どうやら3軒隣くらいの家で結婚式が開催されるらしい。写真を撮ってきたら?と言われて、またも昨日と同じように遠くから眺めていると、一人の、お兄さんみたいなお姉さんから手招きされる。この島の人々はなんでこんなに優しいんだろう?日本から来たと言ったら、みんな大袈裟に驚いてみせた。沢山写真撮ってね、とのこと。
しばらくすると、似たようなドレスを着た新婦のお友達軍団(?)20人くらいが、一列になって道の真ん中を行進してくる。一人一個ずつ、大きなケーキを胸に持っている。空き地に停められたトラックに乗ったスピーカーからは、島中に響き渡らんとする大音量で、ポップスとレゲエを混ぜたような陽気な音楽が流れる。
女性陣が席に着くと、道の向こうから別の音楽が聞こえてくる。どうやら今度は新郎側だ。白いスーツに身を纏った若い男性陣が、花を持った新郎を取り囲むようにしてやってきた。
すると、Noraの祭りの方に参加していたおばさまたちが、何やら急いで準備をしている。ネックレスを持ってきたり、ベルトを外したりと、紐状のものを準備しながら、これで良いかな?みたいな感じで相談している。その両端を二人で持って、新郎の通るルート状に、ゴールテープのように掲げながら、新郎の到着を今か今かと待ち望んでいる。すると、新郎がやってきて、短い儀式みたいなものが始まった。新郎に触ってもらうと、その物に良い気が宿るのだろうか。ブーケトスのような、恋愛的な意味はなさそうだ。なぜなら、お母さん達は友達を呼んできて並んでいるから。
新郎の祝福を受けた後のネックレスを受け取ったお母さんは、とても幸せそうに、愛おしそうに、それをもう一度身につけていた。それを見ていたら、また泣けてきた。こんなにも幸福を受け取れる二日間。コーヨー島から幸せなエネルギーをたくさん分けてもらった。
あるおじさんがすっごくニコニコしながら見てくる。英語で話しかけるも、特に返事は返ってこない。英語ができないのかな?と思っていたら、「あの人は耳が不自由なのよ」と、そばにいたおばさんが教えてくれた。その聾者が結婚式場を指差した後、両掌を水平にして、下の掌を押しつけるように、上の手で叩きながら、ニヤニヤしている。爆笑してしまった。じじいの下ネタに弱い。
地図の読めない島民たち
そろそろ出たかったが、デューおばさんが見当たらない。ちょっと見かけたと思っても、また裏に戻ってしまう。すごく忙しそうだ。12時ごろにやっと話しかけられて、「もう出たいです」と言ったら、あらそうだったわね、といった反応。道端で暇そうにしていたおじさんに話しかけに行く。どうやらおばさん自身で送ってくれるわけではないらしい。今日行きたかった、別の橋を通った先の、島の向こう側にある漁師の村を指差して、スマホで地図を見せるけれど、どこだかよく分からないという反応。ソンクラ?と聞かれるんだけど、ソンクラの市街とは逆側なのだ。普段生活をしていて、地図を見ることなんてないのだろう。(ここだけでなく、この旅を通して、地図では伝わらないことが多かったが)多分この島の人々の地理認識は、〇〇さんの家の向かい側とか、お寺の前の民宿とか、橋を渡ってから三個目の信号とか、もっと言語的なのだろうと思う。言葉ができない僕には、視覚的に伝えることしかできなくて、すごくコミュニケーションが難しかった。
仕事で毎日図面を読んだり描いたりしているので、地図を読むという行為を、訓練して身につけたことだということをすっかり忘れていた。人の差し出したスマホの小さい画面で、かつ言語設定が中国語で、しかも航空写真の表示にしていたものを、即座に理解しろという方が難しい。
そんなこんなで、なかなか意思疎通がうまくいかず、申し訳なくなってきたので、自分で行くことにした。「大丈夫です、自分でいけます。」というと、心なしかデューおばさんもホッとしていた。「どうも二日間ありがとうございました。」と顔見知りになった人々(本当に沢山いた、挨拶だけで10分くらいかかった)に別れを告げて、歩き始める。すごく久しぶりに一人になれて、ちょっと気が楽になった。ありがとう、コーヨー家族(抱擁家族みたいだ)の皆様。
意気揚々と歩いていたけれど、車がビュンビュンと走る橋を見て、その路肩を徒歩で渡るのは流石に無理だと判断し、人生初、ヒッチハイクに挑戦した。誰が乗っているか分からない車に向かって手を振るのは、結構勇気がいる。予想に反して、ものの3分ほどで一台の車が停まってくれた。車内は冷房が効いていて、タイ語の音楽が流れていた。運転手は若いお兄さんで、地図を出して見せると、すぐに分かってくれた。カーナビを普段見ているからなのだろうか。それとも、彼も僕と同じく、設計者なのかもしれない。約5分ほどの、短い距離を乗せてもらう。僕の目的地にあわせて、わざわざUターンをして反対車線に下ろしてくれた。そこからもまだ距離があって、日傘を差しながら歩いていたら、今度はバイクが停まってくれた。「Can I help you ?」と聞いてくれる。タイ人はみんな優しすぎる。時間と体力とお金を随分と節約できた。
漁師の町を練り歩く
漁師町に着いた。イスラム教徒が多いのか、町に入ると、イスラムのお経(らしきもの)が、電柱の上の方についたスピーカーで流れ続けている。宗教都市の小さいバージョンのようで、よそ者をはねつけるような雰囲気がある。心なしか、みんなの視線を感じて、少し居心地が悪い。
この町もコーヨー島と同じように、水際に対して垂直に民家が伸びていく町のでき方をしているのだが、より密度感がある。家々の隙間は狭く、一番狭いところは側溝程度の幅、一番広いところでも、バイクがすれ違えるくらいしかない。そのうちのいくつかを選んで湖側に出てみると、住宅の戸口は皆開け放たれていて、内側で寛ぐ人々が見え隠れし、各住宅の所有物が道にはみ出ていたり、取り囲まれた庭などがあり、とても住み心地が良さそうに見えた。

そして、ここで特に発見だったのは、湖沿いに道を作らない町の作り方だ。これだけ綺麗な湖が見えて、かつ水上に浮かぶ小屋が点在する町では、湖に沿って歩ける道を作った方が、移動がしやすいし、眺めも良くて気持ちがいいはずである。だが、それは観光者目線の論理だ。この町では、湖の水際線から100mほど奥まった内地にやっと道路があり、車はそこまでしか入れない。バイクも歩行者も、そこから入っていくと先は袋小路になっていて、舟に乗らない限り、湖のラインで行き止まりになってしまう。大学時代に都市計画の授業で習ったクルドサックという方法にそっくりで、そこに面する住人しか使用しない道になるので、よりプライベート性が保たれて快適になる。これができるのは、どの家もだいたい舟を持っているからだろう。向こう岸のソンクラの街までは、袋小路の先から舟で向かうことができる。
つまり、車道を通さないことと、湖に近い場所は等高線と並行な道を引かないという選択肢をとることで、舟という交通手段の希少性を保った上で、最高のプライベート空間を獲得している町なのだ。

民家の配置も理にかなっている。等高線に垂直線を引くように建てられた民家は、水の流れを邪魔しない。ここでは日常茶飯事であろうスコールは、民家の隙間の道をまっすぐ流れ、湖に落ちていく。簡便かつ合理的な排水計画だ。昨日からずっと謎だった、垂直に伸びる民家も
、同じ理由で作られたものだろう。イスラム墓場も見に行ったけれど、みんな家と同じ方向(湖側)を向いていた。
それと、鳥を飼っている家がなぜか多かった。インコ、鶏、文鳥だけでなく、本当に様々な鳥を見た。漁と関係があるのだろうか?犬も猫も、鶏までも放し飼いで、人間以外の生物が、この袋小路の道の中では、普通に共存していて、とても新鮮だった。ここでは人間が偉そうにしていない。






コインをねだる子供達
湖を望む場所に座っていたら、小学生くらいの子供二人が僕に興味を示している。英語はまだ全くできなかったので、Google翻訳とスケッチを使って話しかけてみる。
「サッカーが好き?」(レプリカのユニフォームを着ていた)→イエス
「日本は知ってる?」→ノー
「この街が好き?」→イエス
恥ずかしがりな二人は、首振りだけで解答を示してくれる。とても可愛い。狭いコミュニティで生きてきた彼らにとっては、海の向こうは想像をしたことがないのだろう。

別れ際に、余っていたシンガポールとマレーシアの小銭を1枚ずつプレゼントすることにした。本当にいいの?という感じで、太陽光に照らしながら嬉しそうに眺めていたのに、すぐに、まだあるか?とねだってくる。終いには、ポケットから20バーツ札を取り出して、「これはないのか?」と無邪気に聞いてくる。ちょっと気まずくなって、「ないよ、あげないよ」と立ち去ったら、彼らが友達へ言いふらしたのだろう、俺にもくれ、俺にもくれと、4人くらいの小学生に追いかけられた。まだコインは余っていたし、渡そうと思えば渡せたけれど、キリがないので、「もうない、あげられない」と早歩きで村を去った。普通に怖かった。
その無邪気な顔に、気軽にお金を渡すもんじゃないと反省した。僕にとってはもう殆ど価値のないコインも、彼らにとっては貴重なものだ。この、あまり裕福とは言えない地域で、見せびらかすように渡すものではなかった。もしあげるなら、
・これはお土産であって、お金としてではない
・仲良くなった記念だから、友達には内緒
ということをきちんと伝えれば、彼らも僕の気持ちを分かってくれただろう。そういえば、コーヨー島では、お金を目にする場面を、Noraへのお布施でしか見なかった。資本主義の暴力から守られた世界がまだあそこにはあった。
小学生に追いかけられた恐怖を、乗り合いバスに乗ることでかき消しながら、ハートヤイまで帰った。彼らはあの町から出ることはできない。
なんと、行きよりも更に安く乗れて、随分安いと思っていた行きでさえ、まだ多少ぼられていたことを知る。
奴隷船バンコク行き
駅まで歩いて、夜行列車を探しに行く。駅に着くと、今日はもうないよ、と警察っぽい格好をしたお兄さん。「明日の朝にまたきてください。」
まだ7時ごろなので、もっと遅く出る夜行便があると思い込んでいた。どうしようかと思っていたら、「バスならまだ乗れます。」とのこと。夜行列車への憧れがあったけれど、またハートヤイに一泊して、それから昼間移動だと、時間もお金も余分にかかってしまうので、バスで妥協することにした。
「バスはどこに行ったら乗れますか?」と聞くと、一人の男を紹介される、彼はバイクにエンジンをかけ、乗れと言っている。オレンジのジャケットを着ているので、何かの団体に所属していることはなんとなく分かる。まあ従うしかない。ヘルメットはもちろんしていない。彼は走り出すと、5分くらいで小さな建物に着いた。そこで運転手が変わって、また乗れと言われる。
「いくらですか?」→「高くないよ」
「どこでチケットが貰えますか?」→「俺が連れていく」
「クレジットは使えますか?」→キャッシングの機械の前に連れていかれる。
会話が全く成り立たない。しかも、何度も、早く金を寄越せと言ってくる。先にチケットを貰いたい、と言っても、金を渡せの一点張り。時間がないと思って、もう諦めて言い値の1200バーツを渡してしまった。高いと思ったけれど、警察の紹介だからという理由である程度信用してしまっていた。
すると、バスターミナルの方向にバイクを走らせる運転手。バス+タクシー代なのかと無理矢理納得する。ついたと思ったら、なんとバスターミナルには入らず、その前にふてぶてしく建てられたダフ屋に止まって、窓口で何やらやりとりをしている。この時点ではもう、騙されたことには気づいていて、如何に運命を受け入れるかを考えていた。抗議の目で運転手の目をジッと見つめると、彼は目を合わせずに、決まり悪そうに、ここで待っていろと言って立ち去っていった。出発まで1時間あったので、顔を覚えてもらってから(チケットは最後まで貰えなかった)、隣のバスターミナルにいくと、普通にバンコク行きのチケットが860バーツで売っている。先生にもらったカップヌードルに、コンビニでお湯を入れて、立ちっぱなしで食べる。この旅で一番惨めな瞬間だ。
それにしても腹が立つ。僕の1200バーツから、バス代860を引いた340バーツが、警察→紹介屋A→紹介屋B→ダフバス会社というルートに従って、順番にばら撒かれていくのだろう。もしかしたら、警察は関与していないかもしれない。というか、周到に距離が取られていて、そのことを証明できない。いくらでも言い訳ができるし、足切りができる。でも、彼らの職務は市民の安全だろう。市民の一部である旅行者に、正しい情報を伝えることも役割の一つだ。サツを信じるなんて愚者のすることだった。
未然に防ぐ方法があったとすれば
①先に正規の値段を調べておく
→差額を知っていれば詐欺であることに気づけた
②クレジットが使えない時点で断る
→カードが使えない=痕を残したくない=やましいことがある、と考えて問題ない
③警察だからといって信用しないようにする
→これは何も警察だけじゃない。社会的地位がある人間が、自分を騙さないという保証はどこにもない。
というところだろうか。こう書いていたら、結構自分のせいな気がしてきて、怒りもおさまってきた。彼らも家族を養うために、旅行者を騙しているのだろう。くそくらえ。
時間になると、一台のバンがやってきた。バスって言っていたではないか…。しかも、窓が黒塗りになって中が見えない。マジでこれに乗るのか…?自分の愚かさに、辛くて泣きそうだった。見渡すと、僕と同じように騙されたであろう大荷物の観光客が6名ほどいた。乗り込むと、クーラーの勢いがおじいちゃん並みに弱いし、当然のように充電用のUSBポートはない。シートの隙間にはポテチのかけらとか、潰れたコーラの空き缶とかが挟まっており、タバコの匂いと消臭剤の匂いが半々で漂っている。出発したと思ったら、容赦無くラジオをかける運転手。なんなら、それに合わせて歌を歌ったり、大きな声で電話をかけたりしていた。よっぽど「頼むから静かにしてくれ」と思ったけれど、声を出す元気も勇気も湧いてこない。他の乗客も同じ状態だったのだろう、運転手に抗議するものは一人もいなかった。
不幸中の幸いで、12席くらいしかない内の、7席くらいしか埋まっていない。また、僕と、もう一人のおじさん以外は、夫婦と女の子の友達同士だったので、彼らは隣同士に座ってくれた。なので、僕は一番後ろの3席を一人で使うことができて、狭くはあったが横になることができた。
運転の腕はすごく良くて、とにかく速い。高速道路でたまに見かけるうざったいスポーツカーのごとく、車線変更を駆使してぐんぐん追い抜かすし、その割に急ブレーキは殆どなかった。揺れはひどかったけれど、それはタイの道路事情にもよるものだろう。警察の検問が3度ほどあって、その度に「シートベルト!(多分)」とタイ語で言われた。最初はわからなかったけれど、みんながかちゃかちゃやり出すので、おかげでその言葉は聞き取れるようになった。逆に言うと、それ以外の時間はみんな締めていなかった。
途中で、トイレ休憩とガソリン補給を兼ねて、いくつかのサービスエリアで停まったり、運転手が少し仮眠する時間があった。考えてみたら、7人の乗客のためだけに、1000kmもの距離を一人で走行するのもすごいし、ガソリン代も、会社側が負担する分は馬鹿にならないだろう。出発する前には、みんな揃ったか?みたいな感じで、乗客がお互いに見回して人数を確認する時間が何度かあった。なんだか少数精鋭のチームみたいで、楽しくなってくる。
僕は生来の丈夫さと、横になることができた幸運で、休憩地点と検問以外では、8割型ぐっすり眠ることができた。そんなこんなで案外、15時間半の奴隷船は短く感じた。なんと降りる頃には、長時間運転を頑張ってくれてありがとう、という気持ちにさえなっていたのだから、時間と睡眠というものは、感情を抑えるのにとても有効な手段だ。
午後1時半、バンコクのバスターミナルに降り立った。北上すればするほど涼しくなっていくだろうという僕の甘い見立ては、バンコクの太陽の元で、跡形も無く溶かされてしまっていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
