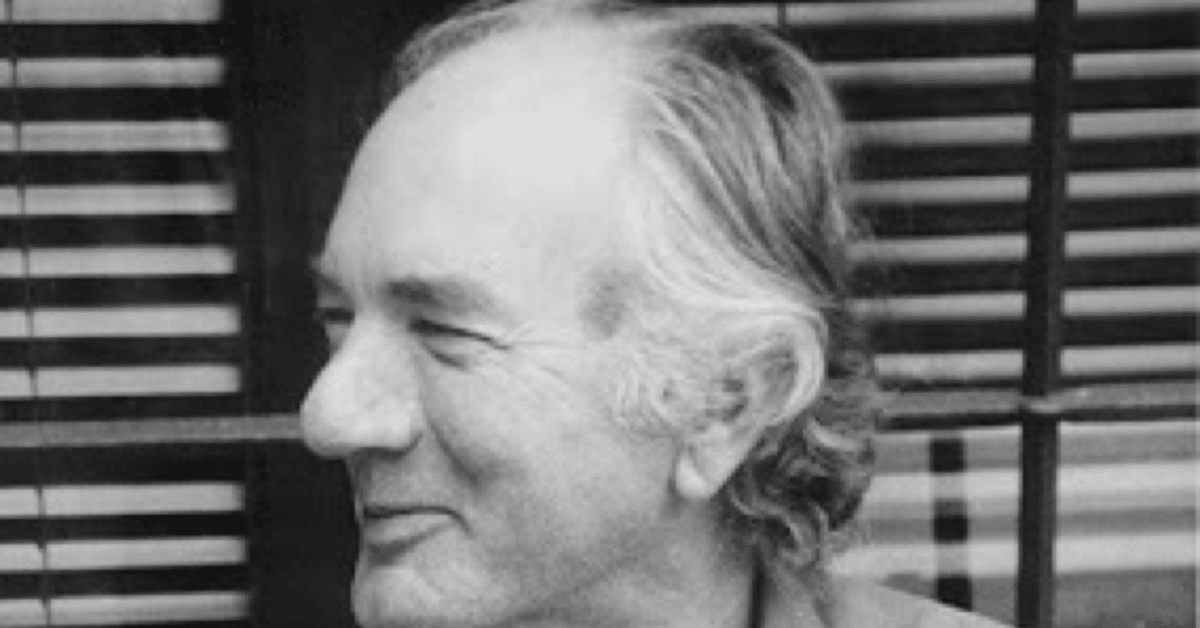
呪詛の如く書かれた小説を読むということ トーマス・ベルンハルト『消去』
断言するがこれから私が書くことになる、トーマス・ベルンハルト『消去』に関しては、紹介したところで、たいていの人は多分「おっ読んでみるか」とはならないだろう。というのは、『消去』は本当に変わった小説で、何しろのっけからこんな具合なのだ。
二十九日にピンチオの丘で教え子のガンベッティと落ち合い、五月の授業日程の打ち合わせを終えた私は、とフランツ・ヨーゼフ・ムーラウは記す、ヴォルフスエックから戻ったばかりのそのときも改めてガンベッティの高度な知性に目を見張る思いをさせられ、大いに感激したこともあって、コンドッティ街からミネルヴァ広場に直行するふだんの道を通らず、フラミナ街からポポロ広場経由でコルソへ抜ける蜜をとったのだが、オーストリアでなくローマこそ自分の住処だとおもいはじめてもう久しくなると考えるうちにだんだんと気持ちがはずんできたので、しばらくコルソをぶらついてから家に戻ったその矢先の午後二時頃、両親と兄ヨハネスの死を告げる一通の電報を受け取ったのだった。
どうだろう。この書き出しは、尤もベルンハルトらしい表現、ベルンハルト的文章といえる。一般的世間的には所謂「悪文」と呼ばれる類の文章だ。センテンスをつなぎ合わせ、入れ子構造のような複雑な文体を紡ぎだしている。学校の作文の課題でこんな文章を書いて出したら、赤字で添削されまった挙句突き返されるだろう。なお、私=フランツ・ヨーゼフ・ムーラウであるのでどうかお間違いなく。で、息継ぎしないで読み上げたら酸欠になりそうなほど長い長い一文はまさにベルンハルトの十八番であり、クライマックスに至るまでその筆は衰えることはない。『消去』の文章が読みにくいということかと言えば、そうではない。改行のない文章がお経のように延々と続くくせに、不思議なことにすっと頭の中に入ってくる。原文を読めないので推測になってしまうが、本作の訳を手掛けたドイツ文学者、池田信雄先生の仕事が相当素晴らしいのだと思う。根性さえあれば誰でも読み通せるような(比較的)容易な文章で、かつベルンハルトの晦渋さを損なわない、そんな見事なローカライズが施されているからだ。
まぁいずれにせよ間違いなくあのけんご大賞などにはまずノミネートされないタイプの、ゴリゴリの読者を選ぶ文学作品というのは強調しておきたいところである。しかしこの「悪文」はベルンハルトの魅力には違いないが、それは彼の魅力の半分しか語っていない。若い衆よ、冒頭の文章に恐れをなし「うわぁ、読みづら…」と尻尾を巻いて逃げるのは今のうちである。むしろここからベルンハルトの真骨頂はむしろここから始まる。彼のもう一つの武器がうなりをあげる。悪口である。
いわゆる成り上がりの女が、ヴォルスクエックのような領地に必ず荒廃をもたらすわけではないが、母にかぎっては荒廃をもたらす成り上がりだった。弱虫の父は、妻の誇大妄想や馬鹿げた言動を制止する力や性格を全然持ち合わせていなかった。それどころか、父は、この女、つまり私たちの母が望むすべてを承認し、それらを知恵にもとづく最後の結論と見なし、母の悪趣味ゆえの過ちのすべてを傑出したこととまでは言わなくとも、いいこと、優れたこととして歓迎し、ほめたたえたから、母は次第に、自分は「ヴォルフスエックの救世主」とあがめられて当然の存在だと思いこみ、それ以後絶えずその役を演じつづけたのである。実際には、ヴォルスクエックにとって母にまさる害虫はいなかったのにだ。
ちなみにムーラウは、自身の妹の配偶者のことを決して名前では呼ばず「義弟」「ワインボトル用コルク栓製造業者」と呼んで憚らない。いかにその職業を蔑んでいるかわかるだろう。そもそも自身の家族についても全くこの人は敬意や愛など感じておらず、ことあるごとに上記の如く、こてんぱんにしてしまう。死んだ父と兄はもちろんだが、とくに家族の女性たちに対する憎悪が凄まじい。彼の二人の妹たちには「残酷」で「醜い」女たちとこき下ろし、亡くなった母親には引用のように「あの女、つまり私たちの母は破壊者以外の何物でもなかった」とののしる。彼の故郷ヴォルスクエックに関しても言うに及ばずであり「芋とソーセージしかないしょうもないど田舎」と突き放す。最早毒を吐く、というレベルを超えて、巨神兵がビームで辺り一面を焼き払うが如く、彼は呪詛のように言葉を吐き続ける。
ムーラウは何故、あたり一面に言葉の毒をまき散らすのであろうか。それは幼少期に彼が家族からうけた酷い仕打ちが深く関係しているのだが、一方でこんな興味深い記述があったりする。
尊大さとは世界に対抗する武器にほかならず、もしこれがなかったら世界は私たちを一飲みに飲み込んでしまうことだろう。世界は私たちにいっさい思いやりがない。
確かに、ムーラウ、ひいてはベルンハルトその人の語りというのは「尊大」という一言に尽きるのかもしれない。彼の文体の「尊大」さは実は、いつか押しつぶされてしまうかもしれないという不安、そして彼を押しつぶそうとするオーストリアへの嫌悪感と、巨大な不信感によってもたらされている。彼は故郷のオーストリアについてこう語る。
ずたずたにされ、落ちぶれ、疲弊しきったオーストリアは考えただけで、と私はこの耐えがたいくらい悪趣味な葬儀の数日前にガンベティに言ったばかりだ、と私は考えた、吐き気がする。このまったく落ちぶれはてた国家のことは言わずもがなだ、ガンベッティ君、この国家の下劣さ、低級さときたらヨーロッパだけでなく、世界にも例がないほどだ。何十年も下劣で落ちぶれた痴呆症の政府ばかりが支配し、国民はその下劣で落ちぶれた痴呆症の政府に見分けのつかなくなるほど切り刻まれ息絶えだえだ、と私はガンベッティに言ったのだ、と私はいま考えた。
ムーラウのそうした毒は、生まれ故郷に対する徹底的な嫌悪に基づかれて生成されているのだ。なんと救い難いのだろうか。彼が語るところの醜きオーストリアはアンシェルスによってドイツに1938年に併合された。かくして二重国家は崩壊した。地元の名士であったムーラウの父親はナチスドイツに協力したばかりか、戦後も敷地内にナチス党員の幹部ををかくまい続け、剰え彼らは事故死した両親の葬儀に出席する有様なのだ。想像を絶する光景、グロテスクな光景だ。罰せられるべき人間を守っただけでなく、のうのうと長生きしているのだから。
彼が語るところの「落ちぶれたオーストリア」はいかなる場所なのだろうか。例えばであるが『ウィトゲンシュタインのウィーン』に詳しい。無茶苦茶ざっくり内容を書くと、第一次大戦後のオーストリアは、「人心の分裂」ともいえる状況に陥っていていたようで、ベルンハルトが嘆く祖国の「落ちぶれ」っぷりを既にうかがい知れて興味深い。なかなか浩瀚な書物でさらっと読める本ではないし、かつ現在は入手も困難だがベルンハルト副読本として読む価値はあると思う。かつて世界の中心であったウィーン、ひいてはオーストリアそのものがいかに引き裂かれ、崩壊したのか。幼き日のムーラウ、そして作者のベルンハルトも目にしただろう祖国の崩壊と人心の堕落は少なからず彼らの語りに影響を与えたのではないだろうか。
このムーラウとは何者なのだろうか。自信満々に言葉を綴るこの男は、『消去』の私=ムーラウはいい歳した(48歳)の無職で、実家からの仕送りで暮らすニートである。ローマの一等地のアパートを借り、ろくに働きもせずに哲学的思考をめぐらせる日々に明け暮れている。時折その語りの中で登場する金持ちの息子ガンベッティ君にドイツ文学の薫陶を施し報酬も得たりしているが、要は彼は定職に付いていない無職のおじさんなのである。そう、彼は信じられないことに仕送りを受けながらも、お金を振り込んでくれる人たちをディスっているのである。この構造が面白い。このいびつな構造が本作にユーモアを齎している。社会不適合者では無いまっとうな大人であれば「なんで養ってもらってるのにそんなにえらそーなんだよw」とページをめくるたびに突っ込まざるを得ない。本作を面の皮が厚いとはこのことだろう、と眉をひそめる人もいるかもしれない。私は死ぬほど羨ましいと思ってしまうが。そうした訳で、この小説はなかなか笑えるところがある。ちょいとハイコンテクストではあるけれども。
と、ここまで書いたものを読み返してみた。私は感じた「一体誰がこんな小説を読むのだろうか?」と。少なくとも、エンターテインメントとか、癒しや感動とかを小説に求める一般的な読書層は定価6000円もする翻訳本を手にするだろうか。多分しないだろう。と、いうか、である。こんなことを披歴したら間違いなく狂人扱いされるのではないか。改めて思うが、『消去』ほど推薦しづらい本はないと思う。「毎月仕送りもらってるニートが己の祖国と家族を呪詛のようにディスりまくる小説なんですけど、大変すばらしいんですよ」などと職場の喫煙所などで同僚に言ったら多分ひかれるだろう。ちなみに、ベルンハルトは自国の批評界から「巣を汚す者」と蔑まれている。
重複してしまうが、『消去』はSNSで感動を共有したり、読了したのを自慢するような目的をもって本を開く人たちには全く向かない本である。じゃあ誰に向いてるのだろう。
とりもなおさず、「まだ自分が読んだこともないようなものを、読んでみたい」という強い好奇心を持ち合わせていれば、その欲望を満たせることは間違いない。そういう文学オタクならもうベルンハルトくらい読んでそうだが、読んでなければGOである。
あるいは、こういう捉え方もある。「憎まれっ子世に憚る」という言葉があるが、確かに憎まれっ子でなければ見えないものがある。それは、文学の世界にとどまらず、だ。ちょっと抽象的な話になるが、大きな構造に唯々諾々と従っているだけでは、その内部に抱える問題は解決できない。問題は外側に立って初めて解決の道が見えるときもある。そうした外部の視座に立たなければならない時、『消去』にとどまらず、ベルンハルトの言葉は有用だ。そういう見どころのある人には、まぁ6000円以上の価値はあるんじゃないかなぁと思う。彼の尊大さは、やたら同町圧力を強いるこの国で押しつぶされないよう生きるうえで最上の武器になるかもしれない。
余談だが、ムーラウは何もかも恨み骨髄ではない。彼にだって尊敬するもの、愛するものがあって、それに対しては最上の敬意を払う。慈愛に満ちた言葉は、ムーラウはただの呪詛を吐く怪物ではなくて、暖かい血の通った人間なのだと教えてくれる。そのあとすぐ激烈なあの悪口に戻ってしまうのが、ご愛敬といえばご愛敬なのだが。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
