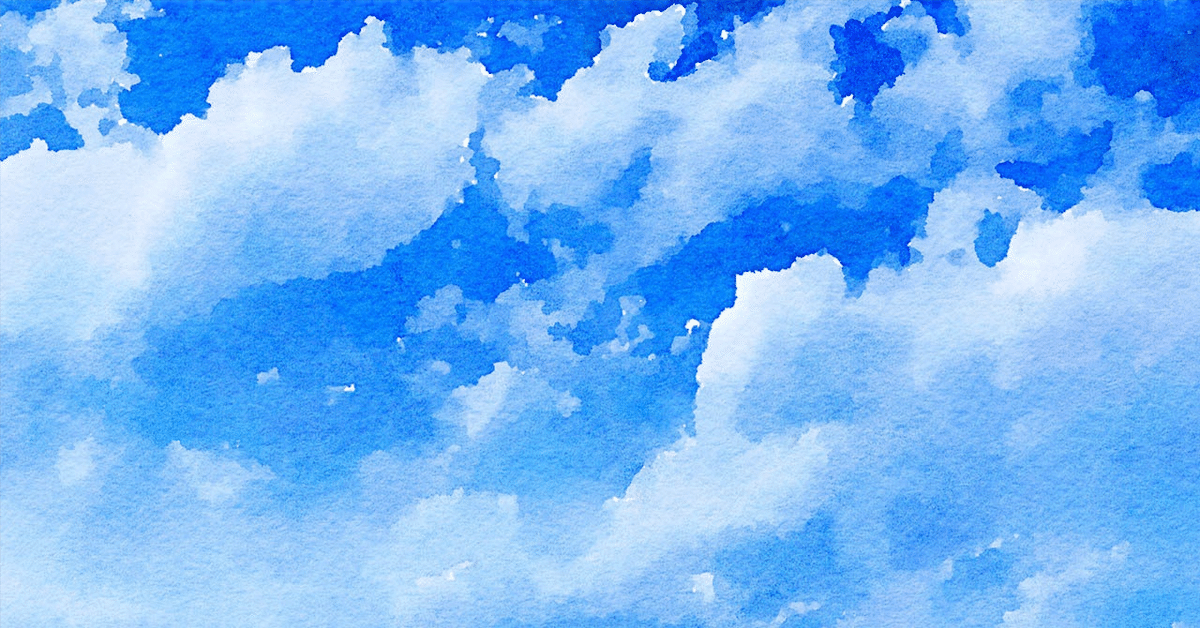
呪われた王女と見捨てられた王子のお話
《あらすじ》
『十八歳で死に、同時に国も滅びる』
父親がろくでなしだったせいで、そんな呪いをかけられてしまった王女エウフェミア。期限まであと一年というときに、彼女の夫となってくれる青年が現れる。敵国に人質として差し出すために育てられ余ってしまった王子、ジェレミアだ。
これは普通ではない生き方をしてきた二人が出会い、幸せになるお話。
《前編》出会い
顔を覆うベールに大粒の雫《しずく》がついた。
手で払い重苦しい灰色の雲に覆われた空を見上げる。
「降ってきたのかしら」
私の呟きに、隣に立つ大臣のひとりが
「あと少しもってくれ」
と祈るように答えた。
王宮の正面玄関前に一斉に並ぶ私たち。最後の王族である私や大叔母たち、ほぼ全ての大臣に宮廷に仕える者たちまで、総出で遠い異国から来る王子を待っている。目に見える形で『これほどまでにあなた様を歓迎している』と表しているのだ。
何しろ私は呪われた王女で、この国は私と共に滅びる予定だ。その期限はきっちり一年後。王子はそんな私の婿になり、そして新しい王に即位するために来てくれる。歓待は当然のこと。彼に至るまで何十という男性に婚姻を断られた。
たとえやって来る王子が残念としか評しようのない人でも構わない。
三月前のこと。滅びを宣告された国を滅亡から守るため、力強い決断と実行力で国を率いてくれた女王が病に倒れ亡くなった。彼女がいたから我が国はパニックにも陥らず人口流出もわずかで済み、国力なんて衰えるどころか増強したほどだったのに。
カリスマを亡くした民は不安におののいている。だから少しでも未来を感じさせる明るい話題が必要なのだ。それが残念な王子だとしても、国民に知られないよう立派な青年に演出すればいい。
「来た」
誰かが声を上げた。
耳を澄ますと、遠くから蹄と車輪の音が聞こえてきた。
「良かった」と先ほどの大臣。
対して私は急に不安になって、彼を見た。
「王子には、私の文様のことは伝わっているわよね」
はいとの返事。
「顔を見せられないことも」
「先方には婚姻の打診をしたときに伝えてありますし、ジェレミア殿下ご一行を迎えに行った宰相が改めて口頭で説明しています」
「そう。何年探しても見つからなかった婿がこのタイミングで来てくれるなんて夢のようだから、伝えていないのかもしれないと不安になってしまったわ」
「問題ありません」
大臣の力強い声にほっとする。
私は呪われているだけでなく、その呪いが黒い文様として全身に刺青のように浮き出ている。あまりに不吉で恐ろしいそれは他人を不安にさせるので、私はけっして肌を晒さない。高襟の服に手袋、顔にはヴェール。物心がついてから、ずっとこの出で立ちだ。
我が国の人には見慣れた格好だけど、異国の人々は顔を隠して迎えなぞ失礼だと立腹するかもしれない。
「万が一、それでもあなたに失礼な態度を取るような王子ならば」と大臣は言葉を継いだ。「我々は一丸となって傀儡政治に励みますから、ご心配なく。それが亡き女王陛下への最後の奉公です」
思わず吹き出す。
「頼もしい。さすが、お母様が選んだ精鋭だけあるわ」
こちらを向いた大臣がニヤリとする。
この国に古くからいた貴族の多くは、滅亡する国にはいられないと他国へ逃げた。残ったのは呪いに打ち勝ってやるという豪気な者たち。
滅亡期限まであと一年。
私の命もあと一年。
やがて王子一行がやって来て、私たちの前に止まった。
出迎えに出た宰相の早馬がもたらした情報通り、馬車も護衛も非常に少ない。相手国はそれなりに国力があるはずだから、この規模であるのは推して知るべしだ。
目前の馬車の扉が開き、青年――らしき男がひとり、降りてきた。私と同い年の17歳のはずだけど、どことなく足元がおぼつかなくて体がふらふら揺れている。
顔はおかしな色をした長い前髪で上半分が隠れてて見えない。その髪は洗っているのかごわごわとしていて、首の後ろでひとつ結びにしているのだけど形が整っていない。
これが私の夫となる人。
胸を張り、王女としての挨拶の構えをしたその時。
青年は何もない地面にけつまづいて転んだ。あちらの人間は誰も王子に駆け寄らない。
ほんの短い間だけ悩み、私は進み出てかがむと
「大丈夫ですか」
と手を差し出した。
「ああ、うん。いつものことだから」
間延びした声。
良く言えば、邪気がない。優しそうな声だ。
「ありがとう」王子は呪われた私の手を躊躇なく取り、ゆっくり立ち上がった。「僕はリューゲ国の第八王子、ジェレミアだ。君が呪われた王女様かい?」
想定していた挨拶を全てすっ飛ばしての、自己紹介。しかもストレートに『呪われた王女』だなんて言われるのは初めてだ。
残念な王子でも、案外楽しく過ごせるかもしれない。
「ええ、そうよ。私が呪われた王女エウフェミア。ようこそ、我が国へ」
◇◇
ジェレミアの母国リューゲと我が国の間には、大きな国をみっつも挟む。それほどまでに遠い。なぜそんな遠方の王子が婿に来たのかといえば単純に、近隣諸国の王族には私との結婚を承諾してくれる者がいなかったからだ。
それほどの遠い国から日数をかけてやって来たリューゲの使節は、王子の荷物を城に運び込むと挨拶もそこそこにさっさと帰って行った。よほど呪われた姫と滅亡する国が嫌なのだろう。それからジェレミアも。
彼と共に城に残ったのは三人。気の狂った母親とその侍女。実兄で第四王子でありながら、ジェレミアの侍従をしているトリスターノだ。
トリスターノは質素倹約を旨とする修道士が着るような簡素な服を着て、頭には目の部分がくり貫かれた頭巾をかぶっている。左腕はおかしな方向に曲がりその手は皮膚がただれて親指以外の四本がくっついている。更に右足を引きずってもいる。
リューゲの王はきっとジェレミアたちを厄介払いしたかったのだろう。
使節が去ったのは、広間でジェレミアにひととおりの必要事項の説明を終えた頃合いだった。
夜には歓迎会がある。それまで少し休んでもらおうと小さなサロンに移ったのだが、彼は座ることもせずに窓を開けて雨の中を遠ざかる一行を見ていた。
空気の読めなさそうな残念王子でもやはり心細いのか。
彼の背中を見ながら私はそうしんみりしていたのだけど、振り返ったジェレミアは突然、
「トリスターノはあまりに美しかったから王妃と義兄たちに妬まれて、たった12歳のときに火炙りにされたのだ。面白半分、見せ物として。その前に暴行も加えられていて、腕と足はあの通り。喉も潰され声も出ない」
と言った。はきはきとして明瞭な声音。ジェレミアの間延びした口調ではない。
混乱した私は、誰か他の人が喋ったのかと部屋を見回した。いるのは私たちの他にはトリスターノと私の侍女グウェン、侍従長と、他何人かのよく見知った使用人たちだ。
「喋ったのは僕だよ、目の前にいるジェレミアだ」
彼はそう言って前髪に手をやるとさっとまとめてピンで留めた。現れたのは意思の強そうな青い目。とんでもない美形だ。
「僕たち兄弟の母は妾の中でも、身分がだいぶ下でね」と美形。「暴行を受けたからといって文句も言えない。無残な姿の息子を目にした彼女にできたのは、気を狂わせて夢の世界に逃げることだけ。城ではこの十年、幽閉生活だった。
母に代わって瀕死の兄を助けてくれたのが侍女ベレタだ。その時にベレタは僕が兄の二の舞にならないよう、マヌケを装うことにさせたんだ」
美形――ジェレミアは嬉しそうににっこりとした。
「人前で演技をしなくていいのは十二年ぶりだ。僕を婿にしてくれてありがとう」
ふんふんという荒い息遣いが聞こえて振り返ると、トリスターノが首を大きく縦に降っている。
「兄も礼を言ってる」
まさか婿になる人から礼を言われるなんて思わなかった。どうやら些かぼんやりした青年のようだとは聞いていたけど、『来てやったのだ、ありがたく思え』的な態度しか想定していなかった。
「……婿入りを喜んでくれるの?私は呪われているし、国は滅亡予定なのよ?」
「生まれた三日後に呪われて、以来十七年間解呪の方法を探している。国の滅亡を防ぐためにあらゆる努力も重ねて、結果として農業産業とも生産力は右肩上がり。天変地異に備えてインフラは完璧、食糧の備蓄も十分。あらゆる流行り病に対処できるよう、医師薬師を国費で育て各地に配置。僕はそう説明されたけど、違うのかな?」
「その通りよ」
「ならば、何か問題があるかい?」
「……普通の王子ならば、それでも滅亡不可避と判断するのよ」
「残念。僕は普通ではないから、解決目指して一緒に頑張ればいいと思っている」
ジェレミアは軽やかに言ってのけると、目を反らして頬を掻いた。それから私のそばまでしっかりとした足取りでやって来た。はにかみの表情だ。
「すまない、僕はちょっとばかり自由になったことに浮かれているのかもしれない。決して事態を軽視しているのではないよ」
ええ、とうなずく。
「周囲にアホウ者と思われ、母が狂人の僕が王子のまま生きて来られたのは何故か。他国と緊張関係に陥った際の人質として差し出すためだ」
そうジェレミアが言うと、トリスターノがまた大きくうなずいた。
我が国の周辺は平和だけれど、リューゲ周辺は時おり国家間の衝突があると聞いている。ジェレミアはそのような事態に備えての捨て駒だったというわけだ。
ちなみにこの婚姻において、我が国がリューゲ国王に膨大な結納金を支払っている。あちらはさぞかし高笑いしていることだろう。
「母は実家にも見捨てられていてね」とジェレミアが続ける。「僕が大人になったら皆を連れて逃げ出すつもりで算段は立てていたのだけど、そろそろ実行をと思っていたところにこの縁談が来た。おかげで僕たちは大手を振って、奴らから離れることができた。
君にもフトゥーロ王国にも感謝しかない。何より僕は僕たちの居場所を失くしたくないからね。必死に滅亡回避に勤しむつもりだ。
――信じてくれたかな?」
「ええ。頼もしい人が来てくれて、私も感謝しかないわ」
「良かった」
にこりとしたジェレミアはとても美しく、胸の奥がツキンと痛んだ。
◇◇
私たちは長椅子に向かいあって座った。ジェレミアの隣にはトリスターノ。彼は従者だからと座ることを固辞したけれど、見たところ引きずっていない足だけに重心をかけているようで、こちらが心配になるのでお願いして座ってもらった。そもそも従者である前に、ジェレミアの兄なのだ。
捨て駒王子として存在を許されたジェレミアだったけれど、ある意味それが幸いした。他国に人質に出したときに王子であることに疑いを持たれては意味がない。だから教育はきちんと受けることができたのだそうだ。
兄のトリスターノはその見た目から当初、母と一緒に幽閉されそうになったのだが、弟の従者になることでそれを免れた。そうして母子と侍女の四人は華やかな王宮の片隅でひっそりと生きてきたそうだ――表向きは。
早いうちから四人揃っての城脱出と自立を考えていたジェレミアはのけ者扱いされていることを逆手にとって、城を抜け出し市井で庶民を装いあらゆる経験をしてきたそうだ。
著名な学者や引退した騎士、鍛冶師や商人、果ては裏社会のボスから知識や技量を授かった。王宮からちょろまかした(本人談)宝石を売って元手にして闇賭博で増やし、秘密の貯蓄もした。
なかなかにパワフルで、思わず『本当に同い年なのか』と確認してしまったほどだ。
些かぼんやりどころか、ずいぶんと逞しい。
「母は気がふれてしまったけれど、トリスターノのことにショックを受けたせいで、ただ過去に生きているだけなんだ。自分は十歳の少女で僕を弟、ベレタを乳母、兄を従僕と思っているだけでね」とジェレミア。
「彼女の望みはただひとつ、庭園を散歩したいということだけ。それに兄はあの外見のせいで死んだことにされてしまった。義兄弟は兄を見つけると必ず嘲り暴力をふるった。
だから僕はどうしても皆を連れて城を出なければならなかったのだ」
「もし良ければだけど、トリスターノ様は従者を辞めてあなたの兄君として暮らすのはどうかしら。リューゲは遠すぎて、どの王子が落命しているかなんて私たちには分からないわ」
そう提案をするとジェレミアは驚いた顔で瞬いたあとに、にこりとした。
「どうだろう、兄さん」
トリスターノは身振り手振りで、恐らくは『考える』と示した。
「『悩む』そうだ」と弟が通訳をする。「あとでゆっくり兄の意見を聞いてみる。ありがとう、エウフェミア」
笑顔のジェレミアはキラキラと輝いて見える。第一印象とは大違いだ。
ときめきながらも痛む器用な胸。それを抑えて、こちらの事情を話すことにした。
私の呪いの元凶は父だ。ろくでもない女たらしのクズ男。
私の祖父で二代前の国王ロベルタ三世は子供に恵まれず、無事に十歳を越したのは長女ベルティーナだけだった。当時の我が国の制度では家長を継げるのは男性のみ。そこでベルティーナは婿を取ることになった。
この婿取り。私とは違い、申し込みが殺到し大変な人気だったらしい。陰で日向で激しい争いがあり、時には血が流れることもあったとか。
その激戦を勝ち抜いたのが隣国の王子カッサーノだった。彼は大変に優秀で博学、王の器もあり尚且つ見目麗しい青年だったけれど大きな欠点があった。とんでもない女好きだったのだ。
それにさえ目をつぶれば、あとは百点満点。ゆえに祖父は、ベルティーナの子、もしくはその伴侶しか国王にはさせない旨と、異性とのトラブルを王家に持ち込まない旨の宣誓書を書かせた上で婿入りさせた。
それから一年後、ロベルタ三世国王夫妻は肺炎を拗らせ相次いで逝去。異国から来たばかりのカッサーノが即位した。その半年後。ベルティーナは珠のように美しい女児を産んだ。私だ。
城中が喜びに沸き、あちこちから祝う人々が訪れた。
そんな歓喜溢れる祝いの場で。客人であるひとりの女性が衆目の中、堂々と私に呪いをかけた。
先走った近衛兵がすぐさま彼女を刺し殺したのだが呪いは完成したあとで、今際のきわの女性は懐から一通の手紙を取り出し「これを王妃へ」と言って死に絶えた。
その手記によると、彼女は来国したばかりのカッサーノに口説かれもて遊ばれ捨てられた。赤子に呪いをかけたのはその恨みから、ということだった。
そしてこの呪いを解く方法は、ふたつ。ひとつは彼女が解くこと。だがこれはもう不可能となった。残りのもうひとつ。それはカッサーノが、全てを懺悔し自らその諸悪の根元を切り落とすことだった。
そうして私に掛けられた呪いは、18の誕生日を迎えたら命を落とす、更には私の命と国の命が繋がるというものだったのだ。
当然、母も大臣たちもみな怒り心頭で父に懺悔と処理を迫った。その最中、先走って女性を殺した近衛兵が、それはカッサーノの指示だったと告白もした。
追い詰められたカッサーノ。彼の下した決断は――。
懺悔ならいくらでもするけど、切り落としはしない。
そんな仰天の決断だった。
父は色魔ではあったけれど、頭脳は優秀だった。私の呪いを解くために必要なものは自分であるゆえ、周囲がどれほど怒り狂っても自分を殺すことは出来ないと判断したのだ。
彼は、向こう十八年弱は今まで通りに享楽的に過ごし、期限ギリギリで処理すれば問題なかろうと主張した。
だが誰も父を信じなかった。きっと十八年後、この下半身に脳味噌がある阿呆は国を捨て他所へ行き、女漁りをするだろう、と。
父を見て国の滅亡を確信した者は、財産を持って他国へ逃れた。
一方で静かに怒った母は残った者たちと連携して憲法を改正して女性も王位につけるようにした。父をその座から引きずり落として幽閉するつもりだったのだ。
ところがその直前にカッサーノは死んだ。別の女性に刺し殺されたのだった。
彼女は地方に住む娘で、半年前に視察に来た国王に無理強いをされてその恨みとのことだった。私の呪いについては全く耳にしていなかったそうで、それを知ったときは号泣して母に謝ったという。とはいえ全て後の祭り。私の呪いを解く方法は失くなってしまった。
「そこで母は御触れを出して魔法を使える人、呪いの知識がある人を募集したの」
世の中には魔法が使える魔女がいると言われているが、実際に存在するのかは私が呪われるまで不明だった。彼女たちはきっと人に知られないよう、ひっそりと暮らしていたのだろう。
だから御触れを出したところで名乗り出る者は皆無だったのだが、母は諦めなかった。根気強く募集に好条件をつけ続け、やがては十一人もの魔女が集まった。今では組合を組織して、私の呪いを解く研究をする傍ら、薬師としても大活躍している。
「言い換えると、それでも私の呪いは解けなかった。残り一年。諦める気はないけれど、間に合わないかもしれない。たとえ間に合わなくても、国だけは救う」
呪われた誕生日に何が起こるのか。
私が母の後を継いで即位しても、もし死んでしまったら王としての務めが果たせない。だから夫になる人に国王になってもらうのだ。
そう説明するとジェレミアは、
「君に会ってまだ数時間だけど、死んでほしくないと心底思うよ」
と優しい声で言ってくれたのだった。
《中編》結婚
異国からやって来た新国王は人は良いけど、ぼんやりしていてマイペース。ごわついた髪で顔を隠した恥ずかしがりや。
誰もがそんな印象を持ったのに、到着した晩に催された歓迎会では快活で美しい青年に変貌していたので、みな仰天した。
私だって改めて支度をしたジェレミアを見たときは、そのあまりの美しさに僅かだが気後れしたほどだ。何しろごわごわの髪がさらさらの金髪に変わっていたのだ。
あの不恰好な髪は、顔を隠すためにわざわざ色々なものを混ぜて固めていたらしい。髪色を隠すための炭の粉末まで入れていたそうだ。
「僕は兄にそっくりらしい」とジェレミアは悲しげな顔をした。「もし彼とベレタが懸命に僕の素顔を隠し、間抜けに仕立て上げてくれていなかったら、きっと僕も義兄たちから酷い仕打ちを受けただろう」
そう話す彼の傍らに、トリスターノの姿はなかった。ジェレミアに尋ねると、彼はますます悲しげになった。
「兄は自分のような姿の者は公の場に出るべきではないと言うのだ」
身体のことだけでなく衣服も含めてだそうだ。トリスターノは着替えや動きが楽であるから、あのような服を着ているという。
それならばと人を介してトリスターノに、『私だって全身が模様まみれで顔を隠している。あなたの見た目など全く気にしない』とは伝えたけれど彼が会に出てくることはなかった。
ジェレミアの母も長い幽閉生活の影響で、大勢が集まるところは怖がるそうだ。だから彼はたったひとりで歓迎会に出たのだけれど、あっという間に我が王宮に馴染んでしまった。
驚く私にジェレミアは、市井で学んだコミュニケーション力があるからねとウインクをした。
――彼はきっと、顔を隠して生きてきたから自分の笑顔が年頃の娘に与える衝撃を知らないのだ。
◇◇
ジェレミアは、女王を亡くした私たちの気鬱を吹き飛ばした。
到着した翌日から精力的に国と政治、呪い対策について学び、かと思えば城中を歩き回って少しでも早く新しい住処に慣れようとした。
そんな活力に溢れた彼の姿に新しい希望を見出だすのは当然のこと。
彼が婿に来たのはきっと亡き女王が天から導いてくれたからだ、なんて説まで出るようになった。
「それなら僕は君の母君に最大限の感謝をしなければね」とジェレミア。「素晴らしい王だったそうだから是非お会いしたかったけれど」
その隣で大きくうなずくトリスターノ。
「兄を苛める下衆もここにはいない。僕たちにとっては楽園のような世界だ」
滅亡予定まで一年だというのに晴れ晴れとした顔で言い切るジェレミアに嘘はなさそうだ。
彼は平気で私の手も取る。
「普通、私に会ったばかりの人は私に触れたがらないのよ」
私がそう言うと、彼は
「普通って何だい?」
なんて質問を返して笑っていた。
「あなたみたいな人は初めてだわ」
「何しろ『普通』の王子ではなかったからね」
真顔で言って、また笑うジェレミア。
彼は自由が嬉しくてまだ浮かれているんだなんて言っているけど、きっと私の婿に来て浮かれる人なんて世界でジェレミア、ただひとりだけだろう。
◇◇
「国内から婿をとろうとは考えなかったのかい?」とジェレミアが尋ねた。
滅亡予定の我が国だけど、母のカリスマ性のおかげで優秀な人物が幾人も残っている。ただ、皆が顔見知りだ。そんな彼らに、呪われた姫の夫になるなんて重責を負わせたくなかった。それに――。
「自分勝手なの。見知らぬ人のほうが割りきって私と国を押し付けられるでしょう?」
「そうか、自分勝手か」
そう言ってジェレミアは何故か私の頭を撫でた。幼児にするみたいに。
「自分が死んだ後の国のために、会ったこともない異国の余り者王子を婿にもらう。大変な自分勝手だ」
「……褒めどころではないのよ。本当に私のワガママなの」
そうかいそうかいとジェレミアは笑顔で言うものだから、呪われている私は結婚のことを考え気が重くなる。
「実は僕も自分勝手だ」と笑顔を引っ込め、彼は言った。「父は横暴な王でね。批判する者気にくわない者は容赦なく粛清する。僕が庶民のふりをして親しくしていた中にも立場が危うい人が何人かいた。こちらで僕が王になったら取り立てるから、是非来てくれと勝手に約束してしまっているのだ」
「滅亡すると言われている国には来ないと思うわ」
「父の支配が続く限り、あちらでも生きられないから同じだよ。来てくれたら重鎮候補として採用していいかな」
「あなたのお墨付きなら大歓迎よ」
それからジェレミアは声をかけた人たちについて、実に楽しそうに話して聞かせてくれた。それからどうやって城を抜け出していたかや城下町で巻き込まれたトラブルとか。
彼のする話はとても面白い。
◇◇
トリスターノに彼が着ているものと同型の、だけど色合いと刺繍が美しい衣服を贈った。すると彼はこちらが思っていた以上に喜んでくれた。一緒に選んだジェレミアも嬉しそうで、
「僕の妻になる人が兄を厭わないでくれる人で良かった」と言った。「大抵の女性は彼を気味悪がるのだ」
「あら。顔を隠すことにかけては私のほうが先輩だと思うわ。トリスターノ様は何年かしら。私は十二年よ」
ぷっと吹き出す兄弟。
「引き分けだ。彼も十二年だ」
「あら、残念。ちなみに何月からかしら?」
「エウフェミアは負けず嫌いなんだ」
ケラケラと笑うジェレミア。
ふと、負けず嫌いの女は可愛げがないだろうかと考えた。子供の頃に読んだお伽噺のお姫様はみんな、控えめだった。
それから私は彼に可愛いと思われたいのだと気がついた。
顔も見せられないのに。
◇◇
余計なことかと躊躇いつつも、ジェレミアの母君ルイーザ様のことを口出しさせてもらった。
「現実を見たくない、幸せな世界にいたいという気持ちは分かるのよ」
ジェレミアとトリスターノは私の話に困惑しているようだった。
「だけど彼女の息子たちは素晴らしいの。姿は変わってしまったけれど優しくて弟思いのトリスターノ様に、行動力があって兄を大切にするジェレミア。それを知らないままというのは、大きな損失だと思う」
「……今の母はそれなりに幸せだよ。自由に好きなところに行けて、弟や馴染みの侍女も従僕もそばにいる」
「そうね。戯れ言だと思って聞き流してくれていいわ。ただ、私はそう思うというだけ。だって素敵な兄弟ですもの」
ふたりは顔を見合せると、視線だけで何やらやり取りをしているようだった。
◇◇
「君の呪いについて、鍵になると思われる書物のことだけど」
ジェレミアの問いにうなずく。
魔女組合の考えでは、私に呪いをかけた女性は恐らく魔女ではない。というのも彼女たちは定期的に集会を開くそうなのだがその女性を見たことがないからだそうだ。
一方で事件が起きた頃から、齢千年と噂されていた大魔女の姿が見えなくなったという。本人がそろそろ寿命だと話していたので恐らくは亡くなったのだろう。
この大魔女は他の魔女が知らない古い魔法を知っていたし、新しいものを作り上げることも得意だったという。
そしてそんな彼女の蔵書が、大魔女宅からごっそり失くなっているのだそうだ。
組合の推理では件の女性が、書物を譲り受けたか盗んだか。
とにかくそれがみつかれば、呪いを解けるのではないかと考えられている。
もちろん独自に解呪の研究もしている。
「あと一年で書物を見つけられる可能性は低いと思う。もう十年以上、探しているのだろう?」
そうなのだ。女性に関係する場所も流通しそうな経路も稀覯書コレクターも闇市場も調べつくしてしまった。
「それよりも魔女たちに呪いの発動を先送りにする魔法を考えてもらうのはどうだろう」とジェレミア。
「もう試したわ。ダメだった」
原因はどうやら魔法の強さではない。女性の怨念の強さが呪いを強固にしているようで、本物の魔女たちは手を焼いているのだ。
「それなら呪いを他人に移すのはどうだろう」
「移す?」
「そう。ちょっと可哀想だけど、赤ん坊に。そうしたら十八年の猶予ができる」
ジェレミアがそう言うと、控えていた侍女たちから歓声が上がった。
私は手袋に隠れた手を見る。他の人に呪いを移したら、この模様もその人が受け継ぐのだろう。
「よし。明日僕が国王に即位して最初にする仕事は、この研究を命じることだ」
ジェレミアはそう言って、私の手を握った。
◇◇
ジェレミアが王宮にやって来て五日目。彼と私は大聖堂で挙式した。その直後には彼の戴冠式も執り行った。聖堂の中は長年私と母を支えてきた人でいっぱいで、その中にはトリスターノと彼らの母ルイーザ、その侍女ベレタの姿もあった。
ルイーザは当初、何故幼い弟が結婚するのかと心配をしていたけれど、私がどうしても我が国には彼が必要でけっして不幸にはしないからと説得をしたら納得してくれたのだった。式の間は弟の晴れ姿に嬉しそうな顔をしていた。
全てを終えて聖堂の外に出ると群衆が待ち構えていて花を投げて祝ってくれた。
溢れる歓喜は明るい未来を信じてのもの。ジェレミアはその場で新国王としての所信表明を堂々として、歓声はますます高まったのだった。
◇◇
出会ってまだ一週間も経っていないのに、私とジェレミアは夫婦になった。
祝いの宴は盛り上がり誰もが新国王を歓迎する。
それに反比例するかのように私の気持ちは沈んでいき、唯一それを分かっている侍女のグウェンが時々手を握ってくれたり肩を抱いたりしてくれた。
何度か彼女は、
「やはり私がジェレミア様にお話しましょうか」
と尋ねてくれて、その度に私は首を横に振った。
そうしていよいよその時がやって来た。
初夜だ。
新国王用に調度品を一新した美しい部屋。入ったときから私の心臓はうるさく鳴っていたけれど、グウェンたちが下がりジェレミアと二人きりになると今にも爆発しそうな勢いだった。
お互いに夜着姿で所在なく部屋の真ん中に向かいあって立っている。なんて切り出そうか、沢山シミュレーションをしたのに思い出せない。結局最初に口をついたのは、
「安心してね」という言葉だった。
「『安心』?」と不思議そうに繰り返すジェレミア。
その美しい顔を見ていられなくて視線を反らした。どうせ私はヴェールをしているから、どこを見ているのかなんて分からない。
「あなたには王になってもらえれば、十分なの」
ジェレミアが
「どういうことかな」と一歩前に出る。
つられて二歩下がる私。
「その。呪われている私に触れるのは嫌でしょう?」
「いいや。手を握っているじゃないか」
また進むジェレミア。下がる私。
「手袋の上からね」
「君は何が言いたいのかな。まさか僕は初夜を拒まれるのかな」
「だって嫌でしょう。私の体には呪いの文様があるの」
まだ幼児だったときですら、私を見る人の目に畏怖があるのを感じとっていた。
親しい人ですらも、だ。だから物心がついて以来、素肌は母とグウェンにしかみせていない。
周りの中から結婚相手をみつけなかったのも、そのためだ。親しい友人が私に触れることを躊躇う姿を見たくなかった。呪われて二十年近く。ある意味呪われのエキスパートだけど私だって花も恥じらう乙女だし、傷つく。
そのためもあってわざわざ見知らぬ王子を選んだのに、私は彼を好きになってしまった。
「ひとつ、確認をしていいかな」
「何かしら」
「君の呪いの文様に触れると死ぬかい?」
「いいえ」
「だよね。グウェンは元気に生きている。では僕が触れても」ジェレミアは素晴らしい笑みを浮かべた。「何の問題もない」
「あるわ。とても忌まわしいものなのよ」
どんなに平気だとジェレミアが思っても、いざ目にしたら怯むかもしれない。そんな姿は見たくない。嫌われるのも、怖がられるのも嫌だ。
「僕がここに到着したとき」とジェレミアが距離を詰めてくる。「転んだ。まだ国の連中がいたから、いつもの間抜けな王子を演じたんだ。勿論、誰も手は貸さない。そこに君が来て手を差し出してくれた。『いらない第八王子』の僕に他人が優しくしてくれるのは初めてだった」
「あれは」
彼の国の人間は誰も動かず、うちの国の人間は対応に迷っていた。ならば私しかいないとそう思っただけだ。
「君にとって普通のことでも、僕は嬉しかった」
「……私はあなたが呪われた私の手を掴むとは思わなかった。ただの礼儀のつもりだったのよ」
「それから兄や母を厭わなかった」
ジェレミアがあんまり進んで来るので後ろに下がり続けていたら、ついに背中が壁にくっついた。
「僕がどれ程兄に感謝して大切に思っているか、言葉では言い表せないほどなんだ。その兄に君は礼を尽くしてくれている。性格も可愛いし。そんな君に惹かれないことがあると思うかい?」
「惹かれてくれたの? 私に?」
そんなことがあるだろうか。呪われているのに。
だけど「そうだよ」と答えるジェレミアの笑顔が何故か怒っているように見える。
「今夜を楽しみにしていたんだ。それなのに君は勝手に僕の気持ちを決めつけて拒むのか。傷ついた」
とジェレミアは体が触れそうな位置にまで迫る。
「とはいえ君の気持ちは分からないでもない。トリスターノも火傷のことで沢山辛い思いをしてきたからね」
彼が私の手を取る。
「エウフェミア。失礼するよ」
するりと手袋を取られる。黒い模様まみれの手が現れた。
「綺麗だ」
ジェレミアはそう言って、躊躇なく唇を押し当てた。
「っ!」
「これで僕はこれっぽっちも嫌だと思っていないと分かってくれたかな」
「あの。ええと」
思いもよらない展開に、頭がうまく回らない。呪いが解かれない限り私の方から申し出て、白い結婚の状態でいるつもりだったのだ。なのに……
「エウフェミア」
ジェレミアがヴェール越しに私の顎を掴んで自分の方を向かせた。
「君は僕をどう思っているか、聞かせてくれないかな」
にこにことしているのに、やはり目が怖い。
「この五日間、良い雰囲気だと思っていたのは僕だけ? 勘違いだった? 答えてくれないなら」
と彼は私の目を見たまま、手の甲に平にと口づけをする。
「ずっと続ける。さあ、言って。エウフェミア」
心臓が破裂しそう。
だけど。
「あなたが好きよ」
彼の目を見て、はっきりと言う。
ジェレミアはにっこりとして私のヴェールをめくった。
黒い呪い文様だらけの私の顔。口から心臓が飛び出る。緊張で吐きそうだ。
「ようやく君の顔を見られた」
笑顔を変えることなく彼はそう言って、キスをした。
《後編》一緒に
ジェレミアと結婚をしてふた月が過ぎた。
新国王としての彼は前国王の方針を踏襲しながらも新しい施策も提案し、大臣や国民たちからの評判は上々だ。
彼は宣言通りに呪いを他人に移す研究も始めさせ、更に呪いを引き受けてくれる赤子の募集も始めた。この報酬は赤子にもその家族にも破格のもので、更には国の英雄にもなれるとのこともあり、問い合わせが多いらしい。
「君はなにひとつ、罪悪感を覚える必要はない」と彼は笑顔で言う。「これは国を存続させるための王としての決断だからね」
存外に精神がタフらしい彼は、冷徹に思える決断も軽やかにしてしまう。私が即位していたならば、この厄介な呪いを他人に移すなんて方法を考えることはなかっただろう。
「でも、私情も入っている。秘密だけど」
そう言って彼は私を抱き寄せ額にキスを落とした。ヴェール越しではあったけど。周りにグウェンやトリスターノがいたから。ジェレミアは人目を憚らずにイチャイチャしてくる。おかげですっかり、おしどり夫婦扱いだ。
グウェンなんて、
「姫様がこんなに幸せな結婚生活を送れるとは」としょっちゅう嬉し泣きをしている。
それは私が一番驚いていることなのに。
そうして更に驚くことに、ジェレミアの母国リューゲから本当に彼を頼った人たちが来た。政治学者や元大臣に老騎士。国にいても遅かれ早かれ、良くて投獄悪くて拷問のち死刑だからだそうだ。
その中のひとり、老騎士が途中の村で拾ったという少女を連れていた。
ノアと名乗る彼女は現在は魔法は使えないけれど、かつて私に呪いを掛けた女性の生まれ変わりなのだと主張した。
女性は自分の死は覚悟をしていて、死後の世界で苦悶するろくでなし男を見て楽しむつもりだったという。ところがカッサーノはあっさり殺されてしまった。
すると女性は急激に後悔したそうだ。自分が復讐したいのはカッサーノであり無垢な赤子でも国民にでもない。こんな展開は予想外で、呪いを解く方法が失くなるとは微塵も考えていなかった。
彼女の魂はもう一度人に生まれ、自分の仕出かしたことの後始末をつけることを神に願った。
願いに願い続け、そしてノアとして生まれた――。
彼女は女性の生まれ変わりの証拠だと、私に呪いを掛けたときのことを詳細に語った。それは事件を知る者を驚かせるほど正確で、地方に住む12歳の子供が知っていることとは考えられないとのことだった。
ノアはあの女性の生まれ変わり。
それは事実のようらしい。
更に彼女は、今際の際の大魔女から魔術書と魔女の才を譲り受けたこと、書物はとある廃墟に隠してあることも語った。
その場所は都からだいぶ遠かったので捜索隊が結成され、何故か国王名代としてトリスターノも加わった。
「兄も、君のために何かしたいというのだ」とジェレミア。
そんな話をしたのは、プライベートの時間だった。とはいえ近くには侍女や侍従がいるのに、彼はおかまいなしに私を膝の上に乗せてキスの雨を降らせる。
「自分と僕を大切にしてくれる恩返しなんだって」
「どう考えても私のほうが幸せになっていると思うの。恩返しをしなければならないのは、私だわ」
私にはまだ恥じらいがちゃんとあるので、こっそりと囁いた。
「恥ずかしがるエウフェミアは可愛いなあ。そう思うだろ?」
ジェレミアは周りの侍従たちに問いかける。彼らの困惑も何のそのなのだ。
「可愛い妻は、僕が全力で守るからね」
◇◇
それから間もなくして、王族の墓がある大聖堂の司教がやって来て、父カッサーノの墓が荒らされたと告げた。ろくでなしのそれは隅に目立たなくあって、墓守りたちもあまり気に掛けていなかったらしい。いつ荒らされたのかも分からないという。
荒らすも何も、副葬品は入れておらず盗るものなどないはずだと侍従長が言えば司教は、遺体が盗まれたのだと答えた。
「そんなものをどうするのかしら」
「バレてしまったら仕方ない」
そう言ったのは、ジェレミアだった。
「あなたが盗んだの!?」
そう、と悪びれもなくうなずく私の夫。
「カッサーノを甦らせてみようと思い、魔女組合にやらせている。君には内緒にしておくつもりだった」
「どうしてそんなことを!」と叫ぶ司教。「神の摂理に反している」
するといつも柔らかい表情のジェレミアが真顔になった。
「摂理よりも国とエウフェミアを救うことのほうが重要だ。元々、正しく呪いを解くにはカッサーノが必要だった。だから彼には生き返ってもらう」
黙る司教。
生き返る。ろくでなしの父が……。
「すまないね、エウフェミア」ジェレミアが私を見る。目には悲しみがあるようだ。「僕は手段は選ばない。正義や道徳よりも自分と愛する人たちの存在のほうが大事だ。嫌いになったかい?」
彼の手が伸びてきてヴェールの隙間から入り込み、頬を撫でる。優しい手つき。
「責任も非難もすべて僕が背負うよ」
「いいえ。私だって愛する人が大切よ。幸福も悲しみも重荷も責任も、ふたりで分かち合うの。婚礼のときにそう誓ったわ」
ジェレミアはにこりとして、司教に「失礼」と一言断りを入れると、ヴェールの上からキスをしてくれたのだった。
◇◇
数週間後、ノアが何十冊もの魔術書と共に帰ってきた。
これで呪いが解けることが実現味を帯びてきた。誰も彼もが浮き足だっている。
ついでにノアとトリスターノはすっかり仲良しになったようだ。トリスターノ曰く、可愛い妹ができて嬉しいらしい。何しろ愛しの弟が妻にべったりになってしまい兄離れをしてしまったからだ。
ノアも早くに両親を亡くし親戚をたらい回しにされていたらしいのだが、どこに行ってもおかしなことばかり言う気味が悪い子と疎まれていたのだそうだ。老騎士に出会ったときは、最後の親戚にも捨てられて、なんとかして私に会わなければならないとひとりで旅を始めて餓死しかけていたところだったそうだ。
だからなのか、なにくれとなく世話を焼いてくれるトリスターノが大好きらしい。
弟の従者を辞めたトリスターノは、今ではまるでノアの兄のようだ。
そんなある晩寝室で、いつも通りに私を膝の上に乗せたジェレミアが深刻な顔をして悩んでいると打ち明けてきた。
「一体どうしたの。悩みなんて初めて聞くわ」
「非常に困っている」ジェレミアはそう言いながらも私の模様まみれの頬にキスをした。
「呪いが消えたら、君のこの模様も消える」
……まさかこれが好きだから惜しいと言い出すのだろうか。
彼と出会って数ヶ月。ジェレミアが一般的な青年とはだいぶ違っているのはすでに深く理解した。だがもしや、性癖も普通ではなかったのだろうか。
「消えたら君はヴェールをやめるよね」
「そうね。楽しみ」
だけど深いため息をつくジェレミア。
「そうしたら君の美貌を皆が見る!」
どういうことだろう。
「僕の可愛い君を見せびらかしたい。だけど他の男どもが君をそういう目で見るのかと考えると嫉妬で腸が煮えくり返る。どうすればいいんだ」
……ええと?
「男どもを城から一掃してしまう?」
「ジェ、ジェレミア?」
「だけど長年に渡りエウフェミアに貢献してきた忠臣たちだ」
ほっと胸を撫で下ろす。
「奴らの目を潰す?」
「ジェレミア!」
「魔女組合に、エウフェミアの顔だけ判別できないような呪いをかけてもらうのもいい」
「ジェレミア。冗談にしては物騒すぎるわ」
すると私の夫は、子犬のような顔をむけた。
「エウフェミア。僕は本気なのだ」
「……私たちの婚約をまとめてきた大使はね、あなたのことを『いささか残念な王子』と評したの。実際はそんなことはなくて最高に優秀で頼もしい王子だったわ。しかも幸運ももたらす福の神」
そうかいと照れるジェレミア。可愛い。
「だけどやっぱり『いささか残念』も正解だわ。そんなことで悩む王はきっと、世界であなただけよ。男の人たちに変なことをしたら、嫌いになってしまうから」
「それは困る」
とたんにジェレミアは私のいたるところにキスをし始める。
私は思いきってその背に腕を回して、抱きついた。
「私が好きなのはジェレミアだけよ。よそ見なんてしないから心配しないで。もし私を好意的に思ってくれる人がいても粛清してはだめよ。あなたのお父様といっしょになってしまう」
「……そうか。ならば僕は寛大にならなければいけないのか」
「そうよ」
「努力する。だから約束だよ。君は僕だけ。僕も君だけ」
「私はあなただけ。あなたは私だけ。約束ね」
◇◇
それから更にひと月。
残念ながら解呪は成功していない。
ノアは組合の魔女たちと契約をしてその力を授かった。そうやって魔女になるのだそうだ。これで呪いが解ける……かと思いきや、ノアと件の女性が別の人間だからなのか、契約した魔女が違うからなのか、うまくいかなかった。
一方で父の甦りは成功した。私は会っていないけど、どうやら生前そのままの性格で復活を遂げたらしい。トリスターノをはじめ、並みいる大臣魔女ノアたちの説得にも耳を貸さずに処置を完全に拒否。あげくに魔女を口説く始末。
これはダメだと父は術を解かれて骨に戻ったそうだ。
となるとジェレミアが最初に提案した、呪いを他人に移す方法が最良だ。今はその研究に取り組んでいる。
期限まで約半年。幸い、国におかしな兆候は出ていない。のんびりはできないけれど、まだ猶予はある。
そんなある日の夕方のこと。
ノアとトリスターノが私のもとにやって来た。内密の話がしたいという。
人払いをして私のほかは侍女のグウェンだけになるとノアとは、
「実はあなたの呪いをとく新しい呪文が完成しています。多分成功するでしょう」
と言った。だけどその顔は陰り、隣に立つトリスターノの手を不安そうに握りしめている。
「何か問題があるのね?」
うなずくノア。
「秘密を漏らしたら極刑と陛下に言われています」
「ジェレミアがそんなことを?」
「ええ。彼は激しい性格みたいですね」
トリスターノがうなずく。
「呪文も手順も簡単です。ただし必要なものがあります」とノア。「あなたを真に愛する人の心臓です」
血の気が引く音が聞こえた気がした。
「陛下は今夜実行するつもりです。知っているのは魔女組合と、私が先ほど打ち明けたトリスターノ様だけ」
ノアが言い終わるのを待てずに走り出した。今の時間、ジェレミアは執政室にいるはずだ。
廊下を疾走する私に皆が声をかけてくるけれど、答えるどころではない。
部屋に飛び込むと、机に座って書類仕事をしていたジェレミアが驚きの顔で瞬いた。それからいつもと変わらない笑顔になって、
「どうしたんだい」と尋ねる。
「幸福も悲しみも重荷も責任も、ふたりで分かち合うと誓ったわよね!」
ジェレミアの顔から笑みが消えた。
「今夜の件は中止よ、ジェレミア。心臓なんて提供したら、あなたを絶対に許さない」
大臣や従者たちが戸惑いの声を上げて王と私を見比べる。
「だけど君に生きてほしい。僕で君を救えるのなら、喜んでこの体を差し出す」
ジェレミアは力強く断言した。
「バカじゃないの!あなたはお母様の悲しみをそばで見てきたのに、私に同じ思いをさせるの?まだ半年もあるのに、何をつまらない決断をしようとしているのよ」
「だが君は呪いを赤子に移すのは、本当は嫌だろう?」
ジェレミアは立ち上がると机を回って私のもとに来た。手をとり、手袋越しに撫で回す。
「エウフェミアは呪いよりも、この文様の苦しみを他人に与えたくない」とジェレミア。「だけど今のところ有効な手立ては他に見つかっていない。二択なら僕を使ったほうがいい」
「バカね。どちらも同じくらい嫌よ。まだ半年あるのだから早まらないで」
「まさか陛下はご自身を犠牲にしようとしているので?」
大臣のひとりが尋ねる。
「そうよ」
「ではそれは最終手段にしましょう。最後のひと月になっても呪いが解けなかった場合に実行を」と大臣。「陛下はもう国民に大変な人気がありますからね。あなたを失うのは、政略的に良くありません」
「ほら。周りも反対しているわ」
ジェレミアがくしゃりと顔を歪めた。初めて見る表情だ。その頬に触れようとしたら、抱きしめられた。
「君を失うことが怖い。こんな気持ちは初めてなんだ。どうすればいいか分からない」
いつも前向きな彼が、初めて見せた弱気だった。
◇◇
ノアと魔女組合はあらゆる試みをし、幾つもの解呪方法を考案してくれた。だがどれもうまくいかず、そんな中で大魔女の古い書物からみつかったのが、呪われた本人が自分の力でそれを解く方法だった。
もちろん簡単なものではない。失敗をすれば私は死ぬ。魔女が魔力を込めた火掻き棒を使って自分で魔方陣を書き、呪文を唱えるそうだ。全て覚えてソラでやらなければならない。魔方陣の書く順番ひとつ、呪文の一句でも間違えたらおしまいだそうだ。
この話にジェレミアは渋い顔をした。私を危険に晒すより、自分が犠牲になるほうがいいと言うのだ。私はそれをそっくりそのまま言い返した。
「ねえ、ジェレミア」
定番の彼の膝の上。近頃の彼は時間があれば私を乗せて抱きしめる。きっと不安からなのだと思う。
「あなたに初めて会ったとき、私は『間に合わないかもしれないけれど、国だけは救いたい』と話したと思うの」
「……そうだね。覚えているよ」彼は私の首筋に顔をうずめる。
「私は物心がつく前から呪われていたでしょう。だから死ぬことは嫌でも覚悟は決まっていたのよ」
「……うん」
頼りない声を出す愛しい人の髪を撫でる。
「だけどあなたに会って覚悟はなくなってしまったわ。ずっと一緒にいたいの」
ジェレミアが顔を上げた。
「僕だって」
「私は自分の望みを叶えるために解呪に挑むわ。絶対に失敗しない」
「エウフェミア」ジェレミアが泣きそうな顔をしている。
「そんな顔をしないで。あなたといつまでも二人でいるためにやるの。あなたの存在が私を強くしてくれる。私のもとに婿に来てくれて、ありがとう」
「僕こそ。選んでもらえて幸せだ」
決して失敗をしないよう、私は時間をかけて魔方陣と呪文を完璧に覚える努力をした。どちらも普通の人間には縁のないもので、書物を見ながらですら間違えてしまうような代物だった。
だけどジェレミアの存在が励みとなり、私は必死に習得に励んだ。
解呪の儀式には、その最中に呪いが解けることを心の底から望む人の思い千人分が必要で、ジェレミアはお触れを出して国民に協力を要請した。
これで失敗をすれば私は死ぬ。
死んだときに国に何が起きるかは分からないけど、できうる限りの対策はとってある。ジェレミアと精鋭大臣たちがいるから心配はないはず。
私は必死に入念な準備を続けた。
傍らにはいつもジェレミアがいて、私の手を握りしめてくれていた。
そうして期限まで残り三ヶ月という日に儀式を決行することになった。ジェレミアが王宮にやって来た日のように、空を重い雲が覆っていた。雨に降られるとまずいので、行うのは城の広間だ。
「妃殿下。窓の外をご覧下さい」
大臣に言われて近寄ると、雨が降りそうだというのに庭に大勢の人が集まっていた。城の人間もいれば、市井の庶民もいる。
「亡き女王陛下と現国王陛下の善政の賜物です」と大臣。
私は窓を開けると、頭を深く下げて礼をした。父がろくでなしだったせいで、国民にいらぬ不安を与えた十八年だった。これが私ができる最後の謝罪と感謝になるかもしれない。
隣にジェレミアが立つ気配がした。彼が私の手を握る。彼の手はいつでも力強くて私の支えとなってくれる。
群衆から拍手が起こり、やがて怒濤のような音になり城を包んだのだった。
広間でジェレミアとグウェンに見守られ、十二人の魔女に囲まれて解呪の儀式に挑む。
絶対にやり遂げてジェレミアと共に生きるのだ。その思いを胸に頭と体に叩きこんだ手順をこなす。火掻き棒で床に傷をつくり魔方陣を描く。本来の用途でないそれを使っての線描は、集中しないと間違えてしまいそうだった。それに加えて呪文の詠唱。何百何千回と練習をしたけれど、緊張で口内が乾き、うまく言えていないのではという不安に襲われた。
それでも、全てを終えることができた時。
炎で焼かれるような激しい痛みに襲われ、その場にくずおれた。まさか失敗したのかと絶望したのはわずかな間だけだった。
痛みは直ぐに引いた。
駆け寄ってきたジェレミアに抱き起こされる。
不安げに私を見る彼。私はそっと手袋をめくった。それから乱暴に脱ぎ捨てる。
素肌の手には何もなかった。
呪いの文様はきれいさっぱり消えていた。
ジェレミアがヴェールをめくる。
「ああ!」
彼はそう叫んで私を抱きしめた。グウェンも良かったと叫んで腰を抜かしている。
魔女の代表がやって来た。笑顔だ。
「おめでとうございます。成功です」
◇◇
私に掛けられた呪いは解かれた。国も安泰だ。
ジェレミアは大喜びで、儀式を行った日を『感謝の日』として国民に祝い酒と菓子を振る舞う祝日と定めた。
誰もが喜び、城の廊下や広間で舞い上がった大臣や侍女が踊る中、ひとり深刻な顔をしたノアがやって来て、全て終わったから自分を処刑してほしいと言い出した。前世での罪を償うと言うのだ。
そんなことを言われてもノアと件の女性は別人だ。大体、ノアがいなくなったらトリスターノが泣く。
「それならば魔女には魔女のやり方で、罪を背負ってもらおう」そう言ったのはジェレミアだった。
それから数日後。私たちの寝室に、朝一番で駆け込んできた青年がいた。ジェレミアによく似ている。
トリスターノだった。
彼は起きたら全ての不具合が治っていた、何が起きたのか分からないと話した。
「僕がノアに依頼したんだ。すごいな。怪我も火傷も完治している」
にこにこと話すジェレミア。
どこか引っ掛かりを感じ、トリスターノが帰ってからジェレミアを問い詰めると、彼の不具合は治ったのではなく移してもらったのだと白状した。
「誰に?」
「もちろん彼に怪我と火傷を負わせた義兄たちにだ」やはりにこにことしているジェレミア。「すまないね、エウフェミア。冷酷な僕に落胆したかい?」
彼はそう言いながら、私の手に額にとキスを落とす。
「まだまだあなたは知らない面を持っているのかしら」
「エウフェミアが探してくれるかな。時間ならば沢山ある」
そうして私の愛しい人は、君といられて幸せだなぁと呟く。
「あら、私も幸せよ」
「いいや、僕のほうがずっと幸せだ」
よいしょと彼は私を膝の上に乗せた。
「今日の公務は休みにしよう。エウフェミアを堪能する必要がある」
「毎日そう言っているわ。飽きないの?」
「飽きないさ。文様のあった君も美しかったけど、ない君も美しい」
扉をノックする音がした。
「ほら、起きる時間よ」
ジェレミアは
「あと半時間後に来てくれ!」
と廊下に向かって叫ぶ。
「一緒にいられる幸福を、ふたりで分かち合わないとね」
そう言って、些か残念な国王は今日も『寝坊』をするつもりなのだ。
もっとも私もやぶさかではない……。
◇◇
ジェレミアたちが我が国に来て一年が過ぎたころ、彼らの母国リューゲでは革命が起きた。あちらから来た学者の話では、革命軍の中心は、ジェレミアが庶民のふりをして親しくしていた人たちだったとか。
事実かどうかは、分からない。
それからトリスターノは妹のように思っていたノア
に迫られている。四年ほど待ってくれれば結婚相手にちょうど良い年頃よなんてアピールされているらしい。
彼は『年の差が』なんてぶつくさ言いながらも満更ではなさそうだ。
兄弟の母君は時々、自分にはふたりの息子がいると思い出すようになった。一瞬でしかないしあれこれ錯綜はしているけれど、兄弟は喜んでいる。
ヴェールを必要としなくなった私の世界は明るくて、となりには素晴らしいジェレミアがいて。
彼に巡り会うために呪われたのだろうかなんて考えてしまうほど、私は幸せになったのだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
