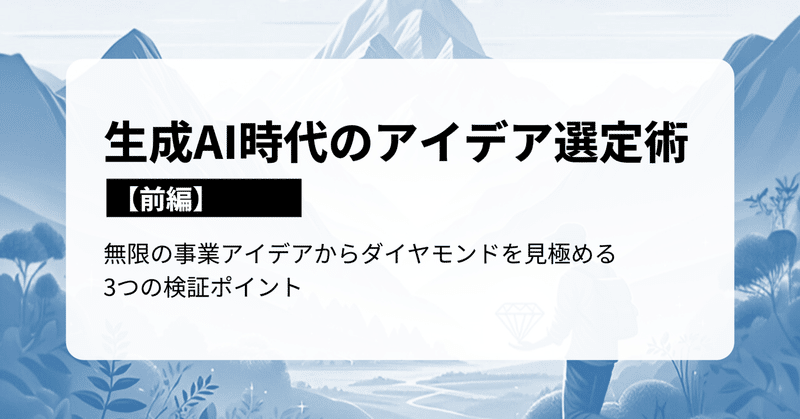
【前編】生成AI時代のアイデア選定術: 無限の事業アイデアからダイヤモンドを見極める3つの検証ポイント
この記事は、Sun* Advent Calendar 2023 22日目の記事です。
生成AIが瞬く間にビジネスにおいて浸透し始め、新規事業開発においても様々なタスクに活用することができるようになりました。
この記事では、新規事業開発に関わる方、特に生成AIを活用したアイデア発想に取り組もうとされている方に、あえて「アイデアの発散」ではなく、その先の、人間の力が試される「アイデアの選定」について、成功率を上げるためのポイントをお伝えします。
新規事業創造を加速させる生成AI
生成AIによって、経営の意思決定から日々のオペレーション実行まで、あらゆるレイヤーで企業経営の在り方が変容し始めていることはもはや言うに及びません。新規事業の創造プロセスにおいても同様に生成AIが活用され始め、日進月歩でその手法がアップデートされています。
特に、事業機会の探索や、顧客課題に対するアイデアの発散においては、生成AIは人間よりも圧倒的な速度で、網羅的かつ大量に思考することができます。例えば、自社の保有アセットや、ターゲット顧客情報、中長期のビジョンやパーパス、着目しているマクロトレンドなどを投入すると、複数の材料を総当たりで組み合わせ、そのうち有望そうな事業アイデアをリストアップさせることができます。
人間によるブレストでは1週間~1か月かけて100案かかっていたところを、生成AIにエンパワーメントされたアプローチでは、1日に数千のアイデアをリストアップすることができるようになりました。今後、音声の識別・発話や、ホワイトボードや付箋の画像認識の精度があがれば、アイデアを考える際には当たり前にAIを同席させる未来が遠くないうちに訪れるでしょう。
アイデアの目利きが新たな課題
しかし、生成AIを活用したアイデア生成を試行する企業が増えるにつれ、新たな課題が発現するようになりました。それは「あまりにも大量なアイデアから、本当に成功するアイデアを選び抜くことができない」という課題です。
アイデアの選択肢が多くなるほど、眺めるだけでも時間がかかり、検討の間もなくそれらしい理由をつけながら個人の感覚で選定してしまうケースがよくあります。しかし、いくら量が質を高めるとはいえ、そもそも確度の低いアイデアを選んでは大量発散した意味がありません。
生成AIが生み出す玉石混交のアイデアの山から、いかに短時間で確度高く成功するアイデアを選定・検証していけるかが、次の競争優位性の源泉となるといえるでしょう。

何がアイデアの見極めを難しくさせているのか?
これまではアイデア発散の段階である程度、根拠付けされながら、アイデアがブラッシュアップされてきました。しかし、現在ではAIが一瞬で出したアイデアを眺めるのみで、人間の手をあまり加えず、時間と資金を投入する対象をごく少数に絞り込んでしまっているケースが増えています。
生成アイデアのよくある選定・検証プロセス
・選定:直感/簡易評価でいきなり少数に絞って(1,000案→2~3案)
・検証:長時間かけて(3か月~) × 高確度の検証(詳細な調査・検討)
→根拠が薄い分、検討を進めてよいか不安な時間が長引く
AIに思考を委ねたからこそ、途中経過がすっとばされ、人間が信じるに値する裏付けや検証が不足すること、これが見極めを困難にしているのです。検証対象のアイデア数が増えないボトルネックは、やはり人間側がじっくり考える、または検証するための、所要時間の長さにあるといえます。
では、アイデア発散の量に、選定の質をバランスさせ、腹落ちした状態で具体的なビジネスデザインに移るためには何が必要でしょうか?それは裏を返すと、完全に絞り込む前に、最低限かつ重要なポイントだけを抑えた検証を、短時間で可能な限り多くのアイデアに対して実行することにあります。
量と質をバランスさせた選定・検証プロセス
・選定:絞りきらず(1,000案→20~30案)
・検証:短時間(半日程度)× 中確度の検証(最低限の裏付け)
+再度クイックに選定し、時間を掛けて検証するアイデアを選ぶ
→最低限の裏付けを持つことで、ビジネスの具体化に時間を掛けられる
この短時間で出される「最低限の裏付け」が、一定期間、船のアンカー(錨)のようにチームがリソースを投入する理由の拠り所となります。
それでは、この最低限の裏付けとは何で、どのようにして得ることができるでしょうか?検証ポイントを明らかにする前に、まずは前提となる2つの原則についてご説明します。
「制限時間内で」「手持ちの材料で」確かめる
大量のアイデアを検証する上で極めて重要なことは、各検証ステップに1案当たりの制限時間を設け、厳格に守ることです。
新規事業のよくある失敗として、筋の悪いアイデアに時間を掛けすぎて、引き返せなくなってしまうことが挙げられます。このフェーズでは「詳細なビジネスデザインの磨き上げ」が目的ではなく、「筋のいいアイデアを見極める」ことにあります。時間制限こそが、アイデア発散だけでなく、アイデア検証の原動力にもなるのです。
また、仲間にできる人材、使えるツール、アクセスできる情報、インタビューできる潜在顧客も限定されていることがほとんどです。重要なことのもうひとつは、いま使えるモノ、分かるコト、協力してくれるヒトの範囲内だけで判断することにあります。
制限時間内で情報が集められない、検証できないアイデアは、思いきって切り捨てなければ時間が足りなくなります。「情報を集めたら、実は光るアイデアになるのではないか」という不安に駆られますが、アイデアは生み出されたときに8割方できあがっており、初期に見込みがなければ別のアイデアにさっさと移ることが重要です。
これらは、優れた起業家の思考・行動パターンを体系化した、エフェクチュエーションの5原則のうち「手中の鳥の原則」「許容可能な損失の原則」に則した考え方ともいえます。

確度を高める3つの検証ポイント
それでは、前述の原則を踏まえたうえで、アイデアの初期段階で検証すべき3つポイントについて、具体的な検証手法とともにご説明します。この3つの検証ポイントとは、「n1顧客の実在性」「十分な市場性」「コンセプトの真新しさと優位性」です。

「n1顧客の実在性」では、少なくとも1人の顧客に深く刺さり、利用してくれるユーザーが存在していることの検証をします。「十分な市場性」は、n1顧客を積み上げたときに十分売上が立つ市場を相手にしているかを検証します。最後に、「コンセプトの真新しさと優位性」では競合と比較しながら、自社が勝ち続けられるポジションを取れる可能性があるかを確認します。
「n1顧客の実在性」「十分な市場性」はコンセプトが市場に受け入れられるかを検証するものに対し、「コンセプトの真新しさと優位性」は持続的に拡大するための競争戦略を確認するものです。
もちろん、他にも収益モデルや自社・他社リソースの活用、コミュニケーションチャネルの検討など様々なビジネスモデルの各要素の検討は必要ですが、これらはコンセプトや競争優位性を支える要素のため、アイデアを絞ったあとに検討すべきものとして、後続フェーズで設計します。
なお、これらの考え方は、Sun*、NEWhが開発した、迅速かつ網羅的なビジネスデザインを検討・検証するためのフレームワーク「Value Design Syntax」に当てはめると、「ミクロ」「マクロ」「競争優位性」の3列をクイックに検証することともいえます。

今回の記事では、まずは3つの検証ポイントのうち、「n1顧客の実在性」「十分な市場性」について実践的な手法を解説します。
検証ポイント1 「n1顧客の実在性」
想定する顧客が1人、確実にこの世に存在することを確認します。コンセプトを文章とビジュアルに落とし込む「可視化」と、ユーザーからフィードバックをもらう「検証」の2ステップで確かめます。
可視化
コンセプトシートを、イメージ図と2~3行の簡単な説明のみのせた1枚で、90分以内でできる範囲で作成します。イメージ図は生成AIでも作成できますし、デザイナー1名がビジュアルのモックアップを作成するもよし、素人の簡単な紙とペンでのスケッチでも問題ありません。
2023年12月現在では、ChatGPTでも画像生成できますし、midjourneyではディテールの修正が容易にできます。インタビューシート用の画像生成に適したプロンプト(命令文)を用意しておけば、ChatGPTのアイデア案+プロンプトのテンプレだけで、クイックにビジュアル化することができます。

検証
30分以内に始められるインタビューツール(例えばsprintなど)を使用します。対象セグメントにフィルタリングを掛け、課題とソリューションが3〜5人以内のインタビューで浮かび上がるかどうかを確認します。フィルタリングにひっかかからない、インタビューで1人も受容しない場合はアイデアを放棄します。
検証事項は2つあります。「課題の実在性」「課題と解決策のフィット」です。切迫性が高く、未充足の課題が実在しているのであれば、解決策を変えればよいので、見込みはあるといえます。想定していた課題や、その周辺にも課題が存在していない場合は、それ以上掘ってはいけない事業機会といえます。

なお、もちろん、インタビューツールでは、想定セグメントで顧客が見つからないケースもあります。インタビューツールを使わなくとも周囲の人々や、既存サービス内でのコミュニケーション、BtoBであれば問い合わせや、取引先との会話などで検証できるのならばそれでも問題ありません。ニッチセグメントなら資金を掛けてビザスクやビザスクnowなどもありうるかもしれません。
いかに手持ちのカードを使って、効果的で効率的(いわゆる”セクシー”)に検証できるかが腕の見せ所ともいえます。
初期に実在する顧客の声を残せて置けることは、チームにとっても、決裁者にとっても強烈な力を発揮します。
検証ポイント2 「十分な市場性」
次に、売上規模が見込める市場かどうかを評価します。これも1アイデア90分以内に調査と計算を行います。市場規模は人数ベースまたは金額ベースで評価します。(難しければ簡易的に算出しやすい人数ベースでも問題ありません。金額ベースに揃えたい場合は、人数さえ出せれば、おおよその想定単価を掛ければある程度金額ベースに合わせられます。)
調査
まずはGoogle検索で探します。言わずもがな、仮説をもって調査することが重要で「仕事中に眠い人の人口」「寝不足の人口」「睡眠時間が6時間以内の人口」と頭の中で知りたい情報は可能な限り具体化しておきましょう
G”ooooo”gleくらいまでの範囲で情報を集めます。(現在のUIではいつのまにか”o”の数でヒット数を表現していませんので)5スクロール以内で探すイメージです。
視覚からのインプットが得意な方は、画像の検索結果をスクロールしているとピンとくる情報に出会い易いかもしれません。
推定
得られた情報から、フェルミ推定を用いながら、ざっくり概算します。フェルミ推定は難解なイメージがありますが、短期間で見積もるためには、どうしても必要なスキルになります。ただ、ここでは正確な値が出せることが重要ではなく、「数値は間違っているかもしれないが、アイデア間で優劣をつけるための概算ができる」ことが重要なのです。
市場の正確な定義や、詳細な計算式設計は置いておいて、とにかく市場が小さくなく、規模が大きく成り得ることを確認します。詳細な算定は後続フェーズで行いましょう。なお、新規事業に求められる売上規模・市場規模があるのならば、このタイミングで加味できると尚良いです。

* * *
早期に競争優位性の見込みをつけるには?
今回は、大量のアイデアの中から確度の高いアイデアを見出すための、3つのポイントのうち、「n1顧客の実在性」「十分な市場性」の2つの具体的な検証ステップを紹介しました。
次回は、残る1つ、「コンセプトの真新しさと優位性」の具体的な検討手法をご説明します。このステップでは単にアイデアを確かめるのではなく、競合と比較しながら競争優位を取れるポジションを発散・収束サイクルの中で見つけ出す必要があります。ここでも、時間制限を設け、精緻な検討をするのではなく、競争優位が取れる可能性があるのかを確認していきます。
今回ご紹介しているアプローチを採用することで、確信と確証を持って、時間をかけすぎる前に、成功するアイデアを選び出すことが可能です。新しいアイデアが次々と湧き出る競争の激しい環境で、効果的なアイデアの目利きが成功の鍵となります。
次回の記事もぜひお楽しみにしてください。
本シリーズの記事はこちら▼
執筆者
渡邊 敦孔 Business Designer / Sun*
消費財、製薬、飲料、鉄道、商社、電力、エンタメ、行政など幅広い業界でビジネスデザインを支援。デザインリサーチから収支計画まで幅広くカバー。
【経歴】大手コンサルティングファームにて、企業統合、データドリブン経営、DXなどの戦略立案から、業務改革・システム導入まで数多くの企業改革に従事。スペキュラティブデザインや事業機会探索サービスを開発・提供。Sun*に参画後、デザイナーやエンジニアと組みながら、事業機会探索、ビジネスデザインを支援。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
