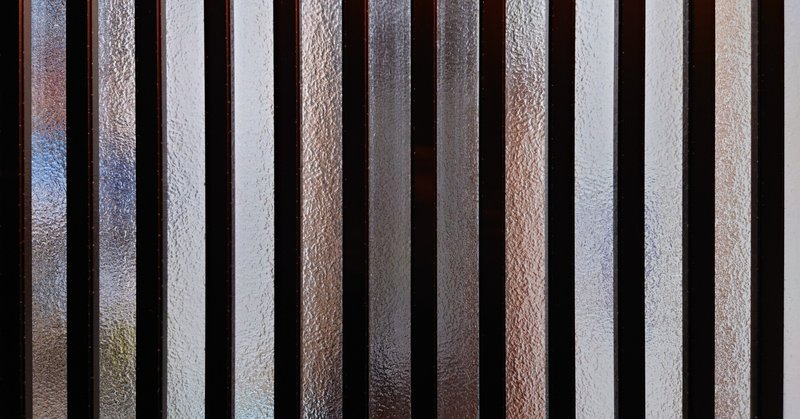
「まあ、ゆっくりしてけや」──隣人の家に招かれて
年末のとある日
「今晩は何や〜?」
隣人のKさんに尋ねられる。
「今晩はみんな出かけてぼくひとりなんでごはんと味噌汁にしようかなあと思ってます」
「そんならカツやるわ」
おれの住んでいるシェアハウスでは、煙草は玄関前で吸うことになっている。吸っていると、よく隣人のKさんと顔を合わせることがあって、しばしば他愛もない話を交わす。今晩はシェアメイトがみんな出払うことになっている。それで、ひとりで晩ごはんを食べる予定だと伝えたら、家に招いてくれたのだ。
Kさんはもう齢70を超えているであろうおじいさんである。シェアハウスのメンバーをいつも気にかけてくれていて、たまにかき餅をくれる(そしてこれがまたおいしい)。Kさんとは玄関先で話すことはあれど、おれが家に招かれるのは初めてだった。
「まあ、ゆっくりしてけや」
お言葉に甘えて着席する。インスタントコーヒーもいただく。砂糖はなしでいいですよ、と言っても、入れることを勧めてくれるので、それならば、と砂糖もたくさん入れる。自分好みの味でコーヒーを飲むということよりも、こうしてもてなされ、お節介を焼いてくれることこそがうれしいのである。「クリープも入れるか〜?」「ありがとうございます、入れます」
そのほかにも、埼玉の老舗のせんべいをいただいては、1個400円という高級みかんをご馳走になり、おれはすっかりくつろいでしまう。とそこへ一言、「タッパー持ってこい。」
今度は何かと思ったら、大和芋のとろろやら、韓国から送ってもらったというキムチの素をお裾分けしてくれると言う。大和芋のとろろは長芋のそれよりも粘りが強く、ひっくり返しても皿にくっつくのだとか。
「ほんまや、めっちゃねばねばですね」
「これにあおさを入れるとうまいんや」
そういって粉末状のあおさを混ぜてタッパーに入れてくれる。
「このキムチの素はな、スーパーで浅漬け買ってきてそれを混ぜたらうまいねん」
Kさんは何から何まで晩ごはんの面倒を見てくれる。結局いただいたのは、トンカツとサラダに、とろろとキムチの素、そして米も三合いただいて、一回では持ちきれない量だ。多謝。深謝。「Kさんは苦手なものとかありますか?」と尋ねたら「なんでも好きやで」との返答。今度手製のチリコンカンでも差し入れようか。
寛ぐということ
近所付き合いが減っているというのはよく耳にすることだし、耳にしなくとも、体感的にそういう時勢なのだということは感じられる。個人主義的風潮は拡がっているし、核家族化も進行している。そこにCOVID-19が重なって、それ以降さらに他者と接することに過敏になっている。個人向けのマンションならば、近所のひととのディスコミュニケーションはいっそう強いのだろう。おれが住んでいるシェアハウスは一軒家なので、なんとなくご近所さんの気配のようなものを感じることができるが、セルに住んでいればそうはいかないはずだ。両隣の家の音は聞こえるかもしれないが、家の前を通る足音はどこかよそよそしい。誰が通っていったのかもわからない。玄関前は通過点であって、そこで雑談するような場所ではない。アパートメントは「apart(離れて)」を含んでいる。限られた空間内に部屋がぎっしり詰め込まれているのに、それら同士は没交渉的だ。空間を限りなく有効に使っているようでありながら、空間を最も無駄に使っている。計量可能なものの域を超え出る意思が全く感じられないからだ。いわば余白がない。
シェアハウスでは、ご近所さんとの付き合いが自然と増える。朝、仕事に行くときに家族以外のひとに「いってらっしゃい」と言ってもらえるのがこんなにうれしいとは思わなかった。この一画は細い道が行き止まったところに家々があるので、相互に行き来するひとを確認しやすいというのはあるかもしれない。Kさんに何かが起こっても、おそらくこの一画の誰かはすぐに気づくだろう。
セーフティとセキュリティの違いに思いを致す。安心と安全。セーフティネットという言葉があるが、この言葉が指しているのは実際にはセーフティではなくセキュリティで、安心感を与え合うというよりは、安全を保障するという意味合いが強い。だが、近所付き合いの豊かさとは、そのようにして第三者から公的に与えられるものではなく、時間をかけて相互のつながりの中から紡ぎ出されてくるものだ。「ここに居てもいい」という実感は、誰かからルールのように与えられるものではなく、内発的に感じられるはずのものだ。安住するということ、寛ぐということ。
お気に入りの場所、喫茶店でもバーでも、友人の家でも、自室でも、山奥の静かな池のほとりでも、どこでもいいのだが、寛ぐことができているとき、「わたし」は無際限の「ここ」にいることができる。つまり「ここ」がどこからどこまでで、そこから先には「ここではないどこか」が広がっていると想定することがない。実際には喫茶店のなかにいるのに、そうだと意識することはない。境界はなく、ただぽっかりと浮かんでいる。その意識を持つことさえないまま。
逆に寛げていない場合を想定する。安住することができないとき、輪郭の意識が強くなっていく。わたしは「ここ」にいる。「ここ」にしか居ることができない。あるいは、疎ましい存在が「そこ」にいる。だから「そこ」にはわたしはいない、いることができない。居心地が悪くて場所を変えようとする。だがそれでも落ち着かない。
落ち着くとは、ここがどこであっても気にしない状態である。だがその無局所性は、特定の局所性に依存している。逆に、落ち着けていないとき、自分は特定のどこかにいざるをえないが、そのときにいる「場」は「特定のどこ」という価値の傾斜を失っているかのようである。
一般的に広い部屋がよいとされるのは、部屋の広さを意識する必要がないためである。部屋が狭いと、どうしても部屋の大きさや身の置き所が気になってしまうものだ。
寛ぐとは、「ここ」が拡がる経験だ。「ここ」を象る境界線の範囲が大きくなるというよりかは、「ここ」でしかない原点の拡大といえる。あるいは円のイメージ。まったき集中。
おれはKさんに迎え入れられ、Kさん宅で寛ぐ。
皆がよそから来るのです。だからといって、ここが自分の場所であっていけないわけではありません。外国人などどこにもいない、いや、われわれ皆が外国人なのです。こことはいたるところのことです。どこにいたってそこが〈ここ〉なのです。したがって、そう、侵入に万歳! 願わくは、客たちの時代の来たらんことを! もはや迎える者と迎えられる者の区別のない時代、誰もが自分のことを客の客であると言うことができる時代の来たらんことを!
100円でも投げ銭をしていただけますと、大変励みになります。よろしければ応援よろしくお願いします。
