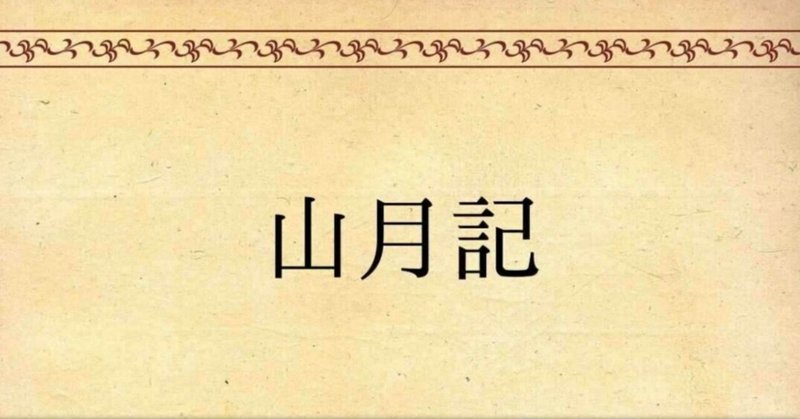
日記40 その声は我が友~!
5月17日
中間テストの直前。
今、高校2年生は山月記をやっている。
国語の仲良しの先生とプチ読書会をした。
皆さんは覚えていますか…李徴のことを…
我が臆病な自尊心と、尊大な羞恥心を!
今読むと、改めて素晴らしい作品だなと思う一方、
例えば17歳あたりって、
周りばかりがよく見えて、自分がとても(事実以上に)力なく思えたり、
身の丈を思い知らされるできごとを経験したり、
自分が主人公になれないと悟る瞬間があったりするじゃないですか。
そんな時期に、李徴の正直すぎる心のうちを、
時間をかけて精読させる教科書はあまりに酷だとも感じます(笑)
実際、自分と重ねてかなりダメージを受ける生徒も過去にはいたらしい(笑)
私が10代で読んだ時にはあまり覚えていなかったけど、今回再読して一番気になったシーンが、
李徴の作品(詩)を聞いた袁傪が
”しかし、このままでは、第一流の作品となるのには、どこか(非常に微妙な点において)欠けるところがあるのではないか、と。”
と独白しているところ。
それを伝えると国語の先生は
「あ~Asamiさんはやっぱりそこが気になるんだね」と言われた。
しかも本文には
”どこか非常に微妙な点において欠けるところ”
が明記されないまま終わるので、
袁傪の主観にして直観、わたしたち読者の完全なる予想、という余白が生まれることとなる。
ここに考える余地を残してくれた中島敦ありがとう…
何かの「正しいひとつのこたえ」がないのが、
私が文学すごく好きだなって思うところ…😌
受験テクニックとして
「本文に必ず答えが書いてあるから」ってパターンもあるけど、
本当に優れていて時代の変化に負けずに生き残る作品には、伏線回収しないと言いますか、
時にはそのままハッキリさせないモヤモヤを散りばめてあって、(作者だって“答えなんて知るか!”と思っているのだろう)
それは、読んだ人が持ち帰るお土産となり、
そのモヤモヤを抱えて考え続けた経験が、
実際の人生において底力を発揮したりする。
作品にどうしても理解できない箇所があったり、
作品そのものがよく分からなかったりすることがあるけど
その分からなさを抱きしめ続けることが大切。
…という、これは私の文学師匠である駒井稔さんの受け売りですが!
いいよね~🤟🔥
さてさて、あったね~山月記!
という方のために、青空文庫のリンクを貼っておきますよ!
SNSにいる我が友、李徴たちよ!読んでくれ~!
"山月記"(中島 敦 著)
こちらから無料で読み始められます: https://a.co/hxQaQeZ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
