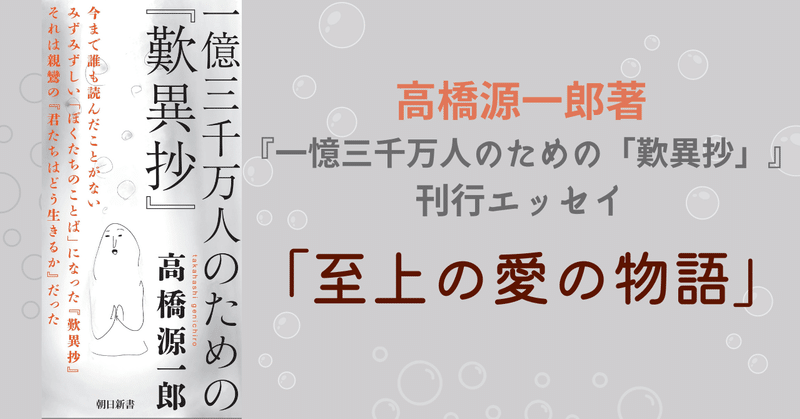
高橋源一郎さんが、ぼくたちには今こそ『歎異抄』が必要だと思った理由/高橋源一郎著『一憶三千万人のための「歎異抄」』刊行エッセイ
高橋源一郎さんの『一憶三千万人のための「歎異抄」』(朝日新書)が刊行されました。なぜ今、『歎異抄』を「翻訳」しようと思ったのか。本書に込めた思いを綴った、「一冊の本」12月号の「著者から」掲載の高橋さんにご自身によるエッセイを掲載します。
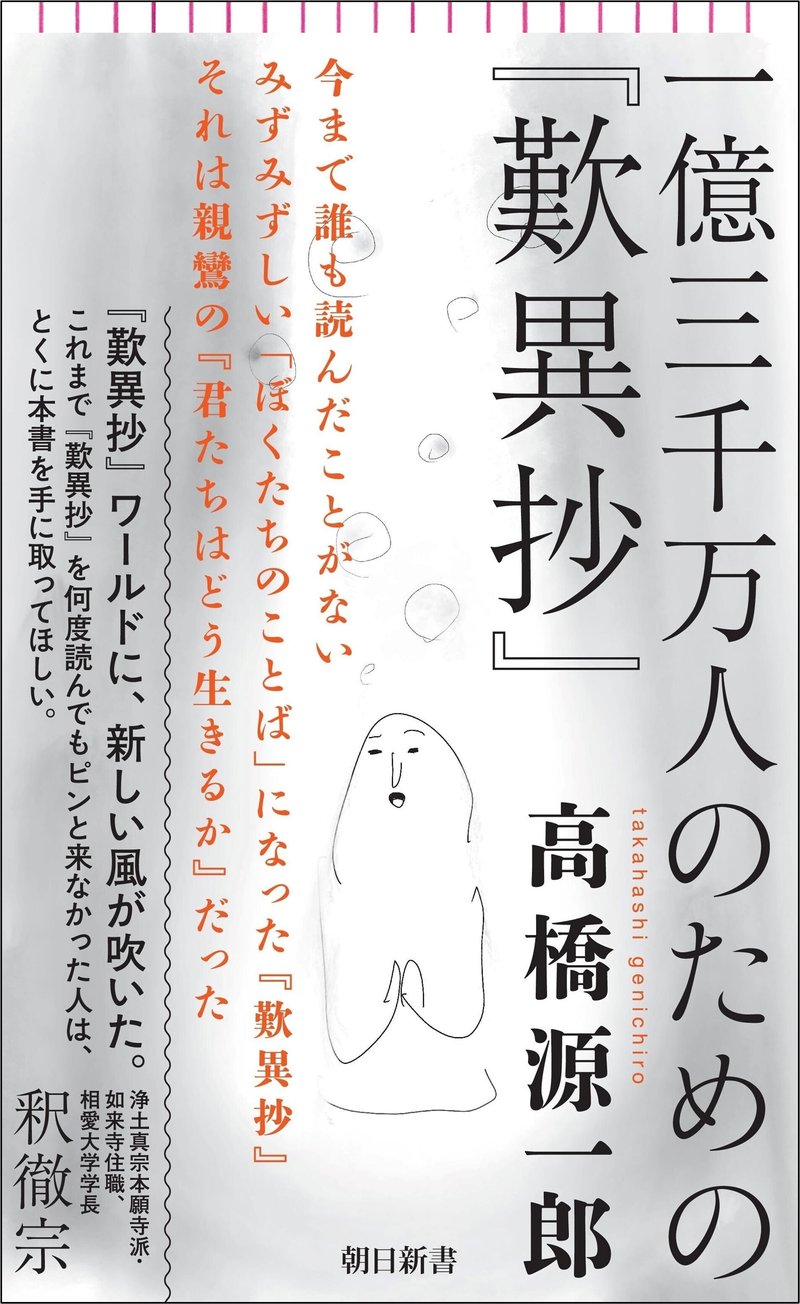
浦沢直樹原作のアニメ「PLUTO」の配信が始まった。約1時間のものが8 本、超大作だ。そのスケールの大きさ故に、テレビ会社では制作できず、世界に配信できるネットフリックスの資本によって制作されたといわれている。実はこの作品、手塚治虫の名作『鉄腕アトム』の中の一エピソード「史上最大のロボットの巻」を長編化、というかリメイクしたものだ。19 歳になる長男に見るように勧めた。すると、長男は8本を一気に見て、「ものすごくおもしろかった! すごい!」といって興奮していた。
ロボットが人間たちの都合のまま争い合う悲劇を描いた手塚の原作が、およそ60 年の後、AIが人間に限りなく近づこうとしている現在にみごとに蘇ったのだ。手塚の原作の中にあって古びない、おそらくは永遠に人びとに訴えつづけるなにかを、浦沢直樹は、いま現在を生きる人びとの切実な問題に変換してみせた。ぼくは、それこそが「翻訳」の意味だと思っている。
外国語で書かれたものを日本語に、古い日本語で書かれたものをいまの日本語に。ぼくはそんな「翻訳」をいくつかやってきた。考えていることはいつも同じだ。
こんなにも素晴らしいのに、いまのぼくたち、いまの読者には少しだけわかりにくい。作者といま目の前にいる読者の間にある、見えない「壁」、それを壊して、作者のことばをいまの読者に直接伝えたい。そのためにはどうすればいいのか。
『ブライト・ライツ、ビッグ・シティ』というアメリカの若い作家が書いた小説を「翻訳」したときには、注を一つもいれなかった。アメリカの読者はそんなものを必要とせず、ただ本文に向かい合うだろうから。もちろん、そのためにやらねばならないことはいくつもあった。
『論語』を「翻訳」したときには、孔子を「センセイ」と呼ぶことにし、その「センセイ」には彼が生きた時代と現代を往還してもらうことにした。古い本の中で奉られている人ではなく、いま生きているぼくたちにこそ必要な「センセイ」になってもらいたかったから。
そして『歎異抄』だ。『歎異抄』はぼくにとって、とても大切な本だった。そこには、いま書かれている本のほとんどよりもずっと、いま読むべきことが書かれている。ぼくはそう思った。いま書かれている本の大半は、書かれた瞬間から古びて消えてゆく。けれど、不思議なことに、ずっと昔に書かれたものなのに、まるでいま書かれたように新鮮な本があるのだ。
古いけれど、興味がない分野だけれど、なんだかおもしろそう。そこにはきっとなにかがある。そんな気がして、本の中に入りこんでゆく。それは、まるで隠された財宝を見つける冒険のようだ。屋根裏部屋で、朽ちたお屋敷の隅っこで、不思議な箱が見つかる。埃をはらい、苦労して蓋を開ける。そこには輝く宝石が入っているのだ。
ぼくにとって「翻訳」はそんな経験だ。おもしろいもの、素晴らしいものは、こちらが待っていて、向こうから勝手にやって来てくれるわけじゃない。ぼくたちもまた、財宝を捜し出す旅に出なければならないのだ。
『歎異抄』は、人間の叡知の「すべて」が詰めこまれた宝の箱だった。けれども、その箱を開けるためには、ちょっとした旅が必要だった。
まず、それは「宗教」や「信仰」に関する本だということだ。そして、それは、いまのぼくたちにはわからない古いことばで書かれているということだ。
でも、ぼくにはわかっていた。「宗教」や「信仰」という形はしているけれど、そこで扱われているのは、これまでも、これからもずっと、ぼくたちがいちばん大切にしている、人間の「精神」の問題だということを。そして、その、一見古めかしいことばの下には、いまのぼくたちが使うのとまったく同じことばが隠れていることを。
「宗教」を信じられない、「信仰」というものを持たないぼくだからこそ、『歎異抄』を「翻訳」することができる資格があるのだ。ぼくはそう思った。そして、ぼくが想像していた通り、『歎異抄』という秘められた宝箱の中には、いまのぼくたちがもっとも必要としているものが詰めこまれていたのだった。そんなふうに読んでもらえるなら、ぼくは嬉しい。
最後に一つ。『歎異抄』という宝箱に隠されていたもの。それは語り手の「ユイエン」の物語だ。『歎異抄』の中心にあるのは、いうまでもなく「シンラン」のことばだ。けれども、その影には、「師」へ「至上の愛」を捧げた「弟子」の物語が隠されていたように思う。それも読んでもらえるなら、ぼくはもっと嬉しい。
