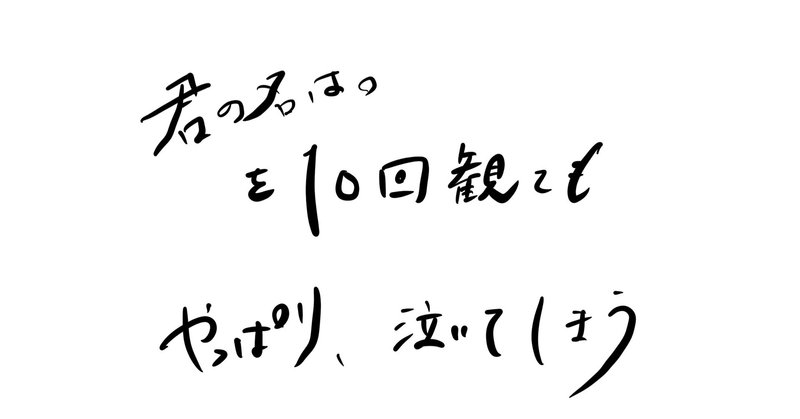
君の名は。を10回観てもやっぱり泣いてしまう
最近観た映画の中で一番印象深かった映画は何かと言われたなら、私は迷わず「君の名は。」だと答えるだろう。映画館に3回足を運び、飛行機の往復で観、金曜ロードショーで観、遂にはDVDも買ってしまった。何がここまで私を虜にさせるって、ストーリーの秀逸さでも、絵の繊細さでも、名前を呼びながら坂を駆け抜けるエモいところでもない。
「大切なはずなのに、どうしても思い出せない切なさ」を痛いほど感じさせてくれ、そして私にとっての大切なものを思い出させてくれたきっかけの映画だからである。
よくある話ではあるが、私の両親は幼い頃に離婚し、私は母方の家族に育てられた。
ありがたいことに周囲の支えに恵まれ、一人っ子だが孤独はあまり感じずに育ったと思う。母も激務の傍、礼儀や勉強を人並み以上に叩き込んでくれた。
幼いながら一人娘✖️シングルマザーのインパクトにはとても敏感だった。我儘を言う立場にないと日々感じていたし、母にとって私は「命よりも大事」だとよくわかっていた。私は皆の為に、自慢できる良い子になりたかった。学校も習い事も必死に頑張り、賞をとったり注目される度に喜ぶ母の顔を見るのが何よりも嬉しかった。大学に受かった時も、受かったことよりも、返済不要の奨学金で入学できたことの方が嬉しくて泣いてしまったのを覚えている。
しかし、幼い頃から持っていた母や家族を喜ばせたいという純粋な気持ちは、視座や付き合いがぐん広がるにつれ、次第にブラックな自分もつくっていった。無邪気に遊ぶ子ども達や放任されている友達の話を聞いていると羨ましくて仕方がなかった。私には、子どもらしい子ども時代の記憶がないのだ。言いつけは素直に守り、目上の話には黙って耳を傾け、ごねる子どもを見掛ければ冷ややかに見ている子どもだった。「本当にいい子ね」と周囲から言われるたび、「これがいい子なんだ。これを維持しなくてはならない」と思い、結果どんどん窮屈になってしまったのだ。
いい大人になっても、私は子ども時代の喪失感と(そんなことないと頭で理解していても)いい子でなければ愛されないのでは、というどうしても拭い去れない不安に悩まされていた。
そんな2016年夏、「君の名は。」は公開された。
3回行った映画館で3回ともティッシュを1パック消費するほど泣いたのを覚えている。
なんとなく大切なことがあった気がする、けれど、思い出せない。日常は普通に過ぎていく、何かがある気がする、でも思い出せない。思い出しそう。でも思い出さない。
というようなもどかしさをずっと感じていた。
きっと、そのもどかしさは私の中にもあるのだろうと思ったが、それがなんなのかはその時はわからなかった。
それから数か月経ち実家を掃除していたある日、埃を被った8ミリのビデオテープが出てきた。
画質も音も荒く、今のクオリティから言わせれば白黒に近いカラーの古いビデオだ。
懐かしさに負けて掃除を中断し、ビデオデッキを探して引っ張り出して家族揃って見始めた。
そこには、3歳の私が写っていた。
言葉を失うほど、3歳の私は衝撃的な姿をしていた。
公園を裸足で走り回り、アイスで全てをベタベタにし、カメラやものに噛みつき、人の話は聞かず、年下にお姉さんぶっているかと思えば突き放し、引くほど自由で敵なしで世界の中心の顔をしていた。
全く私の記憶にはない。けれど確かにそれは私だった。
私以外の家族は皆「懐かしいね〜」と笑いながらビデオを観ている。
傍、私は涙を堪えるのに必死だった。
仕方ないなあという笑い顔で、公園を裸足で走り回る私を戻ってくるまでじっと待っている母。
お姫様の格好をして澄ましている私を専属カメラマンのように撮る祖父母。
どれだけ私に叩かれ、怒鳴られてもいつまでもついてくる2個下の従弟。
聞き分けがよく、制約の中で健気に生きてきたと思っていた私の記憶とは裏腹に、聞き分けは最悪で、自由で、甘えん坊で問題児な私の姿がそこにはあった。
全く相手に対する価値を提供していなくても、ありのままの姿で愛されていたはずだったが、私の記憶はそれを改竄していた。
しかし、ビデオという確固たる証拠を前に、私はどんな言葉よりも強く「私は愛されていた」ということを思い出し、理解したのである。
君の名は。を観て大切なものを忘れている切なさにシンクロした理由がよく分かった。
私は、ずっと何もなくても愛されていたのだ。
でも自分だけそのことを忘れていた。いかに記憶なんて曖昧なものか。いつだって時の流れに沿って薄れていき、解釈も変わっていく。
今でこそ、自分は愛されていた、と強く思っているが、きっとまた忘れてしまうこともあるのだろう。そんな時はまた君の名は。を観て泣くのだと思う。
せめてまた思い出す機会があるようにビデオデッキも8ミリも残すことにした。
8ミリは、まだ8ミリのままだ。そのほうが懐かしさを大事にできる。
きっと誰しも忘れたくないけれど忘れてしまった大切な何かを抱えて生きているんじゃないだろうか。
それを思いだす一つのきっかけは、どうしようもなく切ないという感情かもしれない。
そういう感情に日々もうちょっと心を傾けてみようと思う。
※20200913 天狼院書店ライティングゼミ投稿エッセイ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
