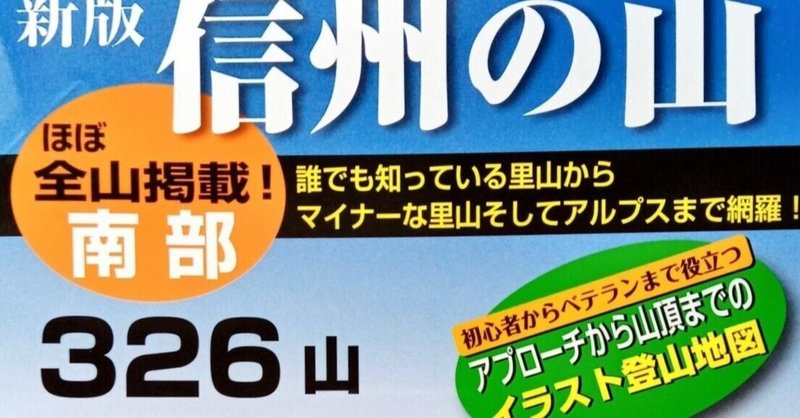
信州の全山~登山家が歩いたガイドブック全5巻
8月8日(日)は「山の日」。名古屋市栄4丁目の久屋中日ビル4階の長野県名古屋事務所に、信州の特産品とともに、「新版信州の山」の全5巻シリーズ(信毎書籍出版センター)が置かれています。
新版全5巻を書いたのは、長野県伊那市在住の登山家、宮坂七郎さん(75)です。普通の山のガイド本と違うのは、身近に行ける山も含めて信州の山をほぼ網羅していることです。「百名山」といった著名な山だけではないのです。
もうひとつは、「コースの詳細図」が手書きで細かく書かれていることです。例えば長野県と岐阜県にまたがる御嶽山(3067㍍)の継子岳のコース図には、「開田口登山口 立派な標識と登山届け箱有り」「避難小屋 すわって4人 横にはなれない」といったアドバイスが書き込まれています。
宮坂さんは2013年に「信州の山」の書名で「中信・南信221山」と「北信・東信209山」の2冊を自費出版しました。ただ、有名な山ばかり取り上げていたため、今度は登山道などが紹介されていない身近な里山まで含めて、ふるさと信州の山に関心をもってもらおうと一念発起したそうです。
2017年に「新版信州の山」の発刊を開始。まず「南部326山」で長野県南部の山をほぼ網羅しました。次いで「中部上巻217山」「中部下巻181山」を出版。2021年に「北部上巻217山」「北部下巻134山」で完結させました。

宮坂さんは20歳から信州・八ヶ岳をホームグランドに、立山連峰や北アルプス、南アルプス、中央アルプスの登山道のすべてのコースを登り続けてきました。「逍遙山河会」(しょうようさんがかい)という山岳会をつくり、リーダーとして活動をしてきました。「信州の山を全山紹介する」という新たな「ピーク」を目指すため、山岳会を解散し、その後は単独登山を続けています。
「登山」と聞くと、元新聞記者の筆者は遭難事故を思い出してしまいます。年末年始は毎年のように、北アルプスの遭難事故の取材に追われていました。
なかでも2008年12月27日に北アルプスで発生した表層雪崩による遭難事故は、重苦しい年明けを迎えました。この遭難事故が印象にあるのは、犠牲者を出した山岳会が2010年に「自戒の念」を込め、報告書をまとめたからです。雪崩の犠牲者のGPSを解析した結果、時速200㌔以上の雪煙を伴う「爆風雪崩」だったという記事になっています。
冬山だけではありません。最近は「密を避ける」ということもあり、夏山も登山者が増えています。長野県警の山岳遭難発生状況(週報・2021年8月3日)によると、7月末の1週間だけで6件7人が滑落や落石で救助を求めていました。今年1月から8月までの山岳遭難は、121件、死者23人。前年同期の70件、12人を上回っていました。
宮坂さんの手書きのイラスト入りのページをめくっていると、山を身近に感じることができます。事故防止のための下調べにも必要な情報が盛り込まれています。

子どもの頃に登った山のページを開いてみました。コースの目印となっている「石灯籠」や「山頂は広場で展望よし」などが書かれていました。当時の山登りの光景が思い出されてきて、また登ってみたくなりました。
宮坂さんの「新版信州の山」で紹介された山は、1075あります。
(2021年8月8日)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
