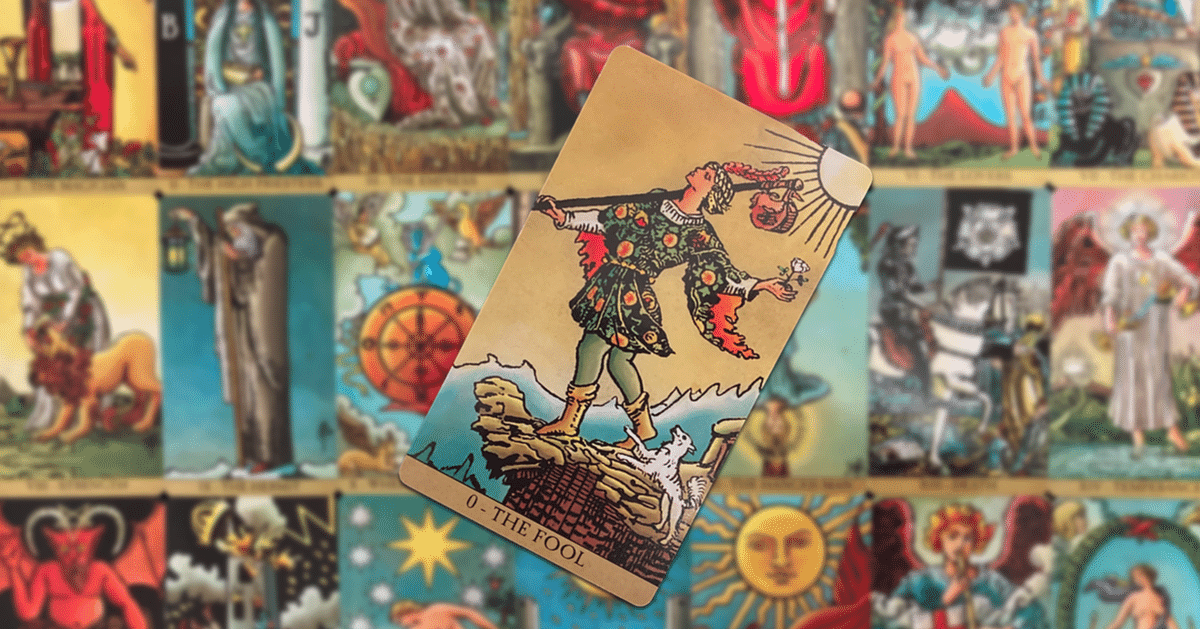
ご本家ウェイト氏にタロットを学ぶ
ごきげんよう!べるがもです。
ゴールデンウィークはいかがお過ごしですか?(←終わりを認めたくないので進行形で書いてみる)
ワタクシの「連休でやりたいことリスト」の1つに挙がっていたのが、「タロットのスタディノートを作る」でした。
普段使っているウェイト=スミス版の、カード1枚1枚のシンボルや解釈などを自分なりにまとめておきたいと思ったのですが。
そういえば製作者ご本人のウェイト氏が書いた本を読んでなかったなあ…。
ウェイト氏の本、読みました?
いわゆるライダーウェイトスミス版が出た時に、 "The Pictorial Key to the Tarot" という解説本をウェイト氏自ら書いたというのは知っていましたが、なんか難しいらしいというウワサもあり、積極的に調べてなかったのですよね。
でも、自分用に「まとめ」を作るならやっぱり本家を見ておかなくてはいけないのでは…?
だって公式ですよ公式。
ということで、あれこれ調べてみましたら、全文翻訳&解説をしてくださっているサイトさんを発見!ありがたやありがたや〜〜〜!
こちらです。
訳だけではなく、細かい解説もあり、キリスト教や神秘主義に詳しくないとピンとこない要素も詳しく記載されていて参考になります。
ただ。ただですね。
ウェイト氏の表現すっごいわかりにくいんですよ!!
この難解さはわざとなのか
もちろん、話の内容ゆえに難解というのはあるんでしょうが、そもそも文章がもっっっのすごくまわりくどい!
1行で言えることを3行ぐらいかけて書く、しかも結論がよくわからないあのスタイル。
ついてこられるやつだけついてこい、なのか。
なんか、文章教室の添削問題にできそうです(苦笑)。
あと、ウェイト氏の基本スタンスは「占いと神秘の教え(秘儀)は違うのだよ。この両者の間には深くて暗い川が流れていて占いごときでこれを分かったと思ってもらっちゃ困る」ってな感じです。
メインの大アルカナに関しても「そもそも深淵すぎて説明できるようなものじゃないからね」です。
一方、小アルカナに対しては「とりあえず絵入りで作ったのは初めてだと思うけど説明は後で」的なさらーっとした扱い。
今のところ、第2部の大アルカナの紹介途中までしか辿り着けていませんが、基本的に、各カードに描かれている図柄や象徴の説明のみで、カードの直接的な意味にはあまり触れられていないです。
でも、これってこういうことを表していたんだ!(「魔術師」の足元のバラとユリが品種改良版だったとか ← 雑なまとめ)というのがてんこもりで非常に興味深い。
「あてにしちゃいけない」例が通説に??
あと、同じ第2部にこんな文章があるんですが。
"The common divinatory meanings which will be given in the third part are largely arbitrary attributions, or the product of secondary and uninstructed intuition; or, at the very most, they belong to the subject on a lower plane, apart from the original intention."
「第3部の中で述べられるであろう通常の占いの意味は、大部分は勝手な帰属、または二流で無知な直観の所産である。また、それらは、せいぜい、(大アルカナ本来の)原型の意図から離れた、より低い次元にある題目に属しているにすぎない。」(上記サイトより引用)
「勝手な」とか「二流で無知」とかひどい言われよう(苦笑)。
ちょっと気になって、その「巷で占いに使われているカードの意味」をチラッと見てみたら。
…なんか見覚えのある「意味」も、ちらほら……??
うーーーーーん。
もともとの「カードに描かれているもの」を全部読み切ってないのでなんとも言えませんが、おそらく「そういうことじゃないんだよ!」という解釈が混ざっているんでしょうね(苦笑)。
ただ、描かれているものを読み取った上で、やっぱり解釈被るわ、というのもありうるだろうなと。
そもそもウェイト氏は「大アルカナは占いのためのものじゃない(占いでは扱いきれない)」スタンスなんですよね。
なので、魔術師ではなく、フツーに占いに使いたい私どもとしては、こうした大アルカナの本質的なところ(の片鱗)を、どう占いという通俗的なところに落とし込むか、というところが腕の奮いがい、という考え方でよいですかねえ。
そんな感じで、まだまだ序盤なのにすっかり沼の気配。
まずは最後まで読みきらなくては!
お勉強楽しすぎるわ〜(満面の笑み)。
しかし、この文章を全部訳しきるなんて、それだけで偉業…。
それを公開していただけるなんて、ありがたい時代になったものです。
ちなみに、日本語版書籍は「タロット公式テキストブック」として魔女の家BOOKSから出ていたようですが、どうも今絶版なのかな??
なんかAmazonですごいお値段ついてましたが。
この前地元のジュンク堂で見た気がするのは…きっと気のせいだ、うん。
おまけ:ノート用タロットカードの印刷方法
自分の備忘録も兼ねて。
スタンダードサイズのタロットを7枚ずつ3段にきっちり並べて、スマホのカメラ(比率4:3)で撮影(上下左右の端は少し空けておいた方がいいです)。
この写真データを、A4の紙にカラー印刷すると1枚約6.5cm×3.5cmサイズのミニサイズのシートが出来上がり。
コンビニだと1枚60円でした。
あとはちまちまはさみで切ってテープのりでノートに貼りましょう〜。
当初コンビニでカード敷き詰めて縮小カラーコピー取ろうかと思ってたのですが、実践する羽目にならなくてよかった(笑)。
本日も最後までお付き合いいただきありがとうございます!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
