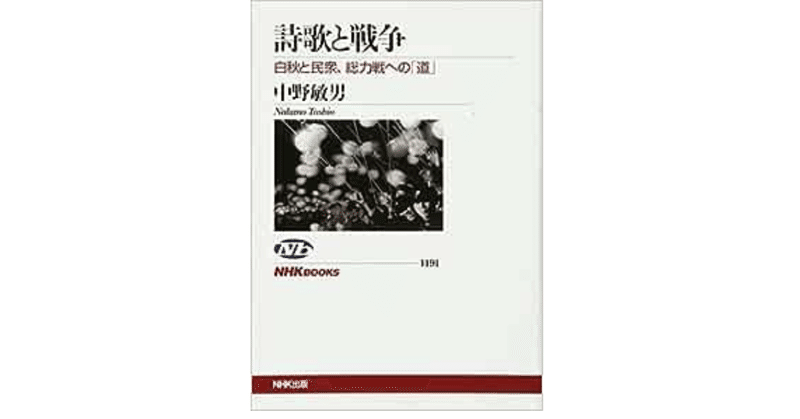
踊ってよろしく郷愁、ジャパン!
『詩歌と戦争 白秋と民衆、総力戦への「道」』中野敏男 (NHKブックス)
官僚がつくる「唱歌」に猛反発した北原白秋は「童謡」を創生し、震災後の社会に受け入れられて国民詩人の地位を確立する。自治への欲求を高めて大正デモクラシーを担った民衆は、詩人に作詞を依頼して「わが町」を歌いあげる民謡に熱狂した。拡大の一途をたどりつつ国民に奉仕を求める国家、みずから進んで協力する人々、その心情を先取りする詩人、三者は手を取りあうようにして戦時体制を築いてゆく。“抒情”から“翼賛”へと向かった心情の回路を明らかにし、戦前・戦時・戦後そして現在の一貫性をえぐり出す瞠目の書。
目次
序章 震災から戦争へ揺れた心情の経験―詩人と民衆の詩歌翼賛への道
第1章 抒情詩歌の成立と本質化される郷愁―日本製郷愁の二つの問題構成
第2章 民衆の植民地主義と日本への郷愁―傷を負った植民者のナショナリズム
第3章 歌を求める民衆/再発見される「この道」―震災後の地方新民謡運動と植民地帝国の心象地理
第4章 国民歌謡と植民地帝国の心情動員―翼賛する詩歌/自縛される心情
終章 継続する体制翼賛の心情
去年の「高橋源一郎の飛ぶ教室」の「戦争特集」で詩人の戦争詩を特集していた。ほとんどの詩人が戦意高揚詩を書いて戦争協力をしたという。そうしなければ生きて行けなかったのだ。
萩原朔太郎『詩論』を読んで、権威に寄り添う詩は書かないようなことを書いていたが、そんな朔太郎も戦意高揚詩を書いていた。
その前身であろう「赤い鳥」(白秋が戦争協力するまで)の戦争協力について描いていて興味深い。それは関東大震災で自治体からの要請で国民を一つにする民謡を要請されたりしたのだ。「東京音頭」のような明るい民謡の裏で植民地政策が進められていた。
例えば白秋の場合、姦通罪で逮捕され、不倫相手の女性と結婚するも彼女はチフスに罹患する。そして白秋は本土から島流しのような小笠原行きの後復活していくのだが、当時島が伝染病の隔離のための島としてあったのは、ハンセン病患者の隔離もあったり、林芙美子原作の映画『浮雲』でも病気療養のために屋久島に行くというシーンがあった。
そうした疎外された状況の中で白秋が求めたものが郷愁という精神だった。一時は姦通罪という村八分的迫害にありながらまともな日本人として生まれ変わるには郷愁の精神が必要だったのだろう。民謡運動のもう一人の首謀者野口雨情、中山晋平も「枯れすすき」(「昭和枯れすすき」の原曲?)という曲を作ったために関東大震災が起きたと非難され、題名を「船頭小唄」に変えたという。
野口雨情と北原白秋は争うように民謡や童謡を作り続けたのは生活のためもあっただろうが、彼らの郷愁の概念が国家主義に利用されたこともあるようだ。
たとえば『東京音頭』はそうした新たな民謡の一つである。それは暗い社会に希望を見出す郷土愛というもの、同じ頃に流行った東京で流行った『東京行進曲』はそうした白化していく東京を描いている。それに対して高屋窓秋は「頭の中で白い夏野となつてゐる」という俳句を残した(夏野→芭蕉の枯野)。
それは当時の植民地政策によって、故郷喪失者や植民地の子供たちに日本語を強制していくという教育の現場での洗脳教育として民謡や童謡は有効だった。それが如実に現れるのが白秋の北海道行き(天皇の行幸の後を追う国民詩人となった
のだ)とアイヌ神話を屍と歌う詩もあった。
戦争は上からの命令で仕方がなかったとされるが下からの要請もあったという。東日本大震災のときも公益法人のJAジャパンが金子みすゞの詩を放送で流し続けて、やたら絆を強調していく(白秋の「赤い鳥」で文学賞を取ったのが金子みすゞだと知った)。今の危うい社会になっている。ほとんど戦時と日本人の精神は変わってないように思える。そういえば「モーニング娘。」の『LOVEマシーン』の踊っていればいいと流行ったのも零落していく日本(0年代)とその後の踊るアイドルたちは、やたら歌の世界だけのイメージ戦略で日本を明るくしようとする。その戦略に乗せてしまったのが安倍首相ということになるかも。安倍の首相の広告がまさにその延長(秋元康と安倍首相との繋がり)で作られたものだった(統一協会の広告塔だったとも)。感性に訴える流行歌やドラマが保守化していく傾向は権力側の常套手段なのだろう。
大きな事件のショックの後に権力側が感情を一つの方向へむけるのに詩や歌は有効なのだ(「ショック・ドクトリン」で学んだ)。
その翼賛体制を知らないはずはないのに、今の政治に怒りを向けるものはいない。もう戦後ではなく戦前なのだという意識を持つべきなのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
