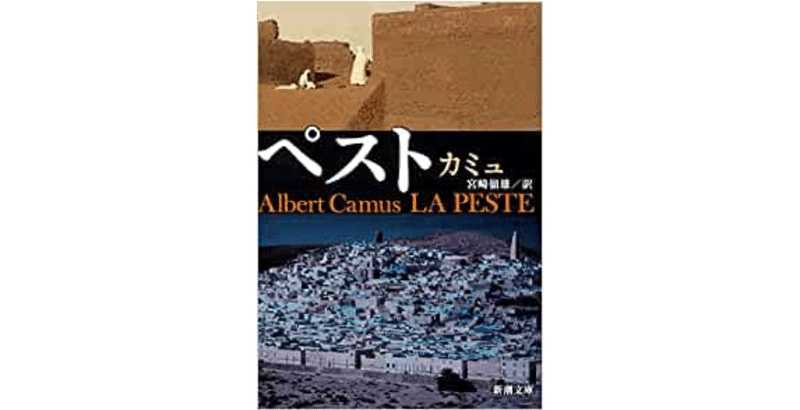
『ペスト』とコロナ禍
『ペスト』カミュ , 宮崎 嶺雄 (翻訳)(新潮文庫)
発表されるや爆発的な熱狂をもって迎えられた、
『異邦人』に続くカミュの小説第二作。
アルジェリアのオラン市で、ある朝、医師のリウーは鼠の死体をいくつか発見する。ついで原因不明の熱病者が続出、ペストの発生である。外部と遮断された孤立状態のなかで、必死に「悪」と闘う市民たちの姿を年代記風に淡々と描くことで、人間性を蝕む「不条理」と直面した時に示される人間の諸相や、過ぎ去ったばかりの対ナチス闘争での体験を寓意的に描き込み圧倒的共感を呼んだ長編。
前半は語り手の描写に戸惑いながらあまり人物には感情移入出来なかった。語り手の視点が多様で焦点が見えてこない。それこそペストの不気味さなのだ。ペストが蔓延していてもどこか他人事のように振る舞う人々が集う場所としてのオペラ劇場でのパニックから一気に読書が進んだ。
新聞記者のランベールはパリに恋人がいて早くオランから逃げ出したいのだが隔離政策でここに閉じ込められている。オペラは『オルフェウスとエウリュディケ』。ギリシア神話の永遠の愛を歌うオペラだけど道化師が登場したところでペストで倒れてしまう。不条理劇。
オペラは愛と死がテーマの劇で死がより身近に侵入してきたにも関わらず、ランベールは恋人がいるパリよりもここで生きる道を探す。パリ出発の手配が整ったのにもかかわらずペストの街に残りリウー(医者)の仕事を手伝う。災いの中での連帯感は9.11でも美談として語られる。でも自然の流れとしての連帯感が描かれている。ソルニット『災害ユートピア』で、災いの中でのユートピア空間について語られている。
重要なのはそこで彼はよそ者(異邦人)からこの街の者と成ったこと。地域住民としてよりも、世界市民という感じか?そして小説もまた連帯小説となっていく。
その後に無垢な子供の死とパルヌー神父との神学問答となっていく(カミュは無神論の実存主義者)のだが、そこで神父はペストは恩寵であるという。リウーはそれには反駁するのだが、無神論であるはずのタルーはパルヌー神父を批判することもなければ受け入れる。ここのわかりにくさはペストを観念として描いているからである。無神論のタルー(リウーの分身であり、リウーにノートを残したデラシネ的人物)はペストは死刑宣告だという。タルーの父が判事で、ある罪人を死刑したところに立ち会ってから、彼に巣食うペストの観念、他者に死を知らしめる人間はペスト感染者だという。ペストがファシズム(ナチズム)を暗示していると言われる。
全体的に暗い描写が延々に続く中で、ラスト近くでリウーとタルーが海水浴に行くシーンは感動的に描かれている。この海水浴はムルソーの殺人のシーンと対になるカミュの生の海のシーンで、白衣を脱いだ(そういう描写はなかったけど)リウーの裸とタルーの筋肉質の身体が海の中に入って、ペストが洗われる。つかの間の二人の幸福なシーン。BL的ではあるけど。
「隠喩としての病」のペストは、例えば下級役人のグランは献身的な行為でペストと戦っている下級役人(コロナ禍の医療従事者のような政府と現場の間に立つ人)だが彼はカフカ的人物で、役人との仕事とは別にいつ発表することもない小説を書いている。書くことが彼の「ペスト」(不条理)の闘いなんだと思う。接続詞一つで全体の小説を破壊してしまうことについて嬉しそうに語る彼もまたペスト感染者だった。(2018/07/14)
関連書籍:ソンタグ『隠喩としての病』
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
