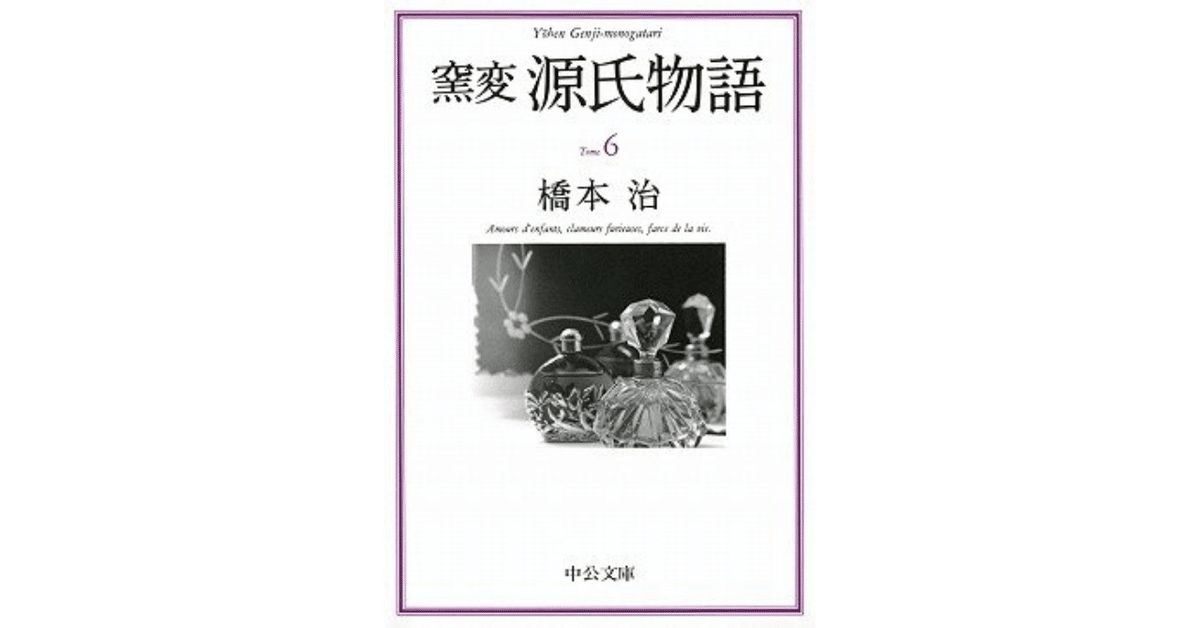
光源氏の手はずとしての娘たち
『窯変 源氏物語〈6〉 朝顔乙女 玉鬘 初音』橋本治 (中公文庫)
源氏物語の心理描写は全部和歌にあり、それを外すと何もわからなくなる。だから和歌も訳したし当時の歌謡も別な形で訳している。(朝顔/乙女/玉鬘/初音)
「朝顔」が結婚しない女のエピソードから「乙女」「玉鬘」では女の幸せは結婚することであるという物語だが、男親に取って娘を嫁がせる幸せというような話になっていく。そして光源氏は一人だけではなく四季折々の妻を得るわけだが中心は次世代の息子の話になっていく。一度目は悲劇として、二度目は喜劇としてというようなコメディ色が強くなっていく。面白いのは惟光の息子と夕霧の関係で、惟光の息子も夕霧同様要領が悪い。結果的に光源氏の息子の妻になれるかもと期待して惟光を喜ばすという。
光源氏の一人称なのに、神の視点というか夕霧の行動も玉鬘の過去も把握している不思議。たぶん光源氏にはスパイ網(女房たちか?女房の噂はあなどれない情報源になっているのかもしれない)のようなネットワークがあるのだろうと考えているが、三人称である語りもあまり不思議に思わないのは、第三者的視線によってコメディ化されているからなのかと考える。光源氏の批評としての『源氏物語』という紫式部の『源氏物語』とはまた違った面白さがあるのかもしれない。紫の上との対話も嫉妬する妻というコメディタッチのような。
朝顔
「源氏物語」で一番目立たない姫か?最初の「帚木」から登場してくるのだが絶えず比較対象としての存在だからだろうか?この巻では「紫の君」の嫉妬を買う女として。前の斎院(賀茂斎院)というのもわかりにくいというかすでに過去の人という感じである。「朝顔」は「夕顔」より高貴なという意味もあるという。「夕顔」が死後も重要な姫であったのに、「朝顔」はいとこ同士という関係だからか、肉体関係よりもプラトニックな手紙のやり取りで、婚期を逃し出家するのだから、源氏の世話を受けずに自立した女として描かれているにもかかわらず惨めさを感じてしまうのは、結婚出来ない女というイメージなのか?
乙女
「朝顔」で結婚できない女(神に仕えて、その後出家する女は光源氏の思い通りにならない従兄妹であった、従姉弟か?)。その分光源氏とは終生の友として手紙をやり取りしていたようである。
光源氏はまあ女性には不自由なく六条院の四季の館にそれぞれ女王として君臨するほどの妻(愛人)がいたのだから朝顔にこだわる必要のなかったのだろう。ただその晩年は寂しいものがあったと思ったに違いない(本人よりも光源氏が)。だから娘たちを皇族へ嫁がせる手段を思索するのである。それに対して息子である夕霧に対しては、親の七光りよりも実力で上がってこいとして、夕霧からも恨まれる。夕霧は光源氏よりも大宮のおばあちゃん子としての甘えがあるのだが、息子世代の生ぬるさは従者の惟光の息子にもあって面白い。雲居の雁と会うのが厳しくなって、惟光の娘を見初めるのだが「空蝉」の二の舞いのような展開になると思えば、惟光は源氏の息子ということで、そういう恋愛も認めようとするのだ。
雲居の雁は頭の中将(内大臣)の娘であり、もうひとりの娘の弘徽殿女御は「絵合」で光源氏との秋好む中宮との争いに敗れている。光源氏に邪魔されたと思っている頭の中将は、ここでも天皇(冷泉帝)の后候補から外れ、明石の姫が天皇の妻という幸福を得ていくのである。「乙女」という捧げもののような家父長制のシステムで娘よりも父親が権力を築くのだ。そう言えば五節の舞もある意味捧げ物としての舞だった。それを惟光が最初はよく思わなかったのは、それによって顔を晒し下位の男の妻になるのを危うんだからだった。そこで光源氏の娘のようにして舞姫として権威付けたのだった。
玉鬘
そういう娘の存在があり「玉鬘」では光源氏が思い通りに出来ない娘が登場してくるのだが、頭の中将の娘であるにも関わらず、自分の娘であるように育てたいというのは、光源氏にかぐや姫のように男どもが妻恋を争うのを愉しみたいという不純な動機だった。そして、そんな娘にも手を出すのだからとんでもない男なのだが、光源氏の中で一番は紫の上であることは間違いないのだろう。
初音
その紫の上の地位を危うくするのが明石の君なのだが、娘を人質にするという(光源氏は娘の為だと考えるが母親としては違うだろう)光源氏と母親との戦いがここにもあるのである。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
