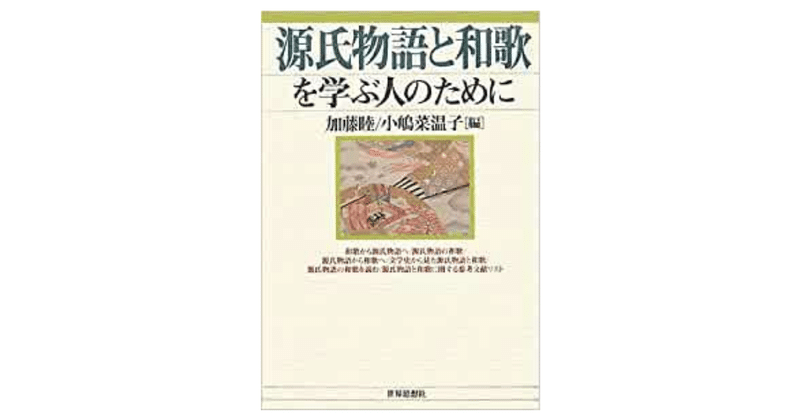
『源氏物語』は和歌の教科書
『源氏物語と和歌を学ぶ人のために』(編集)加藤 睦, 小嶋 菜温子
源氏物語にとって和歌表現がどのような意味を有するかを本格的かつ体系的に解き明かし、日記・物語・説話などのジャンルや散文と韻文という垣根を越えた広い視野に立ち、源氏物語の表現の成立ちを問い直す。新しい日本文学史・文化史の試み。
目次
I 和歌から源氏物語へ
1 三代集と源氏物語 ― 引歌を中心として[鈴木宏子]
2 後拾遺集と源氏物語[松本真奈美]
II 源氏物語の和歌
1 四季の歌 ― 和歌生活としての自然[松井健児]
2 恋の歌 ― 胡蝶巻を例に[高田祐彦]
3 賀歌 ― 盃酌歌と賀歌[小島菜温子]
4 哀傷の歌[土方洋一]
5 雑歌[久富木原 玲]
III 源氏物語から和歌へ
1 源氏物語と中世和歌[加藤 睦]
2 源氏物語と近世和歌[鈴木健一]
IV 文学史から見た源氏物語と和歌
1 前期物語と和歌 ― 竹取物語からうつほ物語へ[室城秀之]
2 蜻蛉日記と和歌
― 源氏物語の「絶望」に向かって[川村裕子]
3 枕草子と和歌
― 枕草子と源氏物語の〈散文への意志〉[小森 潔]
4 狭衣物語
― 独詠歌としての物語[神田龍身]
5 〈法会文芸〉としての源氏供養
― 表白から物語へ[小峯和明]
源氏物語の和歌を読む
― 諸説整理を兼ねて
源氏物語と和歌に関する参考文献リスト
感想
『源氏物語』はそれ以前の勅撰和歌集(三大集『古今集』『後撰集』『拾遺集』)から影響を受けて、それらを引歌(引用)しながら物語を膨らませていく。『古今集』の引歌は210首、『後撰集』からは67首、「拾遺集』からは70首。
それは『源氏物語』以前の『竹取物語』や『伊勢物語』の影響をうけているのだが和歌がもともと記紀歌謡だったことを考えれば歌物語にはその伝統があったわけである。
逆に『新古今集』以後になると『源氏物語』から影響を受けた和歌が出来る(藤原定家など)その相互作用が、『源氏物語』を現代まで読まれ続けた核心なのではないか?という。
そういえば大江健三郎が英詩(ブレイクやイェーツの詩)から物語をインスパイアーさせていくことに近いのかもと思った(大江健三郎は『源氏物語』を影響を受けた文学として上げている)。
『源氏物語』は物語だけではなく和歌も心を刻まれる。ちょっと奥深い世界だった(専門性があるかも)。
本歌取りの技法
本歌取りの技法は、俊成・定家親子によって確立された。
言葉は古きを選び心は新しきを求める。
古典的な美的小世界を形成させる(幻想短歌)。取る場合は主題は変える。新歌の設定した世界の奥行きや溶暗(比喩的象徴性か?)する部分を効果的に使う。
駒とめて袖うち払ふかげもなし佐野のわたりの雪の夕暮 藤原定家 『新古今集・冬』
(本歌)
苦しくも降りくる雨か神(みわ)の崎佐野のわたりに家もあらなくに 長奥麻呂『万葉集・巻三』
第二句「雨」を第五句の「雪」に、第五句「家もあらなくに」を第二・三「袖うち払ふかげもなし」に変換しているという(難しい!)
本歌は古典的美的世界を形成しているので、それを想起させる日常世界を消失させて(恋歌に変換するということか?)、本歌から独立した冬の歌を詠出しているという。
新しい歌の自立性を保つことが出来るか(本歌に寄りかからない)
『源氏物語』編。
「もっぱら言葉だけを取った例」
訪ふ人もあらし吹きそ秋は来て木の葉に埋む宿の道芝 藤原俊成女『新古今 秋下』
(本歌)
とふ人も今はあらしの山かぜに人松虫のこゑぞかなしき よみ人しらず『拾遺集・秋』
(源氏物語)
うち払う袖も露けきとこなつに嵐吹きそう秋も来にけり 夕顔 『源氏物語 帚木』
後鳥羽上皇は「詞は取ってもいいが心を取ってはいけない」と諌めたという。この歌はその成功例なのか?『新古今』の詞の類想的詞が生まれてくるのもこの時期からだった。「虫の音」と「松風」、「白露」と「とこなつの花」など。「袖」と「涙」とか美的象徴性を現しているのか?だから正岡子規は「新古今集」をけなしてストレートな感情を詠む「万葉集」を褒め称えたのだ。新古典主義というような。
「心を含めた場合」
八重にほふ軒ばのさくらうつろひぬ風よりさきにとふ人もがな 式子内親王『新古今・春下』
(本歌)
宮人に行きてかたらむ山桜かぜよりさきに来てもみるべく
光源氏『源氏物語 若菜』
秋の露やたもとにいたく結ぶらむ長き夜あかず宿る月影 後鳥羽院『新古今・秋上』
(本歌)
鈴虫の声かぎりを尽くしても長き夜あかずふる涙かな 『源氏物語 桐壺』
藤原定家が本歌取りに対して「わが身をみな業平になして詠む」と言ったが、これは本歌から自立した上で業平を『伊勢物語』から別世界の和歌へ住まわせることを意味している。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
