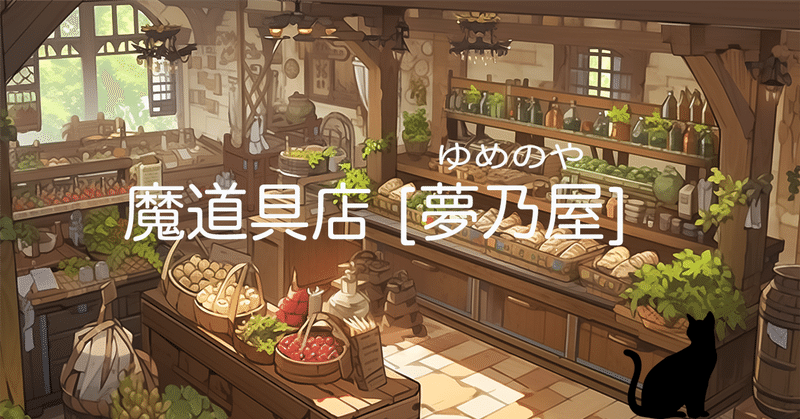
No,7「言霊の壺」(前編)
魔道具店夢乃屋、営業三日目。
この日は朝から少し曇っていた。
天気予報によると、このあと次第に下り坂となり、週末には雨が降るらしい。
「明日とあさっては雨か。買い物、面倒だなぁ」
冷蔵庫の中の食材を思い返しながら数日分の献立を考える。
「よし、今夜はクリームシチューにしよう。まだ鶏肉が残ってるし」
私は朝食で使った皿を片づけると、そのまま野菜を切り始めた。
ジャガイモ、ニンジン、玉ねぎ。ブロッコリーも入れよう。鶏肉はひと口大に切って、まずは鍋で軽く炒める。ブロッコリー以外の野菜も入れて、全体にある程度火を通したら水を注ぎ、灰汁を取りながらしばらく煮込む。
適当なところで一旦火を止めて、下茹でしたブロッコリーと市販のルゥと牛乳を追加したら、もう一度軽く煮込んで、はい出来上がり。簡単なのにあったか美味しいシチューは冷凍保存も可能だし、次の日にアレンジして消費することもできるから、とってもありがたい一品だ。
キッチンに漂う匂いを嗅いで、クロがしっぽを揺らしている。
「いい匂いだね」
「でしょ? これで明日は買い物に行かなくて済むよ」
仕事終わりの夕飯も温め直せばすぐ食べられる。
「煮込み料理、最強」
私はご機嫌で開店準備を始めた。
「いらっしゃ……」
だんだん慣れてはきたものの、店のドアベルが鳴る度にまだ緊張が走る。
「待って待って」
「ホントに入るのぉ!?」
けれども、その日の夕方、賑やかなおしゃべりと共に入ってきた客たちのようすに、私は緊張よりも戸惑いを感じて、挨拶の言葉を最後まで口にすることができなかった。
「へぇ、中はこんな感じなんだぁ」
「なんか映画のセットみたいだね。魔法使いとか出てきそう」
「それよりジブリっぽくない?」
「外から見てもなんのお店か全然わかんなかったもんね」
「…………」
入ってきたのは五名。全員、近所の高校の制服を着た女子生徒だ。
この店は外観だけでなく内装も洒落た欧州風なので、修学旅行でUSJに遊びにきた学生がショップではしゃいでいるような感じになるのは、まぁ無理もないかもしれない。ごく普通の現代人ならば。
(……あ、ヤバいかも)
咄嗟にそう思った。
この店の顧客は、ほとんどが見知らぬよその世界から訪れる人々だ。稀に、この世界に紛れて暮らしている術者や魔物の来訪もある(確かにそれっぽい人もいた)ようだけど、店主になる前の私みたいなごく普通の社会人や学生が間違って入ってくることはまずないのだという。
「大抵の一般人は無意識にここを敬遠するんだ。得体の知れない胡散臭さを感じるみたいだね」と初日の夜、クロが言っていた。きっと本能が何かを察知して回避するのだろう。それで大正解だ。
また、たとえ好奇心に駆られて入ろうとしても、ある程度魔力がないと営業時間内であってもここの扉は開けられないらしい。店主である私以外は。
ということは、つまり。
この五人の学生たちの中に少なくとも誰か一人、強い魔力を持っている子がいるか、あるいは人に交ざってこの世界で暮らしている魔物か術者が含まれているということだ。
(つっても紛れて住み着いてるタイプだったら、わざわざ他の人間と一緒に入ってこないだろうし)
――――おそらくこの中に、強い魔力を保持している子がいる。自覚のないままに。
「もしも、そういうお客さんが来たら注意して」
引継ぎの時間がほとんどなかったせいで、開店前に教えてもらったのは金銭や商品の受け渡し方法ぐらいで、その他の細かい注意事項は聞かされてなかったんだけど、初日の営業を無事に終えたあと、これだけは覚えておいてとクロに言われたのだ。いつもより強い口調で。
店の主として必要なことだから、と。
「どうして?」
「昼間、話したでしょ。普通の人間の方が天界や魔界の影響を受けやすいって」
「ああ……うん」
伯爵が来店したあと、確かにそんな話を聞いた。
『鋭敏な感覚の持ち主は無意識にそれをキャッチしていたりするし、欲望や嫉妬、疑念、不安などが小さな魔を呼び寄せたりもする』と。
「つまり影響を強く受けている人だから用心しろってこと?」
「まぁ、そうだね」
クロは考えを巡らせながら言葉を継いだ。
「例えば……琴音は丑の刻参りって知ってる?」
「知ってるよ。夜中に神社までこっそり出かけて藁人形にでっかい釘を刺すやつでしょ? テレビで見たことがある。実際にやってたかどうかは知らないけど」
「昔から人型の依り代を使って呪詛を行うのは、わりとポピュラーな方法だよ」
「マジか……」
「邪念、怨念、欲望。負の感情に取り憑かれた人間がそういう儀式を行うことで『魔』の力を引き寄せていたんだ」
「魔の力……」
「魔力があるって聞くと、琴音たちは童話やファンタジーの書物に出てくるような華々しくてかっこいい魔法使いが放つものをイメージするかもしれない。実際あれができる世界の人たちもいるし、ボクらのお客さんは大半がそういう人たちだしね」
でも、とクロの眼差しが鋭さを増す。
「琴音がいるこの世界は違うよね。生まれたときから魔力操作の訓練を受けているわけでもない。そもそもどういうものが魔力か実感として、知識として知ることもない。なのに、しっかり影響は受けてしまう。特にマイナスの力を」
「怒りとか、恨みとか……?」
「そういう感情の方が強いでしょ。この世界の一般人が引き寄せる魔力は、正よりも負の力の方が圧倒的に強い。ちなみに正の力とは祈りみたいなものだね。お百度参りとか」
「はぁ、なるほど」
「効力はすごく弱いけど、神社に参拝したり厄除祈禱してもらったりっていうのもそれに含まれるかな」
「へぇ……」
理屈はなんとなく分かったけど、それが店主として注意すべきこととどう関係するのか、今いちピンとこない。結局、何をどう注意すればいいんだろうと内心首を傾げていると、ピンとこないって顔してるね、とクロに嘆息されてしまった。
「じゃあ具体的に言おうか。この近所に生まれつき他の人間より強い魔力を持っている人が住んでいたとする。こっちの世界で言うと、霊感が強いとか霊力があるとか言われるようなタイプの人だね。その人が何かをきっかけにして負の力を増大させてしまい、誰かを呪ったとする。元々の力が余程強かったり恨みが深い場合は、それだけでも多少効力はあるだろうけど、修行や訓練を受けてない人が作った藁人形を使ったところで、そこそこの影響しか出ない」
「そこそこは出るんだ」
「まぁ時と場合、相手にもよるけど」
どちらかというと呪詛をかける側の負担の方が大きいかな。人を呪わば穴二つ、負のパワーは自分にも跳ね返ってくるから、といつもより大人びた口調でクロが言葉を重ねる。
「でもね、そんな人物がこの店の魔道具を使ったらどうなると思う?」
「あ…………」
この世界の人ではない誰かが、人ではないもののために造った魔道具。
それが、この店の商品。
『力だけあっても、使い方を知らないと意味がない』とも言われたっけ。
意味がないだけならまだいい。
「……とんでもないことが起こる可能性がある、ね」
ようやく私も腑に落ちた。
「選ぶ道具にもよるだろうけど、正しい使い方を知らないまま負の力を注ぎ続けたら破滅のリスクが高くなる。本人はもちろん、その周囲も」
意図せず、無自覚なままに。
世界を巻き込む災厄を生んでしまう可能性だってあるかもしれない。
「要するに、うちの商品が魔道具だってことをきちんと理解していないお客さんには売っちゃダメってことだね」
そういうこと、と黒い頭が頷いた。
「強い力を得られる道具は諸刃の剣、きちんと扱える者だけがそれを手にする資格を持つんだ」
(責任重大じゃん……)
その夜、クロの言葉を私は胸に刻んだ。
「すみませーん」
ワイワイとはしゃぎながら棚の商品を物色していた女子高生の一人がカウンターにいる私を呼んだ。
「あのぉ~、これっていくらですか?」
長い巻き髪の子が指差していたのは、表面に埋め込まれた石によって美しい装飾が施されている蓋付きの小さな(手のひらサイズくらいの)壺だった。
よりによって言霊の壺かぁ…………
「えーっ、レナそんな物欲しいの?」
「だってぇ、きれいじゃん? キャンディとか入れて置いといたら可愛くない?」
まぁ本当に飴とかお菓子だけ入れておくなら別に問題ないんだけど。
「そちらは35万円になります」
「え、高っっっっっ! マジで!? 高っっっ!」
「買う人いるの?」
いるんですよねぇ、これが。
「じゃあさ、こっちの人形は?」
次に指さしたのはドールだ。こちらも小さいサイズで、リカちゃん人形よりひと回り大きい程度。でもお値段はそこそこ。
「こちらは50万円ですね」
「うっそ、超高級品ばっかりじゃん」
「マジで~!?」
このとき巻き髪の子と、その隣にいたショートボブの子が軽く目配せをしたのを私は見逃さなかった。
「あ、じゃあ店員さん、あっちに飾ってあるリースとかもすごく高いの?」
今度はショートボブの子が棚の反対側の壁に私を引っ張っていく。
(これは……ひょっとして……)
移動しながらも私は後方にいる他の子たちの動きを気にしていた。リースの値段を答えながら、チラリと後ろを振り返る。すると今度は壁側に設置されている棚の下段を指して、値段を訊かれた。要するに視線を逸らしたいのだろう。
(あー、やる気だな)
まったく、魔道具を万引きしようだなんて。
そのとき後方で(つまりレナって子がいる棚の方で)クロの鳴き声が響いた。
「ニャア!」
さすがに人間の言葉じゃなくて、ちゃんと猫の鳴き声だ。
でも私には何を言っているのか分かる。あの子たちを叱っているのだ。
「残念ながら、この店にはあなたたちが買える商品はないと思いますよ。常連さん以外にお渡しできる品はほとんど置いておりません。冷やかしはお断りですので、どうぞお引き取りください」
最初に隣の子を見て、次に棚越しに立つ他の子たちにも視線をやりながら、よく通るように腹からしっかり声を出して、そう伝えた。この子たちを危険から守るために。
隣に立つ女子高生は一瞬、忌々しそうに面を歪めたけれど、すぐにわざとらしい笑みを張りつかせて「やだ、こわーい」とケラケラ笑った。
「なに、このババア。超失礼!」
「すっごいこと言うねぇ」
「猫までこっち睨んでるし。シッシッ、あっち行ってよ!」
「やな店。もう帰ろ、帰ろ~っ」
捨て台詞を残し、入ってきたときと同様にドヤドヤと足音を立てて女子高生たちが店から出ていく。ところが、最後の一人が出ていこうとした瞬間に、バタンと大きな音を立てて扉が閉まった。
(あ、捕まっちゃったか)
「えっ!?」
逃げ損ねた子がびっくりして棒立ちになっている。そりゃそうだ、自動ドアでもない木製の扉が勝手に閉まっちゃったんだから。
「え……ちょっと、なに?」
取り残された子が慌てて扉を開けようとしてるけど、ガチャガチャとノブが鳴るだけで一向にドアは開かない。
なるほど。お会計を済まさずに持ち出そうとすると、こうなるのか。
「ねぇ、開けてよ! 開けてってば! レナ! リオ!?」
ついにはドンドンと拳でドアを叩き始めた。
扉は内開きだから先に出た子が閉めたわけじゃないんだけど、驚きと焦りでそう思っているのかもしれない。
(あるいは……いつも面白半分にやられているのかな)
「そこ、鍵はかかってないよ」
私は彼女の後ろから静かに声をかけた。
胸元あたりまで伸びた黒髪ストレートの子が怯えた表情で振り返る。
「……開けてください。ここから出して」
「隠しているものを返してくれたらね。何か持ってるんでしょ」
「なんのことですかっ!? 言い掛かりは止めてください!」
カバンをぎゅっと抱きかかえて、そのセリフ言いますか。
「万引きは窃盗罪、れっきとした犯罪だよ」
「警察を呼ぶの?」
「ううん、呼ばない。万引きで検挙してもらうには、店を出てから捕まえないといけない決まりだしね」
「……だったらもう帰っていいでしょ」
おお、露骨にホッとしたね。でも残念。
「それは無理。あなたのためには警察に来てもらった方が断然いいと思うんだけど」
「ハッ、お説教!? 何様のつもりよ」
「そうじゃなくて…………実はこのあと、どうなっちゃうのか私にもよく分からないのよ」
「は!?」
「無事に帰してあげられるといいんだけど」
「えっ……嘘」
途端に青ざめた彼女に、違うよ、と慌てて手を振る。
「奥から怖い人が出てくる的なことじゃなくって」
うちの店、反社とのつながりはないから。悪魔や魔物とのつながりはあるけど。
「ただ、さっきも言った通り、今その扉には鍵がかかってないのよ。もちろん自動ドアでもない。でもあなたの目の前で勝手に閉まったでしょ。だから……このままだとずっと出られないんじゃないかと思うの」
「ど、どういう……こと?」
あ、ホラー映画に出てくるキャラみたいな表情になった。
ですよねぇ。私もほぼほぼそれに近い展開しか予想できないから、すごく不安。
「ねぇ、この子、どうなるの?」
すると猫が人語で答える前に、再びバタンと音を立てて、目の前の扉が開いた。
咄嗟に女の子が店の外に逃げ出そうとしたんだけど――――
「ひっ!」
ドアの向こう側の光景があまりにもインパクトありすぎたせいで、大きく後ろに飛びすさると、そのままぺたんと腰を抜かしてしまった。そして、退がった拍子に勢いよくしがみつかれた私も、同時に床に膝をついた。
「うげっ……」
今このドアとつながっているのは、いったいどこの世界なのだろう。薄暗く、おどろおどろしい感じに荒廃した景色の中、明らかに人間じゃない、というかどう見てもデーモンっぽいやつが立っていて、ガツガツと何かを貪り喰っている。
(き、気色わる~~~~~~~~~~!!!!!)
総毛立ち、硬直している私たちの視線に気づいたのか、デーモンもどきがふとおもむろに振り返った。大きく裂けた口元からは、まだ咀嚼されていない何かの足がぶらーんと垂れ下がっているのが見える。
「ひいぃっ!」
思わず女子高生ちゃんと二人、ひしっと抱き合って悲鳴を上げてしまった。怖すぎる。エグすぎる。刺激強すぎ。
(もういいから!)
私の心の声が届いたのか否か、ここでまた勝手にバタンと扉が閉じた。まったく、脅しにしたって限度があるでしょ。私まで一緒に心臓煽っちゃって、心拍数爆上がりだわ。
「あ……あれ……」
ガクガク震えながらしがみついてくる女子高生はまだ顔面蒼白。
(あ、涙目。ってか、泣いてる…………うん、泣くよね)
あまりの狼狽ぶりに、背中をそっと擦りながら思わず尋ねた。
「だいじょぶ?」
いやまぁ、大丈夫なわけないんだけど。
「…………」
ストレートヘアーを揺らしながら、彼女の頭がふるふると力なく横に揺れる。そして――――そのまま、がくりと力なく頽れ、私の肩にもたれかかってきた。
「あらま」
極度の緊張が緩んで、意識が飛んだのだろう。
その様子を見て、クロが近づいてくる。
「死んじゃった?」
「こらこら、縁起でもないこと言うの止めなさい」
意識を失くした人間の身体はすごく重たい。
床に倒れそうな女子高生の身体を支えながら、さて、どうしたものかと思案しつつ目を泳がせていると、床に転がっている彼女の鞄からはみ出しているドールに気づいた。
「あー、やっぱり……」
高額だと知って、ネットで転売でもするつもりだったんだろう。ギリギリで阻止できたのは僥倖だと安堵しかけたのに、残念ながらこれで事態が終わったわけではなかった。
鞄に小さな頭を突っ込んでゴソゴソと探っていた黒猫が、一つ足りないね、とつぶやいたのだ。
「言霊の壺も棚から盗ってたんだ。二つともこの子が持ってると思ったんだけど、おそらく壺だけはあのレナって子が持ち去ったんだと思う」
「えっ!? 嘘、盗られちゃったの?」
自動防犯システム完備だと思ってたのに。
「じゃあなんでこの子だけ……?」
「おそらく一番魔力が高かったからだよ」
ん? どゆこと???
「入ってきたメンツの中で明らかに魔力が高かったのはこの子と、あのレナって子の二人。でもレナの方が魔力を欲する気配が濃厚だった。そのせいで、あの壺を見た瞬間に魅入られてしまったんだろうね。この店が普通じゃないって認識はなかったと思うけど、彼女の中の何かが察知したんじゃないかな。警戒心が働いたというか。だからボクを蹴散らしたあと、壺だけ持って逃げたんだ。自分よりも魔力の高いこの子をわざと置き去りにして」
「わざと?」
「おそらく。店の扉は魔力に反応するからね」
「えー、そんな方法有りなの?」
「初めてのケースかな。この世界の人間で魔力の高い人物が同時に入ってくることなんて滅多にないから、うっかり突破されちゃったのかも」
「そんな……」
うっかりなんて言ってる場合じゃない。これは一大事だ。
何しろこの店の商品はこの世に出回ってはいけない代物なのだから。
「…………どうしよう」
とにもかくにも万引犯を取り逃がしたのは事実だし。
私は店主失格かもしれない。
「初日に言われて、充分注意してたつもりだったのに」
一瞬で地の底までずどーんと落ち込んだ私を、まぁまぁとクロが宥めてくれた。
「まずはその子を二階に運ぼう。対策を考えるのはそれからだよ」
「そ、そうだね」
冷静にならなくちゃ。
このまま床に寝かせておくわけにもいかないし。
とはいえ、たとえ相手が痩せてる女子高生でも、二階まで運ぶのはかなりの重労働になりそうだ。
「おんぶすれば……いけるかな?」
よし、と覚悟を決めて背負う体勢を取ろうとしたところで、天の助けが入った。
「いいよ、ボクが運ぶから」
横から伸びてきた腕が女子高生の身体をスッと抱き起し、軽々と持ち上げる。
(おお、ありがたい!)
これが世に言うお姫様抱っこか。
私は内心でパチパチと拍手を送った。
男の子がいると、こういうとき助かるよねぇ。
(――――猫だけど)
ええ、ここですぐ我に返りましたよ。
私の他にこの店にいるのは猫。人語を話すけど、猫のはず。
なのに。
困惑しつつ見上げると、すらっとした見目麗しい十代後半の青年が、気を失っている万引き少女を両腕で抱えて立っていた。
「…………誰!?」
思わず平たい目になっちゃったよ。
たぶん顔中に「怪訝」って書いてある、今。
「やだな、分かんないの?」
いや、分かるよ。他に誰もいないから分かるけどね。
心外そうに答えた声は猫のときとほとんど変わっていないから、ますます混乱するわ。
「人間になれるなんて聞いてない」
「うん、これまでは必要なかったから」
「なれるなら、いつもその姿でいればいいのに」
「嫌だよ、面倒臭いし疲れる」
「さいですか」
まぁ人語を話せるんだから、姿が人間になったところでさほど驚くことでもないか。
「じゃあ一旦休憩しよう。紅茶を淹れるよ」
「クッキーもつけて」
「了解」
私たちは二階へ上がった。
他のお客さんが来るまで、お茶で喉を潤しつつ作戦会議である。
よろしければサポートお願いいたします。いただいたサポートはありがたくリラックスタイムのコーヒーに使わせていただき、今後も創作活動を頑張る原動力といたします。

