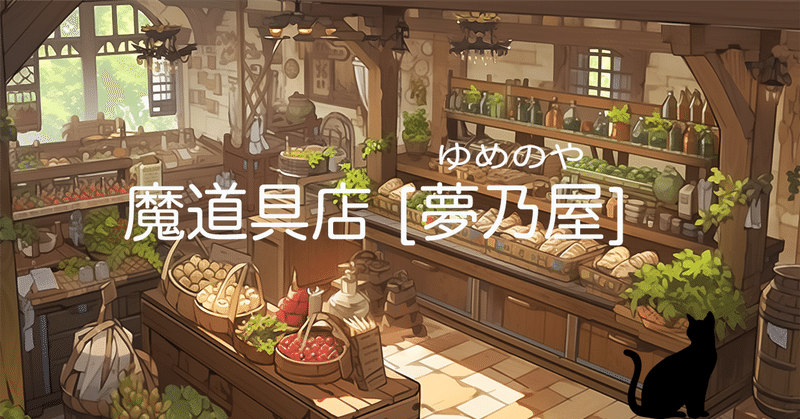
No,8「言霊の壺」(後編)
「あ、目が覚めた? 気分はどう?」
ソファの上でゆっくりと身を起こした少女に、向かいの席から私は声をかけた。
「…………」
彼女はまだ半分夢の中にいるみたいで、ぼんやりと部屋の壁や天井を眺めている。二階は私の住居スペースだから、いきなり見ず知らずの他人の家で目覚めたら、そりゃ不思議な気分だよね。
「ちょうど今、お茶を淹れ直しているところなの。よかったら一緒にどうぞ。クッキーもあるよ」
「あ、あの……?」
「それから、これは返してもらうね」
戸惑う彼女に、私はテーブルの上を指し示した。紅茶のポットとお揃いの花柄のティーカップ、シュガーポット、ミルクピッチャー。そしてアーモンドクッキーが載ったお皿が並んでいる横に、ちょこんと座らされているドールを。
「……ぁ」
途端に夢から醒めたようで、一瞬で青ざめ、表情を強張らせたあと、彼女はぎくしゃくとソファから立ち上がって頭を下げた。
「す、すみません……でした」
万引をして止められたことを思い出せば、当然そのあとの出来事も脳裏に甦ってくる。たちまち全身を縮ませて周囲を警戒しだした彼女に、私はなるべく自然を装った軽い調子で言葉を紡いだ。
「もともと警察を呼ぶつもりはなかったから店を出る前に声をかけたんだけど、一人だけ取り残されて相当ショックだったんだね。突然店内で倒れちゃったから心配したわ」
「……え!?」
「覚えてない?」
「は、はい……だって、あの…………」
突然ドアが勝手に閉じたり開いたりした挙句、その向こうにバケモノが出てきたんで気を失いましたとは主張しづらいよねぇ。
「そのあと何か悪い夢でも見てるみたいにうなされてたから、よっぽど心身に疲労が溜まってるのかなって思ったんだけど」
「…………夢?」
「うん」
「……………………あれは、夢?」
そう、夢です。あなたは悪い夢を見たのです。
そういうことにしておきましょう。
「…………はぁ」
たぶん頭では納得いっていないんだろうけど、なんとなく自分のためにもここは吞み込んでおいた方がいいと察したようで、曖昧に頷いている。
ちょうどそこにタイミングよく、クロが淹れたての紅茶を運んできた。
「はい、どうぞ。召し上がれ」
リボンタイの白シャツに黒のパンツとベスト。まるで少女漫画に出てくるキャラのような出で立ちでお茶を給仕をしてくれる少年(いや、青年?)が、まさか猫だとは思うまい。
「あ、ありがとう……ございます」
まだ相当緊張している様子だけど、それでも彼女はクロを見てわずかに頬を染め、ペコリと頭を下げた。よしよし、イケメン効果は絶大だね。
ちなみにクロは彼女を二階に運んだあと、また猫に戻ろうとしたんだけど、彼女の前で話せなくなるから、もうしばらく人の姿のままでいてくれと私が頼んだのだ。
「今日はカモミールティーにしてみたの。嫌いじゃないといいんだけど」
ハーブのやさしい香りがテーブルの周りを包んでいる。
「あ、砂糖とミルクはご自由にどうぞ」
そう勧めながらも私自身はストレートティーのまま口をつけると、彼女も倣うようにカップを手にして、おずおずと飲み始めた。
「……おいしい、です」
「よかった」
なんと、うちの猫は紅茶まで美味しく淹れられるのです。凄いね。
(ありがたや)
温かいお茶で喉を潤しながら、ほくほくとクッキーの皿にも手を伸ばす。
「ん~っ、やっぱりこのアーモンドクッキー美味しい!」
すると、すかさずクロから横やりが入った。
「ちょっと食べ過ぎじゃない、琴音」
「そんなことないよ。まだ三枚目だし」
「嘘ばっかり。もう五枚ぐらい食べてるでしょ」
「バレたか。だってこれホントに美味しいんだもん。仕方ないよね」
「まぁ、ボクも好きだけど」
この店に来るまでは普通の猫を装っていたくせに、ここに来てからというものクロは普段からチョコレートもアーモンドも平気で食べている。というより猫用カリカリなど目もくれず、人間の私とまったく同じものをいつも食べているのだ。もしかすると、この世界にいるための姿形が猫というだけなのかもしれない。クロの出身がどこの世界か知らないけど。
そんなクロと私のいつものくだらない会話に少し気が緩んだのか、はたまた美味しい紅茶のおかげか、目の前の女子高生もようやく緊張が解けたようで、落ち着いた様子で改めて頭を下げた。
「本当にすみませんでした。ご迷惑をおかけしました」
「うん、いいよ」
頭を上げて、と促す。
分かってるから、と。
「盗ってこいって言われたんでしょ、仲間に」
「……はい」
彼女は高瀬結(たかせゆい)と名乗った。高台にある、そこそこ有名な進学校の二年生らしい。一緒に店に入ってきた四人全員が同じクラスで、だいたいいつも一緒にいるメンツだそうだ。
「リーダー格は最初に話しかけてきたレナって子かな?」
はい、と小さな声で答えたあと、結ちゃんは意を決した様子で再び口を開いた。
「そ、それで玲菜……彼女、その人形だけじゃなくて……」
「うん。壺を持って行っちゃったみたいだね」
「…………」
あ、それも分かってるんだ、と顔に書いてある。
素直な子だな。
「最初は玲菜に言われて、二つとも私が棚から取ったんですけど」
猫を追い払ったあと、壺だけつかんで玲菜が出入り口の方に向かったので慌てて追いかけたら、扉の手前で急に振り向いた彼女に思いきり肩を突き飛ばされて、思わずその場で立ち止まってしまったのだという。
「なんでって思ってる間にみんなは外に出ちゃうし、急にドアが閉まっちゃって……」
「なるほど。それでショックを受けてたのね」
寝起きの嘘と上手く繋がっちゃったな。
「ねぇ結ちゃん、答えにくいだろうけど……いじめられてるよね」
「…………」
無言のまま唇を噛んで俯く彼女の髪が、さらりと肩から流れ落ちた。
「今回みたいなことは初めて? 前にもやらされたことある?」
「…………駅前の……本屋さんとか、コンビニで」
「そう」
捕まっていなくともおそらく目は付けられているだろうから、回数を重ねればいずれは補導されることになるだろう。強要されたと訴えても、直接手を出していない他の連中は知らぬ存ぜぬでシラを切り通して終わりだ。
「誰かに相談しても無駄だった?」
「玲菜も莉生も成績いいから」
「……あー」
リオってのはショートボブの子かな。
進学校だしね。成績だけでしか生徒のこと見ない先生もいるよね。そもそもいじめを訴え出た生徒にきちんと対応してくれるクラス担任って、いったいどれくらいいるんだろう。大人の社会でさえ、いまどきセクハラパワハラ厳禁ですよと口では唱えて、わざわざ研修までするくせに、実例は山ほどある。
『気にしすぎじゃない? 本人も笑ってたじゃん』
『あの程度、単なるコミュニケーションでしょ』
『自意識過剰だな。くだらないことで空気乱すなよ』
周囲の心無い追従のせいで、いじめやセクハラ、パワハラはいつまで経ってもなくならない。苦しい思いをするのも損するのもターゲットにされた被害者だけ。
「親御さんは?」
「うち、父親しかいなくて……」
「そっか」
仕事で忙しい働き盛りの父親が、娘からのささやかなサインに気づくのは難しいかもしれない。仮に相談したとしても、説教されて終わるパターンだってある。言いなりになって万引きするなんて情けない、恥ずかしいことをするなと叱られてしまったら、もう二度と誰にも助けを求められなくなってしまう。
(……厄介だねぇ)
私は思わず天を仰ぎ、深々とため息をついた。
自分の周りを囲んでいる圧力という壁がじわじわと押し迫ってきて、身動きが取れず、息苦しさが増していく日々の中で――――もしも誰かが、ちっぽけな小石ほどでいいから何か一言でも投げかけてくれたら、この状況が変わるんじゃないか。そんな淡い期待すらだんだんと削り取られていく絶望を、私は知っている。
(どこにも味方がいない。何よりそれが一番苦しい)
まぁ、だからと言って、家族でも友人でもない一介の魔道具店主ができることなんて、たかが知れてるんですけど。
「えーと、レナちゃんって子……」
「新堂玲菜です」
「うん、その子のこと、もう少し詳しく教えてくれる?」
「……小学校の頃までは結構仲がよかったんです」
「幼馴染みなの?」
「はい。ずっと同じ学校でした」
「じゃあ今みたいな関係になったのは最近?」
「中学では同じクラスになったことなくて。久しぶりに会ったら、いつの間にか雰囲気が変わってました」
「ふーん……」
思春期につまづくのは、ままあることだ。
「彼女のおうちはどんな感じかな。ご家族がどんなお仕事をしてるか知ってる?」
「お父さんは財務省の偉い人で、お母さんも外国の大学を出て外資系の会社に勤めてたって聞きました。だから二人とも勉強のこととか、すごく厳しいみたいで。お母さんには何度か会ったことあるけど、ちょっと怖い感じでした。お兄さんは今、京都の大学に通ってるらしいです」
「絵に描いたようなエリート一家だね」
そりゃあストレスも半端ないか。
「じゃあ最後に、彼女の家の場所も教えてもらえないかな」
「え……でも」
「壺を返してもらえるように、私たちから直接お願いしてみる。もちろんご家族にはナイショにするよ。他の誰にも言わない。約束する」
学校やPTAにお知らせするとチクったのなんだのと逆恨みされて、もっとひどい事態になりかねないし、親に知られるだけでもストレス爆上がりで結ちゃんへの八つ当たりはさらにエスカレートするだろう。そもそも当店の商品は世間様にあまり大々的にお披露目できる代物じゃないんだよね。
結ちゃんが持っていたドールは対象者の髪や爪を埋め込むことで、見た目が対象者そっくりになるという、いささか気味の悪い品だ。そのせいか憎悪も愛情も執着も注ぎやすく、未熟な術者でも扱いやすいので、影響力はさほど強くないにも関わらず人気が高い一品らしい。想像しただけで、まぁまぁ気持ちが悪い。
学校でいじめられている彼女が、もしもこれの使い方を知ってしまったら、どんな事態になるか推して知るべしだ。
新堂玲菜とい子が持ち去った言霊の壺はさらに厄介で、文字通り注ぎ込んだ言の葉を吸い込み、願いの強さや恨みの大きさに比例して叶えてしまう品らしい。もちろんその規模には限度があるし、リスクもある。願う者の命が削られるのだという。
だから、なんとしても早いうちに取り返さなくちゃならない。
「……本当ですか? 玲菜が素直に返すとは思えないんだけど」
不安そうな結ちゃんにクロが力強く答えた。
「大丈夫、ちゃんとこっちで手を打つから。信用して」
頼もしいね。
では、お手並み拝見といきますか。
――――言霊の壺、奪還作戦だ。
◆ ◆ ◆
その夜、いつも通り閉店作業を終えて二階に上がった私たちは、まず温め直したクリームシチューで腹ごしらえをした。
やっぱり美味しい。空きっ腹に溜まるし、温まる。煮込み料理最高。
「で、結局あの配送業者の人たちに頼んだんでしょ。本当に大丈夫なの?」
「前にも言ったけど、彼らは配送業者ってわけじゃないよ。確かに物を探したり、運んだりするのが得意な連中だけど」
猫に戻ったクロも私と同じものを食べながら(猫舌じゃないんかい)意味深なセリフを吐いた。
「それはなんとなく分かるけど、私にとっては引っ越しを手伝ってくれた配送業者さんなんだから、それでいいじゃない」
「はいはい」
「確かにあの人たちめちゃくちゃ手際よかったけど、さすがに今回はハードル高いんじゃない? おうちの人にバレないようにしなきゃいけないんだし」
「そうでもないさ」
今から数時間前。
結ちゃんが気を失っている間に、私とクロがまず考えたのは、どうやって壺を取り返すかということだった。交渉はおそらく無理。学校や警察はもちろん、親に話を持っていくのも難しい。なにせうちの商品は、不用意にこの世界の(魔力に対して無知な)人間の目に晒すわけにはいかない物ばかりだから。
「離れた場所から呪いをかける方法もあるけど、穏便に済ませたいならやっぱり本人の部屋から直接奪ってくるのが一番かな」
クロの提案はちっとも穏便じゃなかったけど、他に妙案も浮かばなかったので乗ることにした。ただ、彼女の家の場所がすぐに分かるかどうか、どんな建物に住んでいるかによって依頼する相手が変わってくると言われたので、まずは友人である結ちゃんから情報を聞き出すことにしたのだ。
その結果、彼女らはこの町から電車で三駅ほど離れた地区に住んでいることが分かった。結ちゃんはマンション住まいだけど、玲菜ちゃんの自宅は駅からほど近い一等地の戸建てだそうだ。ちなみに高層マンションに住んでいた場合はまた別のツテを使うつもりだったようだけど、そちらの正体も定かではない。
もちろん具体的な方法も私には教えてもらえなかった。
「あいつらは普通の住宅ならどこでも簡単に侵入できるから、難しくはないよ。それより問題は壺を取り返してきた、そのあとだ」
クロ曰く、魔道具に魅入られ、取り憑かれてしまった人間の執着というのは凄まじいものらしい。だから間違いなく奪い返しに来る。すぐにでも。クロはそう主張したのだ。
「普通の状態じゃないからね。もちろん話なんか通じない。怒り狂っていたとしたら、悪鬼の如き形相かも」
「ええぇ、それなんとかなるの?」
「力づくで制止することはできる。ただその場合、彼女が受けるダメージは結構でかい」
「そっか……」
難しいのは分かるけど、あんまりいい解決方法とは言い難いなぁ。
「それでもやらないよりマシだ。このまま放っておくわけにはいかないし、取り戻すなら一刻でも早い方がいい。でないと、あの子は衰弱して死んでしまうかもしれないから」
「……うん」
正論だ。でも、せめてもう少し何か手はないものか。
(こういうとき役に立ちそうな魔道具って何かないのかな)
壺を取り返しに行った配送業者たちが戻ってくるまで、まだ少し時間がありそうだ。
「ちょっと探してみるか」
私はカタログを持ってきて、ひたすらページを捲った。
「これは……違う、これもダメか…………う~ん」
具体的にイメージできているわけではないから、検索ワードが絞り込めず、効果のところを次々に飛ばし読みしていくしかない。捲っても捲っても関係なさそうな物ばかりで、さすがにそう都合のいい品物は見つからないかと諦めかけたとき。
「ん?」
とある商品が目に留まった。
「ねぇクロ、これ!」
私が指差した箇所を横からクロが覗き込む。
「……ふぅん。今日入荷したばかりの品だね」
「使えるんじゃない?」
「そうだね。やってみる価値はありそうだ」
かくして、ちょうど日付が変わる時刻(ころ)、準備を終えた私とクロは店で新堂玲菜が現れるのを待つことにしたのである。
これはドラマの怪談やホラー映画でよくあるやつだ。
得体の知れない何かが、だんだんと近づいてくる気配。建物の周辺を走り回っているような足音。そして、唐突にドンッと響き渡る大きな物音――――激しく叩かれるドアの扉。ガタガタと揺さぶられる窓。
夜半になって降り出した雨がさらに効果を盛り上げている。
「これマジでホラーじゃん……」
思わずカウンターの陰にしゃがみ込んで手を合わせていたら、再び人の姿になっていたクロに見下ろされ、何やってんのと冷たい声で呆れられてしまった。
いや、普通に怖いんですけど。
「でもま、そんなこと言ってる場合じゃないか」
彼女を救ってあげないと。
「よし、やろう!」
ゴクリと唾を飲み込んでから、大きく息を吸って立ち上がる。それを合図にクロが扉の前へと移動した。
「開けるよ」
把手を握っているクロに頷く。
彼が鍵を解除した途端、ドンと舞い込んでくる突風――――のような何か。
「返して! 私の壺を返してえぇぇぇ!」
ドアをぶち破るようにして侵入してきた新堂玲菜の金切り声が響き渡った。
昼間見た女子高生とはまったく別の何かになってしまった彼女は髪を逆立て、それこそ鬼のような形相だ。雨でびしょ濡れの姿がなおさら鬼気迫っていて恐ろしい。
「あなたが欲しいのはこれでしょ」
私は両手で包み込むようにして持っていた壺をカウンターの上に置いた。
(さぁ来い!)
壺に気づいた彼女がすぐさま飛びかかってくる。
「返せえええぇぇぇぇぇ!」
敢えて抵抗はしない。だから、あっという間に壺は奪い取られた。そのまま彼女は店を出て行こうとしたけれど、残念ながらそれは叶わなかった。
壺の蓋が外れたのだ。
「……あ!?」
蓋には私の髪の毛が一本結んであって、私の手首と繋がっていた。カウンター上から壺が持ち去られた瞬間、その蓋が外れて魔道具としての効果を見事に発揮したのである。
【浄化の壺:あらゆる怨念、邪気を吸い込んで結晶化する壺。姉妹品である言霊の壺とセットでご使用いただくと術者のリスク軽減に役立ち、大変効果的です】
「ああああああぁぁぁぁぁ…………!」
叫び声を上げ続ける彼女から怨霊の化身みたいな黒っぽい霧が出て、壺の中にぐんぐん吸い込まれていく。
数秒、いや、十数秒かかったかもしれない。
突然始まった恐怖の時間は唐突に終わりを告げ、ようやく店内に静寂が訪れた。
床にぺたんと座り込んでしまった新堂玲菜からさっきまでの禍々しい雰囲気はきれいさっぱり消え失せ、魂を抜かれたような放心状態に陥っている。
「まさに毒気を抜かれたってやつだね」
「これ……本当に大丈夫? 白目剥いてない? 精神崩壊とかになってないよね!?」
「それはないと思うよ。そこまで強力な道具じゃないから」
「ほんとに?」
目の前で手を振ってみてもノーリアクションなんだけど。
「まぁ今はショック状態だから、そっとしておこう。一晩寝たらきっと治るよ」
「だといいけど」
その言葉を信じるしかないか。
「でも、このままだと風邪引いちゃう」
「それも寝たら治る」
案外雑だな。
「じゃあ悪いけど、この子運んでくれる?」
クロがドアの方を振り返ってそう告げたのは、例の配送業者たちだった。気づけば見覚えのあるツナギを着た男たちが数人、入り口付近に立ってスタンバイしている。
「い、いつの間に……」
壺を置いて帰ったと思ってたのに。
「よろしく頼むね」
「かしこまりました」
「本当に何者なの……」
私のつぶやきを無視して、彼らは玲菜ちゃんの身体を軽々と抱え上げ、店の外へと運び出していく。
「え……ちょっと、荷物みたいに運ぶのは止めてあげて」
「いいから、いいから」
「いや、よくないでしょ。お巡りさんに止められるよ!」
「彼らに任せておけば大丈夫だって」
私の制止は完全にスルーされ、降りしきる雨の中、玲菜ちゃんと謎の業者たちの姿は闇の向こうへと消えていった。
(……絶対風邪引くよね、あれ。ごめん玲菜ちゃん……)
でもまぁ多少熱を出して寝込んだとしても、命が削られるよりはいい。誰かを恨んだり呪ったりしたまま、訳の分からない存在になってしまうより断然いい。
「……これでちゃんとカタがついたの?」
「たぶんね」
彼女が長年腹の底に溜め込んでいたであろう負の感情は、浄化の壺に吸い込まれ、商品説明に書いてあった通り黒い結晶となっていた。覗いてみると、キラキラした黒い粒が壺の中いっぱいに詰まっている。
「うわ、すごい」
「よかった。これで赤字にならずに済むかな」
「へ!?」
「一旦持ち去られた言霊の壺も、この浄化の壺も、商品としてもう一度店に出すにはメンテナンスが必要だからね。さっきの連中に支払う手間賃もかかる。必要経費だから売上分から差し引かれるけど、赤字は出さないに越したことないから」
「そうか……そうだよね」
万引のせいで潰れる店があるくらいだ。
注意事項を気にして彼女たちのことばっかり考えてたけど、店主なんだからコストや利益についてもちゃんと意識しないといけないんだな。
「この結晶はなかなかいい状態だから、これなら素材として売値がつくと思う。マイナスを補填できるよ」
「へぇ……」
吐き出した毒すらお金になるのか。不思議な感じだ。
「そういえばさっきの業者さんたちに、レプリカを渡していたのはどうしてなの?」
クロは玲菜ちゃんを運び出したツナギの男たちに、これも一緒にと浄化の壺のレプリカ品を渡していたのだ。あの壺を使うと決めてから急遽オーダーした模造品を。
驚くなかれ、この店は魔道具のオーダーや取り寄せまで受け付けているらしい。
もちろん普通の商品は取り寄せや完成にとても時間がかかるし、作成不可能な品もある。素材によってはお値段も高額だ。でも今回は形ばかりのレプリカだから安価だし、すぐに出来上がってきたみたい。にしても24時間受注オーケーなんて、カスタマーサービスばっちりだなぁ。
「高瀬結の場合と同じで、さっきの出来事の記憶は曖昧だろうけど、それでもまったく意識に残らないわけじゃない。自分がやったことが信じられなくて、不安と疑心暗鬼が膨らめば、いずれまた魔に取り憑かれる可能性もある。だからあれを彼女の部屋に戻しておくことにしたんだ」
魔力による影響がほとんどない安全な品。けれど見た目は元の品と変わらないから、彼女には見分けがつかない。
やがて目覚めた彼女はあの壺を見て、自分が友人を置き去りにしてまで万引きしてしまったことを思い出すだろう。今夜のことは熱にうなされている間に見た悪い夢としか思えないだろうけど、目の前に盗ってきた現物があれば、その事実からは逃げられない。
「……返しにきてくれるかな」
「そうだといいね」
もしも怖くなって壺をどこかに捨ててしまったとしても害はないから、結果としては店がレプリカ作製費の損失を被るだけで済む。でも、できることなら…………彼女が自分からあの品を持って謝りに来てくれることを願っている。
「あのレプリカは彼女のお小遣いでも買える額だから、買い取ってくれるのが一番ありがたいんだけど」
「さすがにそれは欲張りすぎでは」
「そんなことないよ。この世界の人って、結構壺好きでしょ?」
「どこの宗教団体の話してんの。壺好きな高校生なんていません」
「そうなの?」
「そうだよ」
「じゃあ、やっぱり返しに来るんじゃない?」
「そう願って待つとしますか」
私たちは笑いながら店のドアを施錠して、二階へと上がっていった。
制服姿の新堂玲菜が、高瀬結と連れ立って申し訳なさそうに店内に入ってきたのはそれから三日後、よく晴れた月曜の午後のことだった。
よろしければサポートお願いいたします。いただいたサポートはありがたくリラックスタイムのコーヒーに使わせていただき、今後も創作活動を頑張る原動力といたします。

