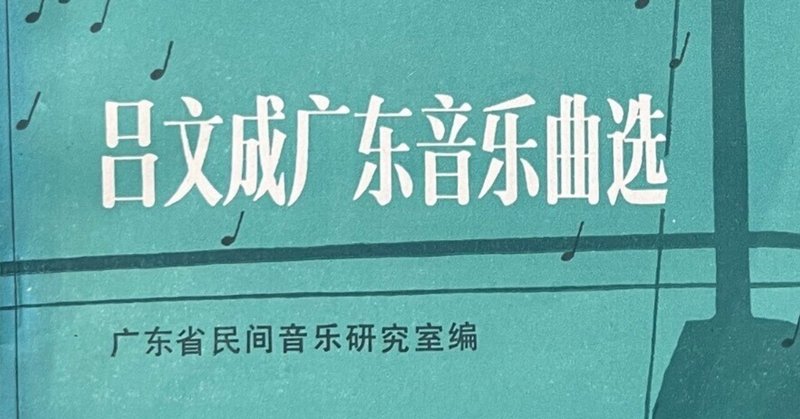
【全文無料公開中】中国音楽ちょこっと解説「廣東音樂」ってどんなヤツ!?
はじめに
「廣東音樂」という名前を聞いた事がありますか?
中国音楽のジャンル名です。ここをご覧の貴方は、何かのキッカケで「廣東音樂」を検索して辿り着いた方でしょうか?歡迎光臨!ようこそ、大歓迎です!願わくば、ここに貴方の知りたかった事が書いてあり「廣東音樂」に関する理解の手助けになれば幸いです。でも、なかなかひと口、ひとくくりに出来ないのが「廣東音樂」。「マニアック…否、専門的になり過ぎず、でもちゃんと説明したい」のせめぎ合いで書いた結果、まあまあ長くなってしまった原稿がこちらです。さて、早速ごく大雑把に言えば言葉通り「広東省広州市の珠江三角州辺りが発祥の音楽」と言えなくもないです。でも、よくよく調べてみるともう少し多層的で幅広い要素を含みます。追々説明しますが「廣東音樂」という名詞は幾つかの概念に跨って使われる場合があります。読み進んで行くと時々違う意味で使われているケースが出て来ますが、おいおい説明しますので頭の片隅に入れておいてください。一般的・慣用的には器楽合奏の一形態を指す事が多いです。
【この記事は全文を公開していますが、役に立ったり面白かったら、音楽活動サポートの投げ銭をどうぞよろしくお願いします!また、新規生徒さん随時募集中です。ホームページからお問い合わせください】
ところで私事ですが、私は子供時代、テレビでも映画館でも香港映画、特にジャッキー・チェンなどのカンフーアクションが大人気だった世代で、それを身近なエンターテイメントとして享受できた世代です。そして、各作品のBGMに使われていた曲を通して廣東音樂を知ったのが原体験です。皆さんもこの「将軍令」のメロディはなんとなく耳にした事があるのではないでしょうか?
後にそれらが「廣東音樂」だと知り、今に至ります。そして日本、ここ東京で一緒に楽しめる仲間が増える事を夢見て「扶桑粤樂社」という集いを作りました。また、同好の士が集まれるように東京都内で廣東音樂・文化が好きな人が集まれる「東京私伙局」というサロン活動を始めました。この先、1人でも多く興味を持ってくれる方が現れる事を願っています。この記事を読んだのも多生の縁。ぜひいつか遊びにいらしてください。
さてさて、ここでは情報が徐々に入って行くように並べてありますから、全く予備知識が無い方は頭から読んでみてはいかがでしょうか。既に色々とご存知の方は興味があるトピックに飛んでも構いません。なので、飛ばし読みの方を想定して同じ事柄の説明を繰り返している箇所もあります事をお断りしておきます。重ねて、読者の皆さんの中国音楽、そして廣東音樂の知識にプラスになれば幸いです。
さて、先程触れたように文字通り「広東」の「音楽」が「廣東音樂」ではありますが、広義の「広東音楽」の世界はとても幅広くて、私が実際に取り上げて研究実践している「カントン音楽」にはちょっと守備範囲や定義に微妙な誤差があります。では、順を追って紐解いて行きましょう。
広東ってどこ?
さて、「広東◯◯」といえば中華料理の数々を思い出す方が多いかもしれません。確かに皆さんご存知の「ワンタン」や「シュウマイ」「チャーシュー」などは広東語経由で定着した名前です。この「広東」は「嶺南」と呼ばれる「南嶺山脈」の南側に位置する、中央から遠く独特な言語風習風俗が色濃く息づいてるエリアです。広東はその一隅を成していて、最も早くからの開港である「広州」を擁して古くから西洋との接点を持ち、新しい物事を受容して来ました。そこに育まれた文化を「嶺南文化」と呼びます。広東のみならず潮州や客家といった独自の文化があるのも、この「嶺南」エリアです。この文化圏には「廣東音樂」の他、「潮州音樂」や「廣東客家漢樂」と言った無形文化財指定の合奏音楽があり、地理的にも社会階層的にも演奏母体が違っていてどれも独自の風格がありますけれど、部分的に楽器やレパートリーが近しいところがあり、お互いに密接な関係も認められて興味深いものがあります。
もっと古くまで遡れば、北ベトナムまでを含めた広い範囲を共有して大きな文化圏を形作っていました。否、今も文化は深く繋がっています(但し、概念としては含みますが、現在は中華人民共和国領土内のみを指し、独立国であるベトナム社会主義共和国北部を含まないのが一般的だそうです。特にベトナムの方と交流する機会がある時には失礼のないように心掛けて発言しましょう)実際にこの地の交流は今も深く、ある種の音階を共有していたり、中国から伝わった筝や琵琶、二弦などの楽器がベトナム独自の発展を遂げています。中国は日本の25倍の面積があります。日本でさえ北海道と沖縄では言葉から食文化まで大きく異なりますね。広大な中国では漢民族同士でも、言葉や習俗文化は大きく異なります。その差異の大きさを明らかにするためにも、地理を把握する事は非常に重要なので冒頭に字数を割きました。
どこで演奏されている音楽?
廣東音樂の分布地域は中国本土の広東省広州市を中心に、その流行地域であると共に歴史的に発達の重要な地域の一つでもある香港や、マカオ、シンガポール、マレーシア、その他カナダやアメリカなど広東系の華僑が多い世界中の広東語通用地域にまで及びます。
さらりと通り過ぎてしまいましたが「広東語」の話者が居住する地域に定着しているというところが示す通り、言語と音楽は不可分でとても重要な要素です。ですから私も、より良い理解のために普通話(共通語である現代漢語)のみならず広東語の勉強をずっと続けています。そしてこれからも続けて行きます(大好きです!)
広東語文化圏で流行している音楽とお伝えしましたが、広東音楽は清末民初に確立し始め、その後絶えず発展する中で五四運動以来の社会的な新文化運動の影響を受け、社会経済文化の発展に伴って元々生まれた広東の珠江三角州一帯の広東語通用地区以外の中国全土、そして上述の海外にも流行したという事ですから、すごい人気だったことが伺えます。今後日本でも認知度が高くなって愛好者が増えると良いなと思っています。貴方もいかがですか?まずは引き続き予備知識をご覧ください!
実は「廣東音樂」が指すものは幅広い
さて、分布エリアをざっくり頭に入れて頂いたところで、いよいよ私が扱う「廣東音樂」そのものに迫って行きましょう。「廣東音樂」は近年になってから生まれた呼び方らしく、元々「自称」ではなかった説も目にした事があります。以前は戯曲(広東語で演じられる地方劇「粤劇」の芝居伴奏音楽であるところの「粤曲」)に由来する物や、語り物である「南音」(福建の南音・南曲・南管とは違う物です)、琵琶曲などの古曲に由来するもの(器楽曲の事は「譜子」と呼びました)などなど、地元では個別の呼び方をしていた物を、後に一括りにまとめて「外の人たち」が「廣東の音樂」という事からひとまとめに「廣東音楽」と呼ぶ事になったようです。文字通りの「廣東の音楽」という呼び方に間違いはないですが、あまりにも範囲が広いというのはそういう事情からです。因みに現代では「粤曲」という呼び方に広東語で歌われる歌謡曲・流行歌も含む事がありますので、混同のないようにお気を付けください。
尚、廣東音樂は一地方の民間音楽でありながら、「雨打芭蕉」「歩歩高」「旱天雷」「彩雲追月」などの有名な曲は全国的に大変良く知られていて、二胡や笛子などの楽器の検定試験の課題曲やコンサートのレパートリーとして、または民族楽団のために編曲されて中国全土で好んで演奏される普遍性を獲得しています。
粤劇の例「琵琶行」。
中国各地にある「地方劇」の一つ。高胡がリードする伴奏がついて、歌唱は広東語の発音に基づいている(一部戯曲の場合は文言音になりますので、話し言葉と違う発音になっています)。楽隊の演奏を良く聴くと京劇の伴奏にはない、チェロの音や琵琶なども聴こえているのに気付かれると思います。
「南音」の例。広東の曲芸(語り物芸)。曾ては盲人の芸人らによって茶楼などで娯楽として鑑賞されていたが、現在は上演場所や継承者も少なく絶滅の危機に瀕している嶺南文化の一つ。思い返せば30年ほど前、香港の路上で見たことがありましたが、その時には全く知識がなかったので残念ながら素通りしてしまいました。弾き語りのスタイルではこの動画のように拍子を取る竹板、または秦琴や古箏が使われる事が多く、複数人の場合、伴奏に加わる楽器は椰胡や洞簫など人間の声域や音量を妨げない低めの楽器が多い印象です。
https://youtu.be/oJvwUMDObrw?si=C9LwY_gTvLU6Kbi-
そして、現代では一般的に廣東音樂という時に多くの人が指す民間器楽合奏の演奏例です。ここでは典型的な五架頭(5人編成のアンサンブルの事)による古曲「楊翠喜」の演奏をお聴き頂きます。リード楽器の高胡(粤胡)と揚琴は固定。あとのパートは互換性のある楽器、即ち洞簫(竹製の縦笛。尺八の親戚)は笛子(竹製の横笛)に、三弦は秦琴(低音担当の撥弦楽器)に、椰胡(胴体がヤシの実で桐板を張った円やかな音の擦弦楽器)は中胡(中音二胡)になど持ち替えられる事があります。因みに「楊翠喜」は実在したとても有名な妃女の名前です。
幾つか「廣東音樂」として示される可能性がある音楽を紹介しましたが、ここでは芝居の音楽や語り物ではなく、特に注意喚起をしない限り主に「高胡(=高音二胡、別称「粤胡」)」が主奏を務める比較的近現代寄りの器楽曲群「粤樂」を指すことにします(けれども実際にはお芝居の音楽という意味での「粤曲」と、ここで言う「廣東音樂」は切っても切れない関係があります。この「楊翠喜」も歌詞がついて劇中で歌われる事が度々あります。つまりレパートリーを共有している訳ですね。後述の見出し「廣東音樂のバリエーションとその周辺」でも取り上げています)
リード楽器「高胡(粤胡)」について
さて、今でこそ廣東音樂の花形を務める「高胡(粤胡)」ですが、それ自体の成立が、呂文成(祖籍が広東省中山の音楽家。上海に住んでいたが第一次上海事変の後に香港へ移住)が1920年代に「二胡」(現代の主な調弦D4・A4)を基に、当時一般的だった絹弦に代えてスチール弦を採用するなどして広東音楽に適する、より音域の高い楽器(主な調弦G4・D5)として開発した比較的新しい楽器です。音色は甲高いイメージを持たれている方が多いのですが、実は一般に目にする事が多い二胡奏者が持ち替えて弾けるように改良された高胡と広東高胡という大きく分けて2種類ありまして、それぞれ楽器も奏法も、そして音色もかなり違います。似て非なるものと言えるかも知れません。
さて、百聞は一見に如かず。私の師匠、香港の陳啓謙先生による高胡領奏で「雙聲恨(双声恨)」をお聴きください。特徴的な乙反調(ファが高めでシが低めの音階)の曲調も併せてお楽しみください。
※広東式の高胡は日本でなかなか手に入らないので、香港の師匠を通じてオーダーメイドして出来上がりを待っています。その到着を待ってこちらに画像など追加でアップする予定です。どうぞお楽しみに!(2023年10月16日)
因みに、動画でお気付きの通り広東の高胡は胴体を膝の間に挟んで弾くという独特な構えなので、あれこれと動画を見ていてもすぐに区別がつくと思います。なんとも「ねばり」がある音色で、改良高胡がアンサンブルの中で高音パートを担当している文字通りの「高音二胡」なのに比べると独奏楽器として、そもそものコンセブトが違う楽器なのだと感じてもらえるのではないかと思います。また、廣東音樂を弾く時の運弓や指遣い、装飾音やビブラートなどに関しても一般的な二胡の演奏とは違う独自の約束事が幾つもあります。余談ですが、我々が良く知っている二胡をCGの調弦に変えて「南胡」と呼んで合奏に加える事があります。15弦あるいは41弦で中音パートを演奏するという訳です。
ここでもう一曲、国家一級演奏家・教育家として高名な余其偉先生の高胡領奏による名曲「雨打芭蕉」をお聴きください(この5人編成を「五架頭」と呼びます。編成にはある程度の柔軟性があり、高胡と揚琴はたいてい固定されていますが、曲目などによって同じ役割を受け持つ楽器に変わることもあります。つまり、椰胡が中胡になったり、秦琴が三弦や中阮に持ち替えたり、笛子は洞簫に変わったりします)
お伝えしたように「新しい」改良楽器である「高胡(粤胡・軟弓)」が、花形の領奏(リード楽器)の編成自体が、そもそも比較的新しいという訳ですが、高胡が成立する以前から廣東音樂は存在していましたし、その初期には「二弦(硬弓)」という楽器で演奏されていた曲たちもたくさんありました。より一層自由闊達な雰囲気で、明らかに音色が違うため、今でも高胡ではなく「廣東二弦」で弾く事が好まれる曲(「娯楽昇平」など)があります。なお、潮州音楽の主奏楽器「二弦」や福建南曲で使う「二弦」など、同名で全く違う二本弦の擦弦楽器が複数あるので、区別のために廣東でもわざわざ「廣東二弦」と呼ぶ場合が多々あります。
これは「二胡」についても同じで、京劇の界隈で単に「二胡」と呼べば「京二胡」を指しますし、廣東音楽の界隈で「二胡」と呼んで「高胡」を指す事もあります。そういった事情から、いわゆる「二胡」をわざわざ「民楽の二胡」と呼んで混同を避ける事さえあります。
閑話休題「同名異曲」
もののついでに、中国音楽関係に興味がある方ににお伝えしたいのは、この楽器名の例のように、名前が同じで違う物を指している事が多々あるのでご注意頂きたいという事です。代表的なのが「曲名」です。いわゆる「同名異曲」が、それはそれはた〜くさんございます。例えば「陽関三畳」と言えば琴曲に由来して、それを二胡に移したり合唱曲にしたり…と十中八九同じ曲の延長線上にあるのですが、「高山流水」とか「漢宮秋月」などは、楽器ばかりかそもそも全く違う曲だったりします。他にも笛の人が話している独奏曲の「小放牛」と、京劇の人が言う演目としての「小放牛」、河北民謡の「小放牛」、果ては黎錦秀作曲の「小放牛」などはそれぞれ違うもの(でもお互い少し関係がある場合もあったりして余計にややこしい)。だから、文献でタイトルを見ても即座に「同じ曲」と判断しないで一度調べてみてください。
もとへ。
廣東音樂の編成の柔軟さ
先ほど高胡より古くから使われていると紹介した「二弦」の演奏例を紹介します。同じく余老師の領奏による硬弓五架頭の「娯楽昇平」です。そして二弦の女房役は椰胡ではなく「竹提琴」(左から2番目の弓奏楽器)と相場が決まっています。また、中低音楽器の秦琴や中阮の代わりに三弦が使われるのが典型なのも面白いところです。さあ、高胡がリードの「軟弓五架頭」とは違う味わいをお楽しみください。
そして、もう一つ廣東音楽の「融通無碍」な点は、曲や編成によってリード楽器が様々に取って代われるところです。ある程度「この曲はこの楽器が前面に出てるのが良い」という定番はあるものの、同じ曲でもリード楽器(これを指して「領奏」と言います)が取って代わる事が良く見られる「柔軟性の幅」は江南絲竹楽(こうなんしちくがく)」には見られないレベルで、とても興味深い事の一つです(江南絲竹は打楽器(板鼓)や笛子、二胡の音色、ニュアンスをアンサンブルのメンバー注意深く聴いて合わせますが、特定の楽器がリードを取るというよりは、各パート全体が渾然一体となったブレンドの妙を楽しむ音楽と言えると思います)個々の楽器の特性を活かした加花(装飾や変奏を一定のルール内で奏者が足したり引いたりする事)の自由闊達さは、同じ曲を聴いても(私は)飽きる事はなく、素晴らしいと思います。
それではここで、江南絲竹楽の八大名曲から「歓楽歌」をお届けします。廣東音樂との雰囲気の違いをお楽しみください。この曲は、呂文成らによって廣東にももたらされ、廣東音樂の語法で「お料理」されて演奏される事もあります。
番外。演奏者が少なく、通常の編成で見かける事はレアですが、広東独特のダブルリード楽器で篳篥(ひちりき)の仲間である「喉管」をご紹介しておきます。華北でよく見られる「管子」と違って長め(即ち低音が出る)を用いる事が多い(高音の物もあります)のと、先端に嗩吶(チャルメラ)の様にラッパ部が付いているのが特徴的です。時代劇の悲愴なシーンなどでこの音色が突如現れる事があるので少し気を付けて耳を傾けてみてください。私、この音色大好きなので推しております。ぜひ知って頂きたいのでございます!
時代変遷による廣東音樂のバリエーションと
さて、一通り廣東音樂の成り立ちや楽隊の構成などを見てきました。そして、演奏されて来たのは、粤劇の伴奏音楽や琵琶曲に由来するような、脈々と伝えられて来た古曲(明代以降清代くらいに遡れるもの)だった訳ですが、時代が下って録音技術の発達によるレコードやラジオ放送などの充実、ダンスホールの流行などに伴う怒涛の廣東音樂新曲ラッシュに乗った需要の中で、廣東音樂はやがてバイオリンやスチールギター、サックスからトランペット、フルート、ドラムセット、チェロ、バンジョーなどまで最新のスタイルとして編成に取り込むようになります。西洋楽器を混在させ、中国音楽の話法で自由自在に演奏する懐の広さを持った50年代から70年代にかけての比較的「新しい」もの(「精神音樂」というカテゴリーを成しています)まで、廣東音樂はスタイルも曲目も本当に変幻自在、唯一無二のジャンルです。さすがは香港・広州という西洋との接点が多いところで育まれた音楽。そして国際都市香港が磨きをかけた文化。さらに、後に作られた器楽曲もまた逆に、填詞(てんし。既にある曲に歌詞を当てはめること)されて粤劇の劇中で歌われるパターンも多々あります。まさに生きている音楽だった証拠ではないでしょうか。江南絲竹も崑曲との関係性を指摘する研究もありますが、粤楽と粤劇ほどの双方向性の密接な関係を見て取れません。江南絲竹楽との明確な違いの一つと言えるのではないでしょうか。ご専門の方にご教示賜りたいところです。
填詞の一例「春風得意」。梁以忠作曲の1930年代末の小曲。他にも「平湖秋月」や「禅院鐘声」などの填詞歌唱も良く耳にします。
洋楽の楽器やコンセプトも取り入れつつ、それでいて江南絲竹とは同じ伝統的な管弦のアンサンブル「絲竹」のジャンルであり、一部楽器の成り立ちやお互いの曲牌を共有するなど「兄弟」とも言える共通点・影響点がありながら、「廣東音楽」は独自に進取の気概に富んだ「伝統音楽」と言えましょう。
以下に、精神音楽の演奏例を貼っておきます。テナーサックスやバイオリン、ドラムセットやシロホン、スチールギターなどが混在しています。廣東音樂にはCやGの曲が多いので、開放弦を使う演奏上の利便性に基づいて一般的にGDAEに調律するバイオリンを全音下げのFCGDというチューニングで演奏する人も珍しくなかったそうです。琵琶などについてもADEaのところGCDgにしている人もいるそうです。この柔軟性がとても面白く興味深いと思います。このように西洋楽器で奏でられる「伝統」音樂が、ダンスホールを満たした若者たちを夢中にしていた時代にノスタルジアを感じるのは私だけでしょうか。
廣東音樂の現在とこれから、そして日本でも…!
そんな「廣東音楽」も、ご多分に漏れず現地でさえ弾く人がとても少なくなっているとあちこちでその現状を耳にします。素晴らしい若手のグループなども存在するのですが、専門教育を受けた職業音楽家に限られてしまうのではなく、仲良しの同好の士が集まってお茶を飲みながらお喋りをしつつ「じゃあ次の曲は何にしようか?」と皆が誦じている曲を共に弾くという和気藹々した本来の「日常に遊ぶ」という場、そしてそのような楽しみ方をする人々が激減しているそうです。確かに現在の幅広い娯楽の選択肢と、人々の好みの変化を考えれば「当時の最先端・大流行」が見向きもされなくなってしまうのは全世界的に仕方がない事なのかもしれません。身近にあったものがふと気づいた時には跡形も無く消えてしまっていることは日本でも随所に見られますね。とても残念に思います。
また、専門教育を受けた人が楽譜を元に再現・演奏するという事は当然可能なのですが、世界中の民族音楽、地方の民間音楽を保存しようと努力をする中で、見られる現象として独自の「味わい」が薄まり失われてしまう現象が起きます。それは、例えば装飾音の加え方だったり、微妙な音程の違いだったりの様々な要素の積み重ねが「味」なのですが、特に採譜という記録方法により、教育を受けて平均律に慣れた人の耳には書かれている情報が最優先になりますので、録音や眼前の地元演奏家の音程を「狂っている」と判断して本来の特徴を良かれと思って直してしまう事が多々あります。多数の無名愛好家が共有して支えている「文化」が楽譜を基準にしたステージに乗る専門家だけのものになった時に、何かが失われてしまうのはお察しの通りです。
我らが日本の横浜中華街には広東系の華僑の方が多くいます。私はご縁あって、廣東同郷會の春節の集まりにも何度かご招待頂いた事がありました。その時バイオリンや秦琴を弾きながら粤曲を歌う方やそれに合わせて歌う、第一世代の方々にお会いする貴重な機会もありましたが、一度お目にかかったきり。残念ながら、その後皆さんご高齢のためお亡くなりになってしまわれました。改めて同郷會の方にお伺いしてみましたが、今も横浜中華街界隈には廣東音樂を定期的に楽しむ集まりは無いとの事でした。
何か廣東音樂を楽しむ集まりがあるならばそこに加えて頂こうと思って調べましたが、そう言ったグループはなさそうなので、まずは自分から日本にもそういった「場」を作ろうと思い立ち、毎月私の主宰する音樂教室で廣東音樂の合奏クラスを開講しているのに加え、この秋「東京私伙局」という集まりを始めます。「私伙局」というのは広東の民間音楽文化の一つで、三々五々楽器を持って集まり粤曲を歌ったり、廣東音樂を合奏したり、場合によってはその時々に流行っている歌謡曲などを演奏したり歌ったりという集まりです。京劇でいうところの「票房」に近いものと言えるかも知れません。第1回は2023年10月22日。翌日が旧暦9月9日重陽の節句なので、菊のお茶を淹れようと思っています。参加者とお茶を愉しみ、お菓子を食べ、広東語話者を招いて広東の文化について皆んなでお喋りをする…。まだ廣東音樂を一緒に演奏できる仲間がいないのが残念ですが、将来的に廣東音樂好きの集まりができるようになることが目標です。ひとまず「動き出す事」を始めてみます。ご興味がある方はホームページからご連絡ください。詳細はホームページのイベントページにアップしています。

お問い合わせください
結びに
最後に香港の「伍人粤Band」という若手のグループを紹介します。教育家としても名高い余其偉先生の薫陶を受けたバンドで、次世代を担っています。因みにこの曲は「餓馬揺鈴」という名曲ですが、独特な音階「乙反調」で演奏されるので趣が異なる事にご注目ください(今回あまり触れられませんでしたが、大雑把に説明するとファが高めでシが低めです。ベトナムの音楽にも共通性が見られるので、冒頭に説明した同じ文化圏であるという事が伺える一例としても面白いと思います)
駆け足ではありましたが、廣東音樂の事に思いつくまま触れてみました。いかがだったでしょうか?そこそこ長くなってしまいましたが、さらに長くなってしまうので詳しい歴史や主な曲名、重要な演奏家などに触れる事は思い止まりました。かつて日本美術の再評価に外国人が果たした役割が大きかったという例があるように、こういう時にその価値を「面白い」「素晴らしい」「美しい」などと積極的に評価して発信する役割を負っているのが外国人かもしれません。もし私もこれから、その楽しさや美しさを発信する事でその一端を担い、日本人で廣東音楽を聴いたりご自身のレパートリーとして楽しむ人が1人でも増えたら幸いです。ぜひ仲間になりましょう!
ご感想やご質問などコメント欄に頂けましたら幸いです。また、記事は全文公開しておりますが、励みになりますので、投げ銭を頂戴できましたら有り難いです。
感謝内外琴友的閲読雅正, 多謝!
創樂社、扶桑粤樂社
安西創
参考文献
・広東漢楽胡琴古筝曲選(居文郁編著、1995年12月初版、人民音楽出版社)
・中国広東音楽(修訂版)高胡名曲薈萃(余其偉編注、2019年1月第一版、上海音楽出版社 上海文芸音像電子出版社)
・広東音楽高胡曲選ー余其偉演奏譜(居文郁編著、2020年9月北京第一版、人民音楽出版社)
・民族器楽(袁静芳編著、1987年3月北京第一版、人民音楽出版社)
・呂文成広東音楽曲選(広東省民間音楽研究室編、1990年12月北京第一版、人民音楽出版社)
※1 私は香港の先生に習っている事や、廣東音樂を聴いた原体験が香港映画の挿入音楽、背景音楽に由来する事、さらに香港が廣東音樂の成立と発展に多大な影響を及ぼした事…などから、敬意を表して原則繁体字で表記を採用しています。もちろん「広東音楽」と書いても、簡体字で表記しても本来一向に差し支えありません!念のため。因みに検索対策として、本文中に敢えて「廣東音樂」「広東音楽」など違う表記を混在させてあります。
※2 私は考えあって中国の固有名詞(曲名・人名・地名など)にカタカナで中国語発音の「ふり仮名」を振らない立場をとっていますので、レッスンでは伝統に則り音読みをするか普通話、もしくは廣東語の読みを相手の理解によって使い分けています。ここで出て来た名前は、それぞれ皆さんが読める読み方を採用してください(そう考えると、つくづく漢字ってすごい便利ですよね!!)
ここから先は
¥ 888
いつも温かいサポートをどうもありがとうございます。お陰様で音楽活動を続けられます!
