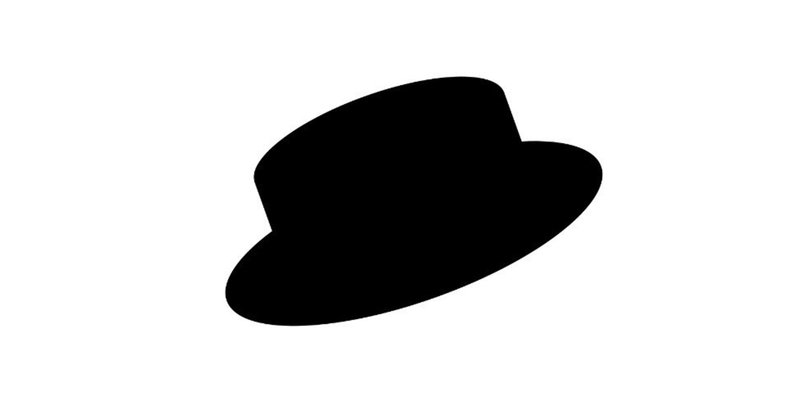
【書評】オランウータン―森の哲人は子育ての達人
ヒトにもっとも近縁なサル (大型類人猿) に、チンパンジー、ボノボ、ゴリラ、オランウータンがいます。このうち、前3種はアフリカのみに生息しているのに対し、オランウータンは東南アジアのインドネシアとマレーシアのみに生息します。アフリカの大型類人猿に関してはこれまでにさまざまな解説書が日本語で出版されているのに対し、オランウータンに関して書かれた専門的な解説書は、英語のものばかりでした。(オランウータンの野外調査に関しては『野生のオランウータンを追いかけて』、子供向けのものには『オランウータンってどんな『ヒト』?』があります)。
今回紹介するのは、2018年7月に出版された、オランウータンの進化、生態、行動について解説した日本語の書籍『オランウータン』です*1。本書を読めば、野生オランウータンに関する最新の研究成果を、網羅的かつわかりやすく理解することができます。
ユニークな特徴
詳しい人には当たり前のことかもしれませんが、オランウータンにはいくつものユニークな特徴があります。すこし挙げてみるだけでもこのとおり。本書では、こうした項目のそれぞれについて、最新の知見が説明されています。
●霊長類としては唯一、群れをつくらずに生涯をひとりで過ごす。
●見た目や強さの違う2種類のオスがおり、一生のあいだに一度だけ、オスは一方通行の「変身」をすることができる (図1)。
●樹上でほとんどの時間を過ごすもっとも大きな哺乳類である。
●体重あたりの安静時エネルギー消費量はナマケモノについでもっとも小さい。
●霊長類のなかでもっとも出産間隔が長く、手厚い子育てをする。
●2017年になって新種のタパヌリオランウータンが報告された。
私もオランウータンを研究対象にしているため、このあたりの感覚が麻痺していたのですが、本書を読んで、自分が研究対象にしていたのはなんとユニークな動物だったのか! とあらためて気づくことになりました。

図1. オランウータンの強いほうのオス (フランジオス)。頬の側面の張り出し (フランジ) や喉の下に垂れ下がったひだ (喉袋) が特徴。体も大きめ。
豊富なエピソード
学術的な硬い話ばかりではなく、本書には、著者がオランウータン研究者として成長していく過程で直面した/している問題や、フィールド調査の様子なども述べられています*2。フィールド調査の現場での研究者の体験があわせて記されていることで、オランウータンのユニークな生態がなんだか妙な実感をもって、するすると理解されてくるように思います。
あわせて、ぜひとも指摘しておきたいのは、載せられている写真のすばらしさです。オランウータンは、葉が茂った高い木の上におり、望遠レンズを向けても逆光になることが多いため、熱帯雨林の霊長類を写真撮影するのはなかなか難しいことです。機材も大事ですが、対象を辛抱強く追い求め、じっくり機会をうかがう忍耐力がさらに重要です。
本書に載っている写真からは、思い思いの体勢で樹上におり、悠々と果物を食べたり、移動したりしているオランウータンのたたずまいが、生き生きと伝わってきます。長年にわたって、日の出ているあいだはずっと森のなかでオランウータンを個体追跡している研究者とその調査助手だからこそ撮れる写真なのだ、と思います。
おわりに
そんなすてきなオランウータンとオランウータン研究ですが、どちらも危機にさらされています。オランウータンの暮らすインドネシアとマレーシアの熱帯雨林は、伐採やプランテーション開発のためにどんどん減少しており、オランウータン自身もペット取引や狩猟のために殺されたりして、生息数を次々に減らしています。
日本に暮らす私たちもこうした危機と無関係ではなく、これらの熱帯雨林で伐採された木材は、高度経済成長の時期に多くが日本に輸入されて使われていました。また、これらの熱帯雨林を切り開いて作られたアブラヤシのプランテーションで生産された「植物油脂」は、現代の生活を支える上でなくてはならないものになってしまっています。(化粧品、加工食品、シャンプーなどあらゆるものに入っています)。最近では、2020年に予定されている東京オリンピックで利用する競技場を建設するために使われている木材が、熱帯雨林の乱伐に由来する懸念が示されました*3。
一方、オランウータンは研究対象として難しい種であるため (群れを作らないため観察可能個体が少ない)、研究者はオランウータンを敬遠しがちで、大学などの研究機関で終身雇用されて研究に専念できるオランウータン研究者は、世界的に見ても非常に少ないそうです。
ユニークな進化の隣人であるオランウータンを守っていくために、私たちひとりひとりができることも、あるのかもしれません。
(執筆者: ぬかづき)
注
*1 久世濃子. 2018. オランウータン―森の哲人は子育ての達人. 東京大学出版会.
*2 そうした側面は、本書の著者の久世博士と同じフィールドで調査をされている金森博士の書かれた以下の書籍により詳しく記されています。
金森朝子. 2014. 野生のオランウータンを追いかけて―マレーシアに生きる世界最大の樹上生活者. 東海大学出版会.
*3 たとえば以下など。
持続可能な五輪を目指して/新国立競技場の木材調達を契機に|HUFFPOST
新国立の建設、熱帯林の木材使用に批判 東京五輪に課題|朝日新聞DIGITAL
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
