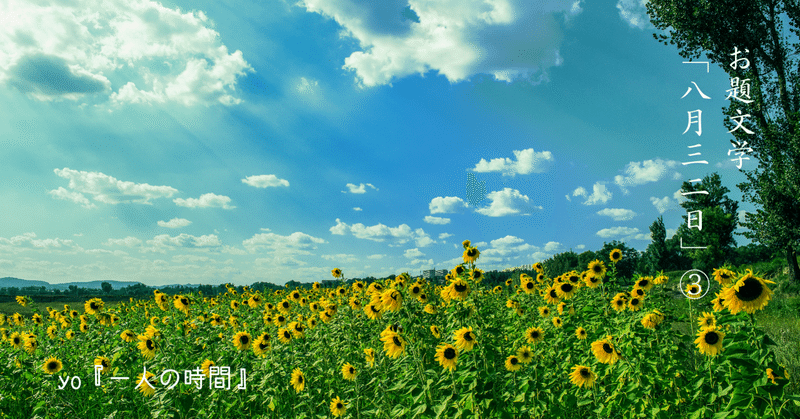
【文学批評】一人の時間を「読む」人の横顔(yoさん『一人の時間』【お題文学企画「8月32日」】)
yoさん『一人の時間』
齋藤圭介 評
現実に、夏はもう終わってしまったらしい。それでも8月32日の誤謬世界の旅を、季節を忘れながらもう少し続けてみたい。静花さんの紡ぎ出した物語から「身体性」や「季節感」といったキーワードを抱えながら、「二人の時間」から「一人の時間」へ、わたしはわたし自身を移動させようと思う。重力や時間をある程度は歪ませることのできる、言葉の連なりという転送方法で。どうやら8月32日は、現実よりも長い一日である。
朝。それは当たり前のようにやってくるが、どこまでが朝で、どこからが朝か、なんてことは、人それぞれの部屋の中においてそれぞれにデザインされているものであって、それについては何人も何人の生活ぶりを侵害できないように、とやかく言えるようなものではないし、もちろんその他者がこちらに直接的な影響を及ぼさない限りは、現実においては何の差し障りもないはずである。
この作品の部屋の中で作品中の朝を迎えるひとりの男についても同様で、一読者にのみ許された覗き穴から、その男の生活ぶりを、そのダラダラを、その右往左往を、それらを観察している限りは、何の差し障りはない。あるいは「サークル活動、友人との遊びの予定、三つのアルバイト」というその男の生活のデザインについても、それぞれのコミュニティに疲弊をしているということについても――しかし、事態は急に変わる、例えば――行動の観察をしているうちにその男の部屋に立て掛けてある姿見にちらりと写った横顔が、どこか見覚えのある場合には。例えばそれが、自分の顔であった場合には。過去でも未来でもある顔。性別はない、それは人間の顔。
そうなると、他人事ではない。違和感のずれの落とし穴に落ちると、今度はわが身を保身しなければならない。行動をひとりの男に託すこと、あるいは期待して予想することでそれらはまた解決もするし迷走することにもなるが、この保身のための方法こそまた言葉の強みに拠るところがあるので、読むという体験とは、たとえそれが空想の小部屋であっても他人事ではないと思われてくるのである。
もっともそこには、語彙の問題もあるだろう。タイムライン、スクリーンショット、SNSアプリ、セルフレジ。これらの語彙は、一見新しいということで不思議な世界にいるということを思わせない語彙たちである。総じて、仮想世界にバグを引き起こさせるものたちである。しかし問題なのは、それらがまた現実の語彙ではないということである。紙を、あるいはディスプレイを間に挟んで、そこ描かれているだけなのである。もっともそこには表現上の問題もからんでくるが、あくまでも作品中の語彙として距離を置くことで現実を再認識させるという文章法というものも、ある種の認識のエラーなのである。
そういう文字通りの試行錯誤をしているうちに、わたしの部屋のアナログ時計はもう9月27日の0時を回っている。本当だろうか。疑いが生じる。現実が静まり返ってくる。部屋にあるくすんだ鏡には、誰かの横顔が映っている気がする。
※イベントの批評文字数を超えてしまいましたが、超過分はわたしの今回のイベント課題に対する提出作品として、お許しください。(メンバーでわたしだけ8月32日の物語を提出していないので。)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
