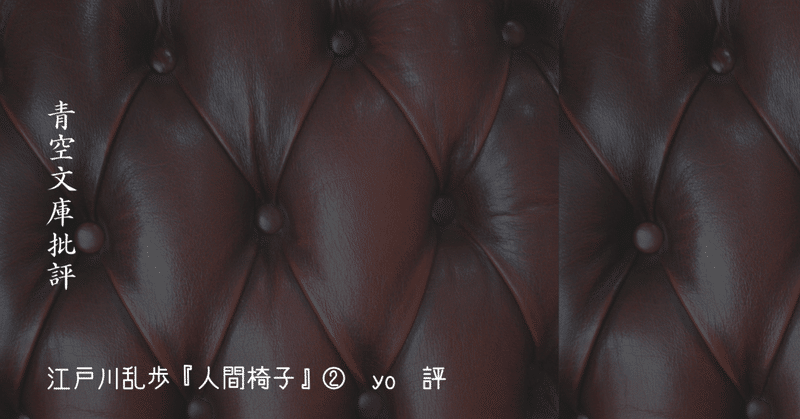
【江戸川乱歩『人間椅子』】いるの、いないの
江戸川乱歩『人間椅子』
yo 評
※本作は重大なネタバレを含みます。ご了承ください。
――――――――――――――――――――――――――――――
読んで「はー、楽しかった」で終わらせてくれるような作品ではない。ぜひ、『人間椅子』を読まれた方は私が関心を抱いた以下の点について、思い思いの感想をお聞かせ願いたい。
『人間椅子』の薄気味悪さと魅力
いきなりネタバレを含む話をすることをお許し願いたい。
これを読まれた読者諸兄は、1通目の手紙(手紙A)の主人公である私(以降、〈私〉とする)と、2通目の手紙(手紙B)の送り主である私(以降、[私]とする)のどちらが真実だと感じるだろうか。
解釈①:作中作創作説
素直に読み取れば、手紙Bに従って、[私]が「人間椅子」と題した創作を手紙Aとしてしたためたものと理解するだろう。とすれば〈私〉はあくまで作中人物であり、佳子は「なんだ、びっくりした」とばかりに落ち着くことができる。佳子の椅子には(当然ながら)誰も入ってなどいないからである。
実際、乱歩自身こう述べている。
『赤い部屋』にしても『人間椅子』にしても、前人未踏を心掛ける余り、内容が荒唐無稽で、出来相もないことで、それが一そ幻想的な小説ならいいのだけれど、やっぱり写実的に書く方が面白いものだから、内容の荒唐無稽と、書き方の写実との間に、どうしても無理が出来る。実際あったこととして書放して置くのが、作者にはどうにもやましいのだ。そこで、仕方がないので、あれは嘘だったという結末をつけて、やっと写実を徹底させる。
(江戸川乱歩『江戸川乱歩全集第24巻 悪人志願』、光文社、2005年、601頁)
写実性、言い換えれば「真実味」ともいえるだろう。乱歩自身、作中作だけでは真実味が足りないと考え、「人が椅子に入っているなんて嘘でした」というのが真相だとしたのだと書いている。
しかし、この部分は、乱歩の「本当は作中作の部分をこそ真実として描きたかった」という悔しさが滲む文章だとも読み取ることができるのではないか。乱歩の気持ちを深堀するのが本稿の趣旨ではないが、一度この仮説に基づき、敢えて作中作の部分を真実として考えると、以下のような解釈が成り立つ。
解釈②:作中作真実説
〈私〉は作中作の通り、椅子に入っていて、佳子への恋慕の情を抱く。この感情を伝えたくて手紙Aを執筆した。しかし、手紙Aを出した後に改めて後悔の念が湧き出てきてしまう。しかし、手紙は取り戻せない。この後悔の中で、それでも今後とも佳子への「暗闇の中の恋」を継続するための苦肉の策として、手紙Bを送り、「小説」という体裁を整えた。
こちらの解釈の場合、佳子の腰かけていた椅子の中には男が潜んでいたことになる。
解釈②を可能とする要素
かなり無理な解釈にも見えるが、この解釈を可能とする要素もいくつか挙げることができる。
1つは手紙Bを読んだ佳子の反応が記載されていないこと。
もう1つは敢えて手紙が2通に分けられている違和感である。
しいて言えば、「もう一度ハッとさせた様な」という一言が佳子の反応だったということもできるものの、ハッとしたという言葉一つでは、それが「なんだ、嘘だったのか」という安心感をもたらすものなのか、そこまでの確信を与えずにさらなる懐疑の念を抱かせて終わるものなのかが不明瞭である。
なぜ、乱歩は佳子の反応を明確にしなかったのか。
そこに、解釈の余地を残しておきたかったからと考えることもできるだろう。
そして手紙を分割した意図についてはどう捉えるべきだろうか。
「ある理由の為に、原稿の方は、この手紙を書きます前に投函致しました」と手紙Bに記載があることからも明らかなとおり、まず手紙を2通に分けるという行為自体は極めて不自然なものである。
そして、この「ある理由」も明記されていない。先ほどの乱歩の引用の通り、執筆時に写実性を持たせるために追加したものだとすれば、その目的においては手紙が2通に分かれた理由まで敢えて記載しておく方が写実性は増したことだろう。
なぜ、乱歩は敢えて手紙を分けた理由を伏せたのか。
もちろん、こうも深読みしてしまうと、解釈の可能性は際限なく広がってしまう。上記2つとも、言ってしまえば「締め切りに間に合わなかったから書かなかった」とという説さえ解釈可能である。
両義性を受け入れて
したがってここで私が敢えて書き留めなければならないのは、ここで綴っている解釈は、あくまで私が『人間椅子』を楽しむために行った個人的な解釈であり、推測の域を出ず、したがって何ら「これこそが真相だ」と新説を打ち立てる者ではない、ということである。
その上で、上記2つの解釈が両方成り立つことに思いを馳せながら改めて本文を読み返してみるといかがだろうか。
敢えて真相がわからず、椅子の中に男が忍び込んでいたか否かも不明なまま物語を終えることとなる。これは薄気味の悪い読後感として読者の心に残り、かつ椅子に入り込み数多の人と触覚を中心としたふれあいという〈私〉の奇怪な行動の気味の悪さとも重なり、その迫力を強める結果になる。
これが、私が『人間椅子』を読んで感じた1番の魅力である。
――――――――――――――――――――――――――――――
批評は以上となります。
この記事を読んで、自分の作品の批評の依頼をしたい!と思った方は以下記事に応募フォームがございますので、そちらからご応募くださいませ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
