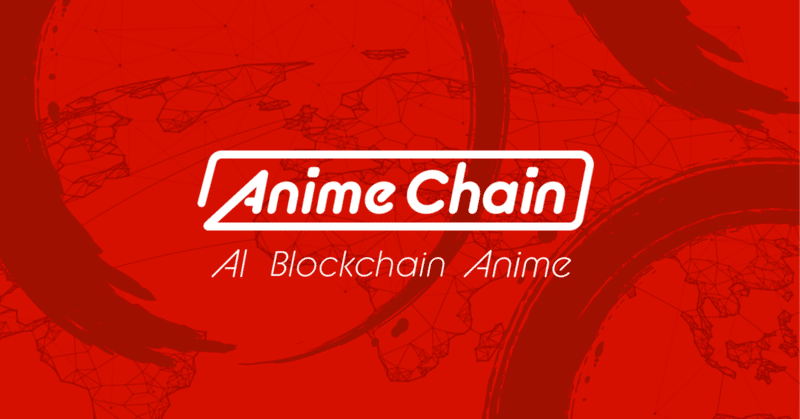
Anime Chain FAQ(日本語版)1/10,11,14,18一部追加
※1/10 皆様の意見を受けてFAQを一部追加いたしました。
※1/11 皆様の意見を受けてFAQを一部追加いたしました。
※1/14 FAQを一部追加、カテゴリー分けを行いました。
※1/18 皆様の意見を受けてFAQを一部追加いたしました。
お世話になっております。アニメチェーン準備委員会です。
2024/1/9に発表した「生成系AIにまつわる著作権や倫理的問題を解決し、コンテンツ・エコシステムの拡大を目指す「アニメチェーン構想」を発表」についてFAQをこちらに記載いたします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
アニメチェーンについて
Q: 「アニメチェーン」準備委員会は、今後法人化を予定していますか?
A: はい、私たちは「アニメチェーン」プロジェクトの発展と拡大を目指し、法人設立に向けた準備を進めています。
Q: 「アニメチェーン」プロジェクトはアニメ産業に特化したものでしょうか?漫画やゲームなど他のエンタメ・コンテンツにも展開を考えていますか?
A: 本構想のビジョンは、アニメ産業だけでなく、漫画、ゲーム、VTuberを含む日本のエンタメ・コンテンツ業界全体の健全な発展と持続可能性の向上にあります。このためアニメ領域に限定されず、今後加わっていくパートナーと共に、さまざまなエンタメ・コンテンツへの適用可能性を検討していきます。
Q: 「アニメチェーン」構想によって、生成系AIの著作権・倫理的問題をどのように解決するのですか?
A: 本構想では、すべてのデータセットを権利者から正式な許諾を受けたオプトイン方式によって厳格に管理し、既存の基盤モデルは一切使用せず、新規の生成系AIおよび関連ツールを開発し提供します。また、生成系AIによる職の置き換えという懸念に対して積極的に対応するため、まずは人手不足が産業の持続可能性に大きな影響を与えている日本のアニメ業界を支援する目的でこの技術を導入し、この取り組みを通じて業界全体のルールや仕組みを整えながら、著作権と倫理的な問題に対処していきます。さらに、このアプローチが他のエンタメ・コンテンツ分野にも適用される可能性を探り、産業の発展と持続可能性、創造性の向上に貢献することを目指します。
Q: 「アニメチェーン」へ参加することによる利点は何ですか?
A: 生成系AI技術は驚異的な速度で進化し続けており、今後のアニメ制作の生産性向上、問題解決、品質向上に寄与する蓋然性が高いと予測されています。ただし、現在のオープンソースの画像生成AIは商用利用・プロ用途に最適化しておらず、業界で使用する際には専用の調整が不可欠となります。また、これらの画像生成モデルはほとんどがオプトイン方式ではなく、使用する際に倫理的な懸念や法的問題を引き起こす可能性があります。さらに、本構想に参加されることなく、かつ独自の画像生成AI作成も行われない場合で、ある段階から生成AIを用いるように制作体制を変更する事になると、基本的にはオープンソースか国外の大手企業によるプロ用アニメ制作AIモデルの開発に期待する必要があり、権利や資金上の制約を受ける可能性があります。それだけでなく、それらは主に開発主体が海外であり、絵柄や特性、品質、商習慣、文化・文脈理解などの面で日本のアニメ関係者の期待に応えられるかは不確かです。さらに、国内で開発を行う場合でも、豊富な素材や多様な出力を実現するためには相応の規模が必要で、数社が保持する素材だけでこれを達成するのは困難を極めます。しかし本構想のように、事前に業界全体で協力関係を築くことができれば、クオリティを管理しつつ、倫理的に問題ない方式の生成AIを開発することが可能になります。また、生成系AIとブロックチェーン技術を組み合わせることで、収益分配やデータ保護を自動化し、権利や収益を保護できます。以上の理由から、本構想は業界全体での協力と先進技術の利用を通じて、アニメ制作の将来にとって最適な選択肢であると考えています。
Q: 「アニメチェーン」への参加による資金面のメリットについて教えてください。
A: 本構想は、ブロックチェーン技術を活用した分散型金融システムを導入することにより、アニメ産業における資金調達と市場の拡大に前向きな変化を促す可能性が高いと考えています。分散型金融は、その特性から大型のマーケットキャップを形成する傾向にあり、これによって大規模な市場資本を形成しやすくなります。これが結果としてアニメ業界の市場規模を大きく拡大させ、制作資金の増加を実現させます。この新しい資金調達の手法は、アニメシリーズや映画の制作にかかる人件費の拡充、新しいコンテストの創出、アニメ制作会社によるオリジナル作品のリリース数増加など様々な可能性を開くことを意味し、業界内の創造性と競争力を高めます。また、この過程で優れた監督やクリエイターの出現も促進されるでしょう。初期段階では投機による価格変動が見られるかもしれませんが、バブル経済時代の日本がインフラ網を構築したように、一旦創造されたコンテンツは長期的な価値を持ち続けます。さらに、育成された才能もこの過程で失われることはなく、業界のさらなる発展を支える貴重な人材となるでしょう。アニメチェーン構想は、アニメ産業における新しい資金調達の機会を提供し、市場を拡大させることで、業界全体の未来を切り開く重要なステップです。この構想によって、アニメ業界は新たな時代へと進化し、その成長と革新を加速させることが期待されます。
Q: 「アニメチェーン」は独自ブロックチェーンになりますか?
A: 初期段階では、既存のパブリックブロックチェーンやそのLayer2ソリューションを活用することを想定しておりますが、将来的には独自ブロックチェーンの構築に取り組む予定です。これらの計画はロードマップにも記載してありますので、ぜひご覧ください。
Q: 「アニメチェーン」のコンテンツ・エコシステムに参加したいのですが、どうすればいいですか?
A: ありがとうございます。本構想の最新情報を発信するXアカウントを公開しておりますので、今後のアップデートをお待ちください。
日本語版:https://x.com/anime_chain_jp
グローバル版:https://x.com/anime_chain
Q: 「アニメチェーン」で、共同でのアニメ制作プロジェクトに取り組む予定はありますか?
はい。本構想を通じ、アニメ業界関係者やパートナーと協力しながら、生成系AIやトークンを活用した共同アニメ制作プロジェクトを企画していく予定です。アニメ産業の発展と繁栄には、多くの著名な監督や才能あるクリエイターを輩出したオリジナルビデオアニメーション(OVA)文化や劇場版アニメ、アニメコンテストのようなイノベーションが不可欠です。これらの取り組みを積極的に支援することで、業界のさらなる発展を目指します。
Q: 「アニメチェーン」のトークンを購入したいのですが、どこから購入できますか?
A: クリエイター/開発者支援のための「アニメチェーン」トークン発行についてはロードマップに位置づけておりますが、現在は時期は未定となっております。本構想の最新情報を発信するXアカウントを公開しておりますので、今後のアップデートをお待ちください。
日本語版:https://x.com/anime_chain_jp
グローバル版:https://x.com/anime_chain
Q: トークンはいつ発行され、いつ上場しますか?
A: 現在のところは確かなスケジュールはお伝えできませんが、ロードマップに基づいて進行していきます。本構想の最新情報を発信するXアカウントを公開しておりますので、今後のアップデートをお待ちください。
日本語版:https://x.com/anime_chain_jp
グローバル版:https://x.com/anime_chain
Q: 制作会社です。「アニメチェーン」が開発する生成系AIツールを利用してみたいのですが、どうしたら良いですか?
A: 今後提供予定の生成系AIツールなどについて、本構想の最新情報を発信するXアカウントを公開しておりますので、今後のアップデートをお待ちください。
日本語版:https://x.com/anime_chain_jp
グローバル版:https://x.com/anime_chain
アニメチェーンエコシステムについて
Q: ”エコシステムの拡大”は、クリエイターの基本的な考えのひとつ「反商業主義」の精神と相性が良くない気がするのですが、どのように向き合っていきますか?
A: 確かに”エコシステムの拡大”という目標は、クリエイターの「反商業主義」的な精神と一見矛盾するように思えるかもしれません。しかし、私たちの目指す”エコシステムの拡大”は、単に商業的な利益を追求することではなく、生成系AIを正しく用いることで、クリエイターが自らの創造性や価値観を最大限に発揮できる状況を作り出し、文化圏そのものを拡大することを指しています。私たちのいう”エコシステムの拡大”は、需要と供給に多様性を生み出し、クリエイターに「反商業主義」の自由をも提供します。私たちは、クリエイターが商業圧力に左右されることなく自身の芸術的志向や独自性を追求する自由を享受しつつ、同時に生計を立てるための選択肢も持てる場を提供したいと考えています。
Q: 本当にクリエイターの権利が守られ、収益化が最大化されるようになるのですか?(利用されていませんか?)
A: 本構想は、コンテンツ業界において現役で活躍されている関係者たちからの具体的な声を聞き取り、それに応える形で生まれたものです。この経緯により、初期段階から倫理的な正しさと、クリエイターの権利保護が本構想の立脚点となっています。私たちの目標は、クリエイターが自らの権利をコントロールし、その価値を公正に評価される環境を提供することです。収益の最大化とは、目先の経済的利益を追求することではなく、クリエイターが創造的活動に専念し、その成果が適切に評価されることで自然と利益が生まれる状況を指します。クリエイターが不当に利用されないよう、オプトイン・オプトアウトのメカニズムやブロックチェーンによるトレーサビリティなど、透明性と倫理性を基盤とするシステム構築に注力しています。このような取り組みにより、クリエイターの権利保護と収益の最大化を実現することが可能だと考えています。
Q: 生成系AIが社会に広がっていくことで、クリエイターの権利や収益が阻害されませんか?
A: 確かに、現状のまま「権利者の許諾を受けない素材を使用した生成系AI」が社会に広がってしまうことで、クリエイターの権利や収益が不当に扱われる可能性は高いと考えています。一方で、日本のアニメ業界は深刻な“人手不足”に直面しており、クリエイターの仕事を守ったり収益を最大化する以前に、産業自体が危機に瀕しています。本構想は、コンテンツ業界において現役で活躍されている関係者たちから聞き取った、これらの課題を解決するために生まれました。本構想は、AI時代に懸念されるような、クリエイターの仕事や権利を脅かす目的ではありません。むしろ、最大限にクリエイターの権利を尊重しながら、現在も持続可能性が脅かされているアニメ業界を蘇らせるためのものです。私たちは、ブロックチェーンを活用して透明性と正当性を担保しながら、権利者の許諾を受けた生成系AIを提供することによって、クリエイターの権利を守りつつも産業界の持続可能性の危機を防ぎ、ひいてはクリエイター収益の最大化が図れると考えています。
Q: アニメ業界は人手不足ではなく人件費不足だと思います。技術革新は本当に必要ですか?
A: それら業界全体の課題を解決するためには、誰かが積極的に行動を起こし、エコシステムの改善に取り組む必要があります。業界の持続可能な発展を実現するためには、全ての関係者が一丸となって協力し、健全な産業構造の構築に取り組むことが不可欠です。新技術の導入や新しいビジネスモデルの開発は、必然的に一部の批判や抵抗に直面するかもしれません。しかし、何も行動を起こさなければ、現状の問題は決して解決しません。本構想は、様々なステークホルダーと協力し、新たなビジネスモデルや支援システムの導入を検討しています。これには、クリエイターの適正な報酬確保や、業界全体の労働環境の改善が含まれます。また、技術革新を活用し、作業の効率化やコスト削減を図ることも重要なアプローチの一つです。本構想の目標は、アニメ業界における全てのクリエイターが、適切な評価と報酬を受けることができ、自由な作品を制作できる環境を実現することです。このために、業界全体での意識改革と組織的な取り組みが求められています。私たちはこの挑戦に全力で取り組み、アニメ業界の持続可能な成長と繁栄を目指しています。
Q: 生成系AIの成熟が結局はクリエイターの食い扶持を減らすことになるのではないかと疑っています。また、人材不足とは、どちらかというとプロデュースする側の意見で、日本はむしろイラストレーターで溢れるレッドオーシャンではないですか?
A: 私たちは、生成系AIの発展がクリエイターの生計に否定的な影響を与えるという懸念を真摯に受け止めています。しかし、本構想は、アニメ制作会社をはじめとするコンテンツ業界の現役関係者からの具体的な声を基にしており、これらの業界の持続可能性を保護するための解決策として考えられました。特にアニメ業界は複数の課題に直面しており、既に一部は危機的な状況にあります。本構想の目的は、これらの問題に対処し、業界全体の健全な発展を支援することにあります。私たちは著作権や倫理的な問題に対応した生成系AIの導入と適切な利用、さらには全体的なエコシステムの構築を通じて、持続可能な業界構造の実現を目指しています。また、イラストレーター業界の現状についても認識しており、本構想は特にアニメ制作に重点を置いていますが、ここでのチャレンジと解決策は、今後イラストレーター業界のみならず、ゲームやその他すべてのコンテンツ制作にも新たな可能性をもたらすと考えています。確かに、生成系AIの技術が成熟しルールが策定された後も、現状の規模の市場がそのまま維持されると仮定した場合、市場の飽和が進む可能性は否定できません。しかし新たな技術の登場は、単に既存の作業を置き換えるだけではなく、新しい方法で人々を支援し、市場の可能性を広げます。特にクリエイティブ業界では、生成系AIを活用することでクリエイターの能力を拡張し、未探索の創造的分野に挑戦する機会が増え、さらに、既存の産業に係るクリエイターもその才能を最大限に発揮できるようになります。また、この進化は、既存の市場を再定義し、新たな需要と雇用を生み出すことにも繋がります。本構想は、単に既存の作業を効率化し続けて雇用機会を奪うといった目的のものではなく、AIとブロックチェーン技術の融合というアプローチを通じて、クリエイティブ業界全体の成長と繁栄に寄与し、既存産業の活性化と、新しい市場の開拓を目的としています。
Q: 生成系AIの導入によって、新人の大部分が不要になってしまうのでは?
A: 本構想は、コンテンツ業界において現役で活躍されている関係者たちからの具体的な声を聞き取り、それに応える形で生まれたものです。この中でも、高齢化に伴う後継者不足の問題が指摘されています。また、業界の持続可能な成長には、経験豊かなベテランだけでなく、新しいアイデアとエネルギーをもたらす、業界への新たな参入者の存在が不可欠です。"新人"こそが、業界の新たな力となり、革新的なアイデアや技術をもたらし、アニメ業界のさらなる発展に貢献する重要な存在です。私たちは、業界全体のエコシステムの改善に伴い、様々な人材の重要性を認識しています。それに伴って、全てのクリエイターが活躍できる機会を提供し、それらの新しい才能が開花する環境を創造することも、本構想の目指すところとなっています。
Q: 還元の額の具体的な金額について教えてください。
A: 私たちは、現時点で還元の額に関して具体的な数値を提供することが、責任ある対応とはいえないと考えています。還元に関する決定は、単に数値を提示すること以上の意味を持ちます。これを現時点で確定することは、関係各方面に対する不当な約束につながりかねません。金額の提示は、慎重な検討と多角的な評価を必要とする複雑な問題であり、その決定は支援パートナーおよび関係者全員の共同作業によって行われるべきです。私たちは透明性と公正性を最前線に置いています。このプロセスは、すべての関係者が納得し、参加することができる形で行われなければいけません。これには、市場の動向、業界の標準、プロジェクトの規模と影響、および持続可能なエコシステム構築に向けた長期的な戦略が含まれます。本構想は、関係者各位の意見を尊重し、公平な議論を重視する立場を取ります。最終的な金額は、これらの要素を踏まえた上で、関係者全員の合意に基づき決定されることになります。このプロセスを通じて、私たちは業界全体の健全な発展に貢献し、持続可能なエコシステムの構築を目指しています。
Q: 構想が実現することで、既得権益化するのでは?
A: 日本のコンテンツ産業は、アニメ、ゲーム、映画など多岐にわたり、その独自性と創造性で世界的に高い評価を受けています。しかし、インターネットの普及と共に、デジタルコンテンツの流通と管理のインフラは海外の大手企業によって抑えられるようになり、日本のコンテンツ産業における制作者や企業にいくつもの課題をもたらしました。一つは、収益の大部分が海外のプラットフォームに流れることにより、国内のクリエイターや制作会社の経済的な余裕が著しく圧迫された点です。次に、これら海外のプラットフォーマーが設けるルールやアルゴリズムによって、コンテンツ制作や配信の自由度に制約が課される懸念です。さらに、データの管理や利用に関する透明性が不足しているため、著作権や個人情報保護に関する懸念もあります。これらの既得権益構造は、日本のコンテンツ産業のエコシステムの循環が健全でなくなる一因となり、国内産業の持続可能な成長を妨げる要因ともなっています。しかし、本構想の自律分散協調型のアプローチにより、コンテンツ産業は、より多様なクリエイターや企業が参加でき、より公平な収益分配が可能になります。ブロックチェーン技術の透明性と分散型の特性を活用すれば、一部の大手企業や特定の集団による支配を防ぎ、より平等な機会を提供できます。また、既得権益の集中を避けることができ、日本のコンテンツ産業は、自身のインフラを構築し、より公平に収益を分配し、クリエイティブに対して自由度を確保し、不正に対抗し、クリエイターの権利を正しく保護することができます。これは、国内産業の健全なエコシステムを取り戻し、世界に向けてさらに競争力のあるコンテンツを生み出すための重要な一歩です。結論として、本構想はむしろ既得権益に挑む機構そのものであり、生成系AI時代におけるコンテンツ産業のエコシステムを再構築し、より健全で分散型の構造を目指すものです。本構想が適切に実施されれば、産業全体の利益が正当に分配できると考えています。
Q: ”エコシステムの拡大”と言いつつ、産業全体からの中抜き構造を作り出す目的があるのでは?
A: ご指摘のような懸念が生じることは理解しています。生成系AI時代の到来により、クリエイターが公正な報酬を得る機会が失われようとしていることは事実です。しかし、現在の産業構造には”人手不足”という問題も存在し、この矛盾が持続可能性に影響を与えています。この問題を解決するためには、クリエイターの権利を守る形で生成系AIを作成し、クリエイターの生産能力を最大化すると同時に、ブロックチェーン上に利用経緯を記録し、その記録を元に利益を公平に再分配することが必要です。本構想では、これらの目標を達成するためのルールと仕組みの策定を進めていきます。私たちの取り組みは、クリエイターが自らの才能と労力に見合った報酬を受け取ることを通じて、産業全体の健全な発展を促すことを目的としています。私たちのいう”エコシステムの拡大”は、「クリエイター、ファン、関係者それぞれの価値を創造し拡大すること」であり、相互に貢献する環境を提供することで、利益追求ではありません。
Q: 発起人が主導権を握り、大きな利益を得ることを目的としているという懸念があります。
A: 本構想に関する一部の懸念について、私たちは深く理解しています。ただ、現在のプロジェクトメンバーは、中央集権的なシステムを支持することなく、むしろ分散型の構造を目指す思想に基づいて本構想を発起しており、このラディカリズムを持つメンバーが本構想の根底を成しながら、分散型エコシステムの構築を目指しています。しかし、これを実現するためには、まず権利関係や既存の中央集権的な組織との協調が不可欠です。そのため、プロジェクトの進行にあたり、必要なルール作りを行い、業界全体の合意形成を目指す必要があります。ですので、本構想の実現に向けて、広範なステークホルダーと協力し、公正で透明なプロセスを通じて進行していきます。この取り組みを通じて、私たちは業界に新たな価値をもたらし、持続可能な成長と発展を支援することを目指しています。全ての関係者が納得し、支持する仕組みの構築を目指し、この挑戦に全力で取り組んでまいります。
Q: 『”コンテンツ・エコシステム拡大”のためのイメージ図』で示されている、"Proof of Generation"や"Proof of Training"とはなんでしょうか?
A: 「Proof of Generation」は、生成系AIによって生まれたコンテンツの質と独自性に基づいて、報酬が与えられるシステムです。一方、「Proof of Training」は、AIモデルの学習と進化に重点を置き、生成系AIの性能を向上させるために投じられた計算資源や労力、素材を提供した人に対して報酬が与えられます。これらの採用により、技術革新と経済的インセンティブの結合を目指します。
ブロックチェーンについて(技術)
Q: 「アニメチェーン」構想において、ブロックチェーンを活用する必要はありますか?
A: 本構想においてブロックチェーンを活用する必要性には、いくつかの重要な理由が存在します。
・透明性と信頼性の確保:ブロックチェーンの不変性と透明性を活用し、生成系AIを作成する際のデータセットの出自と、コンテンツの著作権及び使用履歴を明確に記録します。これにより、利用者が安心して取引や利用を行える信頼性の高い環境を提供します。
・著作権管理の効率化:ブロックチェーンを用いて、コンテンツの著作権情報を効率的に管理し、クリエイターや権利所有者への自動収益分配を実現します。これは権利管理の簡素化と手続きの効率性向上に寄与します。
・データセキュリティの強化:分散型ネットワークによるデータの改ざん防止と不正アクセス対策が、特に個人データや知的財産権の保護に重要な役割を果たします。
・分散型エコシステムの進化:ブロックチェーンを通じて制作データを安全に管理し、これを基盤モデルの継続的なアップデートに利用することで、持続可能で公平なコンテンツエコシステムを構築します。
Q: 「透明性」という用語が使われていますが、これは学習データや生成系AIの出力が公に閲覧可能な状態で公開されることを意味しますか?
A: 構想が目指す透明性は、必ずしも全ての学習データや制作物がそのまま公にされることを意味するわけではありません。データセットが他の生成系AIへ流用されるリスクを考慮し、少なくとも現段階では、独立機関、第三者委員会、研究機関、権利管理団体、公的機関、専門家などによる検証を予定しています。これらの検証を通じて、データの安全性、倫理性、および生成系AIの出力の品質を確保します。このアプローチは、最終的な生成系AIの品質と信頼性を高め、多方向に及ぶリスクを最小限に抑えるためのものです。倫理的な生成系AIの開発は、本構想の最優先事項であり、この方針は私たちの目的を反映しています。
Q: 生成系AIに使用したオプトインのデータセットの正当性を第三者検証で管理するなら、わざわざパブリックブロックチェーン技術を使う必要はないのでは? 利益分配や独自トークンが主目的ですか?
A: まず本構想の目的は、日本のアニメ産業の持続可能性を確保することにあります。アニメ制作会社をはじめとするコンテンツ業界の現役関係者からの聞き取りによれば、現在のアニメ産業は、クリエイターの創造性と能力を最大限に発揮できないという構造的な問題を抱えています。かつて日本のアニメ産業は、費用の制約にもかかわらず、クリエイターの力が強く、多様なオリジナル作品が生まれ、才能ある監督やクリエイターが持続的に輩出される環境にありました。しかし現在、そのような環境は危機に瀕しています。この問題に対処するために、クリエイターの能力を最大限に引き出し、その結果として生じる収益を正しく分配し、クリエイターの力を取り戻すことが重要だと考えています。この変革を起こすためには、創造的な解決策と前向きな取り組みが不可欠です。生成系AIを用いてクリエイターの力を過去を超えるレベルまで向上させ、才能ある創作者の持続的な輩出を促進する必要があります。これらを現実的に実行し、アニメ産業の持続可能性を担保するためには、分散型エコシステムの構築が不可欠です。また、プライベートブロックチェーンでは、特定の裁量による改ざんの余地が生まれます。これに対し、パブリックブロックチェーンは、この分散型エコシステムの実現に向けて、クリエイターの貢献と収益の追跡や公正な利益分配を可能にする重要な要素となります。また、学習データの提供のように、直接的な利益に結びつかない行動に対する報酬を支払う際には、独自トークンを用いるのが最も適切です。そのため、私たちはエコシステムを強化する一つの手段として、独自トークンの導入を積極的に検討しています。一部の異論や疑念も理解していますが、アニメ産業の将来を形作るためであれば、私たちは倫理的で革新的なアプローチをいくつでも採用します。次に、本構想は耐改ざん性と透明性の確保に重点を置いています。ブロックチェーンの分散化された構造は、規模が大きくなるほどデータの改ざんを困難にし、これが生成系AIの時代における信頼性の高いデータ管理において不可欠な要素となります。また、ゼロ知識証明のような先進技術を採用することにより、制作データを直接公開することなく、使用される生成系AIの正当性を公が確認する新たな道が開かれる可能性もあります。このアプローチは技術的な挑戦を伴いますが、成功すれば大きな価値を提供できるため、私たちはこの分野で持続的な研究開発に力を入れていく予定です。さらに、第三者による検証プロセスは現在の運用方法の一つであり、今後は類似度分析を利用してオプトインの可能性が低いデータを機械的に識別するシステムを追加で導入することも検討しています。これにより、より高精度なデータ検証が可能になると考えています。最後に、生成系AIのデータセットに関する法整備が現在進行中であるため、柔軟なデータ管理アプローチが必要です。政府機関を含めて、パブリックブロックチェーンの使用は透明性、耐改ざん性、真正性を高める有効な手段として検討されています。私たちは、この分野での法的枠組みが確立されるまで、効果的なデータ管理方法を模索し続けます。
生成系AIについて(技術)
Q: 基盤モデルから再構築するとのことですが、仮にその基盤モデルにも不正なデータが紛れ込んでしまった場合はどうしますか?
A: 細心の注意を払い、不正なデータが混入することのないように開発を進めます。しかし、万が一、不正なデータが基盤モデルに混入した場合は、判明した時点でブロックチェーン上のデータベースと照合し、基盤モデル構築用のデータセットから除外します(オプトアウト)。その後、基盤モデルを0から再学習します。さらに、不正なデータセットに基づいて生成されたデータに関しては、法的枠組みを遵守した、可能な限り適切な手段で対処します。これにより、クリエイターは安全かつ倫理的な生成系AIを使用し続けることができます。さらに、私たちは特定のデータセットを既存のモデルから効率的に除外できる技術の研究開発にも取り組んでいます。この技術は、モデルが既に学習してしまった不適切なデータを特定し、それを後から除去することを可能にします。これらの措置は、生成系AIの安全性と倫理性を維持するために極めて重要であり、私たちはこれを継続的に改善し、最先端の技術を提供することに努めます。
Q: インターネット上のデータを何十億枚も学習して作った既存の基盤モデルを、オプトイン・オプトアウトのデータセットで超えることが可能ですか?
A: 既存の基盤モデルは、広範な汎用性を持つ基盤モデルを目指し、膨大なデータセットの収集に努めてきました。これは、可能な限り多くのデータを集約することで、モデルの多様性と包括性を高めるための戦略です。ただし、特定の用途に特化したモデルを構築する場合、同様の枚数のデータは必ずしも必要ではありません。加えて、最新の研究により、トレーニングコストを大幅に削減する技術も登場しています。これにより、ドメイン特化モデルでは、現在の画像生成AIを超えるクオリティの出力も十分に可能と考えられます。
Q: 現在の画像生成系AIを超えるクオリティの出力も十分に可能と考えられるとのことですが、『考えられる』というのは、実用化前の検証結果に基づかないということでしょうか?
A: 私たちは、少数の画像データに基づくファインチューニングを通じて、世界的に認められるクオリティを実現可能なレベルにまで引き上げることができる、世界有数のオープンソースソフトウェア(OSS)のコントリビューター集団や、グローバルな技術者、企業との緊密な協力体制を築いています。この協力体制は、少数のデータセットを用いたファインチューニングだけでなく、基盤モデルの構築においても重要な役割を果たします。私たちは、この分野でトップレベルの技術を有していると考えており、本構想は、既に行われた内部研究と検証が基盤となっています。新規の支援パートナーには、これらの成果を公開し、ご理解を頂いた上で参加して頂きます。また、既にエンターテインメント業界のトップ企業を含む関係者との対話において、この成果は公開しています。さらに、FAQ上でいう『考えられる』という表現は、単に現在のクオリティの範囲を超えるという意味を指すだけではなく、アニメ制作者の高い基準を包括的に満たすことができるかという意図を含んでいます。これらは今後、クリエイターや関係者との継続的な確認作業と研究開発を通じて達成されるものであり、私たちが無責任に、この段階で断言することを慎重にしています。
Q: 既存モデルへのオプトイン以外の追加学習、不正なデータセットの混入、およびインセンティブを目的としたデータ操作のリスクについて教えてください。
A: 本構想の基盤モデル及びファインチューニングモデルの開発は、まずは厳密に確認されたオプトインのデータセットのみを使用し、不正なデータの混入を徹底的に防ぎます。万が一、不正なデータが発見された場合は、再学習を通じて迅速に排除します。アニメスタジオやその他の最終ユーザーが行う学習段階では、彼らが用意したオリジナルのオプトインデータセットを使用し、これらのデータもブロックチェーン上に記録されます。最終段階での学習はユーザー側の責任において行われますが、契約やその他の法的な縛り、ブロックチェーン技術を通じて、不正なデータの混入を可能な限り防ぐ措置を講じます。もちろん、ここでも不正なデータが混入していた際にはモデルの再学習を行います。また、これらのデータセットは、私たちの側で基盤モデルの作成やファインチューンを行う際に、品質保証のため厳密に管理され、その際も不正なものかどうかが確認されます。さらに安全性を確保するため、初期段階では支援パートナーのみにサービスの提供を想定しており、追加学習も支援パートナーの管理するデータに基づいて行われる予定です。これにより、品質の維持とデータのセキュリティが保証されると考えています。生成系AIの一般公開やオプトイン学習データの広範な収集について現時点では計画しておらず、安全な利用方法や法整備が確立されれば、その際に初めて検討を開始する予定です。私たちは安全性と信頼性を最優先にし、リスクのないエコシステム構築を目指しています。
Q: 供出してくれる人のデータをそのまま無差別に学習するのですか?
A: 提供されたデータについて、それらを無差別にデータセットとすることはありません。ただし、ファインチューニングを行う前段階の基盤モデル構築においては、(あくまで全てオプトインのデータであることを前提として)必要に応じて広範囲な学習を実施することがあり、これは高品質な生成系AIの開発において重要な役割を果たします。その後、ファインチューニングに使用されるデータについても、その質と安全性に関する厳格な基準に基づいて慎重に選定されます。これらの基準は、技術者とクリエイターや関係者との連携によって策定され、最適なデータセットを製作し、生成系AI系の開発に用います。私たちの目標には、安全で高品質な生成系AI技術の開発を確実に行うことが含まれ、このためには最適なデータの選定と使用が不可欠です。
Q: 画像生成AI基盤モデルの開発において、当社がアニメチェーン構想に素材を提供することのリスクはありますか?
A: 現在の状況を鑑みると、国内外のAI企業は、既にアニメーションコンテンツを含む多くの素材を積極的に収集し、自らのAI開発へ使用しています。このような状況下では、仮に本構想へ素材の提供を見送っても、将来的には該当の素材を利用した他のAI企業の製品が市場に登場することは避けられません。特に海外では、フェアユースの原則を盾に、企業が他者の知的財産を自社のキャラクターのように使用し、莫大な視聴回数を記録しているケースが増えています。このような状況が続けば、権利者や製作者にとっては不利益を被る可能性が高く、倫理的な問題も生じることが懸念されます。本構想への参加により、参加者は資金提供やAIによる生産性向上のメリットを享受できるだけでなく、ブロックチェーン技術を通じてデータの権利保護や収益分配が可能になります。これらの施策を業界標準とすることで、業界全体の発展と競争力の向上に貢献できると考えています。したがって、本構想への素材提供は、リスクを管理しつつ、業界の発展に貢献し、自らもメリットを享受する重要な機会となります。もちろん、権利の保護と倫理的な観点から、提供される素材の管理と使用については慎重に検討し、適切なガイドラインを設定していきます。このようなバランスを取ることによって、リスクを最小限に抑えつつ、業界の健全な成長とパートナーの権利保護を実現することが可能になると考えています。
その他
Q: 本当にコンテンツ業界の協力関係を築けますか?
A: 本構想はコンテンツ業界において現役で活躍されている関係者たちからの具体的な声を聞き取り、それに応える形で生まれました。本構想は、業界が直面している現在の課題に緊急かつ具体的な解決策を提供することを目的としており、既にエンターテインメント業界のトップ企業を含む多くの関係者との対話が進行中です。これは構想が業界全体の成長と発展に寄与する実現可能なプロジェクトであることを示唆しています。過去の技術革新が社会にもたらした変化を振り返ると、新しい技術が初期段階で抵抗や疑念を生むことは一般的ですが、時間の経過と共に、ルールの整備が行われ、それが業界の新たな標準として定着し、私たちの日常生活に不可欠な存在となっています。ですので、コンテンツ業界の具体的なニーズに基づいて設計し、生成系AIとブロックチェーン技術を活用して複数の課題を解決する本構想は、業界全体と協力関係を築けると考えています。
Q: 関係者から具体的な声を聞き取ったとのことですが、なぜ現在の支援パートナーに入っていないのですか?
A: 今後、クリエイターの支援パートナーも順次発表し、参画していただく予定です。しかしながら、現在は著作権や倫理的な問題を抱える生成系AIの拡散に対応するための具体的な策として、本構想を打ち出すことを優先しています。アニメ関係者の皆様の支援は非常に重要であり、適切な時期にその参画を発表できることを楽しみにしています。
Q: 生成系AIやブロックチェーンについてネガティブな印象が世間に広がっていると思いますが、どう払拭していきますか?
A: 確かに、既存の生成系AIやブロックチェーン技術は、法的および倫理的な基盤が十分に整う前に急速に拡散してしまいました。しかしこれらの技術は、適切に活用されれば産業の発展に大きく貢献する可能性を秘めています。私たちは、倫理的かつ責任ある方法で生成系AIを開発し、ブロックチェーンのトレーサビリティを利用してその正当性を確保することで、クリエイターやアニメ業界の支援に着手します。特に、”人手不足”が顕著な日本のアニメ業界では、これらの技術がクリエイターの仕事を補助することは明らかです。現在の技術に対するネガティブな印象は、適切な使用法と啓蒙活動を通じて徐々に改善されると考えています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
