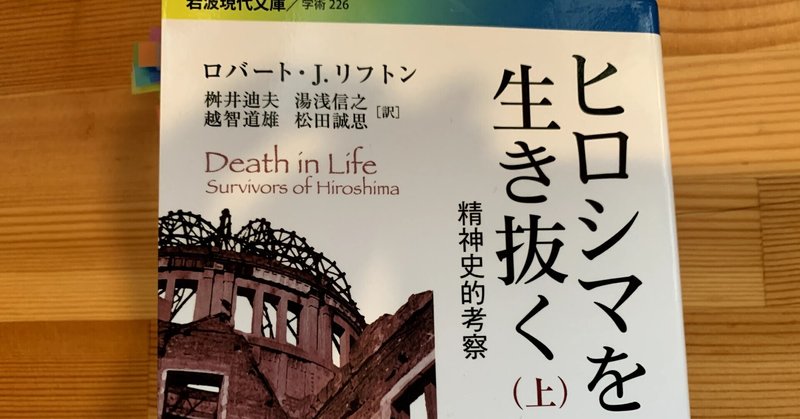
読書感想文:ロバート・J・リフトン『ヒロシマを生き抜く(上)』(岩波現代文庫)
1962年から広島の原爆被爆者に聞き取り調査を行い、1968年に出版された原爆投下の「心理歴史(サイコ・ヒストリー)」的な影響を記述した著書だ。岩波現代文庫版で上下分冊900ページに及び、しかも、注意書きを見れば、分量の都合上、原著にある二章ぶんと付録は割愛してあるという。まだ上巻しか読んでいないのだが、下巻まで読み終わってからだと、感想を忘れてしまいそうなので、まずは覚えているうちに上巻の感想から書くことにする。下巻を読むと、感想もまた変わるかもしれない。
著者は、アメリカ人精神科医である。この調査以前から、日本に強く興味を抱いて、総計で4年ほど日本に滞在していたとある。そのため、日本の文化的土壌についても深い洞察があり、本書の分析を説得力のあるものにしている。調査対象者は、73名の被爆者で、うち31名は広島大学原爆放射能医学研究所の持つ被爆者リストの中から無作為抽出したものだ。無作為抽出の調査対象者から聞き取りが行われていることが、本書の内容における被爆者内における普遍性を担保しているように思える。残りの42名は、社会的活動を行っている原爆問題について強い発言権と主張を持つ人たちで、この中には、ハーシー『ヒロシマ』の取材対象となった人たちも複数含まれている。また、『広島長崎修学旅行案内』の著書である松元寛氏も聞き取り対象者に入っている。合わせて読んでいると、出来事がどのようにリフトンによって切り取られ、分析されているかも、いくばくか立体的に浮かび上がってくる。ラファエル『災害の襲うとき』も、本書を基礎文献の一つとして参考にしたという趣旨のことが書かれていたと記憶するが、確かに、被爆者の直面する状況について細部に渡って行き届いた考察であると感じる。
一部には、被爆者の他者依存性の問題など、被爆者というよりも、元々の日本人の精神土壌に起因するところが大きいのではないかと思われるが(著者も土居健郎『「甘え」の構造』を引きながら、この点は指摘している)、ときおり辛辣ささえ感じるこの指摘が、広島の原爆問題周辺の人々にどのように受容されてきたのだろうかとの興味も抱く。ちなみに、松元寛氏は上記著書の中で、リフトンについて簡単にではあるが好意的に言及しており、氏自身も著書の中で被爆者や広島の人たちについて、厳しいコメントも行っている。こうした批判的な観点が、昨今のヒロシマを巡る言説から失われていることにも気付かされる。
戦前の廣島が軍都であったという説明は、簡単には耳にしたことがあったが、日清戦争の時には大本営まで置かれ、軍事拠点とされることによって近代都市としての発展を遂げた、まさに軍事都市であったということまでは、私は明確に理解していなかった。原爆投下の際に、呉や江田島といった島嶼部を除いて軍事拠点としての痕跡もほとんど消えてしまったからという理由もあるだろうが(ハーシーの著書の描かれる爆心地からほど近い広島城に置かれていた軍本部の兵士の悲惨な状況は筆舌に尽くし難い)、被害性を際立たせるための、無自覚な隠蔽意識が働いていた側面はあるのではないだろうか。昨今の日本における全国的な被爆者に対するシンパシーの広がりは、社会に漠然とした「被害者意識」が充満する中で、原爆投下という圧倒的な被害性に引き寄せられた被害者ナショナリズム立ち上げに過ぎないのではないか、とも感じている。
聞き取りに基づく分析も圧巻ではあるが、分析の項目立ても網羅的になされており、災害からの時間経過に伴って起こる社会的側面を、ほとんど網羅的に補足できているのではないかとさえ思える。福島で問題になった、風評、スティグマ、差別、被災者間での分断、報道なども含まれており、本書に含まれる項目を使えば、おおよそ社会的な側面についてはカバーできるのではないだろうか。人間社会で起きる事柄は、あらわれ方は社会や時代によって若干変わるにせよ、そう大きく変わるものではない、ということだろう。
リフトンは、日本では原爆の被害を受け生き残った人たちを「生存者(suivivor)」と呼ばずに「被爆者」と呼ぶことに着目する。日本では、「生存者」という呼称は、生の側に力点を置きすぎ、死者たちを切り捨てたように思え、好まれないと解説する。そして、しばしば被爆者は死者との一体性を強調し、また被爆者が死の観念(「死の影」)に囚われていることが指摘される。生き残ったことに対する罪意識、自責の念は、死者をともなう予期せぬ災害や事故に遭遇した人間は誰しも抱く感情であるが、原爆投下は、死の体験が圧倒的であり、被爆者たちはその影から抜け出すことが困難となる。聞き取りを行ったリフトンにとっても、それは強烈とも言える印象を残したのだろう。第四章の「原爆症」についての記述の乱れからそれがよくうかがわれる。
「原爆症」は、定まった疾病ではなく、原因不明の被爆者が訴える症状まで含めた漠然とした呼称である。原爆による人体への被害は、熱による熱傷と爆風などによる外傷、それと放射線障害とがある。熱傷や外傷については識別は容易だが、放射線障害については、どこまでが放射能の影響によるものか見分けることが難しい。(広島・長崎以前には、LNTモデルも存在せず、白血病やガン発症の確率的増加の閾値もわかっていない。広島・長崎は、まさに「人体実験」の場であった。) 被爆者が訴える症状のうち、どこまでが放射線によるものなのかわからない千差万別の身体の不調については、心因性のものも含まれるのではないかとも指摘される。一方、本書の中で引用される当時の新聞記事の記述などを読むと、「原爆症」は定義が不明瞭なまま、被爆者の健康被害を無際限に拡張していくようなセンセーショナルな伝え方も多くあったようで、それにともなって引き起こされるスティグマタイズや差別といった悪影響の側面も強く懸念されていたようだ。
当然のことながら、被爆者自身もこうしたスティグマを内面化し、抱え込むことになる。それは、「死の影」に深く沈み込むことを意味する。こうした原爆症を訴える被爆者の死の気配の濃厚さに、リフトン自身が気圧されたせいか、この章の記述は感情的に思える箇所もある。とりわけ、被爆者の個人的事情に強く踏み込んでいるところだ。原爆症が心因性のものであることを強調したいばかりに、学術的な研究調査の言及としては踏み込みすぎではないかとさえ感じる。(皮肉なことに)リフトン自身も本書の中で触れているが、だいたいが個人的事情を強調するときは、「自分は違う」「彼/彼女は特別だ」という切り離しを心理的に行いたい時だ。「原爆症」を訴える被爆者を目前にして、リフトンは自分自身の持つ世界観や秩序認識が根底から揺り動かされる恐怖を抱いたのではないだろうか。「生者」の側に自分を位置付ける人間にとって、自らを死者に列すると位置付ける「死の影」に覆われた被爆者たちの世界認識を受け入れことは、耐えがたかったのかもしれない。
第四章のエピソードの中にはやや衝撃的な後日談エピソードが含まれている。リフトンの聞き取り調査に対して健康への懸念を訴え続けた女性詩人について、彼は、女性の個人的事情をしつこいほど解説し、原爆症は心身相関的であり、彼女の懸念は個人的状況を背景とした心理的な側面が強いことを強調した分析を行う。だが、調査後、彼女は実際に乳がんに罹患し、それによって調査から数年後に亡くなるのである。リフトンは、ここで自分の分析が心理的要因に寄せ過ぎているのではないかと内省した上で、分析を修正する必要はないとの結論に至ったと書き加えている。
本文の記述の中では、女性詩人から感じる依存心に対して、リフトンが辟易していることを感じさせる箇所がある。彼女のそのような態度に対して痛ましさと同時に、ある種の嫌悪感を伴う感覚を持っていたのではないか、とも推測される。1960年代当時、現在よりもはるかにお上意識の強い権威主義的社会であった日本で、アメリカ人の大学教授である医師に対して、市井の窮状に置かれた被爆者がどのような態度で接したかは、おおよそ察しがつく。ねっとりとまとわりつく懇願のような眼差しに、自主独立を心的基盤とするアメリカ人の困惑は察するにあまりある。
一方、ここで垣間見える、被害をセンセーショナルに伝えるマスメディアと、それに対する反動として、健康被害を限定的とする科学的な見解を強調しすぎてしまうことによって生じる軋轢について、文化的、精神的側面への理解がこれほどまでに深いリフトンでも生じさせてしまうのかと嘆息せざるを得ない。
あたりまえのことだが、科学的見解は、その時にわかっている範囲のことがわかるだけだ。それ以上のことはわからない。わからないことについては、沈黙すべきであるのに、しかし、少なからぬ人が話しすぎてしまう。心身相関的であるといっても、どこまでが心で身なのかはわからない。ならば、自分にはわからない、と言うべきなのだ。だが、リフトンにしてみても、心理的側面を強調し過ぎてしまう。そして、その言質は、後に明らかになる現実(乳がんの発症とそれによる死)によって裏切られる。リフトンの大枠の分析は間違っていないとしよう。しかし、ヒビのように入ったその言説への不信は、人々の中で言語化されない、目に見えない太い渦となって流れることになるのだ。
他にも興味深い箇所はいくつもあるのだが、中でも、生き残ったことに対する罪意識を、死者に礼を尽くすことによって生存を正当化しようとするという分析には興味を惹かれた。リフトンはこの心的機制を「死の影」に覆われたものとなる、とネガティブな意味合いを込めた評価をしているが、私は、この箇所は普遍的に、人間がいかにして倫理を立ち上げるかの一場面を捉えているのではないかと肯定的に読んだ。
倫理は、相互契約的なものではない。一方的に命ぜられるかのような契約を義務的に負うことによってしか成立し得ない。そうした不均衡な関係を個人の奥深いところで内面化して成立させるには、日常的な生を超えた、超越的な何かを措定せねばならない。だが、現世利益的で相互互酬的な関係に規定される日本社会では、超越的な何かを措定することが困難であるため、相互監視以外の倫理を立ち上げることが難しい。であるのに、戦後の日本の一時期において、倫理的に見えるものが立ち上がっていたことを不思議に思っていた。そして、それを可能にしたのは、戦中世代の生き残り意識、つまり死者に対する自責感ではないのかとかねてから感じていた。リフトンのここの記述は、自分の抱いていた仮説と符合する。
キリスト教的な超越観念を利用すれば、死者の存在がなくとも倫理を立ち上げることが可能なのかもしれないが、日本的な精神土壌の文化では、死者を介在せずして倫理を立ち上げることは不可能なのではないだろうか。そう考えると、日本における広島の精神的存在意義のひとつには、忘却を許さぬ圧倒性を持って、死者をわれわれの前に現前せしめていることにあるのかもしれない。
気に入られましたら、サポートをお願いします。
