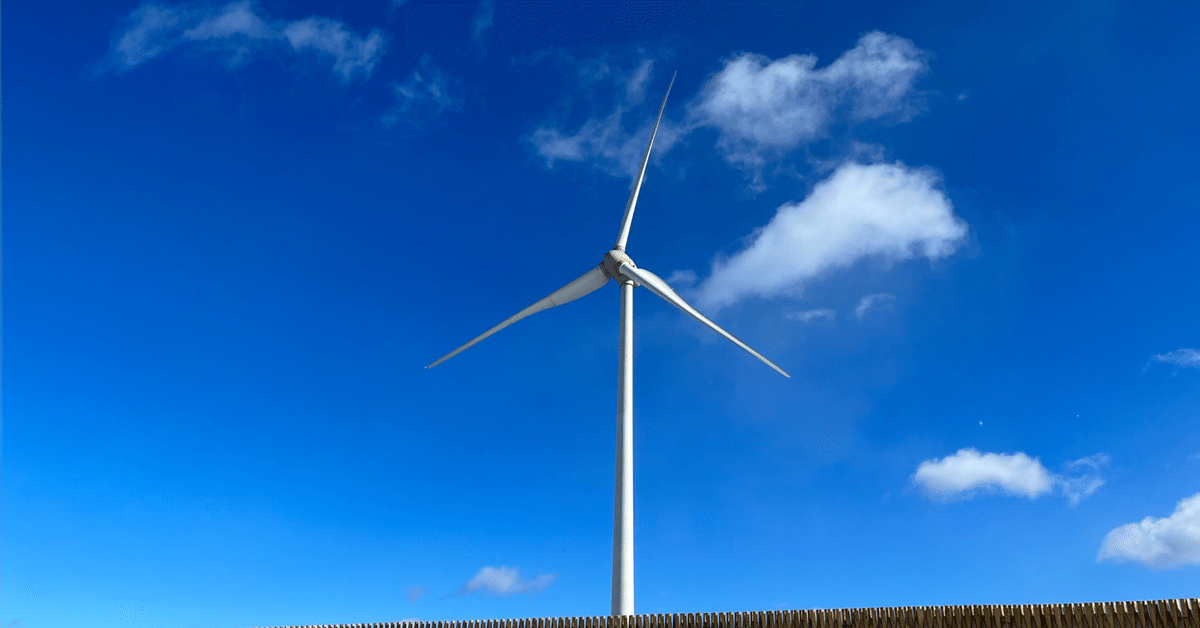
ガラパゴス化する福島から愛を込めて/年頭所感に代えて
この間の正月までは健在だった本家の義伯父も、昨年、足を骨折したのち入院生活に入ったとのこと。齢100歳。お盆につくるぼた餅をご相伴に預かったのは、一昨年の夏だったか。いつまで食べられるかわからないと思い、子供の頃からあまり好物ではないぼた餅を口に運んだ。10年の間に、年寄りたちはひとり減り、ふたり減り、あるいは衰え介護施設に入り、病院に入院し、親戚付き合いもすっかり静かになった。
10月末に見て回っていたこともあり、今年は年末恒例の沿岸の風車めぐりに行かなかった。ここから先はどこまで行っても同じ風景、と感じるようになったことも大きい。復興で開発された景色や箱物は、違和感を感じるものも少なくないけれど、いくつか美しさを感じさせる景物もある。沿岸の巨大風車もそのひとつだ。採算があっているのかどうかはわからないけれど、冬の浜のキーンと冷えた青空と太平洋を背にすっくと立ち上がっている姿は、風景になじんでくるにしたがってどこか懐かしみさえ覚えるようになった。
東日本大震災、そして福島第一原子力発電所事故の復興の10年間を考えたときに、なぜああまでも日本中の多くの人たちが被災地に心を寄せ、また、復興に力を注ごうとしたのかは、不思議に思っていたことでもあった。特徴的なのは、支援に入った少なからぬ人たちが、被災地に強く感情移入をしていた、ということだった。もちろん、過去に例のない未曾有の災害であった、ということもある。津波被災地の衝撃的な光景を見て、感情が深く揺さぶられた、ということもあるだろう。けれど、阪神淡路大震災の時だって、こんなには長期にわたって被災地外からの関心と支援が継続することはなかった。
震災から数年間は、支援に入った人たちから、しばしば「福島の復興に新しい日本の姿を見たい」という言葉を聞くことがあった。当時の私は、自分たちの生活再建に必死だったので、その言葉に冷淡な反応を示していた。けれど、振り返ってみれば、この言葉に込められていた思いこそが、東日本大震災の被災地への前例のない長期の潤沢な支援を可能とさせたのではないかと思う。
震災前の日本は、長いデフレに苦しんでいた。バブル崩壊以後、現在「失われた30年」といわれるうちの20年を経過し、それでも上向かない社会に少なくない人たちは行き詰まりを感じていた。政治も混乱していた。なぜか東日本大震災時にたまたま政権を担当していた民主党政権の混乱ばかり指摘されるけれど、その前の自民党政権だって大混乱していた。デフレは彼らだってどうにもできなかったし、そのくせつまらない政争ばかりに明け暮れ、首相は1年ごとに交代していた。そこに東日本大震災、加えて、原発事故が起きた。自民党時代から迷走し閉塞し、行き詰まった末の巨大カタストロフだった。
予期しなかった劇的な破局は、沈んだ人びとの心を高揚させた。そして、これはこの行き詰まりを打開する千載一遇の機会ではないか、と思った。いや、そうしなければならないのだ、となぜかそう思った。そして、みな、東日本大震災の被災地、とりわけ、福島の復興の形に、行き詰まった日本社会の新しい姿や道筋を作ることに、自分たちの希望を見いだした。そうした人びとの思いを乗せ、「復興」ははじまった。
そのことが幸運だったのか、不運だったのかは、わからない。ただ、前例のない、そして、今後日本でふたたびありえない規模の予算と人手が東日本大震災の復興に注ぎ込まれたことは間違いない。当初のキャッチコピーであった「福島からはじめよう」は、当時の人びとが抱いた、福島からあたらしい日本の姿が提示されることへの期待を、うまく反映したものだったように思える。
そして、いま、その福島は「ガラパゴス化」しつつある。
岐路は2015年頃だった。多くの人の希望を乗せてはじまった「復興」が、その頃に風向きが激変した理由は複数あって、そのなかのいくつかは推測の枠を出ないけれど、大きくいえば、福島の原発被災地の復興予算の流れが自治体経由に変わった、ということがある。
楢葉町が2015年9月に、全域避難自治体として最初の避難指示が解除された。それまでは、避難自治体は混乱の極みにあり、避難先での住民対応に追われ、とうてい復興計画を立てられるような状態ではなかった。おそらくは、福島県庁も似たような状態だったのではないだろうか。だが、この頃から混乱は徐々に収束しはじめ、避難指示発令中という非日常のなかでの日常業務が戻ってきた。
日本の行政システムでは、国は直接住民対応には当たらない。国が対応するのは、自治体がもっばらになる。「被災地対応」と政府がいうときに、暗黙の前提としてあるのは、「被災地=被災自治体」だ。だが、震災直後の大混乱の時期には、上述のように自治体も混乱の極みにあったため、その暗黙の前提が通じず、国が直接、被災地の住民対応にあたるような動きがあった。それは、異文化遭遇とも呼べるような奇妙な事態ではあったけれど、それまでにない風通しの良さを生じさせたことも事実だ。東日本大震災と原発事故の対応において、前例のない動きを国が行った事例はいくつかあるけれど、それは、こうした前例のない異文化遭遇が大きな原動力となって生まれたものもあるはずだ。
だが、2015年以降、自治体が元の運営を取りもどし、行政ルートが平常に戻るに従って、異文化交流の機会は激減した。国は国の業務として、自治体対応を粛々と行う。そこにはなんのあたらしみもなく、政府が口癖のように繰り返した「地元のご意向」すなわち「自治体のご意向」を汲んで作られる復興政策は、よくて、もともと保守的であった福島県内の自治体の動きをそのまま反復再生するものになった。そればかりではない。被災によって民間活動は弱体化していた。もともと原発産業以外の経済基盤は弱い地域ではあったけれど、地域活動の主体がまるごと消失してしまったせいで、被災地においては、ただひとり自治体のみが地域のプレーヤーとなる異常な状況が発生した。そして、そこのみをルートとして、多額の復興予算が注ぎ込まれる。自治体は粛々と復興計画を立てる。復興計画は、唯一絶対の、地域活動の指針となっていった。これにより、期せずして、被災地には、さながら、かつての社会主義計画経済国家と相似した社会が生まれることになった。
もちろん、そうではない動きもある。
「自分は、震災前の地域は大っ嫌いでした。元の地域に愛着なんてまったくありませんし、元に戻したいなんてまったく思いません。」
この言葉を聞いたのは、2014年だった。なかなか強烈な言葉だと当時は思ったけれど、今にして思えば、彼のこの見解には理があった。彼は、避難指示解除になった地域に最初から戻り、自分のやりたいことをやれる地域作りをしている。当時から、言っていることはまったくぶれていない。避難指示解除後に話を聞いたときも、同じことを言っていた。
「震災前は、なにかやろうとしてもいつも潰してくる上の世代がいて、なにもできなかった。いまは、上から潰してくるような年寄りはみんないませんし、戻ってきている地域の人たちは応援してくれている人ばかりです。とても住みよい地域になりました。」
もちろん人口は減少したし、徐々に増えているとは言え、震災前の水準にはほど遠い。でも、人口を増やすことは、彼は最初から期待していない。いずれにせよ過疎化してどん詰まりになることがわかっていた地域だ。それよりも、そこで暮らす人が暮らしやすい場所に、なにかあたらしいことをしたいと思う人が、希望をもってこられる、活力ある地域に、そんな小さな動きもある。
行政は、おおよそ、復興の度合いを人口でしか考えない。そして、どれだけ立派な箱物を作ったかを、自治体同士の面子として競いたがる。(そのせいで、震災前に財政破綻しかけていた自治体もあるというのに。) けれど、「地域作り」は、それとはまったく別軸のベクトルと志向性を持つものではないだろうか。
2017年頃、「福島からはじめよう」というキャッチコピーが色あせ始めた頃、「元に戻せ」という言葉ばかりが、とりわけ県内の報道では踊るようになった。福島の復興に、新しい社会の形を夢見るといった言葉は、もはや語られなくなった。いまや、震災前には、唯一の理想郷・福島があったかのような言われようだ。10年という時間の経過によって、福島以外では社会も世界も大きく変化し、二度と戻ることのない新しい世界へと動いていくのに、福島だけ、10年前の(幻想の)理想郷・福島を目指していく動きは、まるで、現実にはありえなかった夢想のガラパゴスを目指しているかのようだ。
そもそも、震災前のこの場所は、そんなによい場所だったろうか。そのことは、2年前の元旦にも書いた。
放っておいても、過疎化し、限界集落になっていた場所だ。原発がなければ、地域が維持できなかった場所だ。もちろん、そのことが、そこで生まれ育ち、愛着をもつ人たちにとっての価値を決して減じるものではない。どのような場所であっても、そこで生まれ育った人にとっては、その場所は唯一無比の絶対的な場所だ。すべての、被災しなかった人にとっての、被災しなかった故郷も同じくかけがえのないものであるように。
一方で、どこでもかかえる社会課題は、被災地にもあった。とりわけ、福島は、女性や若者にとっては、暮らしにくい場所だった。高齢化も過疎化も進んでいた。だからこそ、多くの人たちは、被災地・福島の復興に自分の夢を重ねたのだ。この社会課題を、被災地である福島から解決できれば、日本の未来はひらけるのではないか、と。そして、10年後、それは訪れなかった未来となった。
歴史に「if」はない。過ぎ去った時間は戻らない。けれど、歴史のいいところは、時間軸と評価軸を変えれば、評価の反転もあることだ。私たちは、10年前に夢見た未来とはまったく違った場所にいる。だが、荒れ野に種をまけば、やがて、芽吹くものもあるだろう。うまくいけば大樹になるものもあるかもしれない。もしかすると芽吹くのは、20年後、30年後になるかもしれない。そんな未来を夢見て、「復興」とはまた違う世界を見いだしていくのが、私たちの次の10年になるのだろう。それを担うのは、あたらしい社会を夢見ることができる世代、人たちだ。
〈お知らせ〉
自分の10年間の経験にきちんと整理をつけたくて、放送大学の修士課程(全科生)で、今流行の「学び直し」をすることにしました。生活健康科学コースというところで、リスク学を学ぶつもりです。修論を2年で書こうとすると、かなりタイトな日程になると思われるので、他のスケジュールも勘案すると、4月以降はTwitterなどSNSへの出現頻度は激減することになると思われます。もし姿が見えなくなっても、ご心配なさいませんよう。
