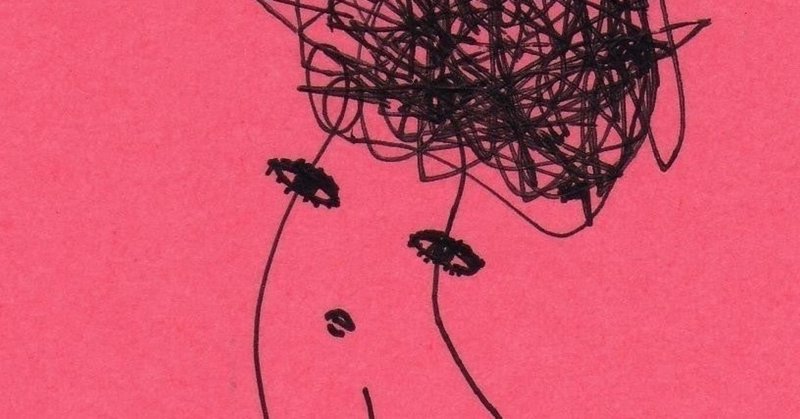
岡本太郎の母〜かの子繚乱
常軌を逸した圧倒的な情念が
強力な崇拝者を引き寄せる。
タイラント(暴君)として支配する者に
被支配者の情念が、渦を巻きながら絡みつき
支配しているのか、されているのか分からない
やがて渾然一体となった巨大な塊になる。
岡本かの子の晩年の作品群は
そうして完成された。
岡本太郎に、深く深く影響を与えた母。
でも、はぁ、困ったなぁ…
というのが正直な感想である。
どうやっても共感が持てないのである。
そもそも、共感という言葉が似つかわしくないのだ。
自由奔放に、情熱の赴くままに生きた女性
…なのだが、一体何なんだ?この人は。
果たして人なのか?
憧れや尊敬とは別次元。
古事記に登場する荒ぶる神のような怪女
という解釈でもしない限り
人として見てしまうと嫌悪感しか出てこない。
純粋な魂とは、混沌とした清濁を併せ持っているのだろうけど。
当時の女性たちにも
相当なバッシングを受けていたらしい。
外で虐められて家に帰ると
履き物を脱ぎ散らし、髪を振り乱して
近所中に聞こえるような大声で泣き散らす。
幼い太郎の目の前でも。
女性に忌み嫌われる一方で
男性からは非常によくモテる。
無垢な童女と独裁者が同居した女性に
大母性、吉祥天女を見いだし喜んでかしずく。
ナボコフのロリータや
谷崎潤一郎の痴人の愛のナオミのような
若く美しい女性ではない。
厚化粧に奇抜な服装。
肉のつまった小柄な体に子供のような手足。
情念で目だけがギラギラと輝いている。
摩訶不思議。そう、摩訶不思議。
本人の作品を何冊か読みかけたが
途中でえずいてしまって最後まで読み切れない。
粘っこい耽美主義。
ロマンチシズムを通り越して
巨大なスライムの塊ような自己愛。
これはもう
誰かのフィルターを通さないと無理だ。
毒をもって毒を制す。
瀬戸内晴美(現在の瀬戸内寂聴)著
『かの子繚乱』。
かの子を表現するには、
この人くらいじゃないと。
岡本かの子
1889~1939
小説家、歌人、仏教研究家。
東京市赤坂区(現在の東京都港区)青山南町に
豪商大貫家の長女として生まれる。
乳母の英才教育、文学活動をする兄晶川や
兄の友人でもあった、谷崎潤一郎の影響を受ける。
与謝野晶子の新詩社、平塚らいてう率いる
青鞜の女たちとの交流の中で、歌人として文学熱を燃やす。
19歳の頃
美術学校の生徒だった岡本一平と結婚。
翌年に長男太郎を出産。
結婚後、一平は夏目漱石の紹介で朝日新聞社に入社。しかし放蕩癖があり、家庭を一切顧みなかった。
経済的に困窮を極めたかの子は
長女出産ののち、精神を病み精神病院に入院する。長女も生後間も無く死亡。
かの子は退院後
歌人かの子のファンであった
早大生の堀切重夫と恋に落ちる。
かの子への悔恨により、
一平は我が家に堀切を招き入れ
夫、妻、息子、愛人という
奇妙な共同生活を始める。
奇妙な共同生活は地獄絵図の様相で
直後に生まれた次男も
ネグレクトに近い形で生後半年で死亡。
堀切が、かの子と全くタイプの違う
妹きんに惹かれ始めたことを知ったかの子は、堀切を追い出す。その後、堀切は郷里にて肺を病み死亡。
かの子と一平は精神の救いを求めて宗教の門を叩く。キリスト教に入信するも、すぐに仏教徒に回心。そこから、かの子の仏教研究が始まる。
この頃、太郎は、慶應義塾幼稚舎の寄宿舎に入る。
一平は漫画に解説文を加えた、漫画漫文という分野で一躍人気を極め、経済的にも恵まれる。
かつての放蕩生活を悔い
生涯をかけてかの子をかばう決意をし
世俗を超えた夫婦関係を貫きとおす。
岡本家に下宿する慶應の大学生だった恒松安夫
かの子が入院した病院の医師、新田亀三という
二人の愛人と岡本一家の共同生活。
岡本一家と愛人二人で渡欧。
太郎はパリに残り、絵画の勉強をする。
かの子は帰国後、執筆活動を再開。
仏教研究家として世に知られると共に
念願の小説にも精力的に取り組み始める。
かの子の為に第一線を退き
かの子文学を世に広めようと
世間に働きかける一平。
日常の細々とした雑務を担う恒松。
腺病持ちのかの子の体調管理をする新田。
夫、愛人二人のサポートにより
ついに小説家として世に認められる。
油壺の宿で若い青年と宿泊中、脳溢血で倒れる。
一平らの看病も虚しく49歳でこの世を去る。
始めにも書いたが、
やはり吐き気がおさまらない。
一刻も早く
吐き出してしまいたい一心で、
これを書き続けている。
太郎はどう思っていたのだろう。
本著の中で、唯一好きな場面がある。
パリでマロニエの並木道を歩いている風景。
この木の花の咲く季節に会ったとき、
彼女は目を一度つむって、それから、ぱっと開いて、まじまじと葉の中の花を見つめた。
それから無言で息子に指差して見せた。すると息子も、彼女のしたとほり、1度目をつむって、ぱっと開いて、その花を見入った。
二人は身ぶるひの出るほど共通な感情が流れた。
息子は、太くほった声でいった。
「お母さん。たうとうパリへ来ましたね」
(母子叙情)
太郎が幼い頃、父の帰りを待ち詫びて
母と夕暮れに染まる赤い空を眺めながら
「あーあ、今に二人で巴里にいきませうね、
シャンゼリーゼで馬車に乗りませうねえ」
と言っていたあの日。
太郎の著書『一平かの子 心に生きる凄い父母』にはこう記されている。
実際、彼女の産んだ子供である私でさえ誤解したくなるくらい、猛烈な性格だったが。
しかし私は誤解のカタマリみたいな人間こそ、すばらしいと思う。
純粋であり、純粋であるがゆえに誤解される。
そしてどこまでが誤解であって、実態がどうなのか、自他ともに分からなくなってしまうくらい、スケールの大きい、
—やはり母にはそういう、いい知れない豊さ、悪く言えば妖怪的な趣があった。
少し胸が救われた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
